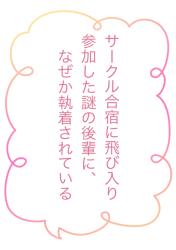「…千冬、」
「あ、先輩。お粥、食べますか?」
「…おう」
「温めるので、少し待っててくださいね」
目が覚めてリビングに行くと、時刻は既にお昼。
千冬は部屋着のまま、ノートパソコンの前で何か作業をしているところだった。
「すげぇ寝た…」
「体調が悪い時は、寝るに限りますよ。熱は計りましたか?」
「熱は下がった。おかげさまで、体も軽いし、頭痛もねぇし。喉がちょっと痛ぇなってくらい」
「それは良かったです」
ダイニングの椅子に座り、キッチンに立つ千冬の背中を見る。
…さっき怒らせちまったこと、謝らねぇと…。
「そうだ。僕から、水森さんに連絡しておきました」
「…え?」
「感染症では無さそうですけど、念の為、水曜のバイトは休むようにって言ってました」
「あ、ああ…。そっか、分かった」
「あと、カゲヤン先輩たちにも連絡してあります」
「え?何を連絡すんだよ?」
「伊織先輩が明日休みますって」
「は?いや、熱下がったら行くつもりだったけど…」
「ダメですよ!ぶり返したらどうするんですか。明日は、うちにいてください」
「うち?」
「はい。僕がしっかり面倒みます」
「………」
俺はやっぱりガキだと思われてんのか…?
それか捨て犬か何かか……。
「はい、伊織先輩」
「あ、さんきゅ。わぁ、美味そう…!」
千冬が、俺の前と、自分の前に皿を置く。
美味そうな香りに、目の前のたまご粥に意識が奪われる。
ほかほか湯気をたてる器の中は、やさしい黄色と白。
刻んだネギもトッピングされていて、食欲をそそる。
「いただきます!」
「ふふ、どうぞ」
「……あ~、美味ぇ……沁みる」
「喜んでもらえて良かったです」
見た目通りの優しい味が、弱った俺の胃を労わってくれる。
幸せ…。
「あ、」
数口食べた後、俺はスプーンを置いた。
千冬に、ちゃんと謝るために。
「千冬…。さっきは、怒らせてごめん」
「え?」
「千冬にはすげぇ迷惑かけてるのに、それなのに、俺、変なわがまままで言って、もっと迷惑かけた」
千冬の手を掴んだ自分を思い出すだけで、恥ずかしい。顔から火が出そうだ。
「言い訳、だけど。俺、熱出すなんて久しぶりで、ちょっと、参ってて…。無意識にやっちゃった、っつうか…」
「無意識…」
「とにかく、ごめん!」
その場で深々と頭を下げると、千冬が小さく笑うのが聞こえ、頭を上げる。
「怒ってないですよ。僕の方こそ、ごめんなさい」
「いや、千冬は悪くねぇだろ。ほんと、ごめんな」
「伊織先輩も、そんなに謝らないでください。ほら、お粥が冷めないうちに、食べてください」
「おう…!ありがとな」
千冬に謝れて、胸の中までスッキリする。
良かった。
たまご粥も、さらに美味しく感じんな。
「俺、千冬とはこれからもいい友達でいてぇからさ。またなんか嫌なことあったら、言ってくれな?」
「友……、」
今度は千冬のスプーンがピタッと止まった。
「伊織先輩は…、僕と…友達でいたいんですね…」
「おう。千冬が良ければ、だけどな」
そこを確認されると恥ずかしいな。
照れ臭ぇ。
「一昨日、千冬の話聞いてて思ったんだよ。友達って、最強なんじゃねぇかって」
「最強、ですか」
「おう。ずっと仲良くできるだろ?」
「……」
「彼女ができたときは一緒に喜んでやるし、もし千冬がフラれたときは、傷心旅行にでも付き合ってやるよ」
ふふん、と得意げに笑って、たまご粥を口に運ぶ。
本当に美味ぇ。
「それは…素敵ですね」
「だろ?彼氏彼女はくっついたり別れたりってあるけどよ、男同士の友情は、『別れ』ってねぇもんな」
「そうかも、ですね…。」
千冬がとうとうスプーンを置く。
「………でも、」
悩ましげに長いまつ毛を下げ、視線を落とす。
微かに震える声が、言葉を続ける。
「友達には、…その先が、ありません」
「…え?」
俺も手を止める。
千冬の、雰囲気が違う。
千冬は意を決したように顔を上げると、真剣な目で俺を見つめた。
ドキリと心臓が跳ねた。
「俺は、その先が欲しいです、伊織先輩。」
「その、先…?」
「手を握ったり、抱きしめたり。……キス、したり……」
「キ…、」
「伊織先輩の、全部が欲しいんです」
………。
え?
「ちょ、ちょっと待て、…俺が…何だって?」
聞き間違いかと思った。
話の流れが、上手く掴めない。
抱きしめたり、キス……?
全部が、ほし…い…?
喉の奥がひくつく。
「俺は、伊織先輩のことが、好きです」
「……す…っ」
「友達じゃ、…足りません」
呼吸が止まる。
手の力が抜けて、床に落ちたスプーンが、カランと音を立てた。
「好きで、好きで…、もう、抑えられる自信がないです」
「……、」
「声が聞きたい、顔が見たい、触れたい、抱きしめたい、キスしたい」
胸がぎゅっと締め付けられる。
長いまつ毛に縁取られた瞳が揺れ、俺の体温を上げた。
「もう、…限界、なんです……」
熱烈な告白に、身体中が燃え上がるように熱くなった。
心臓は早鐘を打ち、頭は真っ白。
「え、そ、……」
呼吸が浅くなって、口から出るのは意味のない言葉だけ。
気持ちが追いつかないし、言葉の意味はわかるけど、理解しきれない。
こういう時、なんて言ったらいいのかなんて、全然分かんねぇ……!
「…友達以上に、なりたいです」
「そ…、か………」
耳まで赤くして、上目遣いに俺を見る千冬。
どう、しよう……。
分かんねぇ。
分かんねぇけど、千冬は真剣だ。
だから俺も、貼りついた喉で、言葉を選びながら、慎重に答える。
「千冬の気持ちは、…分かった。でも、正直、よく分かんねぇ。だって俺、恋愛なんかしたことねぇし……」
断ったら、千冬との縁が切れるんだろうか。
受け入れたら、友達じゃいれなくなるんだろうか。
「千冬のことは、好き、だ。でも、その…、だ、抱きしめたいとか…、キ…キスとか……は、考えたこと、ねぇし…」
言いながら、顔がみるみる赤くなるのが分かる。
「それに、そういう関係は…、もしかしたら、ずっと…続かないかもしれねぇし…、」
目の奥がツンとする。
呼吸が、早くなる。
もう頭はぐちゃぐちゃだ。
「そしたら、千冬と、…一緒にいることなんて、で、できなくなるし……」
頬に涙が伝う。
悲しいのか、苦しいのか、なんの涙なのか、分からねぇ。
分かんねぇことばかりだ。
「伊織先輩…」
呼ばれて顔を上げると、優しい焦茶の瞳と目が合った。
千冬は手を伸ばして、俺の涙を拭う。
「困らせてしまって、ごめんなさい」
「~っ…」
「あの……、…先輩は、友達以上のことをすることと、いずれ別れるかもしれない不安と、どっちが嫌で泣いてるんですか?」
柔らかい声。
小さい子供に諭すように、ゆっくり俺に確認する千冬。
俺の方がよっぽど余裕がなくて、恥ずかしい。
でも、千冬の声で、頬だけじゃなく、心まで撫でられるような感覚がして、少し気持ちが落ち着いた。
「わ、かんねぇ…、どっちも、…怖ぇ、かも…」
情けないほど、弱々しい声が出る。
言いながら、また視線が落ちていき、涙が目の淵から溢れそうになる。
「それなら、どっちも怖くないって思えたら、…僕と、付き合ってくれますか?」
「…え…?」
鼻を啜りながら、再び千冬を見上げた。
千冬は、赤い顔のまま、緊張した面持ちで、俺の視線を受け止める。
「僕が、証明してみせます」
「証、明…?」
「はい。怖いことは、何もないって、伊織先輩に証明します。…どうですか?」
最後にふわりと笑う千冬。
千冬の意図は全く読めない。
それなのに、千冬の笑顔を見て、処理落ちしそうな頭を取り残して、口が勝手に答えていた。
「………わか、った……」
「ありがとうございます、伊織先輩」
千冬はゆっくり瞬きをして、口元に綺麗な弧を描く。
栗色の瞳は、小さな星を宿したようにキラキラ輝いた。
「…大好きです」
やっと解き放たれた言葉。
千冬の真っ直ぐな言葉に、ゴクッ、と喉が鳴った。
俺は、涙で熱くなった頭と目で、ただ呆然と千冬を見つめた。