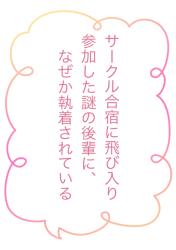帰りの新幹線は指定席。二人掛けのシートに千冬と並んで座る。
「あっという間でしたね」
「ああ。千冬のおかげで、すげぇ楽しかった。ありがとな」
「いいえ。僕こそ、幸せな時間でした」
柔らかく笑う千冬を見ながら、小さく息を吐く。
なんか寒ぃな…。
新幹線内の空調の微風も、寒く感じる。
自分の腕を摩りながら、走り出した新幹線の車窓を眺めた。
夕焼けに染まる厚海の街。
本当に、あっという間だったな…。
「…先輩?」
「…ん?」
呼ばれて振り向くと、栗色の瞳が心配そうに俺を見つめている。
「寒い、ですか?」
「…ん、おう」
「ちょっとすみません」
千冬は自分の着ていた羽織を俺に掛け、そっと、俺の額に触れた。
千冬の匂い。
手の冷たさ。
気持ちいいな…。
「…熱い、気がします。身体は怠くないですか?喉は?頭痛は?」
「んー…、ちょっと痛ぇかも…」
言われてみれば、身体も怠い気ぃすんな…。
頭もぼんやりするし。
疲れとか眠気じゃなくて、風邪かもしんねぇ…。
千冬がカバンからペットボトルのお茶を出して、俺に渡してくれる。
「さんきゅ」
「目もとろんとしてますし、顔も赤いです。……心配です」
千冬の眉が悲しげに下がる。
…そんな表情しても、綺麗な顔だな。
熱で朦朧としてきた頭では、そんなことしか思いつかねぇ。
「とりあえず寝てください。向こう着いたら、解熱剤買って帰りましょう」
「…おう」
霞む視界を瞼で遮り、重い何かに引き込まれるように眠りに落ちる。
千冬に迷惑、かけねぇように早く帰らねぇと。
あー…、しんど……。
*
頭の痛み、体は熱いのに、芯は凍えるように寒い。喉もキリキリ痛ぇし、呼吸も苦しい。
「…み、ず…、」
とにかく喉の痛みを和らげたくて、頭痛に耐えながら目を開ける。
「あれ…、どこ……」
ふわふわの枕に、何枚も重ねて掛けられている、温かい毛布。
清潔感のある白いシーツから、ほんのり千冬の香りを感じた。
「あ、伊織先輩、大丈夫ですか?」
静かに部屋の扉が開けられ、淡いピンク色の髪が目に入る。
千冬だ。
「…ここ、は…」
「僕の部屋です。薬、買ってきました。飲む前に、何かお腹に入れましょう。どんなものなら食べられそうですか?お粥とか、ゼリーとか…」
「……ゼリー…」
「ゼリーですね、持ってきます。他に欲しいものはありますか?」
「…みず」
「わかりました。ちょっと待っててくださいね」
ガンガンと痛む頭に、再び目を瞑る。
……千冬に看病されてんのか、俺。
こんな風に熱を出すのは、久しぶりだ。
大学入って、一人暮らしを始めてからは、初めて。
なんとなく心細くて、再び扉へ視線をやると、丁度、扉が開かれた。
「ゼリー持ってきました。あと体温計も」
グラスに入った水を飲み、体温計を脇に挟む。
喉を通る水分が心地いい。
千冬が側にいて、安心する。
「38.9…。高いですね」
体温計を渡し、スパウトパウチに入ったゼリーを受け取る。味なんてよく分かんねぇけど、とりあえず胃に流し込んだ。
「…もう食ぇねぇ」
「大丈夫ですよ、頑張りましたね。薬も、飲めますか?」
「おう…」
クラクラする。このまま起きてると吐き気もしてきそうだ。
薬を水で流し込み、すぐに横になる。
しんどい…。キツぃな…。
「すぐ良くなりますからね、」
目を瞑ると、すぐに意識が落ちていく。
千冬の声。安心する。
「…、」
それから、頭を撫でられる感触。
優しい手…。
頭痛が和らいで、気持ちいい。
千冬…、千冬……。
側に、いてほしい…な…。
*
「…、ちふ…?…あ、」
次に目覚めた時には、頭痛も弱まり、喉が少し痛むくらい。
まだ怠さはあって頭はぼうっとするけど、身体はかなり楽になっていた。
上体を起こして、スマホで時間を確認する。朝の4時半。
厚海から帰って、そのまま一晩、千冬に世話になってたのか…。
とりあえず起きて、水でも飲みに行こう。
そう思い、ベッドから起き上がろうとしたところで、部屋の扉が開いた。
「あ、おはようございます。体調はどうですか?」
「だいぶ、いい。…世話かけて、悪ぃな…」
「いいえ、先輩のお世話なら、いくらでも引き受けますよ」
にっこり微笑む千冬。
てか千冬、朝早ぇな…。
「熱はどうですか?薬、飲みます?お腹は?」
「…腹、減った」
「良かった。またゼリーにします?それか、お粥とかうどんとかも作れますけど…」
「……千冬のメシ…、食いてぇ」
散々世話になっておいて、図々しいか?なんて考える余裕はなく、ぼうっとする頭で素直に答えしまう。
身体は、温かい料理を欲している。
千冬の作ってくれた料理が欲しいって、思った。
「……いいか?」
「もちろん。いいですよ」
近付いてきた千冬を見上げると、千冬は一層やわらかく微笑んだ。
優しい手つきで頭を撫でられる。
気持ちよくて、胸の奥が解けるような感覚になる。
「たまご粥はどうですか?」
「…食いてぇ」
「ふふ、作ってきますね」
「…ぁ、」
立ち去ろうとする千冬の手を、反射的に掴んでいた。
「……伊織先輩?」
「………」
驚いた顔で、俺を見つめる。
自分でも自分の行動がよく分からなくて、ただ千冬を見つめ返し、口ごもる。
熱が残っているせいか、頬が熱い。
うっすら目にも涙が溜まる。
「ぇ、っと……、」
言葉が出ない。
でも、手は放せない。
千冬の整った顔を見ながら、ただただ混乱する。
寂しい、近くにいて欲しい。
千冬は、ゴクリと生唾を飲み、それから目を閉じて、震える息を吐き出した。
「はぁ…。先輩…、」
そっと目を開き、俺の体に覆い被さるように、ベッドに手をついた。
──ギシッ、
色気のある薄い瞼から、甘い焦茶が、俺の視線を絡めとる。
千冬から、目が逸らせない。
「…あまり、かわいいこと、しないでください」
「…か、わ……?」
「僕を試してるんですか?」
首を少し傾け、顔を近づけられる。
俺の言葉に被せるように発された声は、低い囁き声。
責めるような口ぶりなのに、声は罪深いほど優しくて、鼓動が早まる。
「千冬…、怒ってる、のか……?」
優しく細められた千冬の目が、ギラリと光った気がした。
何らかの激しさを、内側に隠しているように。
「先輩が、病人だから…、我慢してるんです」
鼻先が触れそうなほど、綺麗な顔が近付いて、思わず少し仰け反る。
我慢…、やっぱり怒ってるってこと、だな…。
反省する気持ちはあるのに、至近距離にある千冬の顔にドキドキが止まらなくて、千冬の声が、耳の奥で甘く焦げ付く。
「お願いなので、それ以上、無防備なところを見せないでください。……我慢、できなくなります」
「…ご、めんな、さい……」
絞り出すように謝り、俯いた姿勢のまま、千冬を見上げる。
俺が掴んだはずの千冬の手は、いつの間にか、俺の手の上に重ねられていた。
「……僕こそ、取り乱しました。すみません…」
千冬の手が、今度こそ離れていく。
「お粥、作ってきますね」
口の端だけを上げた千冬が、静かに部屋を出て行った。
「はぁ……、俺、かっこ悪ぃ…」
そのまま後ろに倒れ込み、顔に手を当てる。
いくら熱があるとはいえ、後輩に甘えて怒られた事実を、ただただ恥じた。
早く、熱を下げよう。
千冬にちゃんと謝って、さっきの醜態は忘れてもらおう。
俺はそのまま、意識を失うように、また眠りについた。