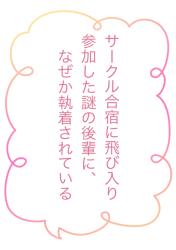翌朝。朝ごはんも、昨晩同様にご馳走になって、その後も千冬の弟たちと遊んでいたら、結局昼前まで居座ってしまった。
「お世話なりました」
「「もう帰るの~?」」
「ちーにぃ、伊織にぃちゃん、今度はいつ来る?」
「伊織ちゃんはうちの子同然なんだから、いつでも遊びに来て!」
「伊織くん。千冬は、口うるさいところがあるかもしれないけど、どうかよろしく頼むよ。」
千冬の弟達も両親も、玄関先まで見送りに来て言葉をかけてくれる。
本当にあったけぇ人たちだな。
「ご飯も美味かったですし、いろいろ気遣ってもらってありがとうございました。楽しかったっす。シュン、ハル、星夏も、またな」
「「は~い」」
「またね!」
千冬の弟達に手を振り、千冬も家族と「また来るね」と言葉を交わし別れる。
「千冬の家族って、すげぇフレンドリーだな」
「今回は、特にそうだったかもしれないです」
「?」
「僕が…初めて伊織先輩を連れてったので…」
「?………あ」
俺は察してしまった。
千冬、もしかして、今まで友達とかいなかったのか…?
だから、千冬が友達を家に連れてくることが珍し過ぎて、熱烈な歓迎を受けたってことか。
なるほど…
妙な沈黙になってしまったところで、千冬が緊張した様子で俺に切り出した。
「伊織先輩。…今日、帰りに、伝えたいことがあります」
「帰り?」
「はい。…最後、に…」
「…おう?分かった」
なんだ?改まって。
千冬はそれだけ言うと、ふうーっと長めに息を吐いた。
「では!早速、お昼ご飯に行きましょうか!」
「あ、今日こそ海鮮丼食いてぇ」
「ふふ、そうでしたね。じゃあこっちです」
千冬の後に続いて、昨日食べ損ねた海鮮丼の店へ向かった。
*
千冬に店に案内してもらい、30分ほど待ってやっとありつけた海鮮丼は、特別に美味かった。
厚海の海の幸に舌鼓を打った後は土産探し。
昼メシがゆっくりだったから、新幹線の時間も考慮して、今は駅近くの商店街で土産物を物色中だ。
「カゲヤン達の土産は何にすっかな」
「プリンとかお饅頭が定番ですよね」
「プリンな!昨日の、美味かったもんなぁ…。昨日の店のプリンって土産にできんのかな?」
「うーん、保冷バッグに入れてもらって…、早めに渡せるなら、大丈夫じゃないですか?」
「おう。アパート近ぇし大丈夫だろ。プリン買ってってやるか。ついでに自分用も」
「最後のがメインに聞こえました」
「はっはっはー、…正解だよ千冬くん」
わざと声を潜めて極秘事項のように言うと、千冬が子供みたいに笑った。
「昨日はグルメロードの方で食べましたけど、人気のお店なので、この商店街にも出店してるはずです」
「おう!行き……、は、はっくしゅん!……悪ぃ」
「大丈夫ですか?」
話してる途中に、くしゃみが出て、背筋にゾクゾクっと寒気が走った。
鼻を啜りながら、千冬に答える。
「大丈夫だ。どうせマンティスあたりが俺の悪口でも言ってんだろ…」
「…あ、そういえば、マンティス先輩って、ボカロ好きなんですか?アイコンが…」
「ああ、確かに。色々聴いてるって言ってたな」
「今度その話をしてみようかな。話が合いそうです」
「いいんじゃねか?多分、早口で聞いてないことまで話してくれっからよ」
「あはは!いいですね、楽しみです」
すぐに千冬が、地図アプリで店の場所を調べてくれて、「こっちですよ」と誘導してくれる。
ほんとスマートだよな、そういうとこ。
それに打って変わって。
カゲヤン達に、「厚海に行く」って話した時、「秘法館」で大人の勉強をして来いとニヤニヤ笑っていた三人の顔を思い出す。
「秘法館」とは、大人の保健体育が学べる、有名な観光施設だ。
そして、「千冬と一緒だ」と言った途端、「海に行け」「絶景カフェに行け」「美術館に行け」など妙に洒落たとこばかり勧めてきた。
…アイツら、俺と千冬のキャラ付けに差がありすぎじゃねぇか?
「あ。あれですね」
「ほんとだ。すげぇ、グッズとかも売ってんだな」
店内は、プリンの他に、キーホルダーやステッカー、エコバッグなどのノベルティが並んでいた。
その中のあった一つのマグカップに、引き寄せられるように手を伸ばした。
深いブラウンの陶器に、厚海プリンのキャラクターの、桜色のハリネズミのワンポイント。
無意識に、惹かれるように、…手に取っていた。
「このマグカップ、……買おうかな」
「どれですか?」
「え…?あ、これな。…なんか、良くねぇか?好きな感じ」
「ふふ、そうですね。これからの季節、温かいものを飲む時に良さそうです。」
「だよな。…あ、」
「?」
マグカップを千冬の前にかざす。
自分のひらめきに、自然と口の端が上がる。
「わかった!千冬っぽいわ」
「え?」
「これ。ハリネズミがピンクだからか?」
「……、」
手元のマグカップのハリネズミと、目の前の千冬をじっと見比べる。
千冬は少し目を見開いて、俺を見つめ返す。
若干、緊張してるようにも見える。
「このマグの焦茶も、千冬の目の色に似てるな。だから余計そう思うのかも知れねぇ」
「……伊織先輩、」
「ん?」
千冬が、長いまつ毛を伏せ、俺の手のマグカップに手を掛ける。
熱い指先が微かに触れて、栗色の瞳が俺を覗き込んだ。
「それ、無自覚ですか…?」
ため息を混ぜたような、吐息と小さな声。
切なげに、やや伏せられた瞼。
そしてマグカップは千冬に取り上げられる。
「…え?」
「これ、僕が買います。伊織先輩に」
「あ…いや、自分で買う…」
「いいえ」
千冬が、同じマグカップをもう一つ手に取り、再び俺を見た。
瞼の下から、甘やかすような焦茶の瞳が覗き、挑発的に口角を上げる。
「砕けさせません。絶対に」
「………え??」
なんだか上機嫌にレジに向かう千冬の背を見送る。
砕けさせない……?
俺がマグカップを割ると思ったってことか?
そんなそそっかしいつもりはねぇけどな…。
「~っくしゅん…!…あー」
くしゃみと一緒に、直前の思考も散る。
店内の空調のせいか、頭が少しぼうっとしてくる。
お土産用のプリンを手に、俺も会計へ向かった。