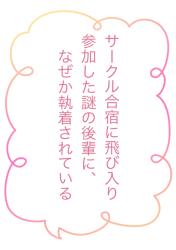賑やかな夕餉後は、千冬の弟達とゲームで遊んだ。もともと友好的に接してくれてたけど、最終的には、連絡先の交換までした。
高校生と中学生の友人ができるとは思ってなかったな。
「弟達がうるさくてすみません」
「そんなことねぇよ。楽しかった」
俺は千冬の部屋に案内される。
今晩はここで、千冬と布団を敷いて、寝させてもらうことになっている。
「面白いものは何も無い部屋ですけど…」
「そうか?」
風呂はもう済ませているから、あとはもう寝るだけだ。
千冬の部屋は、6帖くらいの畳部屋。勉強机とハンガーラック、そして壁際には棚が置かれていて、中は学校の教科書や参考書、そして「DTM入門」「ボカロ基礎」「ギター教則本」などの背表紙が並ぶ。
「これって…、」
「ああ、始めたばかりの頃、使ってた本です。なかなか捨てられなくて、そのままなんです」
昔の友人を見るかのような目で、それらを眺める千冬。
本は、教科書より使い込まれ、端が折れたり欠けたりしている。
千冬の努力の一端を、垣間見た気がして、少し胸が熱くなった。
「布団、敷いちゃいましょうか」
「…おう、そうだな」
用意してもらった敷布団を広げ、その上に寝転ぶ。
横になると、途端に疲れと眠気が押し寄せてくるから不思議だ。
朝も早かったし、なんだかんだ、もう22時近い。
「千冬の家族って、いいな。」
目を擦りながら、夕飯やゲームの時間を思い出して、頬が緩む。
「ふふ、はい。ありがとうございます」
「俺の方こそ、…ありがとな」
「電気、消しますね」
「おう」
千冬が部屋の電気を落とし、隣の布団に寝転ぶ。
開けられた窓からは涼しい夜風が入り、月明かりが部屋に落ちる。
「寒くないですか?窓、閉めましょうか?」
「俺は大丈夫。千冬は?」
「僕も大丈夫です。」
秋の虫が遠くで鳴り、隣で話す千冬の声が、耳に心地良い。
…もっと、聞いていてぇな。
窓辺に視線を移すと、薄がりの中、勉強机の奥に、ギターが立て掛けてあるのを見つける。
「あれって、昔使ってたギターか?」
「はい。最初に使ったギターです。中学生の時、父に買ってもらいました。」
「……千冬の歌、聞きてぇな…」
「え…」
寝返りを打ち、隣の千冬を見る。
黄色い月明かりは、千冬の整った顔を儚げに照らしている。
淡いピンク髪が、ふわりと揺れた。
「あ、悪ぃ、もう寝ようって時に…」
「えっと、いいえ…、それは構わないんですけど…、」
少し考える様子を見せながら、布団から起き上がり、窓際のギターを手に取る。
俺の近くに座り、胡座をかいた上にギターを乗せ、チューニングを始める。
千冬は黙ったまま。
長いまつ毛を伏せ、しなやかな指が、弦を小さく弾く。
俺も起き上がって、千冬と向かい合うように布団の上に座る。
しばらくして、チューニングが終わったらしい千冬は、手を止め、ゆっくり俺を見上げた。
「……」
しっとりと、俺を見つめる栗色の瞳。
月明かりが逆光になり、千冬のやわらかい髪を、細い光が縁取る。
静かな千冬の表情は、月影を映す夜の湖のように神秘的だ。
「千冬?」
千冬は、優しい微笑みだけを返して、視線を落とし、落ち着いた旋律を奏で始める。
──♪
これ、聴いたことあるな。
確か、初めて千冬の動画を見ようとした時に止められた…、「初春の月」。
あのあと一人で聴くことは無かったから、俺は前奏しか知らねぇ。
心地良いギターの音色に、小さく息を吸った千冬が、静かに歌い始めた。
「あ………」
甘く切なく心を揺らす声。
「……、」
弦を見つめる栗色の瞳が、不意に俺を見る。
全身が、ぞわぞわと粟立つ。
悪い意味ではなくて、千冬の視線が、声が、優しいメロディに乗って体の中を侵食するような気がした。
……すげぇ、ラブソング……。
千冬の「初春の月」は、叶わない初恋の、切なさを歌った歌だった。
歌詞は、焦がれる気持ちに溢れている。
受け止めきれないほどの「求める気持ち」が、感情を揺さぶる。
…なんか、大人っぽい、な。
俺には分からない、知らない感情。
目の前にいる千冬が、急に自分よりずっと大人に思えて、千冬の熱のこもった視線から逃れるように俺は顔を背けた。
それでも千冬の歌声には、強く惹きつけられ、俺は深く聴き入っていた。
……
…
「……、おわり、です。聴いてもらって、ありがとうございました」
歌い終わった千冬は、照れくさそうにはにかんだ。
「なんつーか、すげぇ…、良かった。…俺の知ってる千冬じゃねぇような気さえしたし。その…、」
…歌の相手は、…こんなにも千冬に想われる相手は、どんな人なんだろうって思った。
「…とにかく、ありがとな。千冬、やっぱ上手ぇよ」
「ありがとうございます」
そう言って、千冬は一呼吸置いてから続けた。
「あの…、この曲は、僕の…大切な人を想って作った曲なんです」
顔をほんのり赤くしながら語る千冬を、また、少し遠くに見る。
言われなくても、それは十分伝わってる。
「……大切な人って、千冬の、今の彼女のことか?」
「え!?ち、違います!彼女はいませんから」
「ええっ!?そうなのか?」
さっきまでの眠気が吹き飛ぶくらいには驚いた。
え、いねぇの?
「まだ、片思い中、です…」
「うっわ…」
「『うっわ』って何ですか…」
拗ねたように唇を尖らせる千冬に、少し笑う。
「お前なら、告白してフラれることなんてねぇだろ。学校でも、あんなに女子に囲まれてたじゃねぇか。今までだってモテてたんじゃねぇの?」
「それは…まぁ…、それなりに、付き合ったりとかはありますけど…、違うんです。僕、自分から好きになったのって、…初めてで」
「へぇ?」
「僕に話しかけてきてくれる人が、どれだけいたとしても、その人は遠くから手だけ振って、立ち去っちゃうような人ですし…」
「…はぁ。なるほどな」
つまり、相手はそれほど積極的じゃねぇってことか。
いや、でも、千冬だぞ?
…あ、もしかして、彼氏持ちの子か?
「そういうことか…」
「え?」
「あ、いや、何でもねぇ」
茨の道だな。
略奪愛ってやつだろ?
千冬には、あまり勧めたくねぇな…。
「僕、今までずっと、曲を作って歌声合成ソフトに歌わせてたんですけど、…この曲だけは、自分で歌いたくて」
「……おう」
「一目惚れで、接点もないし、きっと叶わないだろうから…、歌にして、昇華させようと思って…」
無意識なのか、ギターの縁を何度も親指で撫でながら、俯く千冬。
「でも…、諦めきれなくて」
千冬の瞳が、静かに光った。
「そう、か…」
その視線に、ドキリとした。
どうやら、千冬はガチらしい。
でも彼氏持ちだろ?
もし、その相手が千冬を選んだとしたら、元カレはやりきれねぇよな。
仮に俺が、その元カレの立場だったら……、多分、結構…いや、かなり辛ぇと思う。
大切な人に、別れを告げられるんだからな。
でも千冬の歌を聴けば、千冬がどれほどその人が好きなのかは、痛いほどに伝わる。
うーん…。
「千冬、」
「…はい」
ゴホン、と咳払いをして千冬に改めて向き合う。
「お前の真剣な気持ちは分かった」
「はい……えっ!?それって、どういう…」
「俺にお前を止める権利はねぇ。だから、お前が諦められねぇって言うなら、告白なり何なりするのは、自由にやったらいいと思う。」
「はい…、」
「でもな、あくまで、正々堂々だ。お前の気持ちをちゃんと伝えて…、それで、その先は、相手に委ねろ」
「え…、はい…、え…?」
「相手の気持ちを尊重して、ちゃんと相手に決めさせるんだ」
「えっと…は、はい…」
お、なんか俺…、結構いい感じのアドバイスできてねぇか?
「大丈夫。俺はいつでも、千冬の話、聞いてやるからな」
「っ!?、そ、そう…ですか……」
「ちゃんと言えば、スッキリすんだろ。男なら、当たって砕けろ!」
「砕け……!?」
本気で泣きそうな反応をする千冬に、思わず笑う。
いくら千冬でも、万が一にも、フラれる可能性だってあるしな。
千冬が失恋したときは、また温泉でも誘ってやるか。
「ふぁ~…。俺、そろそろ眠くなってきたわ。今日はもう寝ようぜ」
「……、わかり…ました」
なんだか妙に大人しくなってしまった千冬が、ギターを片付ける。
布団に入って目を瞑ると、すぐにでも眠れそうなほど、意識がぼんやりする。
「千冬、おやすみな」
「…おやすみなさい、伊織先輩」
やっぱ、心地いい声。
そうだ、「彼女」は、いつか別れる未来があるかも知れねぇけど、俺は千冬の「友人」だ。
だから、いつまでも仲良くできるじゃねぇか。
…それって、最高だな?
口元を緩ませながら、俺は幸せな眠りについた。