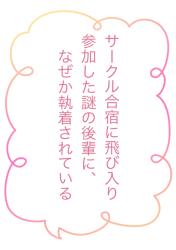千冬が案内してくれた温泉は、海の見える露天風呂。
「うわぁ~…癒されんなぁ…」
「気持ちいいですよね。僕も、家族とか友達とかと、よく来てました」
ピークタイムを避けたとは言え、やっぱり連休中の観光地となれば、それなりに人は多い。
海は見えにくいけど、人の少ない場所に座り、壁に背を預け、石でできた縁に頭を寝かせる。
体を温めるやわらかいお湯。
眩しい青空に目を瞑ると、温泉の湯気を含んだ風が、濡れた肌を撫でる。
とぽとぽと、お湯が絶え間なく流れる音と、鳥の鳴く声、風の音。
「あ゛~~~………」
「……伊織先輩、オッサンぽいです」
「もうオッサンでいいわ…。この時のために生きてきたまであんな…」
「ふふ、そうですか」
ちゃぷん、と隣で千冬が動いた音がする。
遅れて、お湯が波を作り、体が受け止める。
「一人暮らししてっと、湯に浸かるってあんましなくねぇか?」
「僕はしますよ」
「え?マジかよ。浴槽洗うの怠くねぇ?」
頭を起こして隣を見ると、千冬は俺とは逆に、壁に腹を向けて、縁に肘をついて頭を乗せていた。
湿ったピンクの髪が、いつもより濃い色に感じる。
「お風呂に浸かるの、好きなんです。僕は好きなことだったら、面倒とか思わないタイプなので」
「そうなのか?」
「はい。音楽も好きだし、お風呂も好きだし…。あと、好きにな人にも、尽くしたいタイプです」
「す、…、へ、へぇ?」
温泉で上気した頬と、しっとりした綺麗な肩。
幸せそうな微笑みを、俺に向ける。
その笑顔は、はちみつが溢れるかのように甘い。
また鼓動が高鳴るのを感じて、俺は空に視線を戻し目を閉じた。
「僕のご飯が好きだと言われたら、毎日作ってあげたいし、お風呂に入るのが好きだって言うなら、僕が毎日いれてあげます」
千冬の優しい声が心地いい。
恋人に愛を囁くような、甘やかすような声。
頭に乗せていた冷たい濡れタオルをずり下ろし、顔を隠す。
なぜか、顔も体も、全身が熱ぃ。
そろそろ上がったほうがいいのかも知れねぇな。
「僕、重い…ですか…?」
切ない声に、胸がぎゅっとなる。
…これって、千冬の、彼女との話…だよな。
「恋愛相談したいなら、人選ミスってんぞ」
残念ながら、俺は恋愛のことなんて全く分かんねぇ。
彼女もいたことねぇし。
「でもまあ、千冬のことが好きな奴なら、千冬になんかしてもらえたら、嬉しいんじゃねぇの?…ていうか、その好きな人とやらに、直接聞けよ」
千冬の、恋人。
千冬の口から聞いたことはねぇけど、十中八九いるだろう。
そう思わせることが今までも何度かあったし、今だってその人を思って、俺に相談してる。
…ちょっとだけ、なんかつまらないような、気はすっけど…。
「…俺、そろそろ上がるわ」
「なら、僕も」
千冬は、一緒にいて、楽しいし。
なにより、心地いい。
だから…、今はなんか悩んでるみてぇだけど、幸せになってくれたら、俺は嬉しい。
…と、思う。
「風呂上がりの一杯、飲もうぜ?」
「はい!そうしましょう」
そこまで考えて、原因不明のこのモヤモヤには、とりあえず蓋をする。
今は旅行中だ。
目の前のことを楽しもう。
「あっちに、サイダー売ってますから、サイダーで…」
「はぁ?温泉の後はコーヒー牛乳だろ」
「…伊織先輩。ここのサイダーは、飲まないと後悔しますよ」
「え?そんな美味ぇの?それとも、わさび味とかのご当地系か?」
「ふふん。なんと140年の歴史があります」
「は…?140年?明治から!?」
「しかもかつては宮内省御用達です」
「宮内省…!?……そんなすげぇの…?」
「…ぷっ、あはは!はい、『四ツ矢サイダー』です!」
「うっわ、騙された!」
千冬に案内された先には、どこのスーパーでも買えるであろう、四ツ矢サイダーがビンで売られていた。
「僕は昔から、ここに来るとお風呂上がりにはサイダーを飲むので、伊織先輩とも一緒に飲みたくて」
ちょっと幼い顔で笑う千冬。
その頭をポンポンと撫で、サイダーを2本、購入する。
「いいんですか?」
「千冬のプレゼン力に負けたからな」
ふふ、と笑う千冬に一本渡し、ビンを、カチンと合わせる。
「「乾杯」」
グッと喉に流れる炭酸。
ほてった体に、冷たく弾ける感覚が気持ち良い。
「確かに美味ぇな」
「ふふ、ありがとうございます」
こうやって、千冬と一緒に温泉入って、サイダー飲んで、笑って。
それが、すげぇ嬉しいし、楽しい。