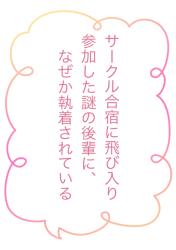「あっつ…!」
「えっ、どうました!?」
手に走った痛みに、反射的に声を漏らす。
ふわりと髪を跳ねさせ飛んできたのは、俺の大学の後輩であり、バイトでは先輩の、雨宮千冬。
緩くパーマがかかった淡いピンク髪に、一度見たら忘れないほど整った顔立ち。
綺麗な平行二重と、光を取り込む栗色の瞳は、優しげで柔らかな印象を与えている。小さな顔には、白くきめ細やかな肌の上に、全ての顔のパーツが、完璧な位置に配置されている。
文句なしの、美形。
千冬は、熱いコーヒーの入ったカップを俺から取り上げると、慌てて俺の手を掴み、流水に当てた。
「熱湯ですよ!熱いに決まってるじゃないですか」
「悪ぃ…」
千冬は、俺と同じ大学の1年生。俺の1学年下だ。
学部は違ぇけど、千冬とはちょっとした知り合いだった。
というのも、俺は夏まで、向かいにあったコンビニでバイトをしていて、千冬はそこの常連客だった。
そこで、千冬に話しかけられて、少しずつ言葉を交わすようになっていた。
そして9月の半ば。コンビニが閉店し、次のバイト先をどうすっかなーと、このコーヒーショップで求人情報を見てたところ、千冬が声をかけてくれた。
──良かったら、ここで一緒に働きませんか?……僕が、仕事教えるので…。
それが、つい先週の話。
「痕、残っちゃうかな…」
心配そうに小さな声で呟く千冬。
いや、別にいいけどな、そんくらい。
というか、正直、火傷くらい自分で対処できる。
でも、千冬は結構、…いや、かなり世話焼きなのか、バイト初日の昨日からずっとこんな感じだ。
「千冬、もう大丈夫だから放せ」
「!」
俺の声にパッと手を放すと、一瞬視線を彷徨わせ、それからジトっとした目で俺を見た。
「カップの上の方、持つようにしてください」
「…はい、すみません」
「僕がいない時は、自分で応急処置してくださいよ」
「はい」
「ていうか、怪我しないでください」
「……ぷっ、ありがとな、千冬」
「…何笑ってるんですか」
「あー、すみません、悪かったって」
俺を心配してくれてるのは分かるが、子供が駄々をこねるようにぶつぶつ文句を言うのが、なんだか面白くて笑ってしまう。
千冬はまた目を逸らした。
「千冬くん、こっちお願い」
「はーい。先輩は、しっかり冷やしといてくださいよ!」
「はいはい、ありがとうございます、千冬センパイ」
やや不満そうな顔のまま、別のスタッフに呼ばれ仕事に戻っていく千冬。
その後ろ姿に、また小さく吹き出す。
あんな綺麗な顔してるのに、オカン気質だよな、アイツ。
*
「お疲れさまです、伊織先輩」
「おう。今日もありがとな……うわ、すげぇ雨」
「あー、風もかなり強いですね」
バイト終わり。裏口から外に出るとバケツをひっくり返したような雨が降っていた。
傘をさしていても、数歩歩いただけで、すでに靴やパンツの膝下はびしょびしょだ。
「バス、間に合いそうですか?」
「あー、ていうかこの雨だからな…。もしかしたら…」
9月もそろそろ終わりの今は、台風シーズン真っ只中。
今日も夜は暴風雨になるとニュースで言っていた。
店長の指示で予定より早く退勤となったが、すでに手遅れ感がある。
嫌な予感は当たるもので、スマホを確認した俺は、肩を落とした。
「バス運休になってるわ」
「え!冠水ですか?伊織先輩のアパート、二葉キャンパスの方って言ってましたもんね」
「あっちは坂が多いからな。千冬は一ノ宮キャンパスの近くって言ってたな?地下鉄だろ?そっちはまだ動いてるみてぇだぞ」
「……」
傘の中でもスマホの画面に雨粒が落ちる。
一刻も早く帰った方が良さそうだ。
スマホをポケットにしまい、千冬に手を振った。
「じゃ、俺は歩いて帰るわ。千冬も気をつけて帰れよ」
「え!?ちょ、ちょっと待ってください!」
カバンを掴まれ、ややよろけながら立ち止まる。
あぶねぇ。
振り返ると、千冬が、頬を赤くして俺を見つめていた。
「あの……、」
「?」
「その……」
「なんだよ?」
何を躊躇っているのか知らねぇけど、雨はどんどん強くなってきている。
帰り道の過酷さを想像し、げんなりしていると、とうとう千冬が口を開いた。
「良かったら……、うちに、泊まっていきません、か…?」
え、マジ?
助かる。