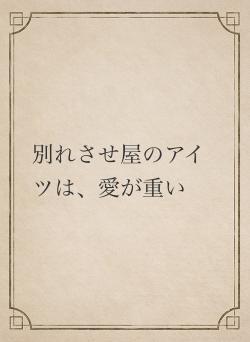葵ちゃんを知ったのは、4月に大学の体育館で開催した新歓ライブ。
新入生しかいない館内では、女の子たちが前方を占めていた。男の子たちは後方に散らばっていて、1番後ろの壁の前に数人で聴いていたのが葵ちゃんだ。
明るい照明での演奏と視力の良さのおかげで、遠くにいる葵ちゃんの顔もしっかり見ることができた。
いわゆる一目惚れだった。くしゃっとした笑顔、綺麗な目元、程よい厚みの唇、柔らかそうな茶色のストレート髪、少し華奢な身体…、一瞬で心を鷲掴みにされた。
ライブ後、控室に戻っても俺の頭の中は、葵ちゃんのことでいっぱいだった。
「どうしよう。めちゃくちゃ可愛い子に出逢っちゃった。ビビッと来たんだよ」
「ユズがそんなの言うの珍しいな。あ、もしかして前列にいた子?」
「ううん、1番後ろ」
「後ろ?……え、男?」
大きく頷いた俺に光たちは一瞬驚いたが、意外とあっさりした反応を見せた。
「ユズを射止めるとか、その男子めっちゃレアじゃん」
「モテるのに恋愛興味なしのゆずくんにやっと恋の季節が来たんだね!」
「女遊びしてそうな雰囲気出してるくせに、恋愛経験ほぼゼロだもんな、翠は」
それから光たちに協力してもらいながら、少しずつ葵ちゃんの情報を手に入れていった。
名前は能勢 葵。経営学科で、スポーツサークルに所属。高校の同級生である須藤くんと仲が良い。性格は見た目に反して男らしくて、楽しいことが好き。実家から通っていて、電車通学。彼女は…多分いない。
学科も学年も違うと構内でたまに見かけるくらいで、じっくり会うチャンスはほぼなかった。
接点を持てぬまま、季節は秋になろうとしていたある日。学園祭のライブ打ち合わせのため、実行委員会メンバーが待つ講義室へ4人で向かっていた。
隣の講義室の前を通った時、ちょうど声が聞こえて足を止めた。
「経営学科1年、能勢 葵です」
…えっ!
急いで室内を覗くと、そこには女装姿の能勢くんがいた。
ーうそ!やば…。
「お疲れ様でーす」
打ち合わせの講義室に入るとすぐに実行委員会に聞いた。
「あの、隣の部屋って何してるんですか?」
「あぁ、女装コンテストのオーディションですよ。オーディションで選ばれた学生が、初日のステージに参加するんです」
能勢くん、女装コンテストに出るかもなんだ。本人が志願したとは思えないから、誰かが推薦したんだろうな。推薦した人、ありがとう!
打ち合わせを終えて、部室に向かう途中。
「ちょー可愛いんだけど!!ねぇ、見た!?」
「はいはい、見た見た」
俺の興奮に反して、湊はいつも通り冷静な返しをしてくる。
「ほんとやばい。いつも可愛いけど、女の子の格好してる能勢くんの破壊力やばい!あんなの絶対グランプリじゃん」
「もし能勢っちがグランプリになったら、一緒に写真撮ってもらえばいいじゃん」
「光、それ名案!」
「ゔー振られたぁー…」
学園祭初日の夜、わっくんの家でテーブルに伏せて落ち込む俺に光たちが言葉をかける。
「あはは、人生初告白がダメだったか!」
「いきなり告白したら振られるに決まってるだろ」
「しかも相手は男子だしね。でも、連絡先交換できたんでしょ?」
「うん」
「写真は?撮ってもらえた?」
「それは大成功!見て!!」
能勢くんとの写真を自慢げに見せた。
「おぉーカップルみたいじゃん!能勢っち、ガチ女子だな」
「可愛いよね、ほんとかわいい」
「翠は結局、能勢くんに女子みたいな見た目してほしいわけ?」
「ううん、違う。能勢くんが女の子みたいにしてるから可愛いって思うだけで、俺はいつもの能勢くんが1番好きだから」
「へぇー」
学園祭2日目の夜にスポーツサークルの打ち上げに居合わせたのは、本当にたまたまだ。
「おい、なにお持ち帰りしてんの」
週明けの火曜日、湊は半分呆れながら注意してくる。
「え、だめだった?」
「いきなり能勢っちが帰って、ユズもいつもみたいに勝手に抜け出したと思ったら、まさかの連れ帰ってるんだもんな。…交流持てて嬉しいのは分かるけど、飛ばしすぎー」
「そーかなぁ」
「ゆずくんらしいっちゃらしいけどね」
「わっくん、優しー」
それからの俺は、早く葵ちゃんを独占したくて、あの手この手で必死にアピールをした。
知れば知るほど葵ちゃんへの想いは大きくなっていき、それに比例して真剣な気持ちは伝わっていると信じていた。
そして、2回目の仮デートの今日。良い雰囲気だと思っていたのに…
「柚原さんが好きなのは、女装した俺でしょ!?女の姿の俺が好きなだけじゃないっすか…」
「違う!そんなことないから」
「もういいっすよっ…俺、帰ります」
「待って、葵ちゃんっ…」
葵ちゃんは振り向くこともなく、走り去ってしまった。
「…。」
俺が女装姿の葵ちゃんだけを好きだと勘違いされているなんて全然知らなかった。
…初めて声を掛けたのが女装してる時だったし、最初のデートも気遣いのつもりで女装で来るのを提案したし、勘違いされてもおかしくないか…。
「えぇ…こーゆー時どうすればいいの…」
数日後、バンド練習前に自動販売機で飲み物を買っていると須藤くんがやってきた。
「あ、お疲れー」
「お疲れ様です」
いつもと違う雰囲気で俺を見ている。
「須藤くんもなんか飲む?奢るよー」
「いえ、大丈夫です。…あの、大人気の柚原さんにこんなこと言うのおこがましいんですけど…俺の能勢傷つけるのやめてもらえますか?」
「…どういう意味?」
「一昨日あいつ、泣いてたんで」
「えっ…」
「柚原さんと会ってた日ですよね?…何があったのか知らないですけど、他の男に泣かされるぐらいなら、俺が幸せにします」
「えっ…」
軽く会釈をした須藤くんは、それ以上何も言わず立ち去った。
俺が幸せにするって…もしかして須藤くん、葵ちゃんのこと…。ていうか、葵ちゃん泣いてたんだ…。
「え、なに。正式に振られたの?」
練習の合間に湊から葵ちゃんとの近況を聞かれ、一昨日の出来事をかいつまんで話した。
「だから昨日から元気ないんだ!」
光は心配しているとは思えないほど明るく言う。
「しかも、ライバルまで現れたんだけど…」
「ライバル?」
「いや、それはこっちの話」
「ゆずくんは、大事なことを言葉にしなかったりするから、そういう勘違いをされたのかもね」
わっくんはたまに、優しい口調で厳しいことを言う。
「ちゃんと好きとか、可愛いとか伝えたよ?」
「そうじゃなくて、能勢くんの不安を消すためには、もっと違う角度から伝えないとダメだと思う」
「違う角度…」
それから葵ちゃんに会うことなくクリスマスイブになり、大学は冬休みに入ろうとしていた。
「うー寒ーっ。能勢あっためてー」
「やだよ、カイロでも握っとけ」
クリスマスイブの今日は、年内最後の大学へ行き、夜は部員みんなでカラオケでクリスマスパーティーだ。
カラオケの室内にいるメンバーは、先輩の提案で男子は女装してサンタコス、女子はトナカイやツリーのコスプレをしている。
「やっぱり能勢が断トツで可愛いな!」
「いやいや、先輩には敵わないっすよー」
「おい!心がこもってねんだよ!」
「須藤も残念だったなー?女装の能勢とクリスマスデートするつもりが、自分も女装してさ」
「何言ってんすか。みんなと解散した後が、俺と葵ちゃんの時間ですから」
「あはは!能勢お持ち帰り決定だな!」
悪ノリする時の須藤は頭の回転が早い。
「よっしゃ!歌うぜー!!」
「いぇーい!」
3年の先輩が先陣を切り、マイク片手に歌い始める。
みんなでクリスマスソングを歌いまくって、好き勝手食べて喋って、わちゃわちゃふざけて、すげぇ楽しい時間なのに…何でだろ。ずっと頭の片隅に柚原さんがいる。
「次集まるのは、新年会だな!みんな良いお年をー!」
部長たちと少し早い年末の挨拶を交わし、カラオケの前で解散した。
「能勢、帰ろうぜー」
「おぉ」
俺たち男子は私服に着替えたが、ウィッグとメイク、サンタ帽はそのままだ。
「つーか、この格好で電車乗るの嫌なんだけど」
「イブの夜だし、何の問題もないだろ」
平気そうな須藤と駅に向かいながら自分の格好が恥ずかしくなる。
「…葵ちゃん?」
ーあっ…。
駅の入り口前で鉢合わせのは、あの日から会っていなかった柚原さん。
「…。」
よりによって女装してる時に会うなんて…。
「こんばんは、お疲れ様です」
気まずさで黙ったままの俺の代わりに須藤が挨拶をした。
「お疲れ。今日は須藤くんも女装してるんだ」
「はい。似合ってますか?」
「うん、葵ちゃんの次にね」
「…。」
「じゃあ俺たち、失礼しますね」
須藤は俺の肩を軽く抱き寄せ、駅に進もうとする。
「…待って」
ーえっ…。
柚原さんが俺の手首を握った。
「須藤くん、ごめん。葵ちゃんを幸せにするのは俺だから」
そう言い、俺を連れて走り始めた。
「えっ!?」
数分走り、公園の中で足を止めた。
「はぁ…はぁ…なんすかいきなり…」
「…はぁ…はぁ。走らせてごめん。……どうしても伝えたいことがあって…。寒いのに申し訳ないんだけど、座ってもらっていい?」
息を整えた柚原さんは、目を合わせられない俺を見ながらゆっくりと口を開いた。
「…学園祭の時、初めて会ったみたいな言い方しちゃったけど、本当は4月から葵ちゃんのこと知ってた」
「え…」
「一目惚れしたのも本当は4月で…ずっと声をかける機会を待ってた。…やっとあの日、目の前に葵ちゃんが現れて、前から知ってたのがバレるの恥ずかしくて、女装姿を好きになったみたいな言い方になっちゃったけど…俺は葵ちゃん自身がずっと好きだから」
「…。」
「関わるようになって、中身を知ったらもっともっと好きになって…。俺は…葵ちゃんそのものが大好きで付き合いたいと思ってるし、誰にも葵ちゃんのこと譲りたくないよ…」
いつもどこか余裕があって、飄々としている柚原さんとは思えないほど、不安そうな表情をしている。
好きと自覚した時からずっと不安だった。柚原さんみたいな完璧な人が、俺なんかを本気で好きなわけないって。弄ばれてるだけだって。
「……俺だって…柚原さんのこと誰にも譲りたくないっすよ。……本当に俺でいいんですか?」
色んな感情が溢れ出しそうで目が潤んでくる。
ぎゅっ…、柚原さんが強く俺を抱きしめた。
「葵ちゃんがいいんだってば。…だから、俺と付き合ってください」
その言葉に涙が頬を伝い、返事は涙声になる。
「…っ、よろしくおねがいします」
「どうしよう、めちゃくちゃ嬉しいんだけど」
抱きしめながら頭を優しく撫でられる俺の目には、まだ涙が溜まっている。
「葵ちゃんって、意外と泣き虫なんだねー」
「…柚原さんが泣かしてくるから」
「ごめんごめん。…この可愛い泣き顔も俺のものだけにするから、俺の前では好きなだけ泣いて」
いつもの調子に戻った柚原さんの顔を見つめた。
「…すげぇ会いたかったです」
「俺も…」
引かれ合うようにお互いの冷たい唇が重なる。
多分、このキスを俺は一生忘れないと思う。
新入生しかいない館内では、女の子たちが前方を占めていた。男の子たちは後方に散らばっていて、1番後ろの壁の前に数人で聴いていたのが葵ちゃんだ。
明るい照明での演奏と視力の良さのおかげで、遠くにいる葵ちゃんの顔もしっかり見ることができた。
いわゆる一目惚れだった。くしゃっとした笑顔、綺麗な目元、程よい厚みの唇、柔らかそうな茶色のストレート髪、少し華奢な身体…、一瞬で心を鷲掴みにされた。
ライブ後、控室に戻っても俺の頭の中は、葵ちゃんのことでいっぱいだった。
「どうしよう。めちゃくちゃ可愛い子に出逢っちゃった。ビビッと来たんだよ」
「ユズがそんなの言うの珍しいな。あ、もしかして前列にいた子?」
「ううん、1番後ろ」
「後ろ?……え、男?」
大きく頷いた俺に光たちは一瞬驚いたが、意外とあっさりした反応を見せた。
「ユズを射止めるとか、その男子めっちゃレアじゃん」
「モテるのに恋愛興味なしのゆずくんにやっと恋の季節が来たんだね!」
「女遊びしてそうな雰囲気出してるくせに、恋愛経験ほぼゼロだもんな、翠は」
それから光たちに協力してもらいながら、少しずつ葵ちゃんの情報を手に入れていった。
名前は能勢 葵。経営学科で、スポーツサークルに所属。高校の同級生である須藤くんと仲が良い。性格は見た目に反して男らしくて、楽しいことが好き。実家から通っていて、電車通学。彼女は…多分いない。
学科も学年も違うと構内でたまに見かけるくらいで、じっくり会うチャンスはほぼなかった。
接点を持てぬまま、季節は秋になろうとしていたある日。学園祭のライブ打ち合わせのため、実行委員会メンバーが待つ講義室へ4人で向かっていた。
隣の講義室の前を通った時、ちょうど声が聞こえて足を止めた。
「経営学科1年、能勢 葵です」
…えっ!
急いで室内を覗くと、そこには女装姿の能勢くんがいた。
ーうそ!やば…。
「お疲れ様でーす」
打ち合わせの講義室に入るとすぐに実行委員会に聞いた。
「あの、隣の部屋って何してるんですか?」
「あぁ、女装コンテストのオーディションですよ。オーディションで選ばれた学生が、初日のステージに参加するんです」
能勢くん、女装コンテストに出るかもなんだ。本人が志願したとは思えないから、誰かが推薦したんだろうな。推薦した人、ありがとう!
打ち合わせを終えて、部室に向かう途中。
「ちょー可愛いんだけど!!ねぇ、見た!?」
「はいはい、見た見た」
俺の興奮に反して、湊はいつも通り冷静な返しをしてくる。
「ほんとやばい。いつも可愛いけど、女の子の格好してる能勢くんの破壊力やばい!あんなの絶対グランプリじゃん」
「もし能勢っちがグランプリになったら、一緒に写真撮ってもらえばいいじゃん」
「光、それ名案!」
「ゔー振られたぁー…」
学園祭初日の夜、わっくんの家でテーブルに伏せて落ち込む俺に光たちが言葉をかける。
「あはは、人生初告白がダメだったか!」
「いきなり告白したら振られるに決まってるだろ」
「しかも相手は男子だしね。でも、連絡先交換できたんでしょ?」
「うん」
「写真は?撮ってもらえた?」
「それは大成功!見て!!」
能勢くんとの写真を自慢げに見せた。
「おぉーカップルみたいじゃん!能勢っち、ガチ女子だな」
「可愛いよね、ほんとかわいい」
「翠は結局、能勢くんに女子みたいな見た目してほしいわけ?」
「ううん、違う。能勢くんが女の子みたいにしてるから可愛いって思うだけで、俺はいつもの能勢くんが1番好きだから」
「へぇー」
学園祭2日目の夜にスポーツサークルの打ち上げに居合わせたのは、本当にたまたまだ。
「おい、なにお持ち帰りしてんの」
週明けの火曜日、湊は半分呆れながら注意してくる。
「え、だめだった?」
「いきなり能勢っちが帰って、ユズもいつもみたいに勝手に抜け出したと思ったら、まさかの連れ帰ってるんだもんな。…交流持てて嬉しいのは分かるけど、飛ばしすぎー」
「そーかなぁ」
「ゆずくんらしいっちゃらしいけどね」
「わっくん、優しー」
それからの俺は、早く葵ちゃんを独占したくて、あの手この手で必死にアピールをした。
知れば知るほど葵ちゃんへの想いは大きくなっていき、それに比例して真剣な気持ちは伝わっていると信じていた。
そして、2回目の仮デートの今日。良い雰囲気だと思っていたのに…
「柚原さんが好きなのは、女装した俺でしょ!?女の姿の俺が好きなだけじゃないっすか…」
「違う!そんなことないから」
「もういいっすよっ…俺、帰ります」
「待って、葵ちゃんっ…」
葵ちゃんは振り向くこともなく、走り去ってしまった。
「…。」
俺が女装姿の葵ちゃんだけを好きだと勘違いされているなんて全然知らなかった。
…初めて声を掛けたのが女装してる時だったし、最初のデートも気遣いのつもりで女装で来るのを提案したし、勘違いされてもおかしくないか…。
「えぇ…こーゆー時どうすればいいの…」
数日後、バンド練習前に自動販売機で飲み物を買っていると須藤くんがやってきた。
「あ、お疲れー」
「お疲れ様です」
いつもと違う雰囲気で俺を見ている。
「須藤くんもなんか飲む?奢るよー」
「いえ、大丈夫です。…あの、大人気の柚原さんにこんなこと言うのおこがましいんですけど…俺の能勢傷つけるのやめてもらえますか?」
「…どういう意味?」
「一昨日あいつ、泣いてたんで」
「えっ…」
「柚原さんと会ってた日ですよね?…何があったのか知らないですけど、他の男に泣かされるぐらいなら、俺が幸せにします」
「えっ…」
軽く会釈をした須藤くんは、それ以上何も言わず立ち去った。
俺が幸せにするって…もしかして須藤くん、葵ちゃんのこと…。ていうか、葵ちゃん泣いてたんだ…。
「え、なに。正式に振られたの?」
練習の合間に湊から葵ちゃんとの近況を聞かれ、一昨日の出来事をかいつまんで話した。
「だから昨日から元気ないんだ!」
光は心配しているとは思えないほど明るく言う。
「しかも、ライバルまで現れたんだけど…」
「ライバル?」
「いや、それはこっちの話」
「ゆずくんは、大事なことを言葉にしなかったりするから、そういう勘違いをされたのかもね」
わっくんはたまに、優しい口調で厳しいことを言う。
「ちゃんと好きとか、可愛いとか伝えたよ?」
「そうじゃなくて、能勢くんの不安を消すためには、もっと違う角度から伝えないとダメだと思う」
「違う角度…」
それから葵ちゃんに会うことなくクリスマスイブになり、大学は冬休みに入ろうとしていた。
「うー寒ーっ。能勢あっためてー」
「やだよ、カイロでも握っとけ」
クリスマスイブの今日は、年内最後の大学へ行き、夜は部員みんなでカラオケでクリスマスパーティーだ。
カラオケの室内にいるメンバーは、先輩の提案で男子は女装してサンタコス、女子はトナカイやツリーのコスプレをしている。
「やっぱり能勢が断トツで可愛いな!」
「いやいや、先輩には敵わないっすよー」
「おい!心がこもってねんだよ!」
「須藤も残念だったなー?女装の能勢とクリスマスデートするつもりが、自分も女装してさ」
「何言ってんすか。みんなと解散した後が、俺と葵ちゃんの時間ですから」
「あはは!能勢お持ち帰り決定だな!」
悪ノリする時の須藤は頭の回転が早い。
「よっしゃ!歌うぜー!!」
「いぇーい!」
3年の先輩が先陣を切り、マイク片手に歌い始める。
みんなでクリスマスソングを歌いまくって、好き勝手食べて喋って、わちゃわちゃふざけて、すげぇ楽しい時間なのに…何でだろ。ずっと頭の片隅に柚原さんがいる。
「次集まるのは、新年会だな!みんな良いお年をー!」
部長たちと少し早い年末の挨拶を交わし、カラオケの前で解散した。
「能勢、帰ろうぜー」
「おぉ」
俺たち男子は私服に着替えたが、ウィッグとメイク、サンタ帽はそのままだ。
「つーか、この格好で電車乗るの嫌なんだけど」
「イブの夜だし、何の問題もないだろ」
平気そうな須藤と駅に向かいながら自分の格好が恥ずかしくなる。
「…葵ちゃん?」
ーあっ…。
駅の入り口前で鉢合わせのは、あの日から会っていなかった柚原さん。
「…。」
よりによって女装してる時に会うなんて…。
「こんばんは、お疲れ様です」
気まずさで黙ったままの俺の代わりに須藤が挨拶をした。
「お疲れ。今日は須藤くんも女装してるんだ」
「はい。似合ってますか?」
「うん、葵ちゃんの次にね」
「…。」
「じゃあ俺たち、失礼しますね」
須藤は俺の肩を軽く抱き寄せ、駅に進もうとする。
「…待って」
ーえっ…。
柚原さんが俺の手首を握った。
「須藤くん、ごめん。葵ちゃんを幸せにするのは俺だから」
そう言い、俺を連れて走り始めた。
「えっ!?」
数分走り、公園の中で足を止めた。
「はぁ…はぁ…なんすかいきなり…」
「…はぁ…はぁ。走らせてごめん。……どうしても伝えたいことがあって…。寒いのに申し訳ないんだけど、座ってもらっていい?」
息を整えた柚原さんは、目を合わせられない俺を見ながらゆっくりと口を開いた。
「…学園祭の時、初めて会ったみたいな言い方しちゃったけど、本当は4月から葵ちゃんのこと知ってた」
「え…」
「一目惚れしたのも本当は4月で…ずっと声をかける機会を待ってた。…やっとあの日、目の前に葵ちゃんが現れて、前から知ってたのがバレるの恥ずかしくて、女装姿を好きになったみたいな言い方になっちゃったけど…俺は葵ちゃん自身がずっと好きだから」
「…。」
「関わるようになって、中身を知ったらもっともっと好きになって…。俺は…葵ちゃんそのものが大好きで付き合いたいと思ってるし、誰にも葵ちゃんのこと譲りたくないよ…」
いつもどこか余裕があって、飄々としている柚原さんとは思えないほど、不安そうな表情をしている。
好きと自覚した時からずっと不安だった。柚原さんみたいな完璧な人が、俺なんかを本気で好きなわけないって。弄ばれてるだけだって。
「……俺だって…柚原さんのこと誰にも譲りたくないっすよ。……本当に俺でいいんですか?」
色んな感情が溢れ出しそうで目が潤んでくる。
ぎゅっ…、柚原さんが強く俺を抱きしめた。
「葵ちゃんがいいんだってば。…だから、俺と付き合ってください」
その言葉に涙が頬を伝い、返事は涙声になる。
「…っ、よろしくおねがいします」
「どうしよう、めちゃくちゃ嬉しいんだけど」
抱きしめながら頭を優しく撫でられる俺の目には、まだ涙が溜まっている。
「葵ちゃんって、意外と泣き虫なんだねー」
「…柚原さんが泣かしてくるから」
「ごめんごめん。…この可愛い泣き顔も俺のものだけにするから、俺の前では好きなだけ泣いて」
いつもの調子に戻った柚原さんの顔を見つめた。
「…すげぇ会いたかったです」
「俺も…」
引かれ合うようにお互いの冷たい唇が重なる。
多分、このキスを俺は一生忘れないと思う。