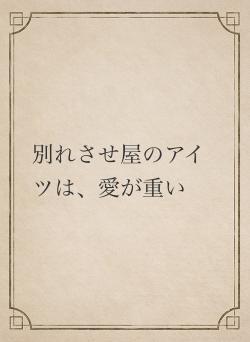「いらっしゃいませー」
ーあっ…。
土曜日の午後、バイト先のネットカフェに見覚えのある美女が現れた。
「女性専用って、まだ空いてますか?」
目の前にいるのは、ミスコングランプリの増田先輩。きっと俺のことは知らないだろうから、普通に接客するだけだけど。
「はい、ご案内可能です」
「よかった。じゃあ…あれ、あなたって女装グランプリの…」
え、嘘、まさか俺のこと分かんの!?
「あ、はい、1年の能勢です」
「びっくりしたぁ、ここでバイトしてるんだ」
「そうっす」
「私、よくここ利用するけど初めて見かけたわ」
「あ、常連なんすね!いつもありがとうございます!」
「ふふっ。能勢くん元気だね」
増田先輩の美女オーラは、ネカフェには場違いなレベルだった。
「…。」
増田先輩が柚原さんの隣にいるのは、自然に想像できる。もし増田先輩に告白されたら、柚原さんはどうすんだろ…。
「お疲れ様でした。失礼しまーす」
バイト終わりにスマホを確認すると柚原さんから連絡が入っていた。
『ゆっくり会いたいんだけど、来週の日曜日あいてる?』
…これは、デートのお誘い?
勝手に口元が緩む。柚原さんは、いつだってストレートに気持ちを伝えてくれる。俺はそれが恥ずかしくて、そして嬉しいと思っていることに最近気付いた。
「…何着てこっかな」
「能勢くん、おはよう」
月曜日の朝、大学の門を通ったところで、後ろから増田先輩がやって来た。
「あ、おはようございます」
「この前帰り際、能勢くんのこと探したけどいなかったよ」
「あー、夕方には上がったんで」
「そうなんだ。また行くと思うから、その時はよろしくね」
「了解っす。お待ちしてます!」
「ありがとう。じゃあ、また」
去り際まで華やかな人だなぁ…。
「おい、能勢!お前いつの間に増田先輩と親しくなってんだよっ!」
サークルの先輩が後ろから首に腕を回してきた。
「ゔー苦しいっす」
「能勢、まさか増田先輩狙ってんのか!?」
「は?狙ってないっすよ!」
「ま、狙ったところで無理だけどな。増田先輩、柚原と良い感じって噂だし」
ー…えっ。
「あの2人ならみんな納得するだろ」
「…。」
講義を受ける俺は、教授の話も聞かず上の空だ。
デートに誘われて浮かれていた気持ちは、一気に急降下。…いや、普通に考えて選ばれるのは俺じゃなくて、増田先輩だろ。分かってる、分かってたはずなのに、なんで俺はこんな気持ちになってんだ…。
「そういや、忘年会の返事した?」
知らない間に講義は終わっていて、隣に座る須藤の声で現実に引き戻された。
「忘年会?」
「高校メンバーのやつ。連絡来てたろ?」
「あー、まだ返事してねぇわ。須藤はしたの?」
「もちろん。能勢と行くって伝えた」
「おい、何勝手に俺連れて行ってんだよ」
「どうせ行くだろ?」
「…うん、後で返事しとく。ちょい飲み物買ってくる」
階段を降りていると、少し先に柚原さんと増田先輩の姿を見つけ、足を止めた。
「…。」
楽しそうに話す2人はカップルにしか見えなくて、増田先輩のポジションを自分に置き換えてみたけど、笑えるくらい似合わなかった。仮に女装姿の俺だったとしても、あんな風に絵になる2人にはなれないと痛感する。
それが悔しいのか、ショックなのか、何なのか、この感情がうまく言葉にできない。
水曜日の夕方、いつもよりサークルの時間が1時間遅くなった関係で、平賀、水森と空いてる講義室で時間を潰していた。ちなみに須藤は急きょバイトになり先に帰った。
「つーかさ、クリスマス須藤誘えば?」
「は!?無理無理!みんなでとはいえ、イブに一緒に過ごせるし、それで十分だよ」
「クリスマス午前中でバイト終わるから暇だって言ってたよ?」
「楓、何でそんなこと知ってんの!?」
「この前バスケの待機中に聞いた」
「ほら、チャンスだぞー」
「だって大学以外で2人きりで会ったことないし、いきなりクリスマスなんかに誘ったら怪しまれるじゃん!」
「それはそうかも…。じゃあ、クリスマス前に2人で会うのは?」
「無理に2人きりにならなくて大丈夫なのっ!それに…長期戦を覚悟して好きになったんだから」
「水森、俺らの心ちゃんがかっけーこと言ってんぞ」
「うんうん、健気で泣けてくるよ」
「もぉー馬鹿にしてんでしょー!そういう2人はどうなのよ!気になる人とかいないわけ!?」
「俺らは…なぁ?」
「…ねぇ?」
「何なのよ2人とも!」
「あはは」
「ねぇ」
体育館で、平賀と先輩のバドミントン試合を壁側に座って見ていると水森が話しかけてきた。
「ん、なに?」
「能勢、好きな人いるでしょ?」
「へっ!?」
水森は、私に隠し事はできませんよ?みたいな顔して見てきてる。
「…心理学科怖ぇ。……好きな人っつーか、うーん…好きになっていいのか分かんないみたいな?」
「他人のものなの?」
「いや、フリーの人。向こうから好きって言われて最初は戸惑ったんだけど、少しずつ気になり始めてさ。だけど、俺と違って手の届かない存在の人で、しかもさ…」
…水森になら言ってもいいか。
「相手は男だから…」
口に出した後、一瞬後悔しそうになりかけたが、間を空けることなく水森は言ってきた。
「手の届かない人って言ったけど、相手から好きって言われたなら、それはもう手が届いてるよ」
「え…」
「それにさ、好きになるのに男とか女とか関係ある?男だから迷うんじゃなくて、相手自身をしっかり見た上で迷うべきじゃない?」
水森の言葉にハッとした。見定めてって言われたのに、相手の立場や性別ばっか気にして、ちゃんと向き合ってなかった。
「…そだよな。水森、ありがと!」
柚原さん自身を好きかどうか、付き合いたいかどうか、そのことだけ考えればいいのか。
次の日の朝、講義室に入ると平賀が机に伏せる友達を慰めていた。
「そんな最低な男忘れたいよね、分かる。あー私までムカついてきた!」
「…どしたの?」
少しだけ距離を空けて座り、平賀に訊ねた。
「あ、おはよう。あのね、聞いて!華、良い感じの人がいてさ、その人が可愛いとか好きとか言ってきてて、そろそろ付き合う感じかと思ったら、まさかの他の女と付き合い始めたの!つまり、その女にもおんなじこと言って口説いてたわけ。最低じゃない!?」
「今思えば、人前では言われたことなかったの。メッセージや2人きりの時だけで、自分にだけ言われてるつもりでいたのがバカだった…」
「華は馬鹿じゃないよ!元気だしな!!」
いつもなら女って大変だなーと思って終わりだけど、今の俺には他人事じゃなかった。
だって、柚原さんが俺に好きとか可愛いとか言ってくるのは2人きりの時だけ。そうだよな、相手の甘い言葉が自分にだけしか言ってないなんて分かんねーよな!?…え、まさかの同時進行だったりする?
昼飯を食べ終えた俺は、寒さで誰もいない中庭のベンチで、ダウンを着てボーッと日向ぼっこをしていた。
頭の中は、昨日の水森の言葉や今朝の出来事、そして柚原さんのことがぐるぐる回っている。
「はぁー…」
俺、いつもどんな風に恋愛してたっけ?こんな考えて好きかどうか判断したことあったか?そもそも、あの告白の返事っていつすべきなわけ?
「なーにしんてんの」
目をつぶっていた俺の隣に座り、声をかけてきたのは須藤だ。
「…日向ぼっこ」
「俺もしよーっと…って、さみぃーよ!上着着てねーし」
「部屋に戻れ戻れ」
「はいはい。風邪引くなよー」
「うぃー」
須藤が立ち去り、再び目をつぶった。
…考えても無限ループだな。頭使い過ぎて眠くなってきたし。
ぴとっ…、ほっぺにほんのりあったかい缶が当たる。
「…えっ」
目を開けると目の前に柚原さんが立っていた。
「柚原さん!?」
「やっほー。お昼寝中?」
さっきの須藤よりも近い距離で隣に座ってくる。
「日向ぼっこです…」
「あはっ、可愛い答え」
…可愛い。その言葉は俺だけのものなのか…?
「これあげる」
ほっぺに当ててきたカフェオレを差し出した。
「ありがとうございます」
「今日の自販機のホットは、ぬるいのしか出ないらしい」
「そうなんすか?嫌がらせですね」
「だよねー。…あ、日曜なんだけど、買い物に付き合ってもらってもいい?」
「全然大丈夫ですよ」
「ありがと」
「…寒くないっすか?」
「んー寒いっ」
「…良かったら」
着ていたダウンを柚原さんの肩にかけた。
「え…」
珍しく驚いた顔を見せた柚原さんは、太ももに肘をつき両手で口元を隠した。その横顔は、頬がほんの少しピンクに染まって見えた。
「今のは、ずるいって…」
「…?」
「ありがとう。でも葵ちゃんは、寒くない?」
「さっきまで蓄えてた太陽の熱であったかいんで」
「あはは、それいいね」
…その嬉しそうな笑顔も俺だけに向けてくれてるのかな。そんなこと聞きたくても聞けねーよ…。
約束の日曜日の昼間、俺と柚原さんは大型ショッピングモール内を並んで歩いていた。
「どこもかしこもクリスマス一色だねー」
「そうっすね。俺、当日も好きですけど、このクリスマスを待つワクワクした雰囲気、結構好きなんすよねぇ」
「それ分かるかも。イブやクリスマス当日はバイトだっけ?」
「イブはサークルメンバーで集まって、クリスマスは、昼過ぎから夜までバイトです」
「そっか。俺もイブは夜までバイト」
2人でモール内の雑貨屋に入店した。
「いつもここのお店でルームフレグランス買ってるんだけど、そろそろ無くなりそうでさぁ」
へぇ。あの良い香りはもっと高級なとこで買ってんのかと思ってた。
「どの香りが好き?」
「え?」
「冬になったし、香り変えてみようと思って。せっかくなら葵ちゃんに選んでほしいなぁ」
テスターを俺に向けてくる。
「…分かりました」
今使ってる香りを除いた3種類を嗅ぎ比べた。
ーあ、この匂い好きかも。柚原さんに合いそうな気もする。
「これですかね」
俺の手にあるテスターを柚原さんもクンクンと嗅ぎ「うん、良い匂い」と嬉しそうに言った。
「葵ちゃんって、部屋にルームフレグランス置いてる?」
「置いてないっすね」
「そっか。じゃあ、俺買ってくるから向こうで待ってて」
「はい」
「お待たせー」
買い終えた柚原さんの手には2つ紙袋があり、片方を俺に渡してきた。
「はい!」
「…ん?」
「俺が今使ってる方。ちょっと早いけど、クリスマスプレゼント」
「えっ!?いやいや、そんな受け取れないっすよ!」
「そんな大したものじゃないし、受け取って」
どこまで出来る男なんだよ…。
「ありがとうございます。あの、俺も何かプレゼントしたいです」
「え、いいの?」
「はいっ!」
気を遣わなくて、でもプレゼントっぽいもの…。うーん、消耗品がいいよなぁ。…あ、そうだ。
「ボディーソープって、こだわりとかありますか?」
「ボディーソープ?いや、特にメーカーとかは決めてないかなぁ」
「じゃあ、あそこのボディショップで、好きなの選んでほしいです!」
店内に入ると、自分では買わない少しいい値段のするボディーソープがずらりと並んでいた。
「おー、いっぱいあるね」
「何系がいいですか?こっちは爽やかな感じで、そっちのは甘い系っすね」
「せっかくだし一緒に選ぼうよ。葵ちゃんも使うことあるだろうし」
…ん?俺が使う…?それはつまり…俺が柚原さん家の風呂に入るってこと!?
「あ、この匂い良いかも。葵ちゃん、どう?」
「え、あ、いいっすね」
「お互い香りに関するものプレゼントし合ったねぇ。今から使うのが楽しみー」
「今年最速のクリスマスプレゼントっすね」
「だね。…モール出たあたりに美味しい洋食屋があるんだけど、夜ご飯にどう?」
「大賛成です!」
モールを出るため出入り口に向かい歩き出した。
「あのダッフルコート似合いそう」
歩きながら柚原さんが指差した先には、アパレルショップの店頭に置かれた女のマネキンが、ベージュのコートを着ていた。
「葵ちゃんが着たら絶対可愛いよ」
「…。」
…柚原さんって、俺の中身好きなのかな?いつも可愛いとか言ってくれるけど、それは見た目に対してのことだし。柚原さんの目に映る俺は、初めて話した日の女装姿のままなんだろうな…。
それに…俺は気付いている。今日は一度も手を繋いでいない。前にデートした時は、ずっと繋いでたのに。
…きっと女装していないからだ。男の姿の俺なんかと手繋ぎたくないよな。…俺は柚原さん自身を見ようとしてんのに、先に好きって言ってきたくせに、柚原さんは俺自身を全然見てくんねーじゃん。
あぁ、こんなきっかけで気付くなんて嫌になる。…俺、柚原さんが好きなんだ。
外は一段と寒くなっていた。
「夜はやっぱ冷えるねぇ。寒くない?」
「大丈夫です…」
「良かったらコレ使って」
自分のマフラーを俺の首にかけようとする柚原さんの手を振り払うように止めた。
「…女の子扱いしないでください。…俺は男です」
「え…分かってるよ?だけど、寒いと思って…」
「女だと思ってるから優しくしてるんすか…」
「何言ってんの。葵ちゃんのことが好きだから…っ」
「柚原さんが好きなのは、女装した俺でしょ!?女の姿の俺が好きなだけじゃないっすか…」
「違う!そんなことないから」
「もういいっすよっ…俺、帰ります」
「待って、葵ちゃんっ…」
掴まれた手を振り払い、走り出した。
寒さも忘れて走っていたら、イルミネーションが施された街路樹に着いた。
脇にあるベンチに腰掛けた俺は下を向き、寒さと涙で鼻をすする。
「…ぐずっ…」
こんなことで泣くとか俺、ダセェな…。
「能勢…?」
顔を上げるとバイト終わりであろう須藤が偶然通りかかった。
「…須藤」
「え、泣いてる!?」
「…すとぉーっ!!」
須藤の顔を見たら安心して、思わず抱きついた。驚いているはずの須藤は、初めて見る俺の涙に何かを察したのか、馬鹿にすることもなく、頭をぽんぽんしながら受け止めてくれた。
あぁ…俺、何やってんだろ…。
ーあっ…。
土曜日の午後、バイト先のネットカフェに見覚えのある美女が現れた。
「女性専用って、まだ空いてますか?」
目の前にいるのは、ミスコングランプリの増田先輩。きっと俺のことは知らないだろうから、普通に接客するだけだけど。
「はい、ご案内可能です」
「よかった。じゃあ…あれ、あなたって女装グランプリの…」
え、嘘、まさか俺のこと分かんの!?
「あ、はい、1年の能勢です」
「びっくりしたぁ、ここでバイトしてるんだ」
「そうっす」
「私、よくここ利用するけど初めて見かけたわ」
「あ、常連なんすね!いつもありがとうございます!」
「ふふっ。能勢くん元気だね」
増田先輩の美女オーラは、ネカフェには場違いなレベルだった。
「…。」
増田先輩が柚原さんの隣にいるのは、自然に想像できる。もし増田先輩に告白されたら、柚原さんはどうすんだろ…。
「お疲れ様でした。失礼しまーす」
バイト終わりにスマホを確認すると柚原さんから連絡が入っていた。
『ゆっくり会いたいんだけど、来週の日曜日あいてる?』
…これは、デートのお誘い?
勝手に口元が緩む。柚原さんは、いつだってストレートに気持ちを伝えてくれる。俺はそれが恥ずかしくて、そして嬉しいと思っていることに最近気付いた。
「…何着てこっかな」
「能勢くん、おはよう」
月曜日の朝、大学の門を通ったところで、後ろから増田先輩がやって来た。
「あ、おはようございます」
「この前帰り際、能勢くんのこと探したけどいなかったよ」
「あー、夕方には上がったんで」
「そうなんだ。また行くと思うから、その時はよろしくね」
「了解っす。お待ちしてます!」
「ありがとう。じゃあ、また」
去り際まで華やかな人だなぁ…。
「おい、能勢!お前いつの間に増田先輩と親しくなってんだよっ!」
サークルの先輩が後ろから首に腕を回してきた。
「ゔー苦しいっす」
「能勢、まさか増田先輩狙ってんのか!?」
「は?狙ってないっすよ!」
「ま、狙ったところで無理だけどな。増田先輩、柚原と良い感じって噂だし」
ー…えっ。
「あの2人ならみんな納得するだろ」
「…。」
講義を受ける俺は、教授の話も聞かず上の空だ。
デートに誘われて浮かれていた気持ちは、一気に急降下。…いや、普通に考えて選ばれるのは俺じゃなくて、増田先輩だろ。分かってる、分かってたはずなのに、なんで俺はこんな気持ちになってんだ…。
「そういや、忘年会の返事した?」
知らない間に講義は終わっていて、隣に座る須藤の声で現実に引き戻された。
「忘年会?」
「高校メンバーのやつ。連絡来てたろ?」
「あー、まだ返事してねぇわ。須藤はしたの?」
「もちろん。能勢と行くって伝えた」
「おい、何勝手に俺連れて行ってんだよ」
「どうせ行くだろ?」
「…うん、後で返事しとく。ちょい飲み物買ってくる」
階段を降りていると、少し先に柚原さんと増田先輩の姿を見つけ、足を止めた。
「…。」
楽しそうに話す2人はカップルにしか見えなくて、増田先輩のポジションを自分に置き換えてみたけど、笑えるくらい似合わなかった。仮に女装姿の俺だったとしても、あんな風に絵になる2人にはなれないと痛感する。
それが悔しいのか、ショックなのか、何なのか、この感情がうまく言葉にできない。
水曜日の夕方、いつもよりサークルの時間が1時間遅くなった関係で、平賀、水森と空いてる講義室で時間を潰していた。ちなみに須藤は急きょバイトになり先に帰った。
「つーかさ、クリスマス須藤誘えば?」
「は!?無理無理!みんなでとはいえ、イブに一緒に過ごせるし、それで十分だよ」
「クリスマス午前中でバイト終わるから暇だって言ってたよ?」
「楓、何でそんなこと知ってんの!?」
「この前バスケの待機中に聞いた」
「ほら、チャンスだぞー」
「だって大学以外で2人きりで会ったことないし、いきなりクリスマスなんかに誘ったら怪しまれるじゃん!」
「それはそうかも…。じゃあ、クリスマス前に2人で会うのは?」
「無理に2人きりにならなくて大丈夫なのっ!それに…長期戦を覚悟して好きになったんだから」
「水森、俺らの心ちゃんがかっけーこと言ってんぞ」
「うんうん、健気で泣けてくるよ」
「もぉー馬鹿にしてんでしょー!そういう2人はどうなのよ!気になる人とかいないわけ!?」
「俺らは…なぁ?」
「…ねぇ?」
「何なのよ2人とも!」
「あはは」
「ねぇ」
体育館で、平賀と先輩のバドミントン試合を壁側に座って見ていると水森が話しかけてきた。
「ん、なに?」
「能勢、好きな人いるでしょ?」
「へっ!?」
水森は、私に隠し事はできませんよ?みたいな顔して見てきてる。
「…心理学科怖ぇ。……好きな人っつーか、うーん…好きになっていいのか分かんないみたいな?」
「他人のものなの?」
「いや、フリーの人。向こうから好きって言われて最初は戸惑ったんだけど、少しずつ気になり始めてさ。だけど、俺と違って手の届かない存在の人で、しかもさ…」
…水森になら言ってもいいか。
「相手は男だから…」
口に出した後、一瞬後悔しそうになりかけたが、間を空けることなく水森は言ってきた。
「手の届かない人って言ったけど、相手から好きって言われたなら、それはもう手が届いてるよ」
「え…」
「それにさ、好きになるのに男とか女とか関係ある?男だから迷うんじゃなくて、相手自身をしっかり見た上で迷うべきじゃない?」
水森の言葉にハッとした。見定めてって言われたのに、相手の立場や性別ばっか気にして、ちゃんと向き合ってなかった。
「…そだよな。水森、ありがと!」
柚原さん自身を好きかどうか、付き合いたいかどうか、そのことだけ考えればいいのか。
次の日の朝、講義室に入ると平賀が机に伏せる友達を慰めていた。
「そんな最低な男忘れたいよね、分かる。あー私までムカついてきた!」
「…どしたの?」
少しだけ距離を空けて座り、平賀に訊ねた。
「あ、おはよう。あのね、聞いて!華、良い感じの人がいてさ、その人が可愛いとか好きとか言ってきてて、そろそろ付き合う感じかと思ったら、まさかの他の女と付き合い始めたの!つまり、その女にもおんなじこと言って口説いてたわけ。最低じゃない!?」
「今思えば、人前では言われたことなかったの。メッセージや2人きりの時だけで、自分にだけ言われてるつもりでいたのがバカだった…」
「華は馬鹿じゃないよ!元気だしな!!」
いつもなら女って大変だなーと思って終わりだけど、今の俺には他人事じゃなかった。
だって、柚原さんが俺に好きとか可愛いとか言ってくるのは2人きりの時だけ。そうだよな、相手の甘い言葉が自分にだけしか言ってないなんて分かんねーよな!?…え、まさかの同時進行だったりする?
昼飯を食べ終えた俺は、寒さで誰もいない中庭のベンチで、ダウンを着てボーッと日向ぼっこをしていた。
頭の中は、昨日の水森の言葉や今朝の出来事、そして柚原さんのことがぐるぐる回っている。
「はぁー…」
俺、いつもどんな風に恋愛してたっけ?こんな考えて好きかどうか判断したことあったか?そもそも、あの告白の返事っていつすべきなわけ?
「なーにしんてんの」
目をつぶっていた俺の隣に座り、声をかけてきたのは須藤だ。
「…日向ぼっこ」
「俺もしよーっと…って、さみぃーよ!上着着てねーし」
「部屋に戻れ戻れ」
「はいはい。風邪引くなよー」
「うぃー」
須藤が立ち去り、再び目をつぶった。
…考えても無限ループだな。頭使い過ぎて眠くなってきたし。
ぴとっ…、ほっぺにほんのりあったかい缶が当たる。
「…えっ」
目を開けると目の前に柚原さんが立っていた。
「柚原さん!?」
「やっほー。お昼寝中?」
さっきの須藤よりも近い距離で隣に座ってくる。
「日向ぼっこです…」
「あはっ、可愛い答え」
…可愛い。その言葉は俺だけのものなのか…?
「これあげる」
ほっぺに当ててきたカフェオレを差し出した。
「ありがとうございます」
「今日の自販機のホットは、ぬるいのしか出ないらしい」
「そうなんすか?嫌がらせですね」
「だよねー。…あ、日曜なんだけど、買い物に付き合ってもらってもいい?」
「全然大丈夫ですよ」
「ありがと」
「…寒くないっすか?」
「んー寒いっ」
「…良かったら」
着ていたダウンを柚原さんの肩にかけた。
「え…」
珍しく驚いた顔を見せた柚原さんは、太ももに肘をつき両手で口元を隠した。その横顔は、頬がほんの少しピンクに染まって見えた。
「今のは、ずるいって…」
「…?」
「ありがとう。でも葵ちゃんは、寒くない?」
「さっきまで蓄えてた太陽の熱であったかいんで」
「あはは、それいいね」
…その嬉しそうな笑顔も俺だけに向けてくれてるのかな。そんなこと聞きたくても聞けねーよ…。
約束の日曜日の昼間、俺と柚原さんは大型ショッピングモール内を並んで歩いていた。
「どこもかしこもクリスマス一色だねー」
「そうっすね。俺、当日も好きですけど、このクリスマスを待つワクワクした雰囲気、結構好きなんすよねぇ」
「それ分かるかも。イブやクリスマス当日はバイトだっけ?」
「イブはサークルメンバーで集まって、クリスマスは、昼過ぎから夜までバイトです」
「そっか。俺もイブは夜までバイト」
2人でモール内の雑貨屋に入店した。
「いつもここのお店でルームフレグランス買ってるんだけど、そろそろ無くなりそうでさぁ」
へぇ。あの良い香りはもっと高級なとこで買ってんのかと思ってた。
「どの香りが好き?」
「え?」
「冬になったし、香り変えてみようと思って。せっかくなら葵ちゃんに選んでほしいなぁ」
テスターを俺に向けてくる。
「…分かりました」
今使ってる香りを除いた3種類を嗅ぎ比べた。
ーあ、この匂い好きかも。柚原さんに合いそうな気もする。
「これですかね」
俺の手にあるテスターを柚原さんもクンクンと嗅ぎ「うん、良い匂い」と嬉しそうに言った。
「葵ちゃんって、部屋にルームフレグランス置いてる?」
「置いてないっすね」
「そっか。じゃあ、俺買ってくるから向こうで待ってて」
「はい」
「お待たせー」
買い終えた柚原さんの手には2つ紙袋があり、片方を俺に渡してきた。
「はい!」
「…ん?」
「俺が今使ってる方。ちょっと早いけど、クリスマスプレゼント」
「えっ!?いやいや、そんな受け取れないっすよ!」
「そんな大したものじゃないし、受け取って」
どこまで出来る男なんだよ…。
「ありがとうございます。あの、俺も何かプレゼントしたいです」
「え、いいの?」
「はいっ!」
気を遣わなくて、でもプレゼントっぽいもの…。うーん、消耗品がいいよなぁ。…あ、そうだ。
「ボディーソープって、こだわりとかありますか?」
「ボディーソープ?いや、特にメーカーとかは決めてないかなぁ」
「じゃあ、あそこのボディショップで、好きなの選んでほしいです!」
店内に入ると、自分では買わない少しいい値段のするボディーソープがずらりと並んでいた。
「おー、いっぱいあるね」
「何系がいいですか?こっちは爽やかな感じで、そっちのは甘い系っすね」
「せっかくだし一緒に選ぼうよ。葵ちゃんも使うことあるだろうし」
…ん?俺が使う…?それはつまり…俺が柚原さん家の風呂に入るってこと!?
「あ、この匂い良いかも。葵ちゃん、どう?」
「え、あ、いいっすね」
「お互い香りに関するものプレゼントし合ったねぇ。今から使うのが楽しみー」
「今年最速のクリスマスプレゼントっすね」
「だね。…モール出たあたりに美味しい洋食屋があるんだけど、夜ご飯にどう?」
「大賛成です!」
モールを出るため出入り口に向かい歩き出した。
「あのダッフルコート似合いそう」
歩きながら柚原さんが指差した先には、アパレルショップの店頭に置かれた女のマネキンが、ベージュのコートを着ていた。
「葵ちゃんが着たら絶対可愛いよ」
「…。」
…柚原さんって、俺の中身好きなのかな?いつも可愛いとか言ってくれるけど、それは見た目に対してのことだし。柚原さんの目に映る俺は、初めて話した日の女装姿のままなんだろうな…。
それに…俺は気付いている。今日は一度も手を繋いでいない。前にデートした時は、ずっと繋いでたのに。
…きっと女装していないからだ。男の姿の俺なんかと手繋ぎたくないよな。…俺は柚原さん自身を見ようとしてんのに、先に好きって言ってきたくせに、柚原さんは俺自身を全然見てくんねーじゃん。
あぁ、こんなきっかけで気付くなんて嫌になる。…俺、柚原さんが好きなんだ。
外は一段と寒くなっていた。
「夜はやっぱ冷えるねぇ。寒くない?」
「大丈夫です…」
「良かったらコレ使って」
自分のマフラーを俺の首にかけようとする柚原さんの手を振り払うように止めた。
「…女の子扱いしないでください。…俺は男です」
「え…分かってるよ?だけど、寒いと思って…」
「女だと思ってるから優しくしてるんすか…」
「何言ってんの。葵ちゃんのことが好きだから…っ」
「柚原さんが好きなのは、女装した俺でしょ!?女の姿の俺が好きなだけじゃないっすか…」
「違う!そんなことないから」
「もういいっすよっ…俺、帰ります」
「待って、葵ちゃんっ…」
掴まれた手を振り払い、走り出した。
寒さも忘れて走っていたら、イルミネーションが施された街路樹に着いた。
脇にあるベンチに腰掛けた俺は下を向き、寒さと涙で鼻をすする。
「…ぐずっ…」
こんなことで泣くとか俺、ダセェな…。
「能勢…?」
顔を上げるとバイト終わりであろう須藤が偶然通りかかった。
「…須藤」
「え、泣いてる!?」
「…すとぉーっ!!」
須藤の顔を見たら安心して、思わず抱きついた。驚いているはずの須藤は、初めて見る俺の涙に何かを察したのか、馬鹿にすることもなく、頭をぽんぽんしながら受け止めてくれた。
あぁ…俺、何やってんだろ…。