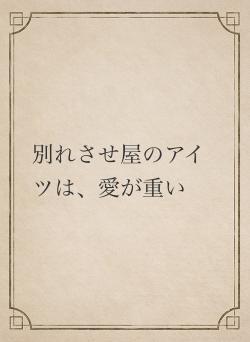「いつの間にライブチケット貰うほど仲良くなったわけ?」
月末の金曜日。大学を出てライブハウスに向かう途中、須藤は俺と柚原さんの関係を不思議そうに聞いてくる。
「うーん…俺にもよく分かんねぇ」
「なんだそれ」
開演5分前ギリギリにライブハウスに着くと、中にはたくさんの人がいた。見た感じ女性が7割くらいを占めている。俺と須藤は1番後ろで見ることにした。
「平賀と水森も来てるはずなんだけど、ぱっと見いねーな」
「どうせ前の方だろ。後で終わったら出口で待ってみようぜ」
開演時間になり、4人がステージに登場すると歓声が飛び交う。大学の体育館とは違い、本格的なステージに立つ4人は、本当の芸能人みたいに輝いて見えた。
「みなさん、こんばんはー!nextでーす!」
ステージ左側に立つ乙倉さんがMCを始める。
「今日は俺たちのライブに来てくれてありがとう!外は寒いけど、今夜はアツい時間にできたらと思ってるんで、みんな一緒に盛り上がっていきましょう!!」
1曲目から会場内は熱気に包まれる。ステージの真ん中で歌う柚原さんは、カッコ良さと色気が倍増していて、目が離せなかった。…胸の奥がずっとドキドキしてる。
「あと残り2曲なんだけど、その前に今夜は…特別にユズが弾き語りしまーす!!」
ーえっ…。
乙倉さんの発言に会場内のファンたちは、驚きと喜びの悲鳴を上げている。メンバーたちは一度ステージから離れた。
「柚原さんピアノ弾けるんだな」
「あ…うん、すげぇな」
スタッフによりステージにキーボードが設置され、柚原さんがヒラヒラと手を振りながらステージに出てきた。
「えーっと、久々の弾き語りだから緊張してるんだけど…頑張るね」
キーボードを弾き始めた柚原さんは、さっきまでと違う優しく柔らかい声で歌い出す。
歌っているのは、好きで好きで仕方ない、必ず幸せにするからぼくのところへ来てよ、という男目線の一途な片想いの曲。
「…。」
今そんなの歌われたら…俺に向けて歌ってるって思うじゃん。俺のこと想って歌ってるって思うじゃん。…まじ何なんだよ…こんなのずりぃって…。
ライブが終わり、須藤と出口付近で平賀たちを待っていると着信が鳴った。柚原さんの名前が表示されている。
「…もしもし?」
「葵ちゃん、もう帰っちゃった?」
「いや、まだ出口んとこいますけど…」
「一旦1人で中に戻って来れる?」
「え、あーはい…」
電話を切ったタイミングで平賀と水森が俺たちに気付いた。
「あ、お疲れー!」
「おつー」
「やっぱ外は寒いねー。これから楓とファミレス行くけど、2人も行く?」
「腹減ったし行こうかな。能勢も行くだろ?」
「うん、行く。でも、先行っといて」
「分かった。須藤、行こう」
「あ、うん…」
中に戻ると観客席側に柚原さんが立っていた。
「お疲れ様です」
「お疲れー」
「あれ、乙倉さんたちは?」
「楽屋で休んでる」
「そうっすか」
「今日来てくれてありがとね」
「いえ、こちらこそ招待してくれてありがとうございました。みなさん、むちゃくちゃかっこよかったです!」
「ありがとう。1番後ろにいたよね?」
「え、見えてたんすか!?」
「もちろん。遠くに居ても、好きな子は気づくもんでしょ?」
「…。」
好きな子…。
「…俺の気持ち伝わった?」
「えっ?」
「葵ちゃんに向けて弾いたんだけど」
あぁ、やっぱり俺への歌だったんだ。
俺の片手をそっと握った柚原さんは身体を向けて、じっと見つめてきた。そして、弾き語りした歌のサビを小さな声でゆっくり口ずさんだ。
目の前で歌われ、どんな顔をすればいいのか分からず下を向いた。
「…。」
…!?
歌い終わった柚原さんに顎をくいっと持ち上げられ、目が合った。
「…来月デートしよ?」
「…はい」
…キスされるかと思った…。
「この後、光たちとご飯行くけど葵ちゃんも来る?」
「あ、いえ。須藤たちが待ってるんで」
「そっか。また大丈夫な日連絡して。じゃあ、今日はありがとー」
「分かりました。…失礼します」
ファミレスへ向かう俺の頭の中には、ライブで楽しそうに歌い、女子たちの声に笑顔で応える柚原さんの姿。そして、さっき目の前で口ずさんだ優しくて甘い歌声。
柚原さんの存在が、少しずつ俺の中に入ってくる。だけどそれを素直に認められず、気づかないフリをしてしまう。
水曜日、サークルに行く前に須藤と大学内のコンビニに寄った。
「すげーお腹空いてるけど、今いっぱい食ったら動けねぇよなー。今日フットサルの予定だし」
弁当棚の前で須藤は腕を組み悩んでいる。
「ゴレイロすればいいじゃん」
ゴレイロはフットサルのゴールキーパーのこと。
「なるほどな。じゃあ、ナポリタン買おーっと」
飲食可能なフリースペースで、ナポリタンを頬張る須藤に聞いてみた。
「須藤ってさー、どんな子がタイプだっけ?見た目とか性格とか」
「なんだよ、いきなり」
「いや、ふと気になって」
「んータイプ…気が合えば何でもありだけどなぁ。いきなり好きになるより、徐々に知って一緒にいるうちに好きになるから」
「へぇー」
つまり一緒にいる時間が長い方が有利ってことか。…平賀、可能性大じゃね?
「お前、聞いてきたくせに興味ない感じやめろ」
「興味ありありだって」
「そういう能勢は、タイプどんなのだよ」
「えー、俺?うーん…好きになった人がタイプだな」
「は!?その答えずりぃって!」
「あはは。んなことより早く食えよ、遅れるぞ」
大盛ナポリタンのせいで、まんまと体育館に着くのが遅れてしまった。
「すみません、遅くなりましたー」
シューズを履き、須藤と中に入った瞬間、空気感が違うことにすぐ気がついた。
ストレッチをするみんなの中に一際目立つ2人がいる。…柚原さんと乙倉さんだ。
「あ!能勢っちだぁー、お疲れー!」
「お疲れ様です!また来てくれたんすね」
「ライブも終わってひと段落ついたら、体動かしたくなってさ。湊たちは課題があるみたいだから、今日は2人でお邪魔しに来た!」
ーライブ…。
あのライブの日から俺に歌った曲が頭から離れない。何百人いたライブハウスで、柚原さんの目には俺しか映っていなかったんじゃないかって自惚れそうになった。
「今日は予告通りフットサルしまーす。3チーム総当たり戦でいこう」
部長の言葉に乙倉さんが反応した。
「ユズ得意じゃん。元サッカー部だもんな!」
あぁ、たしか中学の時サッカー部だったって、質問し合った日に言ってたな。
チーム分けの結果、柚原さんは水森のいるチーム、乙倉さんは平賀のいるチーム、俺は須藤と同じチームになった。
1回戦目は柚原さんと乙倉さんの対決になり、俺と須藤はコートの外へ移動し、スコアボードの横にそれぞれ立った。
柚原さんのボール捌きは、現役のサッカー部じゃないかと疑うレベルで上手かった。
そして、コートの中を楽しそうに駆け回る柚原さんの表情は、いつもより少年らしさがある。そんな柚原さんの姿をぼんやり眺めていた。
…ほんとずりぃよな。歌も上手くて、スポーツも出来て、顔も良くて。そんでそれを思う存分俺に見せつけてきて…。
つーか、カッコいいとこばっか見せられて、俺は何にも良いとこ見せれてないの不平等じゃね?
「…おい、能勢!」
「…んっ?」
「そっち点入ったぞ」
「あ、悪りぃ」
「もー葵ちゃんは俺がいないとダメなんだからー」
「あー頼りになる彼氏がいて幸せだなー」
棒読みの俺に須藤はスコアボードの後ろから腰をくすぐってきた。
「もっと心を込めろぉ!」
「あははっ、やめろって!」
「はい、そこのカップルイチャイチャしなーい!」
コート内から先輩が、戯れている俺たちを注意してくる。
「すんませーん」
須藤は謝りながらも笑顔だ。
コート内に視線を戻すと、たまたま柚原さんと目が合い、何か反応されるかと思ったけど、あっさりと目線を外された。
試合は柚原さんのいるチームが勝ち、2戦目は俺たちのチームと乙倉さんいるチームの戦い。コンビニで言っていた通り、須藤はゴレイロをすることになった。
試合の途中、相手チームの先輩がゴールに向かい勢いよく蹴ったボールが須藤の手に当たった。何故か須藤は手をグーにしていて、ドンピシャで当たったボールは弾かれ、2階部分に飛んでしまった。
「わー!めちゃ飛んだわー!」
「後で取りに行くから、もう一個のボール使って」
部長がボールを須藤に渡した。
「あざーっす」
終了時間になり、そこまで汗をかかなかったため着替えずに帰ることにした。みんなが荷物を取りに更衣室へ向かう中、最後の方にいた俺はふと思い出し、2階のボールを取りに階段へ。
階段を登り、2階に着いた瞬間照明が消えた。
ーえっ!?
もうみんな出たと思った誰かが、消してしまったのだろう。
想像よりも真っ暗な空間に驚きつつ、スマホのライトで足元を照らそうと思ったが、今日に限って荷物と一緒に置いてきてしまったことに気付き、絶望する。
「まじかよぉ…」
とりあえずボールが飛んだあたりに進んでみるか…。
歩き進もうとした時だ。暗闇の中にライトの光が差し込んだ。
ーえっ…
振り向くと同時に「葵ちゃんっ」と柚原さんの声がした。
「え、柚原さん!?」
暗闇に目が慣れ始め、柚原さんの姿を確認できた。
「大丈夫!?」
「だ、大丈夫っすけど、柚原さん何で…」
「葵ちゃんがボール取りに行ってるの分かって、追ってきたら電気消えちゃってさ、びっくりだよね」
「そうだったんすね。ボール先に拾いたいんで、ライトそのまま付けておいてもらっていいですか?」
「もちろん」
柚原さんのスマホで照らしてもらいながらボールの方へ進む。
「あ、あった」
「みんなボール飛んだの完全に忘れてたよね」
「ですね。もっかい照明付けるの面倒なんで、このまま倉庫にボール持っていこうと思います」
「りょかーい」
暗い倉庫に入り、ボールを戻した。
「柚原さんがいて良かったです。助かりました。じゃあ、みんなのとこ行きましょっ…」
ぎゅっ…
突然、柚原さんに抱きしめられた。運動後とは思えない、いつもと変わらない柚原さんの香りが暗闇の中を漂う。
「…柚原さん…?」
「俺ともイチャイチャしてよ…」
俺とも?…何のことだ?
言葉の意味がわからないが、声のトーンや言い方から拗ねているのがなんとなく理解できた。
つーか、イチャイチャってなんだ!?え、もしかして、キスしてくる感じ!?
身体に力の入った俺から腕を離し、そっと指を握ってきた。
「冷た…」
そう言って、俺の中指や薬指をゆっくり指でなぞってくる。その触り方がなんだかエロくて、キスされるよりも恥ずかしくなりそうだ。
「…どうする?一緒にここで一晩過ごしちゃう?」
「…。」
本気でないと分かっていても、ドキッとしてしまった。
絡まっていた指が解け、柚原さんの手が俺の頬に触れた時「能勢ー?いるー?」と外から須藤の声がした。
「…いるー!」
許可なしに返事をしてしまったけど、大丈夫だったか…?
チラッと柚原さんの顔を見ると目が合い、ふわっと笑みを浮かべた。
「…行こっか」
須藤たちと駅に向かう途中、倉庫での出来事を思い出す。須藤の声がした時、安心するよりもほんの少しだけ残念な気持ちが上回った気がした。
頬に触れた手はあの後どうするつもりだったんだろうか…。
月末の金曜日。大学を出てライブハウスに向かう途中、須藤は俺と柚原さんの関係を不思議そうに聞いてくる。
「うーん…俺にもよく分かんねぇ」
「なんだそれ」
開演5分前ギリギリにライブハウスに着くと、中にはたくさんの人がいた。見た感じ女性が7割くらいを占めている。俺と須藤は1番後ろで見ることにした。
「平賀と水森も来てるはずなんだけど、ぱっと見いねーな」
「どうせ前の方だろ。後で終わったら出口で待ってみようぜ」
開演時間になり、4人がステージに登場すると歓声が飛び交う。大学の体育館とは違い、本格的なステージに立つ4人は、本当の芸能人みたいに輝いて見えた。
「みなさん、こんばんはー!nextでーす!」
ステージ左側に立つ乙倉さんがMCを始める。
「今日は俺たちのライブに来てくれてありがとう!外は寒いけど、今夜はアツい時間にできたらと思ってるんで、みんな一緒に盛り上がっていきましょう!!」
1曲目から会場内は熱気に包まれる。ステージの真ん中で歌う柚原さんは、カッコ良さと色気が倍増していて、目が離せなかった。…胸の奥がずっとドキドキしてる。
「あと残り2曲なんだけど、その前に今夜は…特別にユズが弾き語りしまーす!!」
ーえっ…。
乙倉さんの発言に会場内のファンたちは、驚きと喜びの悲鳴を上げている。メンバーたちは一度ステージから離れた。
「柚原さんピアノ弾けるんだな」
「あ…うん、すげぇな」
スタッフによりステージにキーボードが設置され、柚原さんがヒラヒラと手を振りながらステージに出てきた。
「えーっと、久々の弾き語りだから緊張してるんだけど…頑張るね」
キーボードを弾き始めた柚原さんは、さっきまでと違う優しく柔らかい声で歌い出す。
歌っているのは、好きで好きで仕方ない、必ず幸せにするからぼくのところへ来てよ、という男目線の一途な片想いの曲。
「…。」
今そんなの歌われたら…俺に向けて歌ってるって思うじゃん。俺のこと想って歌ってるって思うじゃん。…まじ何なんだよ…こんなのずりぃって…。
ライブが終わり、須藤と出口付近で平賀たちを待っていると着信が鳴った。柚原さんの名前が表示されている。
「…もしもし?」
「葵ちゃん、もう帰っちゃった?」
「いや、まだ出口んとこいますけど…」
「一旦1人で中に戻って来れる?」
「え、あーはい…」
電話を切ったタイミングで平賀と水森が俺たちに気付いた。
「あ、お疲れー!」
「おつー」
「やっぱ外は寒いねー。これから楓とファミレス行くけど、2人も行く?」
「腹減ったし行こうかな。能勢も行くだろ?」
「うん、行く。でも、先行っといて」
「分かった。須藤、行こう」
「あ、うん…」
中に戻ると観客席側に柚原さんが立っていた。
「お疲れ様です」
「お疲れー」
「あれ、乙倉さんたちは?」
「楽屋で休んでる」
「そうっすか」
「今日来てくれてありがとね」
「いえ、こちらこそ招待してくれてありがとうございました。みなさん、むちゃくちゃかっこよかったです!」
「ありがとう。1番後ろにいたよね?」
「え、見えてたんすか!?」
「もちろん。遠くに居ても、好きな子は気づくもんでしょ?」
「…。」
好きな子…。
「…俺の気持ち伝わった?」
「えっ?」
「葵ちゃんに向けて弾いたんだけど」
あぁ、やっぱり俺への歌だったんだ。
俺の片手をそっと握った柚原さんは身体を向けて、じっと見つめてきた。そして、弾き語りした歌のサビを小さな声でゆっくり口ずさんだ。
目の前で歌われ、どんな顔をすればいいのか分からず下を向いた。
「…。」
…!?
歌い終わった柚原さんに顎をくいっと持ち上げられ、目が合った。
「…来月デートしよ?」
「…はい」
…キスされるかと思った…。
「この後、光たちとご飯行くけど葵ちゃんも来る?」
「あ、いえ。須藤たちが待ってるんで」
「そっか。また大丈夫な日連絡して。じゃあ、今日はありがとー」
「分かりました。…失礼します」
ファミレスへ向かう俺の頭の中には、ライブで楽しそうに歌い、女子たちの声に笑顔で応える柚原さんの姿。そして、さっき目の前で口ずさんだ優しくて甘い歌声。
柚原さんの存在が、少しずつ俺の中に入ってくる。だけどそれを素直に認められず、気づかないフリをしてしまう。
水曜日、サークルに行く前に須藤と大学内のコンビニに寄った。
「すげーお腹空いてるけど、今いっぱい食ったら動けねぇよなー。今日フットサルの予定だし」
弁当棚の前で須藤は腕を組み悩んでいる。
「ゴレイロすればいいじゃん」
ゴレイロはフットサルのゴールキーパーのこと。
「なるほどな。じゃあ、ナポリタン買おーっと」
飲食可能なフリースペースで、ナポリタンを頬張る須藤に聞いてみた。
「須藤ってさー、どんな子がタイプだっけ?見た目とか性格とか」
「なんだよ、いきなり」
「いや、ふと気になって」
「んータイプ…気が合えば何でもありだけどなぁ。いきなり好きになるより、徐々に知って一緒にいるうちに好きになるから」
「へぇー」
つまり一緒にいる時間が長い方が有利ってことか。…平賀、可能性大じゃね?
「お前、聞いてきたくせに興味ない感じやめろ」
「興味ありありだって」
「そういう能勢は、タイプどんなのだよ」
「えー、俺?うーん…好きになった人がタイプだな」
「は!?その答えずりぃって!」
「あはは。んなことより早く食えよ、遅れるぞ」
大盛ナポリタンのせいで、まんまと体育館に着くのが遅れてしまった。
「すみません、遅くなりましたー」
シューズを履き、須藤と中に入った瞬間、空気感が違うことにすぐ気がついた。
ストレッチをするみんなの中に一際目立つ2人がいる。…柚原さんと乙倉さんだ。
「あ!能勢っちだぁー、お疲れー!」
「お疲れ様です!また来てくれたんすね」
「ライブも終わってひと段落ついたら、体動かしたくなってさ。湊たちは課題があるみたいだから、今日は2人でお邪魔しに来た!」
ーライブ…。
あのライブの日から俺に歌った曲が頭から離れない。何百人いたライブハウスで、柚原さんの目には俺しか映っていなかったんじゃないかって自惚れそうになった。
「今日は予告通りフットサルしまーす。3チーム総当たり戦でいこう」
部長の言葉に乙倉さんが反応した。
「ユズ得意じゃん。元サッカー部だもんな!」
あぁ、たしか中学の時サッカー部だったって、質問し合った日に言ってたな。
チーム分けの結果、柚原さんは水森のいるチーム、乙倉さんは平賀のいるチーム、俺は須藤と同じチームになった。
1回戦目は柚原さんと乙倉さんの対決になり、俺と須藤はコートの外へ移動し、スコアボードの横にそれぞれ立った。
柚原さんのボール捌きは、現役のサッカー部じゃないかと疑うレベルで上手かった。
そして、コートの中を楽しそうに駆け回る柚原さんの表情は、いつもより少年らしさがある。そんな柚原さんの姿をぼんやり眺めていた。
…ほんとずりぃよな。歌も上手くて、スポーツも出来て、顔も良くて。そんでそれを思う存分俺に見せつけてきて…。
つーか、カッコいいとこばっか見せられて、俺は何にも良いとこ見せれてないの不平等じゃね?
「…おい、能勢!」
「…んっ?」
「そっち点入ったぞ」
「あ、悪りぃ」
「もー葵ちゃんは俺がいないとダメなんだからー」
「あー頼りになる彼氏がいて幸せだなー」
棒読みの俺に須藤はスコアボードの後ろから腰をくすぐってきた。
「もっと心を込めろぉ!」
「あははっ、やめろって!」
「はい、そこのカップルイチャイチャしなーい!」
コート内から先輩が、戯れている俺たちを注意してくる。
「すんませーん」
須藤は謝りながらも笑顔だ。
コート内に視線を戻すと、たまたま柚原さんと目が合い、何か反応されるかと思ったけど、あっさりと目線を外された。
試合は柚原さんのいるチームが勝ち、2戦目は俺たちのチームと乙倉さんいるチームの戦い。コンビニで言っていた通り、須藤はゴレイロをすることになった。
試合の途中、相手チームの先輩がゴールに向かい勢いよく蹴ったボールが須藤の手に当たった。何故か須藤は手をグーにしていて、ドンピシャで当たったボールは弾かれ、2階部分に飛んでしまった。
「わー!めちゃ飛んだわー!」
「後で取りに行くから、もう一個のボール使って」
部長がボールを須藤に渡した。
「あざーっす」
終了時間になり、そこまで汗をかかなかったため着替えずに帰ることにした。みんなが荷物を取りに更衣室へ向かう中、最後の方にいた俺はふと思い出し、2階のボールを取りに階段へ。
階段を登り、2階に着いた瞬間照明が消えた。
ーえっ!?
もうみんな出たと思った誰かが、消してしまったのだろう。
想像よりも真っ暗な空間に驚きつつ、スマホのライトで足元を照らそうと思ったが、今日に限って荷物と一緒に置いてきてしまったことに気付き、絶望する。
「まじかよぉ…」
とりあえずボールが飛んだあたりに進んでみるか…。
歩き進もうとした時だ。暗闇の中にライトの光が差し込んだ。
ーえっ…
振り向くと同時に「葵ちゃんっ」と柚原さんの声がした。
「え、柚原さん!?」
暗闇に目が慣れ始め、柚原さんの姿を確認できた。
「大丈夫!?」
「だ、大丈夫っすけど、柚原さん何で…」
「葵ちゃんがボール取りに行ってるの分かって、追ってきたら電気消えちゃってさ、びっくりだよね」
「そうだったんすね。ボール先に拾いたいんで、ライトそのまま付けておいてもらっていいですか?」
「もちろん」
柚原さんのスマホで照らしてもらいながらボールの方へ進む。
「あ、あった」
「みんなボール飛んだの完全に忘れてたよね」
「ですね。もっかい照明付けるの面倒なんで、このまま倉庫にボール持っていこうと思います」
「りょかーい」
暗い倉庫に入り、ボールを戻した。
「柚原さんがいて良かったです。助かりました。じゃあ、みんなのとこ行きましょっ…」
ぎゅっ…
突然、柚原さんに抱きしめられた。運動後とは思えない、いつもと変わらない柚原さんの香りが暗闇の中を漂う。
「…柚原さん…?」
「俺ともイチャイチャしてよ…」
俺とも?…何のことだ?
言葉の意味がわからないが、声のトーンや言い方から拗ねているのがなんとなく理解できた。
つーか、イチャイチャってなんだ!?え、もしかして、キスしてくる感じ!?
身体に力の入った俺から腕を離し、そっと指を握ってきた。
「冷た…」
そう言って、俺の中指や薬指をゆっくり指でなぞってくる。その触り方がなんだかエロくて、キスされるよりも恥ずかしくなりそうだ。
「…どうする?一緒にここで一晩過ごしちゃう?」
「…。」
本気でないと分かっていても、ドキッとしてしまった。
絡まっていた指が解け、柚原さんの手が俺の頬に触れた時「能勢ー?いるー?」と外から須藤の声がした。
「…いるー!」
許可なしに返事をしてしまったけど、大丈夫だったか…?
チラッと柚原さんの顔を見ると目が合い、ふわっと笑みを浮かべた。
「…行こっか」
須藤たちと駅に向かう途中、倉庫での出来事を思い出す。須藤の声がした時、安心するよりもほんの少しだけ残念な気持ちが上回った気がした。
頬に触れた手はあの後どうするつもりだったんだろうか…。