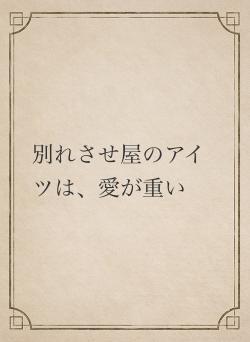土曜日の柚原さんとのデート中、甘い雰囲気を出され照れた俺は尋ねた。
「柚原さんは…」
「ん?」
「今まで男の人と付き合ったことって…あるんですか?」
「ないかなぁ」
会話を遮るように再び花火が打ち上がる。
やっぱ、男が好きってわけじゃないんだな。安心した。だって、この人の隣には見た目の良い女の子がいてほしいってみんな思ってる。俺だってそう思ってる。
「ほんとに家まで送んなくて大丈夫?」
「大丈夫です!」
駅のホームで電車を待つ俺を柚原さんは心配している。
「可愛い女の子が、夜道歩いてたら危ないよ?」
「いや、俺、男ですよ?それに電車降りたら着替えるんで」
「そっか。……これ、良かったら友達と来て」
2枚のチケットを手渡された。打ち上げで乙倉さんが言っていたライブだ。
「いやいや、タダで行くのは申し訳ないです」
「好きな子を招待できるのは、演者の特権だから。あ、電車来たよー」
走り出した電車の中から、ホームで手を振る柚原さんに振り返した。
最後の最後まで俺を女の子扱いする柚原さんは、優しさと気遣いの塊だった。あーこうすればモテるのかって勉強になるレベル。歩いている時は常に手を繋いで、人混みの中で守られている感覚になった。
スマホの通知が鳴る。
『今日はありがとう!家に着いたら連絡ちょーだい』
柚原さんの文面は、まるで彼氏だ。…そう、今日はただ遊ぶんじゃなくて、恋愛として、恋人としてありかどうかを考えるための日でもあったんだ。
そもそも、男を好きになったことねぇし、何を基準に決めればいいわけ?ドキドキは…したけど、イケメンにあんなことされたら誰だってドキドキすんだろ。
つーか、男同士で付き合うって、男女で付き合うのと何が違うんだっけ。え、待てよ。何も違わないんじゃね?デートはもちろん、キスとかそれ以上のことすんだよな…?柚原さんとキス…え、俺できる?
数日後、大学内は朝からいつもと雰囲気が違った。特に何かイベントがあるわけでもないのに、メイクや服装に気合いの入った女子だらけ。
ーあ、そうか今日は11月11日…。
廊下から外を見ると、人だかりができている。その中心にいるのは、柚原さん。
取り囲む女子たちはラッピングされたモノやお菓子を渡している。…そう、今日は柚原さんの誕生日。nextのメンバーの誕生日は、プレゼントや手紙を渡すため朝からお祭り騒ぎになる。初夏にあった乙倉さんの誕生日を初めて見た時は衝撃的だった。
「あれどうやって持って帰るんだろうな」
横に来た須藤は嫌味ではなく、純粋に疑問に思っている。
「俺らは一生経験しないな」
ちょっぴり惨めな気持ちになり、須藤と講義室に入っていく。
あんな風に誕生日を祝われる有名人みたいな人とデートしたなんて、今だに不思議で仕方ない。
ー俺、渡すタイミングあるかな…?
結局、朝以来柚原さんを見かけることもなく、帰る時間になった。
バイトあるし、練習終わるの待っとくのも無理だから、渡すの今度にするか。
廊下を歩いていると、階段を上っていく柚原さんの後ろ姿が見えて、急いで駆け寄った。
「柚原さんっ!」
「あ!葵ちゃんだ」
「お疲れ様です。…あの、お誕生日おめでとうございますっ!」
「覚えててくれたんだぁ。ありがとう」
「さすがに忘れないっすよ」
質問し合った夜、お互いの誕生日も知った。
「もう色んな人に貰ってると思うんすけど…良かったら」
今日の日付にちなんだお菓子を渡した。
「…えー嬉しい、ありがとぉ!」
笑顔を見せる柚原さんは、目の前で箱を開け始めた。そのまま階段に座り、隣に座るようジェスチャーで俺に指示をする。
「…?」
「俺、誕生日って何でもわがまま聞いてもらえるって思ってるんだよねぇ」
袋から1本取り出し、軽く口に咥えた柚原さんは、そのまま俺の方を向いた。
「ん」
軽く顔を突き出され、やっと意味が分かった。
…これ、お互い端から食べ進めて最後キスするやつじゃね!?…は?え!?
動揺する俺を早くと言わんばかりにじっと見つめてくる。菓子を咥えてるだけなのに、色気ダダ漏れな柚原さんを前にどんどん鼓動が早くなっていく…。
男同士のふざけたノリだと思えば全然いける…はず。うん、大丈夫…ドキドキすんな俺。
少し緊張しながら端を咥え、食べ始めた。ゆっくり柚原さんの顔が近づいてくる中、聞こえるのはお互いの咀嚼音だけ。
「…サクッ…」
あと数ミリで唇が重なる…。
「それでさー…」
突然人の声が聞こえ、急いで口を離した。
「…っ」
あっぶねぇ…。心臓止まるかと思った。
「残念…」
そう言った柚原さんは俺の手を持ち、一緒に立ち上がった。
「明日のサークル終わり時間ある?」
「ありますけど…」
「じゃあ、俺ん家来てよ。後で一応住所送っとく」
「え、あ、でも…」
「待ってるね…ちゅ」
ーえっ…
おでこにキスをされた俺は固まってしまい、柚原さんの「またね、葵ちゃん」にうまく返事ができなかった。
もしかして今、すげぇ攻められた?え、つーか、柚原さんは俺とキスしたいってこと?
翌日の夕方、体育館でバドミントンをする俺はソワソワしている。この後、俺は本当に柚原さんの家へ…。
「能勢、電車乗る前コンビニ寄っていい?」
「あ、悪りぃ。俺、この後寄るとこあって」
「そうなんだ」
大学の門で須藤たちと別れ、柚原さんの家に向かう。初めて行くわけじゃないのに、緊張しているのが何故なのか自分で分かってしまうから嫌だ。
一呼吸してインターホンを鳴らす。
「お疲れー。どーぞー」
玄関のドアを開けてくれた柚原さんは、いつもと変わらない様子だった。昨日のことを意識してんのは俺だけ…?
「お邪魔します…」
部屋に入ると、昨日貰ったであろう大量のプレゼントが置かれていた。
「すごい量っすね」
「お返しできるわけじゃないから申し訳ないんだけど、みんな優しいよね」
きっと連絡先と同じで、ファンの子達に何かあげるのはNGなんだろうな。
「つーか、この匂い…」
「さすがにバレるよねぇ。…一緒に食べようと思って、作ってみましたー」
テーブルの上のガスコンロに鍋が置かれている。蓋を開けるとキムチ鍋が出来上がっていた。
「わぁ!うまそー!」
「初挑戦だけど、上手くできた気がするんだよね。よし、食べよっ!」
「俺、よそいますよ」
取り皿に熱々の具を乗せる。
「ありがと。…いただきまーす」
「いただきますっ!…ん、うまっ」
「旨辛でおいしいね。…シメの希望ある?」
「米の気分ですけど、柚原さんは?」
「じゃあ、チーズ雑炊にしよっか」
「それ最高です!」
あっという間に鍋の中は空っぽになった。熱さと辛さで身体がずっとポカポカしている。
「めちゃくちゃ美味かったです!ごちそうさまでした!」
「いえいえー。得意料理キムチ鍋にしようかな」
「あはは、いいっすね!」
つーか、あちぃ…。パーカー脱ぎてぇけど、さすがにここじゃ無理だよな。
「暑くない?俺に遠慮せず脱いでいいからね。俺は脱ごーっと」
シャツを脱いだ柚原さんは半袖のTシャツ姿になり、脱ごうか迷ってるいる俺に「バンザイして」と言ってきた。
「えっ」
戸惑いながらバンザイすると、柚原さんがパーカーを脱がせてきた。お世話されてるみたいで恥ずかしくなる。
「鍋ご馳走してくれるために誘ってくれたんすか…?」
「それもあるけど…」
柚原さんは立ち上がり、プレゼントの山からお菓子を取ってきて、再び横に座った。
「昨日の続き…したいんだけど」
…え!?昨日の続き!?それって…つまり…。
柚原さんの口元に目線がいってしまう。
「…今度は葵ちゃんが先に咥えてよ」
1本差し出され、気持ちが追いつかないまま受け取った。
さっきまで楽しく鍋を食べていたのが嘘みたいに、目の前の柚原さんは甘い雰囲気を醸し出す。
「…。」
ゆっくり咥えると、柚原さんは口角を上げ、反対側を咥えた。邪魔の入らない2人きりの空間で、このゲームをするということは必ず…。
どんどん顔が近づいていく…。口ん中キムチ臭いけど大丈夫か!?いや、お互い様か。って、そんなこと考えてる間にもう…
…ちゅっ…
ーあ…。
唇が重なり、俺の鼓動は死ぬほど激しくなる。触れた唇は離れず、キスは終わらない。舌は入ってきてないものの、軽いキスを何回もされる。
「ちゅ…ちゅっ…」
そして、唇が離れると俺を抱きしめ、耳元で囁いた。
「…今日泊まってく?」
待って待って。これ…落としにきてんじゃん!
「…明日朝早いんで…帰ります…」
「絶対そう言うと思ったー」
腕を離した柚原さんは、残りのお菓子を食べ始めた。俺の口にも1本差し出し「終電までは一緒にいて」と妥協案を伝えてくる。
終電に間に合うようにここを出るまで2時間以上…。俺の心臓もつかな…。
「柚原さんは…」
「ん?」
「今まで男の人と付き合ったことって…あるんですか?」
「ないかなぁ」
会話を遮るように再び花火が打ち上がる。
やっぱ、男が好きってわけじゃないんだな。安心した。だって、この人の隣には見た目の良い女の子がいてほしいってみんな思ってる。俺だってそう思ってる。
「ほんとに家まで送んなくて大丈夫?」
「大丈夫です!」
駅のホームで電車を待つ俺を柚原さんは心配している。
「可愛い女の子が、夜道歩いてたら危ないよ?」
「いや、俺、男ですよ?それに電車降りたら着替えるんで」
「そっか。……これ、良かったら友達と来て」
2枚のチケットを手渡された。打ち上げで乙倉さんが言っていたライブだ。
「いやいや、タダで行くのは申し訳ないです」
「好きな子を招待できるのは、演者の特権だから。あ、電車来たよー」
走り出した電車の中から、ホームで手を振る柚原さんに振り返した。
最後の最後まで俺を女の子扱いする柚原さんは、優しさと気遣いの塊だった。あーこうすればモテるのかって勉強になるレベル。歩いている時は常に手を繋いで、人混みの中で守られている感覚になった。
スマホの通知が鳴る。
『今日はありがとう!家に着いたら連絡ちょーだい』
柚原さんの文面は、まるで彼氏だ。…そう、今日はただ遊ぶんじゃなくて、恋愛として、恋人としてありかどうかを考えるための日でもあったんだ。
そもそも、男を好きになったことねぇし、何を基準に決めればいいわけ?ドキドキは…したけど、イケメンにあんなことされたら誰だってドキドキすんだろ。
つーか、男同士で付き合うって、男女で付き合うのと何が違うんだっけ。え、待てよ。何も違わないんじゃね?デートはもちろん、キスとかそれ以上のことすんだよな…?柚原さんとキス…え、俺できる?
数日後、大学内は朝からいつもと雰囲気が違った。特に何かイベントがあるわけでもないのに、メイクや服装に気合いの入った女子だらけ。
ーあ、そうか今日は11月11日…。
廊下から外を見ると、人だかりができている。その中心にいるのは、柚原さん。
取り囲む女子たちはラッピングされたモノやお菓子を渡している。…そう、今日は柚原さんの誕生日。nextのメンバーの誕生日は、プレゼントや手紙を渡すため朝からお祭り騒ぎになる。初夏にあった乙倉さんの誕生日を初めて見た時は衝撃的だった。
「あれどうやって持って帰るんだろうな」
横に来た須藤は嫌味ではなく、純粋に疑問に思っている。
「俺らは一生経験しないな」
ちょっぴり惨めな気持ちになり、須藤と講義室に入っていく。
あんな風に誕生日を祝われる有名人みたいな人とデートしたなんて、今だに不思議で仕方ない。
ー俺、渡すタイミングあるかな…?
結局、朝以来柚原さんを見かけることもなく、帰る時間になった。
バイトあるし、練習終わるの待っとくのも無理だから、渡すの今度にするか。
廊下を歩いていると、階段を上っていく柚原さんの後ろ姿が見えて、急いで駆け寄った。
「柚原さんっ!」
「あ!葵ちゃんだ」
「お疲れ様です。…あの、お誕生日おめでとうございますっ!」
「覚えててくれたんだぁ。ありがとう」
「さすがに忘れないっすよ」
質問し合った夜、お互いの誕生日も知った。
「もう色んな人に貰ってると思うんすけど…良かったら」
今日の日付にちなんだお菓子を渡した。
「…えー嬉しい、ありがとぉ!」
笑顔を見せる柚原さんは、目の前で箱を開け始めた。そのまま階段に座り、隣に座るようジェスチャーで俺に指示をする。
「…?」
「俺、誕生日って何でもわがまま聞いてもらえるって思ってるんだよねぇ」
袋から1本取り出し、軽く口に咥えた柚原さんは、そのまま俺の方を向いた。
「ん」
軽く顔を突き出され、やっと意味が分かった。
…これ、お互い端から食べ進めて最後キスするやつじゃね!?…は?え!?
動揺する俺を早くと言わんばかりにじっと見つめてくる。菓子を咥えてるだけなのに、色気ダダ漏れな柚原さんを前にどんどん鼓動が早くなっていく…。
男同士のふざけたノリだと思えば全然いける…はず。うん、大丈夫…ドキドキすんな俺。
少し緊張しながら端を咥え、食べ始めた。ゆっくり柚原さんの顔が近づいてくる中、聞こえるのはお互いの咀嚼音だけ。
「…サクッ…」
あと数ミリで唇が重なる…。
「それでさー…」
突然人の声が聞こえ、急いで口を離した。
「…っ」
あっぶねぇ…。心臓止まるかと思った。
「残念…」
そう言った柚原さんは俺の手を持ち、一緒に立ち上がった。
「明日のサークル終わり時間ある?」
「ありますけど…」
「じゃあ、俺ん家来てよ。後で一応住所送っとく」
「え、あ、でも…」
「待ってるね…ちゅ」
ーえっ…
おでこにキスをされた俺は固まってしまい、柚原さんの「またね、葵ちゃん」にうまく返事ができなかった。
もしかして今、すげぇ攻められた?え、つーか、柚原さんは俺とキスしたいってこと?
翌日の夕方、体育館でバドミントンをする俺はソワソワしている。この後、俺は本当に柚原さんの家へ…。
「能勢、電車乗る前コンビニ寄っていい?」
「あ、悪りぃ。俺、この後寄るとこあって」
「そうなんだ」
大学の門で須藤たちと別れ、柚原さんの家に向かう。初めて行くわけじゃないのに、緊張しているのが何故なのか自分で分かってしまうから嫌だ。
一呼吸してインターホンを鳴らす。
「お疲れー。どーぞー」
玄関のドアを開けてくれた柚原さんは、いつもと変わらない様子だった。昨日のことを意識してんのは俺だけ…?
「お邪魔します…」
部屋に入ると、昨日貰ったであろう大量のプレゼントが置かれていた。
「すごい量っすね」
「お返しできるわけじゃないから申し訳ないんだけど、みんな優しいよね」
きっと連絡先と同じで、ファンの子達に何かあげるのはNGなんだろうな。
「つーか、この匂い…」
「さすがにバレるよねぇ。…一緒に食べようと思って、作ってみましたー」
テーブルの上のガスコンロに鍋が置かれている。蓋を開けるとキムチ鍋が出来上がっていた。
「わぁ!うまそー!」
「初挑戦だけど、上手くできた気がするんだよね。よし、食べよっ!」
「俺、よそいますよ」
取り皿に熱々の具を乗せる。
「ありがと。…いただきまーす」
「いただきますっ!…ん、うまっ」
「旨辛でおいしいね。…シメの希望ある?」
「米の気分ですけど、柚原さんは?」
「じゃあ、チーズ雑炊にしよっか」
「それ最高です!」
あっという間に鍋の中は空っぽになった。熱さと辛さで身体がずっとポカポカしている。
「めちゃくちゃ美味かったです!ごちそうさまでした!」
「いえいえー。得意料理キムチ鍋にしようかな」
「あはは、いいっすね!」
つーか、あちぃ…。パーカー脱ぎてぇけど、さすがにここじゃ無理だよな。
「暑くない?俺に遠慮せず脱いでいいからね。俺は脱ごーっと」
シャツを脱いだ柚原さんは半袖のTシャツ姿になり、脱ごうか迷ってるいる俺に「バンザイして」と言ってきた。
「えっ」
戸惑いながらバンザイすると、柚原さんがパーカーを脱がせてきた。お世話されてるみたいで恥ずかしくなる。
「鍋ご馳走してくれるために誘ってくれたんすか…?」
「それもあるけど…」
柚原さんは立ち上がり、プレゼントの山からお菓子を取ってきて、再び横に座った。
「昨日の続き…したいんだけど」
…え!?昨日の続き!?それって…つまり…。
柚原さんの口元に目線がいってしまう。
「…今度は葵ちゃんが先に咥えてよ」
1本差し出され、気持ちが追いつかないまま受け取った。
さっきまで楽しく鍋を食べていたのが嘘みたいに、目の前の柚原さんは甘い雰囲気を醸し出す。
「…。」
ゆっくり咥えると、柚原さんは口角を上げ、反対側を咥えた。邪魔の入らない2人きりの空間で、このゲームをするということは必ず…。
どんどん顔が近づいていく…。口ん中キムチ臭いけど大丈夫か!?いや、お互い様か。って、そんなこと考えてる間にもう…
…ちゅっ…
ーあ…。
唇が重なり、俺の鼓動は死ぬほど激しくなる。触れた唇は離れず、キスは終わらない。舌は入ってきてないものの、軽いキスを何回もされる。
「ちゅ…ちゅっ…」
そして、唇が離れると俺を抱きしめ、耳元で囁いた。
「…今日泊まってく?」
待って待って。これ…落としにきてんじゃん!
「…明日朝早いんで…帰ります…」
「絶対そう言うと思ったー」
腕を離した柚原さんは、残りのお菓子を食べ始めた。俺の口にも1本差し出し「終電までは一緒にいて」と妥協案を伝えてくる。
終電に間に合うようにここを出るまで2時間以上…。俺の心臓もつかな…。