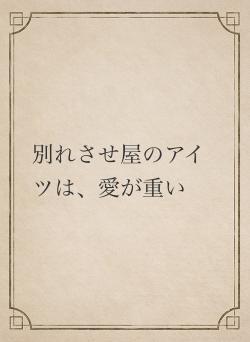ゴールデンウィーク明けの今日は、約束通りボウリング優勝チームへ最下位チームがスイーツを奢る。
昼飯を食べ終え、大学のカフェに集まった8人。俺たちのチーム4人は食べたい物を伝え、先に席へ着いた。
「お待たせー」
須藤たちも自分用に買い、みんなでワッフルやケーキを食べ始める。
「うーん、美味しい!」
「ここのスイーツって、本格的でもっとお金払っていいレベルだよね」
前に座っている女子の先輩2人は、甘い物を食べ上機嫌だ。
「能勢、ついてる…」
隣に座っている須藤が、俺の口元についていた生クリームを親指で取り、ぺろっと舐めた。
「さんきゅ」
「…いや、カップルか!」
先輩が思わず突っ込んだ。
「ていうかさ、私てっきり須藤と能勢が付き合うと思ってた」
「あー分かる!そろそろ、付き合いました報告来るのかと思ってたよねぇ」
「いやいや、俺ら男同士っすよ!?」
「それを柚原くんと付き合ってる能勢が言う?」
サークルの先輩たちには、柚原さんとのことをボウリングの帰りにこっそり伝えた。
「ゔっ…。柚原さんは別枠というか…」
「惚気かい。あんなに葵ちゃん、司ってラブラブだったのに」
「…先輩、俺も辛いんすよ。まさか二股かけられてるなんて。あの日から何度枕を濡らしたことか…」
須藤はわざとらしく目頭を押さえた。
「すとー辛かったねー!!後でジュース奢ってあげるから元気だしな?」
「…はい、ありがとーございます」
「…。」
講義室に戻る途中、先輩に買ってもらったペットボトルのジュースを飲んでいる須藤に文句を言った。
「俺を悪者にして奢ってもらうとかずりぃよなぁ」
「怒んなってー。はい、一口やるから」
飲みかけを渡され不満だったが、喉が渇いてたから受け取り、グビグビ飲んだ。
「おい、一口つったろ!」
「あはは、ケチケチすんなよ」
「…葵ちゃん!」
前からnextの4人がやって来た。
「あ、お疲れ様です」
「お疲れ!」
「葵ちゃん、ちょっと来て」
「えっ」
俺の腕を引いた柚原さんは、乙倉さんや須藤を置いてその場から離れた。
誰もいない階段を数段登るといきなりキスをされた。
ー…っ!?
柚原さんの舌が入ってきて、ゆっくり絡まった。
「…あんなとこで、間接キスとかしないでよ」
…あ、さっきの須藤とのやりとり見られてたんだな。ヤキモチ妬いてすぐキスしてくるとか…可愛いかよ。
「よし、戻ろ」
今戻ったら顔が赤いの須藤にバレそうだな。
次の日、大学から平賀、高見さんとライブハウスへ向かう。
今日は、待ちに待ったnextのライブだ。
「私まで誘ってもらってごめんね」
「いえ、須藤たちが無理だったんで来てくれて助かりました」
「あおちゃんの自慢の彼氏が出るライブだもん、盛り上げちゃうよ!」
「あざーっす」
「あはは。…ねぇ、下の名前なぁに?」
高見さんが平賀に尋ねた。
「心です」
「じゃあ、心ちゃんって呼んでいい?」
「はい!もちろんです。私はなんて呼べばいいですか?」
「あおちゃんはふざけて、たかみーとか呼んでくるけど…」
「いやいや、ふざけてないっすよ!しかもさん付けてますから!」
「すみません、能勢と須藤もふざけてばっかで」
「あはっ、楽しくていいじゃん。うーん、私、薫って名前だから、薫さんとか薫ちゃんとかかな」
「じゃあ、薫さんって呼ばせていただきますね」
「うん、ありがとう」
去年の秋に初めて行ったライブと違い、今回は平賀のおかげで前方の位置をゲットできた。
あの時と違う立場で、違う気待ちで柚原さんたちの登場を待ち侘びている。
ライトが照らされたステージに乙倉さんを先頭にnextが登場した。客席からは大きな拍手と歓声が起こる。
センターのマイク前に立った柚原さんを見ていたら目が合った。俺にしか分からないぐらいの軽い笑みを浮かべられ、きゅんとなってしまう。
「みんなこんばんはー!nextでーす!!」
MCをするのは、やはり乙倉さんだ。
「楽しいゴールデンウィークが終わって下がったテンションを、今日はまた最高潮にしてもらえたらと思います!最後までみんなで盛り上がっていきましょう!!」
和久井さんのスティックカウントを合図に最初の演奏が始まり、1曲目にふさわしい選曲にライブハウス内は瞬く間に熱気に包まれる。
やっぱ乙倉さんのベースも、唐沢さんのギターも、和久井さんのドラムも、めちゃくちゃかっこいいな。
そんでさ…俺の彼氏もやばくね?かっこ良すぎじゃね?ちょっと汗ばんで色気増してさ、甘い歌声響かせてさ、そりゃあみんな虜になるって。
「あっという間なんだけど、次でラストです!」
乙倉さんの言葉を聞き、残念がる声が飛び交う。
「最後は、今の季節らしく爽やかな曲をお届けしまーす!」
ラストを飾ったのは、青春ソング。観客もnextの4人も、会場の全員が笑顔になる時間でライブを締め括った。
「すっごく良かったねー!」
「やばかったですねー!!確実に全員と目が合いましたよ!」
出口に向かう平賀と高見さんは、興奮が冷めず盛り上がっている。
「ていうか、能勢は柚原さん待つんじゃないの?」
「あーうん、でも一旦外に出ようと思って」
「そっか。薫さん、私らこの後どうします?よかったらどっかでご飯一緒に食べません?」
「食べよ食べよー!この近くに美味しいイタリアンあるんだよ」
「わぁーイタリアン好きですー!」
2回目の絡みとは思えないほど、意気投合してる2人に俺が入る隙はない。
平賀と高見さんと別れ、ライブハウス近くの公園で柚原さんを待っていた。
ー大丈夫かなぁ。
いつもライブ後は、控え室である程度ゆっくりすると聞いた。その理由は、終わってすぐ外に出ると出待ちの女子たちの対応に追われるかららしい。
今日は久々にすぐ帰るから、出待ちに囲まれる可能性がある。
「あーおいちゃんっ」
ベンチでスマホを見ていた俺の横に柚原さんが座った。
「あ、お疲れ様です。出待ち大丈夫でした?」
「光たちに先に出てもらって、対応してる隙に急いで帰った」
「うわぁー乙倉さんたちに感謝っすね」
「みんな優しいから大丈夫ー。じゃあ…帰ろっか」
「…はい」
今夜は柚原さん家に泊まるため、2人で駅へ向かう。隣を歩く柚原さんがいつも以上にかっこよく見えるのは、きっとさっきまでのライブのせいだ。
「帰ったらご飯の前にシャワー浴びていい?」
「もちろんです」
家に着き、柚原さんがシャワーを浴びに行ったので、とりあえずソファに座った。
すぐに浴室から「葵ちゃーん」と声がした。
「どうしました?」
浴室の扉越しに尋ねた。
「ごめん、シャンプーの詰め替えリビングのどっかにあるから取ってきてもらっていい?」
「了解っす」
「お待たせしましたー。ここ置いときますねー」
ーこれ、扉開ける前に出た方がいいよな?
「ありがとー」
扉が少し開き、湯気が立ち込める中、髪から水の滴る柚原さんが見えた。
あまりの色気に目を見開き、言葉を失った。
「…。」
「葵ちゃん?」
「あ、いえ。失礼しまっ…」
リビングに戻ろうとした俺の腕をグッと掴んだ柚原さん。
「…一緒に入っちゃおうよ」
「えっ…」
付き合って4ヶ月過ぎ、キス以上はしていないし、風呂に一緒に入ったこともない。着替えている柚原さんをチラッと見た時に腹筋が綺麗に割れているのを確認したぐらい。
「葵ちゃん、バンザイして」
「え、あ、でも…」
戸惑っている俺を無視して、裸のままの柚原さんは俺の服を脱がせ始める。
「自分で脱ぐんで…詰め替えしながら待っててください」
顔を赤くしながら精一杯の抵抗をした。
「はぁーい」
男友達と風呂に入るのとは、全然意味が違う。だって俺らは恋人同士だから。他の男の裸を見たって何にも思わねーけど、柚原さんは別じゃん?ましてやあんな色気爆発してる状態を前に俺は正気を保てんのか…。
「…お邪魔します…」
「どーぞー。シャンプー詰め替えたよぉ。俺まだ髪濡らしただけだから、洗い合いしようよ」
「いいっすね、洗いますよ」
「わぁー気持ちぃー。葵ちゃん上手だね」
「そうっすか?痒いとこありますか?」
「ないでーす」
「じゃあ、流しまーす」
シャンプーし合って、俺からのクリスマスプレゼントであるボディーソープでそれぞれ身体を洗った。
まともに柚原さんの身体が見れず視線に困ったのは言うまでもない。
脱衣所で拭き終えたタイミングで、柚原さんが俺をお姫様抱っこした。
「えっ!?」
「…ベッド行こ」
ー…えええ!?
リビングからの照明が差し込む寝室に連れて行かれ、ベッドサイドにおろされた俺は、柚原さんと横並びに座った。
「…。」
薄暗い中、風呂上がりの柚原さんに見つめられてドキドキしない奴なんかいない…。
手が重なり、キスをした。唇からでも俺の激しい鼓動が伝わりそうな勢いだ。
「葵ちゃん、愛してる…」
この言葉も、この表情も、この気持ちも、全て俺だけに向けられている。
数時間前まで大勢のファンの前で歌っていた声は、恋人への甘い声に変わる。
ーあぁ…すげぇ幸せ。
首筋にキスをされ、ゆっくり押し倒された。覆い被さった柚原さんの色気は、想像の遥か上をいくレベル。
自分の心臓がドクンドクンなって痛ぇ…。それに、なんか俺ばっか緊張してる気がする。
「どうしよう、やばいな…」
「え?」
「緊張とドキドキで、どうにかなりそう…」
あ、柚原さんも同じ気持ちなんだ。余裕あるように見えたけど、俺と一緒で安心した。
「…俺もです」
俺の言葉にふっと優しく微笑んだ柚原さん。
「優しくするね…」
重ねた肌の温もりが、優しく触れた感触が、部屋に溶け込んだ声が、全てが愛おしくてたまらない。
昼飯を食べ終え、大学のカフェに集まった8人。俺たちのチーム4人は食べたい物を伝え、先に席へ着いた。
「お待たせー」
須藤たちも自分用に買い、みんなでワッフルやケーキを食べ始める。
「うーん、美味しい!」
「ここのスイーツって、本格的でもっとお金払っていいレベルだよね」
前に座っている女子の先輩2人は、甘い物を食べ上機嫌だ。
「能勢、ついてる…」
隣に座っている須藤が、俺の口元についていた生クリームを親指で取り、ぺろっと舐めた。
「さんきゅ」
「…いや、カップルか!」
先輩が思わず突っ込んだ。
「ていうかさ、私てっきり須藤と能勢が付き合うと思ってた」
「あー分かる!そろそろ、付き合いました報告来るのかと思ってたよねぇ」
「いやいや、俺ら男同士っすよ!?」
「それを柚原くんと付き合ってる能勢が言う?」
サークルの先輩たちには、柚原さんとのことをボウリングの帰りにこっそり伝えた。
「ゔっ…。柚原さんは別枠というか…」
「惚気かい。あんなに葵ちゃん、司ってラブラブだったのに」
「…先輩、俺も辛いんすよ。まさか二股かけられてるなんて。あの日から何度枕を濡らしたことか…」
須藤はわざとらしく目頭を押さえた。
「すとー辛かったねー!!後でジュース奢ってあげるから元気だしな?」
「…はい、ありがとーございます」
「…。」
講義室に戻る途中、先輩に買ってもらったペットボトルのジュースを飲んでいる須藤に文句を言った。
「俺を悪者にして奢ってもらうとかずりぃよなぁ」
「怒んなってー。はい、一口やるから」
飲みかけを渡され不満だったが、喉が渇いてたから受け取り、グビグビ飲んだ。
「おい、一口つったろ!」
「あはは、ケチケチすんなよ」
「…葵ちゃん!」
前からnextの4人がやって来た。
「あ、お疲れ様です」
「お疲れ!」
「葵ちゃん、ちょっと来て」
「えっ」
俺の腕を引いた柚原さんは、乙倉さんや須藤を置いてその場から離れた。
誰もいない階段を数段登るといきなりキスをされた。
ー…っ!?
柚原さんの舌が入ってきて、ゆっくり絡まった。
「…あんなとこで、間接キスとかしないでよ」
…あ、さっきの須藤とのやりとり見られてたんだな。ヤキモチ妬いてすぐキスしてくるとか…可愛いかよ。
「よし、戻ろ」
今戻ったら顔が赤いの須藤にバレそうだな。
次の日、大学から平賀、高見さんとライブハウスへ向かう。
今日は、待ちに待ったnextのライブだ。
「私まで誘ってもらってごめんね」
「いえ、須藤たちが無理だったんで来てくれて助かりました」
「あおちゃんの自慢の彼氏が出るライブだもん、盛り上げちゃうよ!」
「あざーっす」
「あはは。…ねぇ、下の名前なぁに?」
高見さんが平賀に尋ねた。
「心です」
「じゃあ、心ちゃんって呼んでいい?」
「はい!もちろんです。私はなんて呼べばいいですか?」
「あおちゃんはふざけて、たかみーとか呼んでくるけど…」
「いやいや、ふざけてないっすよ!しかもさん付けてますから!」
「すみません、能勢と須藤もふざけてばっかで」
「あはっ、楽しくていいじゃん。うーん、私、薫って名前だから、薫さんとか薫ちゃんとかかな」
「じゃあ、薫さんって呼ばせていただきますね」
「うん、ありがとう」
去年の秋に初めて行ったライブと違い、今回は平賀のおかげで前方の位置をゲットできた。
あの時と違う立場で、違う気待ちで柚原さんたちの登場を待ち侘びている。
ライトが照らされたステージに乙倉さんを先頭にnextが登場した。客席からは大きな拍手と歓声が起こる。
センターのマイク前に立った柚原さんを見ていたら目が合った。俺にしか分からないぐらいの軽い笑みを浮かべられ、きゅんとなってしまう。
「みんなこんばんはー!nextでーす!!」
MCをするのは、やはり乙倉さんだ。
「楽しいゴールデンウィークが終わって下がったテンションを、今日はまた最高潮にしてもらえたらと思います!最後までみんなで盛り上がっていきましょう!!」
和久井さんのスティックカウントを合図に最初の演奏が始まり、1曲目にふさわしい選曲にライブハウス内は瞬く間に熱気に包まれる。
やっぱ乙倉さんのベースも、唐沢さんのギターも、和久井さんのドラムも、めちゃくちゃかっこいいな。
そんでさ…俺の彼氏もやばくね?かっこ良すぎじゃね?ちょっと汗ばんで色気増してさ、甘い歌声響かせてさ、そりゃあみんな虜になるって。
「あっという間なんだけど、次でラストです!」
乙倉さんの言葉を聞き、残念がる声が飛び交う。
「最後は、今の季節らしく爽やかな曲をお届けしまーす!」
ラストを飾ったのは、青春ソング。観客もnextの4人も、会場の全員が笑顔になる時間でライブを締め括った。
「すっごく良かったねー!」
「やばかったですねー!!確実に全員と目が合いましたよ!」
出口に向かう平賀と高見さんは、興奮が冷めず盛り上がっている。
「ていうか、能勢は柚原さん待つんじゃないの?」
「あーうん、でも一旦外に出ようと思って」
「そっか。薫さん、私らこの後どうします?よかったらどっかでご飯一緒に食べません?」
「食べよ食べよー!この近くに美味しいイタリアンあるんだよ」
「わぁーイタリアン好きですー!」
2回目の絡みとは思えないほど、意気投合してる2人に俺が入る隙はない。
平賀と高見さんと別れ、ライブハウス近くの公園で柚原さんを待っていた。
ー大丈夫かなぁ。
いつもライブ後は、控え室である程度ゆっくりすると聞いた。その理由は、終わってすぐ外に出ると出待ちの女子たちの対応に追われるかららしい。
今日は久々にすぐ帰るから、出待ちに囲まれる可能性がある。
「あーおいちゃんっ」
ベンチでスマホを見ていた俺の横に柚原さんが座った。
「あ、お疲れ様です。出待ち大丈夫でした?」
「光たちに先に出てもらって、対応してる隙に急いで帰った」
「うわぁー乙倉さんたちに感謝っすね」
「みんな優しいから大丈夫ー。じゃあ…帰ろっか」
「…はい」
今夜は柚原さん家に泊まるため、2人で駅へ向かう。隣を歩く柚原さんがいつも以上にかっこよく見えるのは、きっとさっきまでのライブのせいだ。
「帰ったらご飯の前にシャワー浴びていい?」
「もちろんです」
家に着き、柚原さんがシャワーを浴びに行ったので、とりあえずソファに座った。
すぐに浴室から「葵ちゃーん」と声がした。
「どうしました?」
浴室の扉越しに尋ねた。
「ごめん、シャンプーの詰め替えリビングのどっかにあるから取ってきてもらっていい?」
「了解っす」
「お待たせしましたー。ここ置いときますねー」
ーこれ、扉開ける前に出た方がいいよな?
「ありがとー」
扉が少し開き、湯気が立ち込める中、髪から水の滴る柚原さんが見えた。
あまりの色気に目を見開き、言葉を失った。
「…。」
「葵ちゃん?」
「あ、いえ。失礼しまっ…」
リビングに戻ろうとした俺の腕をグッと掴んだ柚原さん。
「…一緒に入っちゃおうよ」
「えっ…」
付き合って4ヶ月過ぎ、キス以上はしていないし、風呂に一緒に入ったこともない。着替えている柚原さんをチラッと見た時に腹筋が綺麗に割れているのを確認したぐらい。
「葵ちゃん、バンザイして」
「え、あ、でも…」
戸惑っている俺を無視して、裸のままの柚原さんは俺の服を脱がせ始める。
「自分で脱ぐんで…詰め替えしながら待っててください」
顔を赤くしながら精一杯の抵抗をした。
「はぁーい」
男友達と風呂に入るのとは、全然意味が違う。だって俺らは恋人同士だから。他の男の裸を見たって何にも思わねーけど、柚原さんは別じゃん?ましてやあんな色気爆発してる状態を前に俺は正気を保てんのか…。
「…お邪魔します…」
「どーぞー。シャンプー詰め替えたよぉ。俺まだ髪濡らしただけだから、洗い合いしようよ」
「いいっすね、洗いますよ」
「わぁー気持ちぃー。葵ちゃん上手だね」
「そうっすか?痒いとこありますか?」
「ないでーす」
「じゃあ、流しまーす」
シャンプーし合って、俺からのクリスマスプレゼントであるボディーソープでそれぞれ身体を洗った。
まともに柚原さんの身体が見れず視線に困ったのは言うまでもない。
脱衣所で拭き終えたタイミングで、柚原さんが俺をお姫様抱っこした。
「えっ!?」
「…ベッド行こ」
ー…えええ!?
リビングからの照明が差し込む寝室に連れて行かれ、ベッドサイドにおろされた俺は、柚原さんと横並びに座った。
「…。」
薄暗い中、風呂上がりの柚原さんに見つめられてドキドキしない奴なんかいない…。
手が重なり、キスをした。唇からでも俺の激しい鼓動が伝わりそうな勢いだ。
「葵ちゃん、愛してる…」
この言葉も、この表情も、この気持ちも、全て俺だけに向けられている。
数時間前まで大勢のファンの前で歌っていた声は、恋人への甘い声に変わる。
ーあぁ…すげぇ幸せ。
首筋にキスをされ、ゆっくり押し倒された。覆い被さった柚原さんの色気は、想像の遥か上をいくレベル。
自分の心臓がドクンドクンなって痛ぇ…。それに、なんか俺ばっか緊張してる気がする。
「どうしよう、やばいな…」
「え?」
「緊張とドキドキで、どうにかなりそう…」
あ、柚原さんも同じ気持ちなんだ。余裕あるように見えたけど、俺と一緒で安心した。
「…俺もです」
俺の言葉にふっと優しく微笑んだ柚原さん。
「優しくするね…」
重ねた肌の温もりが、優しく触れた感触が、部屋に溶け込んだ声が、全てが愛おしくてたまらない。