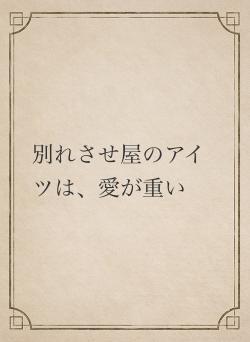4月になり、俺は2年生になった。そして、柚原さんと付き合って3ヶ月が過ぎ、3の倍数は別れやすいなんて聞くけど、俺たちの仲は日に日に深まっている。
…ただ、まだ付き合っていることはnextの3人と水森しか知らない。
「ついにnextがスカウトされたらしいよ!」
ーえ…。
朝の電車内で、同じ大学であろう女子たちの会話が耳に入った。
「私たちのnextが全国区になっちゃうの、嬉しいけどちょっぴり寂しいよねー」
「あー分かる。チケットが取りにくくなるしねー」
「まぁ、でも同じ大学からデビューとかめちゃ自慢だよ」
…いやいや、そんな話初耳なんだけど!!
「2社からスカウトされたって聞いたよ。nextみんな20歳になったし、3年生で就活する前にプロの道を提案しようってのがスカウト側の考えかもね」
サークル中、一緒に待機していた水森にnextについて聞いてみた。
「知らなかったんだけど」
「柚原先輩は、スカウトされたこと自慢するようなタイプじゃないじゃん」
「…そうだけど」
自慢しなくていいけど、恋人なら他の人から知るより先に教えてほしかった。…なんて、それは俺のわがままなのかな。
週明けの月曜日、大学主催の新歓が行われ、去年同様ラストにはnextのライブがある。講義のない在学生たちは音漏れを聴くため体育館を取り囲んでいた。
きっと生でライブを見たら、一気に新たなファンが増えるだろうな。
…去年の新歓ライブで柚原さんは俺に一目惚れしたらしいけど、今年はそんなことないよな?他の奴に一目惚れしないよな?
柚原さんと付き合い始めてからの俺は、自分が思っていた以上に不安になることがある。モテモテの人と付き合うことは、常にライバルがたくさんってこと。ましてや男同士だもんな…。
昼休みに誰もいない講義室で柚原さんと昼飯を食べていた。
「新歓ライブどーでした?」
「すっごく盛り上がったよ。2つ下とは思えないほどみんなフレッシュで、びっくりしちゃったぁ」
「あはは、柚原さんだって余裕で若いじゃないっすか」
「そうだけど、なんか初々しい感じが新鮮ってゆーか、可愛いなって」
…可愛い。
「…その…可愛い子とかいなかったんですか?」
「可愛い子?」
そう聞かれ小さく頷いた。
柚原さんはそんな俺を見て、ほんの少し不思議そうな顔をした後、口角を上げた。
「葵ちゃん…」
…っ!!
隣に座っていた俺を自分の膝の上に乗せ、顔を肩あたりにうずめてくる。
「もしかして、俺が他の子に一目惚れするとか思った?」
「…ちょっとだけ…」
こんなことで不安になるとか、俺は恋する乙女かよ…。
ぎゅーっと強く抱きついてくる柚原さん。
「葵ちゃん、可愛すぎ」
「え…」
「俺の一目惚れは、人生で後にも先にも葵ちゃんだけだよ。1年前に初めて見てたから今日まで、ずーっと葵ちゃん一筋なんだけど?」
…やべぇ、ニヤける。
「…嬉しいです」
「あ、これ見て!」
柚原さんはスマホを見せてくる。
「えっ!?待受にしてんすか!?」
待受画面には、少し前に行った花見デートで撮った俺とのツーショットが設定されていた。
「この写真お気に入りだから。それにスマホ見るたびに葵ちゃんとの思い出に浸れるし。…こんな俺が他の子に興味持つと思うー?」
「思わないっす…」
「よかった。ほんとはさ、スマホケースに葵ちゃんの写真挟みたいぐらいなんだけど、光たちに止められちゃって」
「いやいや!さすがにそれはやめてください!」
どうやら柚原さんは、想像の何十倍も俺のことを好きでいてくれてるみたいだ。
「そーゆー葵ちゃんこそ、可愛いとかかっこいいとか思う子いなかったの?」
「柚原さんと付き合ってて、他の人に目移りするわけないじゃないっすか…」
「あはっ、ちょー好き同士じゃん。……葵ちゃん、好き…」
嬉しそうにキスをされた。
今だに柚原さんとのキスは緊張するし、恥ずかしい。けど、このキスを俺しか知らないと思うと幸せな気持ちが溢れ出す。
スポーツサークルにも新入生が男女合わせて6人入部した。
今日は新入生が初めて体育館で練習する日。
「1年生のみんな今日からよろしく!うちのサークルは、和気あいあいとゆるくスポーツを楽しんでます。部員みんな仲良いから、すぐ馴染めると思う。あ、仲良すぎて恋愛に発展しないのは難点かも」
部長の言葉に俺たち上級生はクスクス笑う。
平賀も笑っているが、内心しょんぼりしてんだろうなと勝手に思ってしまう。今だに須藤と何の進展もない平賀を俺と水森は、ただただ見守っている。
1年生を交えたチームに分かれ、バレーを楽しんでいた。
「やっぱ人数多いと楽しいよな!」
俺と平賀の横で3年の先輩は嬉しそうに言う。
「つうか、今年の1年女子みんな可愛くね?」
俺にコソコソ言ってきたが、当然平賀の耳にも聞こえている。
「ちょっとぉ!それって私たちが可愛くないみたいじゃないですか!ひどー!!」
「違う違う。平賀たちは綺麗系じゃん?」
平賀はほっぺを膨らませ、納得のいっていない顔をした。
「いやいや、俺らは平賀推しだから!…あ、須藤。お前も平賀推しだよな!?」
平賀の圧に焦る先輩は、試合を終え近寄って来た須藤に話題を振る。
「え、推し?…先輩、俺の推しは1人ですよ」
スッと横に来て俺の肩を抱いた。
「葵ちゃんです!!」
…こいつ、まだこのネタ続けてんのかよ。
「そうだったな!須藤は葵ちゃんしか興味ねーもんな!」
「そうですそうです」
ふざけたやりとりの中、俺を見る平賀の視線が痛い。
土曜日の柚原さんとのデートは、新しく出来た話題のカフェに行ってみることにした。
「いらっしゃいませー。2名様ですか?」
「はい」
「お好きな席へどうぞー」
タイミングが良かったのか、店内は空いていて好きな席を選べた。
「あ、2人掛けソファ空いてる」
…横並びの席に座ったら、絶対に柚原さんは密着してくる…。
「こっちの席にしましょうよ!」
1人掛けのソファが向かい合う席を提案した。柚原さんは「…いいけど」と少し残念そうにしたが、人前で密着するわけにはいかない。
「お待たせしましたー」
注文したランチセットが運ばれてきた。
「おーうまそう!いただきまーす」
「いただきまぁす」
「…うま!」
「こっちも美味しいよ、あーん」
店内に他の客もいるのに、スプーンにすくったオムライスを平気な顔で差し出してくる。恥ずかしさよりも早くこのシチュエーションを終わらせたい気持ちが勝って、急いで口に入れた。誰も見てないといいけど…。
「ほんとだ、うまい」
「でしょー?」
そう言った柚原さんは、ニコニコしながら俺を見ている。これは、自分にもあーんしてという顔だ。
「…。」
バターチキンカレーの乗ったスプーンを照れながら柚原さんの口元へ運んだ。
「おいし。…ありがとっ!」
無邪気な笑顔を見せた柚原さん。
「そういえば、軽音部って何人新入生入ったんすか?」
「えーっと、たしか11人かな」
「11!?絶対next目当てじゃないっすか」
「どうなんだろうねー。まぁ、俺たち基本別室で練習してるから他の部員とそんなに絡まないんだけどね。スポーツサークルとのほうが濃い時間過ごしてるかも」
柚原さんたち4人は、今でも月に一度はスポーツサークルの練習に遊びに来てくれている。
「まだ新入生に定期的にnextが来てくれるの言ってないんで、今度来た時パニックになると思います」
「あはは。そんな特別な存在でもないから」
「特別っすよ。nextはみんなの憧れですよ」
「…。」
「美味しかったねー。この後どーする?」
会計を済ませカフェを出たが、ランチ後の予定は決めていなかった。
「せっかく天気良いですし、散歩でもしませんか?」
「大賛成!」
カフェからすぐの河川敷沿いを手を繋ぎ歩く。
「ゴールデンウィーク明けのライブ来れそう?」
「はい。シフト休み希望出したんで、行けると思います」
「よかった。なんか歌ってほしい曲あるー?」
「柚原さんの歌声なら何だって聴きたいです!」
「そんな嬉しいこと言ってくれるんだぁ。そういえば、俺まだ葵ちゃんの歌声聞いたことない」
「そうでしたっけ?」
「聞きたい!」
「さすがにボーカルの前で歌えないっすよ」
「えぇー、だってサークルのみんなは聞いたことあるんでしょ?」
「まぁ、みんなでよくカラオケも行くんで」
「俺彼氏なのに…葵ちゃんの歌声知らないなんて…他の人は聴いたことあるのに…」
「もう、分かりましたって。今度カラオケ行きましょ!」
「やった」
数日後、構内を平賀と歩いていると、少し先に高見さんの姿を見つけた。
「あ、たかみーさんだ」
「ん?あー男装グランプリの。普段から爽やか子犬系イケメンだよね」
「爽やか子犬系…?」
「かっこいいけど、近寄りやすいってこと!」
おんなじ女だからだろ、って言うか迷ったタイミングで、高見さんがこっちに気付き近づいてきた。
「あおちゃん、お疲れ」
「お疲れっす」
高見さんは平賀の方を見た。
「あおちゃんの友達?彼女?」
「友達です」
「あ、初めまして、平賀です」
「初めまして、高見です。…すごくかわいいね」
「えっ」
「じゃあ、またね」
「はい」
「…。」
高見さんが立ち去った後も平賀はその場に立ち尽くしていた。
「どした?」
「やばい…何今の…やばいんだけど」
「え?かわいいってやつ?」
「うん、あれは反則よ」
どうやら高見さんのさらっと言った褒め言葉に見事に撃ち抜かれたようだ。
「どうしよう!私にはnextがいるのにー!揺らぎそうー!」
「勝手に揺らいどけー。つーかさ、平賀ってイケメンとか甘い言葉に弱いのに、何で須藤なんだっけ?アイツもかっこいいとは思うけど、ずば抜けてるわけじゃねーし、甘い言葉を女子に言うタイプじゃないじゃんか」
「うーん…能勢なら分かると思うんだけどさ、須藤って基本ふざけてるじゃん。だけど痒いとこに手が届く優しさを持ってるんだよね」
「あーなんか分かるかも」
「この人の彼女は幸せだろうなぁって思って、そんな風に身近で見てたらいつのまにか好きになってた」
「そっか。良い理由じゃん」
「でしょ?」
好きになる理由は人それぞれだ。見た目だろうが、性格だろうが、才能だろうが、きっかけはあくまで最初の一歩。そこから好きを持続出来るか、どんな一面も受け入れられるかで好きの大きさは変わっていく。
…ただ、まだ付き合っていることはnextの3人と水森しか知らない。
「ついにnextがスカウトされたらしいよ!」
ーえ…。
朝の電車内で、同じ大学であろう女子たちの会話が耳に入った。
「私たちのnextが全国区になっちゃうの、嬉しいけどちょっぴり寂しいよねー」
「あー分かる。チケットが取りにくくなるしねー」
「まぁ、でも同じ大学からデビューとかめちゃ自慢だよ」
…いやいや、そんな話初耳なんだけど!!
「2社からスカウトされたって聞いたよ。nextみんな20歳になったし、3年生で就活する前にプロの道を提案しようってのがスカウト側の考えかもね」
サークル中、一緒に待機していた水森にnextについて聞いてみた。
「知らなかったんだけど」
「柚原先輩は、スカウトされたこと自慢するようなタイプじゃないじゃん」
「…そうだけど」
自慢しなくていいけど、恋人なら他の人から知るより先に教えてほしかった。…なんて、それは俺のわがままなのかな。
週明けの月曜日、大学主催の新歓が行われ、去年同様ラストにはnextのライブがある。講義のない在学生たちは音漏れを聴くため体育館を取り囲んでいた。
きっと生でライブを見たら、一気に新たなファンが増えるだろうな。
…去年の新歓ライブで柚原さんは俺に一目惚れしたらしいけど、今年はそんなことないよな?他の奴に一目惚れしないよな?
柚原さんと付き合い始めてからの俺は、自分が思っていた以上に不安になることがある。モテモテの人と付き合うことは、常にライバルがたくさんってこと。ましてや男同士だもんな…。
昼休みに誰もいない講義室で柚原さんと昼飯を食べていた。
「新歓ライブどーでした?」
「すっごく盛り上がったよ。2つ下とは思えないほどみんなフレッシュで、びっくりしちゃったぁ」
「あはは、柚原さんだって余裕で若いじゃないっすか」
「そうだけど、なんか初々しい感じが新鮮ってゆーか、可愛いなって」
…可愛い。
「…その…可愛い子とかいなかったんですか?」
「可愛い子?」
そう聞かれ小さく頷いた。
柚原さんはそんな俺を見て、ほんの少し不思議そうな顔をした後、口角を上げた。
「葵ちゃん…」
…っ!!
隣に座っていた俺を自分の膝の上に乗せ、顔を肩あたりにうずめてくる。
「もしかして、俺が他の子に一目惚れするとか思った?」
「…ちょっとだけ…」
こんなことで不安になるとか、俺は恋する乙女かよ…。
ぎゅーっと強く抱きついてくる柚原さん。
「葵ちゃん、可愛すぎ」
「え…」
「俺の一目惚れは、人生で後にも先にも葵ちゃんだけだよ。1年前に初めて見てたから今日まで、ずーっと葵ちゃん一筋なんだけど?」
…やべぇ、ニヤける。
「…嬉しいです」
「あ、これ見て!」
柚原さんはスマホを見せてくる。
「えっ!?待受にしてんすか!?」
待受画面には、少し前に行った花見デートで撮った俺とのツーショットが設定されていた。
「この写真お気に入りだから。それにスマホ見るたびに葵ちゃんとの思い出に浸れるし。…こんな俺が他の子に興味持つと思うー?」
「思わないっす…」
「よかった。ほんとはさ、スマホケースに葵ちゃんの写真挟みたいぐらいなんだけど、光たちに止められちゃって」
「いやいや!さすがにそれはやめてください!」
どうやら柚原さんは、想像の何十倍も俺のことを好きでいてくれてるみたいだ。
「そーゆー葵ちゃんこそ、可愛いとかかっこいいとか思う子いなかったの?」
「柚原さんと付き合ってて、他の人に目移りするわけないじゃないっすか…」
「あはっ、ちょー好き同士じゃん。……葵ちゃん、好き…」
嬉しそうにキスをされた。
今だに柚原さんとのキスは緊張するし、恥ずかしい。けど、このキスを俺しか知らないと思うと幸せな気持ちが溢れ出す。
スポーツサークルにも新入生が男女合わせて6人入部した。
今日は新入生が初めて体育館で練習する日。
「1年生のみんな今日からよろしく!うちのサークルは、和気あいあいとゆるくスポーツを楽しんでます。部員みんな仲良いから、すぐ馴染めると思う。あ、仲良すぎて恋愛に発展しないのは難点かも」
部長の言葉に俺たち上級生はクスクス笑う。
平賀も笑っているが、内心しょんぼりしてんだろうなと勝手に思ってしまう。今だに須藤と何の進展もない平賀を俺と水森は、ただただ見守っている。
1年生を交えたチームに分かれ、バレーを楽しんでいた。
「やっぱ人数多いと楽しいよな!」
俺と平賀の横で3年の先輩は嬉しそうに言う。
「つうか、今年の1年女子みんな可愛くね?」
俺にコソコソ言ってきたが、当然平賀の耳にも聞こえている。
「ちょっとぉ!それって私たちが可愛くないみたいじゃないですか!ひどー!!」
「違う違う。平賀たちは綺麗系じゃん?」
平賀はほっぺを膨らませ、納得のいっていない顔をした。
「いやいや、俺らは平賀推しだから!…あ、須藤。お前も平賀推しだよな!?」
平賀の圧に焦る先輩は、試合を終え近寄って来た須藤に話題を振る。
「え、推し?…先輩、俺の推しは1人ですよ」
スッと横に来て俺の肩を抱いた。
「葵ちゃんです!!」
…こいつ、まだこのネタ続けてんのかよ。
「そうだったな!須藤は葵ちゃんしか興味ねーもんな!」
「そうですそうです」
ふざけたやりとりの中、俺を見る平賀の視線が痛い。
土曜日の柚原さんとのデートは、新しく出来た話題のカフェに行ってみることにした。
「いらっしゃいませー。2名様ですか?」
「はい」
「お好きな席へどうぞー」
タイミングが良かったのか、店内は空いていて好きな席を選べた。
「あ、2人掛けソファ空いてる」
…横並びの席に座ったら、絶対に柚原さんは密着してくる…。
「こっちの席にしましょうよ!」
1人掛けのソファが向かい合う席を提案した。柚原さんは「…いいけど」と少し残念そうにしたが、人前で密着するわけにはいかない。
「お待たせしましたー」
注文したランチセットが運ばれてきた。
「おーうまそう!いただきまーす」
「いただきまぁす」
「…うま!」
「こっちも美味しいよ、あーん」
店内に他の客もいるのに、スプーンにすくったオムライスを平気な顔で差し出してくる。恥ずかしさよりも早くこのシチュエーションを終わらせたい気持ちが勝って、急いで口に入れた。誰も見てないといいけど…。
「ほんとだ、うまい」
「でしょー?」
そう言った柚原さんは、ニコニコしながら俺を見ている。これは、自分にもあーんしてという顔だ。
「…。」
バターチキンカレーの乗ったスプーンを照れながら柚原さんの口元へ運んだ。
「おいし。…ありがとっ!」
無邪気な笑顔を見せた柚原さん。
「そういえば、軽音部って何人新入生入ったんすか?」
「えーっと、たしか11人かな」
「11!?絶対next目当てじゃないっすか」
「どうなんだろうねー。まぁ、俺たち基本別室で練習してるから他の部員とそんなに絡まないんだけどね。スポーツサークルとのほうが濃い時間過ごしてるかも」
柚原さんたち4人は、今でも月に一度はスポーツサークルの練習に遊びに来てくれている。
「まだ新入生に定期的にnextが来てくれるの言ってないんで、今度来た時パニックになると思います」
「あはは。そんな特別な存在でもないから」
「特別っすよ。nextはみんなの憧れですよ」
「…。」
「美味しかったねー。この後どーする?」
会計を済ませカフェを出たが、ランチ後の予定は決めていなかった。
「せっかく天気良いですし、散歩でもしませんか?」
「大賛成!」
カフェからすぐの河川敷沿いを手を繋ぎ歩く。
「ゴールデンウィーク明けのライブ来れそう?」
「はい。シフト休み希望出したんで、行けると思います」
「よかった。なんか歌ってほしい曲あるー?」
「柚原さんの歌声なら何だって聴きたいです!」
「そんな嬉しいこと言ってくれるんだぁ。そういえば、俺まだ葵ちゃんの歌声聞いたことない」
「そうでしたっけ?」
「聞きたい!」
「さすがにボーカルの前で歌えないっすよ」
「えぇー、だってサークルのみんなは聞いたことあるんでしょ?」
「まぁ、みんなでよくカラオケも行くんで」
「俺彼氏なのに…葵ちゃんの歌声知らないなんて…他の人は聴いたことあるのに…」
「もう、分かりましたって。今度カラオケ行きましょ!」
「やった」
数日後、構内を平賀と歩いていると、少し先に高見さんの姿を見つけた。
「あ、たかみーさんだ」
「ん?あー男装グランプリの。普段から爽やか子犬系イケメンだよね」
「爽やか子犬系…?」
「かっこいいけど、近寄りやすいってこと!」
おんなじ女だからだろ、って言うか迷ったタイミングで、高見さんがこっちに気付き近づいてきた。
「あおちゃん、お疲れ」
「お疲れっす」
高見さんは平賀の方を見た。
「あおちゃんの友達?彼女?」
「友達です」
「あ、初めまして、平賀です」
「初めまして、高見です。…すごくかわいいね」
「えっ」
「じゃあ、またね」
「はい」
「…。」
高見さんが立ち去った後も平賀はその場に立ち尽くしていた。
「どした?」
「やばい…何今の…やばいんだけど」
「え?かわいいってやつ?」
「うん、あれは反則よ」
どうやら高見さんのさらっと言った褒め言葉に見事に撃ち抜かれたようだ。
「どうしよう!私にはnextがいるのにー!揺らぎそうー!」
「勝手に揺らいどけー。つーかさ、平賀ってイケメンとか甘い言葉に弱いのに、何で須藤なんだっけ?アイツもかっこいいとは思うけど、ずば抜けてるわけじゃねーし、甘い言葉を女子に言うタイプじゃないじゃんか」
「うーん…能勢なら分かると思うんだけどさ、須藤って基本ふざけてるじゃん。だけど痒いとこに手が届く優しさを持ってるんだよね」
「あーなんか分かるかも」
「この人の彼女は幸せだろうなぁって思って、そんな風に身近で見てたらいつのまにか好きになってた」
「そっか。良い理由じゃん」
「でしょ?」
好きになる理由は人それぞれだ。見た目だろうが、性格だろうが、才能だろうが、きっかけはあくまで最初の一歩。そこから好きを持続出来るか、どんな一面も受け入れられるかで好きの大きさは変わっていく。