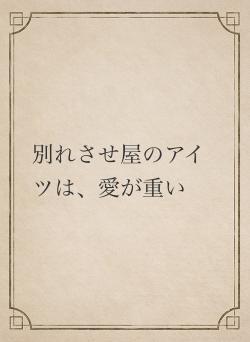クリスマスイブの夜。
気温がどんどん下がってきて、告白の余韻に浸る暇もなく、柚原さんとベンチから立ち上がった。
「明日って昼からバイトだよね?…連れて帰っちゃおーっと」
柚原さんは、ひょいっと俺を縦抱きで持ち上げた。
「うわっ…!ちょっ、下ろしてください!」
「一緒に帰るなら下ろしてあげる」
意地悪な笑みを浮かべた柚原さんは、すこぶる機嫌が良さそうだ。
「…わかりました」
「やった」
白い息を吐きながら、手を繋ぎ駅に向かって歩く俺の心は、すげぇぽかぽかしてる。
翌朝、スマホのアラームで目が覚めた。アラームを止めようとする俺に、まだ眠そうな顔で抱きつき、離れようとしない柚原さん。
ーなんだ、このかわいい生き物は。
なんとかアラームを止め、ベットの上で身体を起こした。
「おはよぉ、葵ちゃん」
「…おはようございます」
柚原さんも身体を起こし、優しい表情を見せると、おでこにキスをしてくる。
「改めて…よろしくね」
「…よろしくお願いします」
俺たちは、昨夜から恋人になった。俺の選んだルームフレグランスが香る部屋で迎えた朝は、まだ夢のようでふわふわしている。
「葵ちゃん、年明けで空いてる日ある?」
パンとスープを用意してくれる柚原さんに聞かれ、スマホ内のアプリで予定を確認した。
「年明け…3日なら今んとこ空いてます」
「3日、ちょうどよかった。光たちと会うんだけど、葵ちゃんも来ない?」
「え!?いや、それは…」
「3人に葵ちゃんとうまくいったの伝えたいんだけど、せっかくなら一緒に言いたいなーって。だめ?」
…この人の甘えた顔は卑怯だ。
「…分かりました」
高校の友達との忘年会当日。夕方、待ち合わせ場所に着くと須藤が1人立っていた。
「よっ」
「おつー」
「珍しく1番じゃん。あ、この前はごめんな?」
「ほんとひでーよなぁ。あの格好で1人電車に乗った俺の気持ち考えてみろよ」
「いや、何の問題もねぇみてーに言ってたじゃん!」
「それは2人での場合だろ。1人はまじで地獄だったから」
「あはは、ほんと悪りぃ!」
「…つうか、柚原さんと何して…っ」
「お待たせーっ」
須藤の言葉を遮るように他の友達がやって来た。
男10人、2テーブルに分かれ、もんじゃ食べ放題を楽しんでいる。
「え、須藤も能勢もまだ彼女出来てねーの?」
「その言い方、お前は出来たのかよ」
「いや、いねーけど」
「いねーのかよ!」
「須藤か能勢なら彼女出来たかなと思ってさ」
彼女というか彼氏は出来たけど…年末のテンションでもそんなことは言えない。
「須藤って、高1の時に別れて以来いない感じだよな?」
「うん、そだな」
そういや、須藤1年の時彼女いたな。隣のクラスだった須藤が俺のクラスの女子と付き合い始めた。
よく教室に来るようになって、顔合わせること増えて、いつのまにか仲良くなったんだよなぁ。懐かしいな。
「でも何で別れたんだっけ?」
俺の質問に須藤は淡々と答えた。
「冷めたから」
「え、そんな酷い振り方したのか!?」
「いや、もっとオブラートに包んだけど。まぁ、告白されて付き合ってみたけど違ったってやつだよ。もう俺の恋愛話はいいから」
「そういや…ー」
別の話題が始まり、恋バナは即終了した。
あっという間に時間は過ぎ、駅前でみんなと解散した。
「またなー、良いお年をー!」
「元気で!来年もよろしくー」
電車に乗る組と改札に向かいながら、時間を確認するためスマホを見ると柚原さんからメッセージが届いていた。
『声聞きたい。家着いて時間あったら電話しよー』
付き合って5日、連絡は毎日するようになった。彼氏になってからの柚原さんは、これまで以上にストレートに想いや要望を伝えてくるようになった。
了解スタンプを送信し、スマホをポケットに入れた。
「なぁ、どっか行こうぜ」
横に来た須藤は俺にしか聞こえない声のボリュームで言ってくる。
「この時間で空いてるとこってそんな無くね?」
「うーん、カラオケはこの前行ったし、空いてるゲーセンとかあるっけなぁ。公園はさみーしなぁ」
「別に無理に行かなくてよくね?」
「何でそんな冷たいこと言うんだよー」
「冷たくねーよ。なに、なんか話あんの?」
「いや、別にねーけど…」
「じゃあ、新年会で会えるし大丈夫じゃん。つーか、誘うならいつでも会える俺じゃなくて、久々に会った奴にしろよ」
「…はいはい、大人しく帰りますよーだ」
結局、須藤とはどこも寄らず、それぞれ家に帰った。
ー風呂に入る前に電話しとくか。
通話ボタンを押すとすぐに繋がった。
「おかえりー。楽しかった?」
「はい、久々だったんで盛り上がりました」
「良かったねぇ。……声で満足できると思ったけど、逆効果だったかも。余計会いたくなっちゃった」
…電話越しにそんなこと言うなんてずるい。
お互い予定があり、年内に会える日はもうない。付き合いたてほやほやで、浮かれているわけじゃねぇけど…
「…まだ終電まで時間あるし、会いに行ってもいいですか?」
「えっ、嬉しいけど外寒いし、わざわざ来てもらうのは…」
「…そうですよね、いきなりはあれっすよね。…じゃあ、俺そろそろ風呂入ってきます」
「待って…!…俺が会いに行くから」
「いやいや、柚原さんが風邪引いたら困るし」
「あはは、俺らお互い気遣い過ぎ。…俺が会いたいって言ったから、会いに行かせて?」
「…ありがとうございます」
「またそっちの駅に着いたら連絡するねぇ」
俺ん家の最寄りの駅で待ち合わせをした。
「葵ちゃんっ」
「わざわざありがとうございます」
「外は極寒だねぇ。めちゃ着込んで来た」
「俺もっす」
「人少ないといいね」
「この時間なんで家族層は少ないと思いますけど、混んでる可能性もありますね」
俺のバイト先とは違うネットカフェに着いた。
「2人用空いてて良かったっすね」
「うん」
飲み物を持ち、フラットの個室に入った。
「なんか漫画とか取ってきます?」
「ううん…葵ちゃんで十分!」
まだ上着を脱いでいないのに俺の腰あたりを引き寄せ、座った状態で後ろからハグをしようとする。
「上着に邪魔されて、葵ちゃんが遠い」
「そりゃあそうでしょ。館内あったかいし、とりあえず上着脱ぎましょうよ」
「だね」
お互い上着を脱ぎ、改めてハグをする。今度は向き合って抱きしめ合う。
「あったか…」
呟いた柚原さんの言い方が恋人っぽさを含んでいて、あぁ…俺たち付き合ってるんだなって実感した。
「来年はさ、一緒に年越ししなきゃねー」
まだ付き合ったばっかなのに、普通に1年後の話をするの柚原さんらしいな。
「そうですね。…つーか、そろそろ…」
ハグを止める気配のない柚原さんから一旦離れようとするが、俺を抱きしめる腕の力は弱まらない。
「離してくださーい」
「やーだ。年内最後の触れ合いだもん」
「来年いっぱい触れ合ったらいいじゃないっすか」
「…。」
柚原さんは俺の顔をじっと見た。
「…?」
「来年は、葵ちゃんにいっぱい触れていいの?」
「付き合ってるんですからいいに決まってるじゃないですか」
「…約束ね。色んなとこにたくさん触れるから…覚悟してて」
「えっ…」
ちゅ…、優しくキスをされた。
色んなとこに触れる…?キスだけで心臓飛び出しそうなのに、柚原さんとそれ以上するってことだよな…?やばい、更なる色気を前に俺は死ぬかもしれない。
駅前で柚原さんを見送った。
「会えてよかった。わがまま聞いてくれてありがと」
「こちらこそありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね」
「うん。また連絡するねー」
毎日連絡しているから“良いお年を”は言わずに別れた。
もうすぐ今年が終わる。数ヶ月前まで遥か遠い存在だと思っていた柚原さんと付き合うなんて、正直まだ夢じゃないかと思う。
それでも、さっきまで触れ合っていた手が現実だと教えてくれて、来年からどんな思い出ができるか楽しみで仕方ない。…色々あったけど、良い1年だったな。
新年を迎え、nextの集まりに参加する日が来た。4人の行きつけである喫茶店に柚原さんと入店すると、すでに乙倉さんたちが1番奥の席に着いていた。
俺たちに気づき、手を振ってくれた。
「おー能勢っちー!あけおめーー!」
「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします!」
「能勢くん、明けましておめでとう。よろしくね」
「明けましておめでと」
手招きされ、乙倉さんと柚原さんの間に座った。前には唐沢さんと和久井さん。
こんなイケメン4人に囲まれて、俺は場違い過ぎねーか?
「能勢っち、何頼む?」
「えっと、おすすめありますか?」
「能勢くんよく食べるから、このカツサンドとか良いかも」
「じゃあ、それにします!」
「ユズは?オムライスでいい?」
「うん」
「翠、その服食べる時、袖気をつけなよ」
「はーい」
当たり前だけど、俺の何十倍、いや何百倍乙倉さんたちは柚原さんのことを知っているし、理解している。そこに嫉妬するとかは全然なくて、むしろこの4人の関係性が好きだなって思う。
「ていうか、能勢っちが新年の集まりに来てくれるとかびっくりだったんだけど。すっかり仲良くなったんだな!」
柚原さんは俺に頭をくっつけ、3人に伝える。
「俺たち…付き合うことになりましたぁ!」
「えぇ!?まじで!?」
「ほんとほんと。応援してくれていた3人に直接報告したくてさ」
「おめでとうー!良かったな、ユズ!!」
「ゆずくんの想いが実ったんだね!2人ともおめでとう」
「ありがとー」
「翠の圧に負けて無理矢理とかじゃない?」
唐沢先輩は心配の意味を込めて聞いてきた。
「いえ、そんなじゃないっす。ちゃんと俺もその…好きで付き合ってます」
「そっか。…翠、おめでと」
「新年早々良い報告聞けて嬉しいね」
「大吉引くよりテンション上がる」
「ほんとかよ」
3人の表情や言葉から心の底から祝ってくれているのが分かった。
それから冬休みが終わり、大学とサークルとバイトに追われる毎日に柚原さんとの時間が加わり、あっという間に俺の1年生期間は終わった。
気温がどんどん下がってきて、告白の余韻に浸る暇もなく、柚原さんとベンチから立ち上がった。
「明日って昼からバイトだよね?…連れて帰っちゃおーっと」
柚原さんは、ひょいっと俺を縦抱きで持ち上げた。
「うわっ…!ちょっ、下ろしてください!」
「一緒に帰るなら下ろしてあげる」
意地悪な笑みを浮かべた柚原さんは、すこぶる機嫌が良さそうだ。
「…わかりました」
「やった」
白い息を吐きながら、手を繋ぎ駅に向かって歩く俺の心は、すげぇぽかぽかしてる。
翌朝、スマホのアラームで目が覚めた。アラームを止めようとする俺に、まだ眠そうな顔で抱きつき、離れようとしない柚原さん。
ーなんだ、このかわいい生き物は。
なんとかアラームを止め、ベットの上で身体を起こした。
「おはよぉ、葵ちゃん」
「…おはようございます」
柚原さんも身体を起こし、優しい表情を見せると、おでこにキスをしてくる。
「改めて…よろしくね」
「…よろしくお願いします」
俺たちは、昨夜から恋人になった。俺の選んだルームフレグランスが香る部屋で迎えた朝は、まだ夢のようでふわふわしている。
「葵ちゃん、年明けで空いてる日ある?」
パンとスープを用意してくれる柚原さんに聞かれ、スマホ内のアプリで予定を確認した。
「年明け…3日なら今んとこ空いてます」
「3日、ちょうどよかった。光たちと会うんだけど、葵ちゃんも来ない?」
「え!?いや、それは…」
「3人に葵ちゃんとうまくいったの伝えたいんだけど、せっかくなら一緒に言いたいなーって。だめ?」
…この人の甘えた顔は卑怯だ。
「…分かりました」
高校の友達との忘年会当日。夕方、待ち合わせ場所に着くと須藤が1人立っていた。
「よっ」
「おつー」
「珍しく1番じゃん。あ、この前はごめんな?」
「ほんとひでーよなぁ。あの格好で1人電車に乗った俺の気持ち考えてみろよ」
「いや、何の問題もねぇみてーに言ってたじゃん!」
「それは2人での場合だろ。1人はまじで地獄だったから」
「あはは、ほんと悪りぃ!」
「…つうか、柚原さんと何して…っ」
「お待たせーっ」
須藤の言葉を遮るように他の友達がやって来た。
男10人、2テーブルに分かれ、もんじゃ食べ放題を楽しんでいる。
「え、須藤も能勢もまだ彼女出来てねーの?」
「その言い方、お前は出来たのかよ」
「いや、いねーけど」
「いねーのかよ!」
「須藤か能勢なら彼女出来たかなと思ってさ」
彼女というか彼氏は出来たけど…年末のテンションでもそんなことは言えない。
「須藤って、高1の時に別れて以来いない感じだよな?」
「うん、そだな」
そういや、須藤1年の時彼女いたな。隣のクラスだった須藤が俺のクラスの女子と付き合い始めた。
よく教室に来るようになって、顔合わせること増えて、いつのまにか仲良くなったんだよなぁ。懐かしいな。
「でも何で別れたんだっけ?」
俺の質問に須藤は淡々と答えた。
「冷めたから」
「え、そんな酷い振り方したのか!?」
「いや、もっとオブラートに包んだけど。まぁ、告白されて付き合ってみたけど違ったってやつだよ。もう俺の恋愛話はいいから」
「そういや…ー」
別の話題が始まり、恋バナは即終了した。
あっという間に時間は過ぎ、駅前でみんなと解散した。
「またなー、良いお年をー!」
「元気で!来年もよろしくー」
電車に乗る組と改札に向かいながら、時間を確認するためスマホを見ると柚原さんからメッセージが届いていた。
『声聞きたい。家着いて時間あったら電話しよー』
付き合って5日、連絡は毎日するようになった。彼氏になってからの柚原さんは、これまで以上にストレートに想いや要望を伝えてくるようになった。
了解スタンプを送信し、スマホをポケットに入れた。
「なぁ、どっか行こうぜ」
横に来た須藤は俺にしか聞こえない声のボリュームで言ってくる。
「この時間で空いてるとこってそんな無くね?」
「うーん、カラオケはこの前行ったし、空いてるゲーセンとかあるっけなぁ。公園はさみーしなぁ」
「別に無理に行かなくてよくね?」
「何でそんな冷たいこと言うんだよー」
「冷たくねーよ。なに、なんか話あんの?」
「いや、別にねーけど…」
「じゃあ、新年会で会えるし大丈夫じゃん。つーか、誘うならいつでも会える俺じゃなくて、久々に会った奴にしろよ」
「…はいはい、大人しく帰りますよーだ」
結局、須藤とはどこも寄らず、それぞれ家に帰った。
ー風呂に入る前に電話しとくか。
通話ボタンを押すとすぐに繋がった。
「おかえりー。楽しかった?」
「はい、久々だったんで盛り上がりました」
「良かったねぇ。……声で満足できると思ったけど、逆効果だったかも。余計会いたくなっちゃった」
…電話越しにそんなこと言うなんてずるい。
お互い予定があり、年内に会える日はもうない。付き合いたてほやほやで、浮かれているわけじゃねぇけど…
「…まだ終電まで時間あるし、会いに行ってもいいですか?」
「えっ、嬉しいけど外寒いし、わざわざ来てもらうのは…」
「…そうですよね、いきなりはあれっすよね。…じゃあ、俺そろそろ風呂入ってきます」
「待って…!…俺が会いに行くから」
「いやいや、柚原さんが風邪引いたら困るし」
「あはは、俺らお互い気遣い過ぎ。…俺が会いたいって言ったから、会いに行かせて?」
「…ありがとうございます」
「またそっちの駅に着いたら連絡するねぇ」
俺ん家の最寄りの駅で待ち合わせをした。
「葵ちゃんっ」
「わざわざありがとうございます」
「外は極寒だねぇ。めちゃ着込んで来た」
「俺もっす」
「人少ないといいね」
「この時間なんで家族層は少ないと思いますけど、混んでる可能性もありますね」
俺のバイト先とは違うネットカフェに着いた。
「2人用空いてて良かったっすね」
「うん」
飲み物を持ち、フラットの個室に入った。
「なんか漫画とか取ってきます?」
「ううん…葵ちゃんで十分!」
まだ上着を脱いでいないのに俺の腰あたりを引き寄せ、座った状態で後ろからハグをしようとする。
「上着に邪魔されて、葵ちゃんが遠い」
「そりゃあそうでしょ。館内あったかいし、とりあえず上着脱ぎましょうよ」
「だね」
お互い上着を脱ぎ、改めてハグをする。今度は向き合って抱きしめ合う。
「あったか…」
呟いた柚原さんの言い方が恋人っぽさを含んでいて、あぁ…俺たち付き合ってるんだなって実感した。
「来年はさ、一緒に年越ししなきゃねー」
まだ付き合ったばっかなのに、普通に1年後の話をするの柚原さんらしいな。
「そうですね。…つーか、そろそろ…」
ハグを止める気配のない柚原さんから一旦離れようとするが、俺を抱きしめる腕の力は弱まらない。
「離してくださーい」
「やーだ。年内最後の触れ合いだもん」
「来年いっぱい触れ合ったらいいじゃないっすか」
「…。」
柚原さんは俺の顔をじっと見た。
「…?」
「来年は、葵ちゃんにいっぱい触れていいの?」
「付き合ってるんですからいいに決まってるじゃないですか」
「…約束ね。色んなとこにたくさん触れるから…覚悟してて」
「えっ…」
ちゅ…、優しくキスをされた。
色んなとこに触れる…?キスだけで心臓飛び出しそうなのに、柚原さんとそれ以上するってことだよな…?やばい、更なる色気を前に俺は死ぬかもしれない。
駅前で柚原さんを見送った。
「会えてよかった。わがまま聞いてくれてありがと」
「こちらこそありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね」
「うん。また連絡するねー」
毎日連絡しているから“良いお年を”は言わずに別れた。
もうすぐ今年が終わる。数ヶ月前まで遥か遠い存在だと思っていた柚原さんと付き合うなんて、正直まだ夢じゃないかと思う。
それでも、さっきまで触れ合っていた手が現実だと教えてくれて、来年からどんな思い出ができるか楽しみで仕方ない。…色々あったけど、良い1年だったな。
新年を迎え、nextの集まりに参加する日が来た。4人の行きつけである喫茶店に柚原さんと入店すると、すでに乙倉さんたちが1番奥の席に着いていた。
俺たちに気づき、手を振ってくれた。
「おー能勢っちー!あけおめーー!」
「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします!」
「能勢くん、明けましておめでとう。よろしくね」
「明けましておめでと」
手招きされ、乙倉さんと柚原さんの間に座った。前には唐沢さんと和久井さん。
こんなイケメン4人に囲まれて、俺は場違い過ぎねーか?
「能勢っち、何頼む?」
「えっと、おすすめありますか?」
「能勢くんよく食べるから、このカツサンドとか良いかも」
「じゃあ、それにします!」
「ユズは?オムライスでいい?」
「うん」
「翠、その服食べる時、袖気をつけなよ」
「はーい」
当たり前だけど、俺の何十倍、いや何百倍乙倉さんたちは柚原さんのことを知っているし、理解している。そこに嫉妬するとかは全然なくて、むしろこの4人の関係性が好きだなって思う。
「ていうか、能勢っちが新年の集まりに来てくれるとかびっくりだったんだけど。すっかり仲良くなったんだな!」
柚原さんは俺に頭をくっつけ、3人に伝える。
「俺たち…付き合うことになりましたぁ!」
「えぇ!?まじで!?」
「ほんとほんと。応援してくれていた3人に直接報告したくてさ」
「おめでとうー!良かったな、ユズ!!」
「ゆずくんの想いが実ったんだね!2人ともおめでとう」
「ありがとー」
「翠の圧に負けて無理矢理とかじゃない?」
唐沢先輩は心配の意味を込めて聞いてきた。
「いえ、そんなじゃないっす。ちゃんと俺もその…好きで付き合ってます」
「そっか。…翠、おめでと」
「新年早々良い報告聞けて嬉しいね」
「大吉引くよりテンション上がる」
「ほんとかよ」
3人の表情や言葉から心の底から祝ってくれているのが分かった。
それから冬休みが終わり、大学とサークルとバイトに追われる毎日に柚原さんとの時間が加わり、あっという間に俺の1年生期間は終わった。