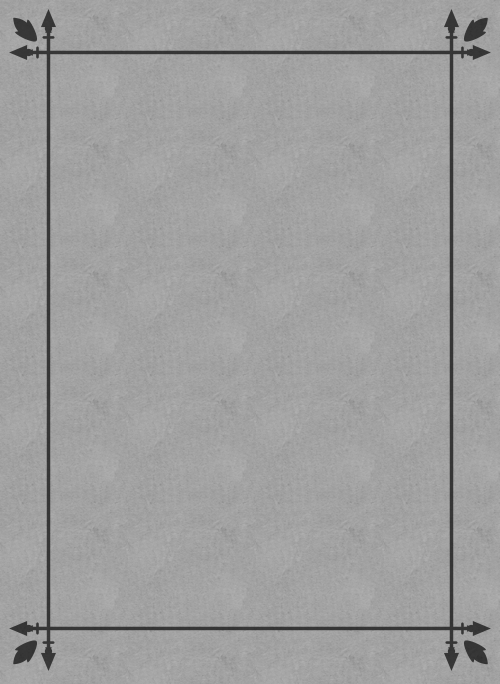柾はスマホをくるっと回して、俺のほうに画面を向けた。
テーブルの上で、黒い四角い板だけがやけに主張して見える。
「ほら、これ。さっき言ってたネタ動画」
さらっと言うけど、「ネタ動画」って単語の響きがすでに不穏だ。
その動きに釣られるみたいに、木村さんと結城さん、篠田さんたち女子が、ぞろぞろと俺の後ろに回り込んできた。
「え、見たい!」
「うわ、ガチのやつ?」
「ちょっと楽しみなんだけど」
わっと一気に背中に気配が増える。
椅子の背もたれ越しに、柔らかい笑い声と、カチャカチャ鳴るアクセサリーの音。
背中側から、女の子のシャンプーの匂いとか、柔軟剤の匂いが一気に押し寄せてくる。
甘いフローラル系とか、柑橘系とか、よくわからないけど「女子の匂い」ってやつがミックスされて、脳が処理を放棄しかける。
お、おい……近い……!
肩のすぐ後ろで、誰かの息づかいがかすかに当たっている。
「ふっ」と笑ったときの息の振動まで伝わってきて、背筋がぞわっとした。
視界の端では、長い髪がふわっと垂れて、俺の頬すれすれをかすめた。
さらさらって音がしそうなくらい、軽い感触。
こんな女子との距離感、人生で初めてかもしれない……!
いや、今までの人生、ここまで女子が密集してきたことあったか?
いやない。絶対ない。あったら覚えてる。
普段なら、女子が半径二メートル以内に入ってきた時点で緊張でフリーズするのに、今日はもう至近距離で囲まれている。
どこのハーレムアニメだよってツッコミたいけど、現実はそんな甘いもんじゃない。
心臓が変な意味でバクバクしてきて、スマホの画面に集中したいのに、意識が後ろの女の子たちに持っていかれる。
変な汗までにじみ始めて、シャツが背中に張り付く感覚が気持ち悪い。
いや、落ち着け俺。今見なきゃいけないのは女子じゃなくて、成瀬くんのネタだろ……!
「じゃ、再生するね」
柾が人差し指で再生ボタンをタップする。
こういうときも指の動きまで無駄に絵になるの、ずるい。
イヤホンじゃなくて、そのままスピーカーから音が流れた。
居酒屋のざわめきと、スマホのちょっとこもった音が混ざる。
画面の中には、私服姿の柾がいた。
今とは違って、ちょっとラフなパーカーにデニム。髪型も今より少しだけラフで、「王子様」っていうより「普通の大学生」に寄っている感じだ。
背景は多分、公園かどこかの広場だ。
遊具の影が端っこに映り込んでいて、遠くのほうには通り過ぎる人の姿も見える。
『はい、じゃあ今から「クラッカー口内爆裂」やります』
動画の中の柾が、妙に明るいテンションでカメラに向かって宣言した。
いつもの落ち着いた声よりちょっと高めで、テンションを意識的に上げているのがわかる。
画面下のほうには、誰かの笑い声も入っている。
男の声が「いけいけー」とか「死ぬなよー」とか、無責任なことを言っている。
「クラッカー……?」
「口内……?」
「なんだろうね?」
後ろの女子たちが、くすくす笑いながら覗き込む。
肩越しに伝わってくるその笑い声が、なんかやけに生々しい。
柾は画面の中で、クラッカーを口にくわえてヒモを引き、口内で爆裂させる。
「うわっ!」
「え、なにこれ!」
女子たちの悲鳴が、ほぼ同時に上がった。
俺の耳元で叫ぶのはやめてほしい。鼓膜が死ぬ。
想像以上に、過激なネタだな……。
もっと言葉遊びとか、ジェスチャー多めのコントを想像してたけど、これは……なんというか、原始的な方向に全力疾走してる。
画面の中で、柾は満足そうに笑っている。
笑顔だけはいつもの「イケメンスマイル」なのが逆にすごい。
動画はそこで終わらず、すぐに次のカットに切り替わる。
『続いて、「ミルクマン」いきまーす』
今度は、紙パックの牛乳を手にした柾が映った。
さっきよりも真顔だ。テンションが一段階下がっているのは、単に恐怖を噛みしめているだけなのかもしれない。
「ミルクマン……?」
後ろで女子たちがざわざわしている中、柾は鼻にストローを突っ込む。
画面越しなのに、見ているこっちの鼻の奥がむずむずする。
ちょっと待て……どこに向かってるんだこの動画……
俺の常識という名の安全装置が、全力で「やめろ」とサイレンを鳴らしている。
『鼻から吸って、目から出しまーす』
宣言した瞬間、「やめろ!」と画面の外から誰かがツッコんだが、柾はお構いなしに牛乳をずずずっと吸い上げた。
ストローを通っていく白い液体が妙に生々しくて、鳥肌が立つ。
数秒後、目の縁からじわっと白い液体がにじみ出てきて、そのままぽろっと垂れた。
「ぎゃああああ!」
「無理無理無理!!」
「やばいやばいやばい!!!」
俺のすぐ後ろで、女子たちがマジ悲鳴をあげる。
「キャーかっこいい~」系の悲鳴とは次元が違う、ガチの拒否反応ボイスだ。
俺の背中に、誰かが思いきりしがみついた。
ぐいっとシャツが引っ張られて、椅子が少しきしむ。
いやいや、俺を盾にしないで!?
こういうときだけ男子の背中頼るなよ!?
心の中でツッコみつつも、背中に感じる体温と柔らかさの反則コンボに、別の意味で心拍数が跳ね上がる。
でも、こんな状況でそれを意識したら俺の人間性が終わる気がするので、必死に柾のほうへ意識を戻す。
画面の中の柾は、涙目になりながらも、必死に笑顔を作ってカメラにピースしていた。
笑顔が若干ひきつっているのは、単純に痛いからだろう。そりゃそうだ。
『成功~……いった、これマジでやば……』
そこで動画が一旦切れる。
最後のほうは、音声だけで「いってぇ……」「お前バカだろ……」みたいな会話が入っていて、そこでフェードアウトだ。
俺は、じっとスマホの画面を見つめたまま、変に冷静になっていた。
さっきまで女子の距離感にうろたえていたのに、今は別の意味で現実感がバグっている。
隣で、今の本人・柾は、ちょっと照れたように笑っている。
「こういうのが好きで、いろいろやってて」
「……」
イケメンからは一ミリも想像できないネタの数々。
普通ならドン引きするのが正解なのかもしれない。
だけど、だからといって、嫌悪感があるわけでもない。
むしろ……この見た目でここまで身体張れるの、ギャップすごすぎるだろ。
あの顔面で、クラッカー口内爆発とミルクマン。
どこの誰がそんな組み合わせを想像できるんだ。
表情管理も完璧で、盛り上げるべきところでちゃんとテンションを上げている。
カメラ慣れしてるというか、「どう映るか」を理解して動いてる感じがあって、単なるバカ騒ぎには見えない。
……くそ、悔しいけどちゃんと「面白い映像」なんだよな。
思わず、口から言葉が滑り出た。
「……ネタの内容が、電撃ネットワークだね」
小さく笑いながら言うと、柾の顔がぱあっと明るくなる。
さっきまで照れ混じりだった表情が、一気に嬉しさに振り切れた。
「そうなんだよ!」
一気に食いついてきた。
椅子がきしむくらい、ぐいっと俺のほうに身を乗り出す。
「俺、電撃ネットワークが好きでさ。ああいうのやりたいんだけど、ことごとくサークルの人たちに、『一緒にはできない』って振られちゃってさ」
肩をすくめて、苦笑い。
でも、その目はどこか誇らしげにも見える。
「だって、『火は無理』『ケガするやつは無理』『学祭で出せない』って、全部止められるんだよ」
「命の危険があるからね」
気づいたら、俺も笑って返していた。
半分ツッコミ、半分本音で。
そりゃあ、普通は止めるよな……でも。
心のどこかで、「それでもやりたいんだな」と思った。
馬鹿みたいだけど、そういう執念みたいなものには弱い。
そこまで話していると、後ろで黙って動画を見ていた木村さんが、やっと口を開いた。
「え、思ってたのと違う……」
「ん?」
俺も振り返る。
木村さんは、眉間にしわを寄せて、あからさまに不満そうな顔をしていた。
結城さんが、腕を組みながら続ける。
「もっと、こう……スーツでかっこよく決めて、面白いこと言うんだと思ってた!それなら推せるって思ってたのに」
「推せるって……」
思わず小声でオウム返ししてしまう。
推しの条件に「クラッカー口内爆裂NG」とかあるんだろうか。
篠田さんも、スマホを胸の前でぎゅっと握りながら、ため息をつく。
「なんか、成瀬くんのイメージ崩れた。がっかり」
その言い方が、あまりにもストレートで。
笑い飛ばせないくらいの、冷たさが混じっていた。
喉の奥が、きゅっと冷たくなった。
……がっかり、ね。
女子たちは、勝手に納得したみたいに「戻ろ」と言い合って、自分たちの席に戻っていく。
歩き方まで、さっきより明らかにテンションが下がっている。
腰を下ろすやいなや、全員一斉にスマホを取り出して、画面をタップし始めた。
あの素早い指の動きには、妙な共通点がある。
何となく視線をやると、彼女たちの親指の動きで、だいたい何をしているか察する。
あれ……完全に、連絡先消してる動きじゃん。
「えーっと……削除、っと」
「グループからも抜けよ」
「なんか、ないわー」
断片的に聞こえてくる言葉が、こっちまで刺さってくる。
さっきまでの「キャー成瀬くん!」のテンションとは、別人みたいな声色だ。
横にいる柾は、一瞬だけ目を伏せて、小さく笑った。
「……好きなこと、全力でやってるだけなんだけどな」
その声が、さっきまでの明るさと違って、妙にか細かった。
冗談っぽく言ってるようでいて、奥のほうに小さな棘が見える。
「イケメンなのに、あんなことしないでよ!」
「成瀬くんは理想であってほしかった!」
「もっとおしゃれで、かっこいい生活してると思ってた」
女子たちは、テーブルの向こう側で、半分冗談、半分本気みたいなテンションで言いたい放題だ。
笑ってごまかしている風だけど、その笑いはまったく優しくない。
……は?
胸の奥が、ぐつっと音を立てた気がした。
さっきまで氷が揺れていた場所に、今度は熱が集まってくる。
いやいやいや……
心の中で、何かが一気に沸騰していく感覚。
指先が、じりじりと熱くなっていく。
今まで散々「成瀬くんカッコいい」「やばい」とか騒いでたくせに……!
いざ本人が、自分たちの想像と違ったら、手のひら返して「がっかり」?
指先が震える。
グラスを持っていた手に、力が入りすぎて、氷がカランと鳴った。
さっきの「週末なにして過ごしてるの?」のときの会話が、頭の中でリピートされる。
「おしゃれなカフェ巡りしてそう」
「ジム行ってそう」
あのときも、柾の本当の週末なんて、誰も聞いていなかった。
質問しているようでいて、答えを聞く気なんてなかった。
ただ、自分たちの「こうであってほしい成瀬柾」を並べていただけだ。
勝手に理想像作って、勝手に落胆してさ……
それで「がっかり」とか、よく言えるな。
気づいたら、俺は席を立っていた。
椅子がガタンと鳴る。
テーブルの会話が、一瞬だけ止まった。
「え?」
俺は女子たちのほうを向いていた。
自分でも驚くくらい、声が大きく出る。
「いい加減にしろよ!」
空気がビリッと震えた気がした。
店内のBGMまで、一瞬小さくなったように感じる。
実際は同じ音量なんだろうけど、みんなの視線が一斉にこっちに集まって、世界の音が遠のいた。
「な、なに……?」
木村さんが目を丸くする。
さっきまで余裕ぶって笑っていた顔から、血の気が引いていく。
「お前らが勝手に成瀬くんに理想を押し付けただけだろ!」
自分の口から出た言葉に、自分で驚くくらい、まっすぐだった。
どこにも笑いはなくて、ただただムカつきだけが前に出ていた。
「さっきの『週末なにして過ごしてるの?』のときもそうだよ!お前たちは『こうあってほしい成瀬くん』を押し付けるみたいに話してただけじゃないか!」
言葉が止まらない。
一度堰を切ったみたいに、思っていたことが次々と口から零れ落ちる。
「カフェ行ってそう、とか、ジム通ってそう、とか……。『そういう成瀬くんがいい』って、勝手に想像してさ。で、自分の考えと違ったら、『がっかり』って……ふざけるな!」
結城さんが、唇を噛む。
「な、なにそれ。別に、ちょっと言っただけで……」
「『イケメンなのにあんなことしないでよ』って言ったよね」
自分でも、声が低くなっているのがわかった。
今まで出したことのないトーンだ。
「それ、どういう意味?イケメンは、クラッカーも口に入れちゃいけないのかよ。牛乳を鼻から飲んだら、イケメン免許剥奪なの?」
「そういう意味じゃなくて……!」
「じゃあどういう意味か説明してくれよ」
女子たちが、言葉に詰まる。
視線は合わない。スマホの画面を見たり、グラスをいじったり、落ち着かない仕草ばかりが増えていく。
誰も、はっきりとした言葉で反論してこない。
それが余計に、さっきまでの彼女たちの発言の軽さと、残酷さを浮き彫りにする。
背中側から、柾の慌てた声が飛んできた。
「あ、相沢くん。お、落ち着いて」
振り返らなくても、困っている顔をしているのはわかる。
「俺のために怒らなくていいよ」って、きっと思ってる。
でも、今は止められなかった。
「俺は……」
喉がひゅっと鳴る。
けれど、そのまま言葉を吐き出した。
「俺は、そのままの成瀬くんが好きだ!」
……言った瞬間、脳内ででっかい警報が鳴った。
……あ。
一拍遅れて、自分の発言の意味が頭に届く。
今の「好き」は、どういう……?
いや、落ち着け俺!
時間が止まったみたいに、テーブルの周りが静まり返る。
さっきまでガヤガヤしていた声さえ、遠くのほうでぼやけて聞こえる。
グラスの中の氷が、ひとつ、コトンと鳴った音だけがやけに響いた。
女子たちはぽかんとして俺を見ているし、男子側の友達も、「え?」みたいな顔でこちらを凝視している。
そして一番近くにいた柾は、目を見開いたまま、俺を見上げていた。
その目に映っている自分の顔が、きっと真っ赤なんだろうなと思うと、余計に逃げ出したくなる。
「……」
数秒の沈黙。
ほんの数秒のはずなのに、体感的には一分くらいあった。
その沈黙に耐えきれなくなって、俺はがくんと椅子に座り込んだ。
「……い、今のは、その……」
フォローの言葉を探すけど、どれも「取り繕いです」と額に書いてあるみたいで、口に出せない。
「友達として」とか、「そういう意味じゃなくて」とか、全部言い訳みたいにしか聞こえない。
終わった……。
頭の中で、俺の大学生活がエンドロールを流し始めている。
「出演:相沢棗(モブ)」ってテロップが浮かんで、流れ星みたいに消えていく。
そのときだ。
「……ありがとう、相沢くん」
柾の声が、静かに落ちてきた。
顔を上げると、彼は少しだけ笑っていた。
いつもの「営業スマイル」とは違う、どこか力の抜けた、柔らかい笑顔。
「本当に、ありがとう」
その目には、さっき女子たちに向けていた時の寂しさが、もうなかった。
代わりにあるのは、少しの照れと、ちゃんとした感謝の色。
胸の奥が、じんわり熱くなる。
柾はゆっくりと立ち上がる。
ポケットから財布を取り出すと、そのまま幹事の榊原のところへ歩いていった。
「お、おい、成瀬?」
榊原が目を丸くする。
柾はにこっと笑いながら、紙幣をテーブルに置いた。
「これ、今日の会費。俺、行くね」
「あ、ちょ、待って。まだ二次会とか――」
「ごめん。今日はもう、いいや」
さらっと言って、コート掛けから自分のジャケットを取る。
その手つきは落ち着いていて、どこにも怒りは見えなかった。
むしろ、妙に清々しい感じすらする。
何かを諦めたんじゃなくて、「ここまで」と自分で線を引いた人間の背中だ。
行く……のか。
俺の胸が、ずきっと痛んだ。
このまま席に座っていたら、きっと俺は一生後悔する。
さっきあれだけ言っておきながら、自分だけテーブルに残るとか、そんなダサいことできるわけがない。
「お、俺も!」
反射的に立ち上がっていた。
足が勝手に動いた、ってこういうときに使うんだろう。
ポケットから財布を取り出して、慌てて中身を確かめる。
細かい計算とかどうでもいい。とりあえず払えるだけ出す。
「え、相沢?」
榊原が俺を見る。
「お、俺も、これ。それじゃ、帰るわ」
勢いのまま、会費をどさっと榊原の手に握らせる。
あとで見たら絶対払いすぎてるやつだけど、今はそんなことどうでもいい。
とにかく今は、ここから出ることのほうが大事だった。
榊原はぽかんとして、俺と柾を交互に見ている。
「え、えっ?二人ともマジで?このあとボウリング――」
「悪い。また今度」
柾が軽く手を振って、入り口のほうへ歩き出す。
声は穏やかだけど、その歩幅は迷いがない。
俺も、その背中を追うように歩き出した。
行かせるかよ。こんな空気の中、ひとりで。
テーブルのざわめきが、背中のほうで遠ざかっていく。
「ちょっと空気悪くない?」「え、どうする?」みたいな声が聞こえた気がするけど、もう耳に入らなかった。
店の扉に向かっていく柾の背中を、俺はただ、必死に追いかけた。
テーブルの上で、黒い四角い板だけがやけに主張して見える。
「ほら、これ。さっき言ってたネタ動画」
さらっと言うけど、「ネタ動画」って単語の響きがすでに不穏だ。
その動きに釣られるみたいに、木村さんと結城さん、篠田さんたち女子が、ぞろぞろと俺の後ろに回り込んできた。
「え、見たい!」
「うわ、ガチのやつ?」
「ちょっと楽しみなんだけど」
わっと一気に背中に気配が増える。
椅子の背もたれ越しに、柔らかい笑い声と、カチャカチャ鳴るアクセサリーの音。
背中側から、女の子のシャンプーの匂いとか、柔軟剤の匂いが一気に押し寄せてくる。
甘いフローラル系とか、柑橘系とか、よくわからないけど「女子の匂い」ってやつがミックスされて、脳が処理を放棄しかける。
お、おい……近い……!
肩のすぐ後ろで、誰かの息づかいがかすかに当たっている。
「ふっ」と笑ったときの息の振動まで伝わってきて、背筋がぞわっとした。
視界の端では、長い髪がふわっと垂れて、俺の頬すれすれをかすめた。
さらさらって音がしそうなくらい、軽い感触。
こんな女子との距離感、人生で初めてかもしれない……!
いや、今までの人生、ここまで女子が密集してきたことあったか?
いやない。絶対ない。あったら覚えてる。
普段なら、女子が半径二メートル以内に入ってきた時点で緊張でフリーズするのに、今日はもう至近距離で囲まれている。
どこのハーレムアニメだよってツッコミたいけど、現実はそんな甘いもんじゃない。
心臓が変な意味でバクバクしてきて、スマホの画面に集中したいのに、意識が後ろの女の子たちに持っていかれる。
変な汗までにじみ始めて、シャツが背中に張り付く感覚が気持ち悪い。
いや、落ち着け俺。今見なきゃいけないのは女子じゃなくて、成瀬くんのネタだろ……!
「じゃ、再生するね」
柾が人差し指で再生ボタンをタップする。
こういうときも指の動きまで無駄に絵になるの、ずるい。
イヤホンじゃなくて、そのままスピーカーから音が流れた。
居酒屋のざわめきと、スマホのちょっとこもった音が混ざる。
画面の中には、私服姿の柾がいた。
今とは違って、ちょっとラフなパーカーにデニム。髪型も今より少しだけラフで、「王子様」っていうより「普通の大学生」に寄っている感じだ。
背景は多分、公園かどこかの広場だ。
遊具の影が端っこに映り込んでいて、遠くのほうには通り過ぎる人の姿も見える。
『はい、じゃあ今から「クラッカー口内爆裂」やります』
動画の中の柾が、妙に明るいテンションでカメラに向かって宣言した。
いつもの落ち着いた声よりちょっと高めで、テンションを意識的に上げているのがわかる。
画面下のほうには、誰かの笑い声も入っている。
男の声が「いけいけー」とか「死ぬなよー」とか、無責任なことを言っている。
「クラッカー……?」
「口内……?」
「なんだろうね?」
後ろの女子たちが、くすくす笑いながら覗き込む。
肩越しに伝わってくるその笑い声が、なんかやけに生々しい。
柾は画面の中で、クラッカーを口にくわえてヒモを引き、口内で爆裂させる。
「うわっ!」
「え、なにこれ!」
女子たちの悲鳴が、ほぼ同時に上がった。
俺の耳元で叫ぶのはやめてほしい。鼓膜が死ぬ。
想像以上に、過激なネタだな……。
もっと言葉遊びとか、ジェスチャー多めのコントを想像してたけど、これは……なんというか、原始的な方向に全力疾走してる。
画面の中で、柾は満足そうに笑っている。
笑顔だけはいつもの「イケメンスマイル」なのが逆にすごい。
動画はそこで終わらず、すぐに次のカットに切り替わる。
『続いて、「ミルクマン」いきまーす』
今度は、紙パックの牛乳を手にした柾が映った。
さっきよりも真顔だ。テンションが一段階下がっているのは、単に恐怖を噛みしめているだけなのかもしれない。
「ミルクマン……?」
後ろで女子たちがざわざわしている中、柾は鼻にストローを突っ込む。
画面越しなのに、見ているこっちの鼻の奥がむずむずする。
ちょっと待て……どこに向かってるんだこの動画……
俺の常識という名の安全装置が、全力で「やめろ」とサイレンを鳴らしている。
『鼻から吸って、目から出しまーす』
宣言した瞬間、「やめろ!」と画面の外から誰かがツッコんだが、柾はお構いなしに牛乳をずずずっと吸い上げた。
ストローを通っていく白い液体が妙に生々しくて、鳥肌が立つ。
数秒後、目の縁からじわっと白い液体がにじみ出てきて、そのままぽろっと垂れた。
「ぎゃああああ!」
「無理無理無理!!」
「やばいやばいやばい!!!」
俺のすぐ後ろで、女子たちがマジ悲鳴をあげる。
「キャーかっこいい~」系の悲鳴とは次元が違う、ガチの拒否反応ボイスだ。
俺の背中に、誰かが思いきりしがみついた。
ぐいっとシャツが引っ張られて、椅子が少しきしむ。
いやいや、俺を盾にしないで!?
こういうときだけ男子の背中頼るなよ!?
心の中でツッコみつつも、背中に感じる体温と柔らかさの反則コンボに、別の意味で心拍数が跳ね上がる。
でも、こんな状況でそれを意識したら俺の人間性が終わる気がするので、必死に柾のほうへ意識を戻す。
画面の中の柾は、涙目になりながらも、必死に笑顔を作ってカメラにピースしていた。
笑顔が若干ひきつっているのは、単純に痛いからだろう。そりゃそうだ。
『成功~……いった、これマジでやば……』
そこで動画が一旦切れる。
最後のほうは、音声だけで「いってぇ……」「お前バカだろ……」みたいな会話が入っていて、そこでフェードアウトだ。
俺は、じっとスマホの画面を見つめたまま、変に冷静になっていた。
さっきまで女子の距離感にうろたえていたのに、今は別の意味で現実感がバグっている。
隣で、今の本人・柾は、ちょっと照れたように笑っている。
「こういうのが好きで、いろいろやってて」
「……」
イケメンからは一ミリも想像できないネタの数々。
普通ならドン引きするのが正解なのかもしれない。
だけど、だからといって、嫌悪感があるわけでもない。
むしろ……この見た目でここまで身体張れるの、ギャップすごすぎるだろ。
あの顔面で、クラッカー口内爆発とミルクマン。
どこの誰がそんな組み合わせを想像できるんだ。
表情管理も完璧で、盛り上げるべきところでちゃんとテンションを上げている。
カメラ慣れしてるというか、「どう映るか」を理解して動いてる感じがあって、単なるバカ騒ぎには見えない。
……くそ、悔しいけどちゃんと「面白い映像」なんだよな。
思わず、口から言葉が滑り出た。
「……ネタの内容が、電撃ネットワークだね」
小さく笑いながら言うと、柾の顔がぱあっと明るくなる。
さっきまで照れ混じりだった表情が、一気に嬉しさに振り切れた。
「そうなんだよ!」
一気に食いついてきた。
椅子がきしむくらい、ぐいっと俺のほうに身を乗り出す。
「俺、電撃ネットワークが好きでさ。ああいうのやりたいんだけど、ことごとくサークルの人たちに、『一緒にはできない』って振られちゃってさ」
肩をすくめて、苦笑い。
でも、その目はどこか誇らしげにも見える。
「だって、『火は無理』『ケガするやつは無理』『学祭で出せない』って、全部止められるんだよ」
「命の危険があるからね」
気づいたら、俺も笑って返していた。
半分ツッコミ、半分本音で。
そりゃあ、普通は止めるよな……でも。
心のどこかで、「それでもやりたいんだな」と思った。
馬鹿みたいだけど、そういう執念みたいなものには弱い。
そこまで話していると、後ろで黙って動画を見ていた木村さんが、やっと口を開いた。
「え、思ってたのと違う……」
「ん?」
俺も振り返る。
木村さんは、眉間にしわを寄せて、あからさまに不満そうな顔をしていた。
結城さんが、腕を組みながら続ける。
「もっと、こう……スーツでかっこよく決めて、面白いこと言うんだと思ってた!それなら推せるって思ってたのに」
「推せるって……」
思わず小声でオウム返ししてしまう。
推しの条件に「クラッカー口内爆裂NG」とかあるんだろうか。
篠田さんも、スマホを胸の前でぎゅっと握りながら、ため息をつく。
「なんか、成瀬くんのイメージ崩れた。がっかり」
その言い方が、あまりにもストレートで。
笑い飛ばせないくらいの、冷たさが混じっていた。
喉の奥が、きゅっと冷たくなった。
……がっかり、ね。
女子たちは、勝手に納得したみたいに「戻ろ」と言い合って、自分たちの席に戻っていく。
歩き方まで、さっきより明らかにテンションが下がっている。
腰を下ろすやいなや、全員一斉にスマホを取り出して、画面をタップし始めた。
あの素早い指の動きには、妙な共通点がある。
何となく視線をやると、彼女たちの親指の動きで、だいたい何をしているか察する。
あれ……完全に、連絡先消してる動きじゃん。
「えーっと……削除、っと」
「グループからも抜けよ」
「なんか、ないわー」
断片的に聞こえてくる言葉が、こっちまで刺さってくる。
さっきまでの「キャー成瀬くん!」のテンションとは、別人みたいな声色だ。
横にいる柾は、一瞬だけ目を伏せて、小さく笑った。
「……好きなこと、全力でやってるだけなんだけどな」
その声が、さっきまでの明るさと違って、妙にか細かった。
冗談っぽく言ってるようでいて、奥のほうに小さな棘が見える。
「イケメンなのに、あんなことしないでよ!」
「成瀬くんは理想であってほしかった!」
「もっとおしゃれで、かっこいい生活してると思ってた」
女子たちは、テーブルの向こう側で、半分冗談、半分本気みたいなテンションで言いたい放題だ。
笑ってごまかしている風だけど、その笑いはまったく優しくない。
……は?
胸の奥が、ぐつっと音を立てた気がした。
さっきまで氷が揺れていた場所に、今度は熱が集まってくる。
いやいやいや……
心の中で、何かが一気に沸騰していく感覚。
指先が、じりじりと熱くなっていく。
今まで散々「成瀬くんカッコいい」「やばい」とか騒いでたくせに……!
いざ本人が、自分たちの想像と違ったら、手のひら返して「がっかり」?
指先が震える。
グラスを持っていた手に、力が入りすぎて、氷がカランと鳴った。
さっきの「週末なにして過ごしてるの?」のときの会話が、頭の中でリピートされる。
「おしゃれなカフェ巡りしてそう」
「ジム行ってそう」
あのときも、柾の本当の週末なんて、誰も聞いていなかった。
質問しているようでいて、答えを聞く気なんてなかった。
ただ、自分たちの「こうであってほしい成瀬柾」を並べていただけだ。
勝手に理想像作って、勝手に落胆してさ……
それで「がっかり」とか、よく言えるな。
気づいたら、俺は席を立っていた。
椅子がガタンと鳴る。
テーブルの会話が、一瞬だけ止まった。
「え?」
俺は女子たちのほうを向いていた。
自分でも驚くくらい、声が大きく出る。
「いい加減にしろよ!」
空気がビリッと震えた気がした。
店内のBGMまで、一瞬小さくなったように感じる。
実際は同じ音量なんだろうけど、みんなの視線が一斉にこっちに集まって、世界の音が遠のいた。
「な、なに……?」
木村さんが目を丸くする。
さっきまで余裕ぶって笑っていた顔から、血の気が引いていく。
「お前らが勝手に成瀬くんに理想を押し付けただけだろ!」
自分の口から出た言葉に、自分で驚くくらい、まっすぐだった。
どこにも笑いはなくて、ただただムカつきだけが前に出ていた。
「さっきの『週末なにして過ごしてるの?』のときもそうだよ!お前たちは『こうあってほしい成瀬くん』を押し付けるみたいに話してただけじゃないか!」
言葉が止まらない。
一度堰を切ったみたいに、思っていたことが次々と口から零れ落ちる。
「カフェ行ってそう、とか、ジム通ってそう、とか……。『そういう成瀬くんがいい』って、勝手に想像してさ。で、自分の考えと違ったら、『がっかり』って……ふざけるな!」
結城さんが、唇を噛む。
「な、なにそれ。別に、ちょっと言っただけで……」
「『イケメンなのにあんなことしないでよ』って言ったよね」
自分でも、声が低くなっているのがわかった。
今まで出したことのないトーンだ。
「それ、どういう意味?イケメンは、クラッカーも口に入れちゃいけないのかよ。牛乳を鼻から飲んだら、イケメン免許剥奪なの?」
「そういう意味じゃなくて……!」
「じゃあどういう意味か説明してくれよ」
女子たちが、言葉に詰まる。
視線は合わない。スマホの画面を見たり、グラスをいじったり、落ち着かない仕草ばかりが増えていく。
誰も、はっきりとした言葉で反論してこない。
それが余計に、さっきまでの彼女たちの発言の軽さと、残酷さを浮き彫りにする。
背中側から、柾の慌てた声が飛んできた。
「あ、相沢くん。お、落ち着いて」
振り返らなくても、困っている顔をしているのはわかる。
「俺のために怒らなくていいよ」って、きっと思ってる。
でも、今は止められなかった。
「俺は……」
喉がひゅっと鳴る。
けれど、そのまま言葉を吐き出した。
「俺は、そのままの成瀬くんが好きだ!」
……言った瞬間、脳内ででっかい警報が鳴った。
……あ。
一拍遅れて、自分の発言の意味が頭に届く。
今の「好き」は、どういう……?
いや、落ち着け俺!
時間が止まったみたいに、テーブルの周りが静まり返る。
さっきまでガヤガヤしていた声さえ、遠くのほうでぼやけて聞こえる。
グラスの中の氷が、ひとつ、コトンと鳴った音だけがやけに響いた。
女子たちはぽかんとして俺を見ているし、男子側の友達も、「え?」みたいな顔でこちらを凝視している。
そして一番近くにいた柾は、目を見開いたまま、俺を見上げていた。
その目に映っている自分の顔が、きっと真っ赤なんだろうなと思うと、余計に逃げ出したくなる。
「……」
数秒の沈黙。
ほんの数秒のはずなのに、体感的には一分くらいあった。
その沈黙に耐えきれなくなって、俺はがくんと椅子に座り込んだ。
「……い、今のは、その……」
フォローの言葉を探すけど、どれも「取り繕いです」と額に書いてあるみたいで、口に出せない。
「友達として」とか、「そういう意味じゃなくて」とか、全部言い訳みたいにしか聞こえない。
終わった……。
頭の中で、俺の大学生活がエンドロールを流し始めている。
「出演:相沢棗(モブ)」ってテロップが浮かんで、流れ星みたいに消えていく。
そのときだ。
「……ありがとう、相沢くん」
柾の声が、静かに落ちてきた。
顔を上げると、彼は少しだけ笑っていた。
いつもの「営業スマイル」とは違う、どこか力の抜けた、柔らかい笑顔。
「本当に、ありがとう」
その目には、さっき女子たちに向けていた時の寂しさが、もうなかった。
代わりにあるのは、少しの照れと、ちゃんとした感謝の色。
胸の奥が、じんわり熱くなる。
柾はゆっくりと立ち上がる。
ポケットから財布を取り出すと、そのまま幹事の榊原のところへ歩いていった。
「お、おい、成瀬?」
榊原が目を丸くする。
柾はにこっと笑いながら、紙幣をテーブルに置いた。
「これ、今日の会費。俺、行くね」
「あ、ちょ、待って。まだ二次会とか――」
「ごめん。今日はもう、いいや」
さらっと言って、コート掛けから自分のジャケットを取る。
その手つきは落ち着いていて、どこにも怒りは見えなかった。
むしろ、妙に清々しい感じすらする。
何かを諦めたんじゃなくて、「ここまで」と自分で線を引いた人間の背中だ。
行く……のか。
俺の胸が、ずきっと痛んだ。
このまま席に座っていたら、きっと俺は一生後悔する。
さっきあれだけ言っておきながら、自分だけテーブルに残るとか、そんなダサいことできるわけがない。
「お、俺も!」
反射的に立ち上がっていた。
足が勝手に動いた、ってこういうときに使うんだろう。
ポケットから財布を取り出して、慌てて中身を確かめる。
細かい計算とかどうでもいい。とりあえず払えるだけ出す。
「え、相沢?」
榊原が俺を見る。
「お、俺も、これ。それじゃ、帰るわ」
勢いのまま、会費をどさっと榊原の手に握らせる。
あとで見たら絶対払いすぎてるやつだけど、今はそんなことどうでもいい。
とにかく今は、ここから出ることのほうが大事だった。
榊原はぽかんとして、俺と柾を交互に見ている。
「え、えっ?二人ともマジで?このあとボウリング――」
「悪い。また今度」
柾が軽く手を振って、入り口のほうへ歩き出す。
声は穏やかだけど、その歩幅は迷いがない。
俺も、その背中を追うように歩き出した。
行かせるかよ。こんな空気の中、ひとりで。
テーブルのざわめきが、背中のほうで遠ざかっていく。
「ちょっと空気悪くない?」「え、どうする?」みたいな声が聞こえた気がするけど、もう耳に入らなかった。
店の扉に向かっていく柾の背中を、俺はただ、必死に追いかけた。