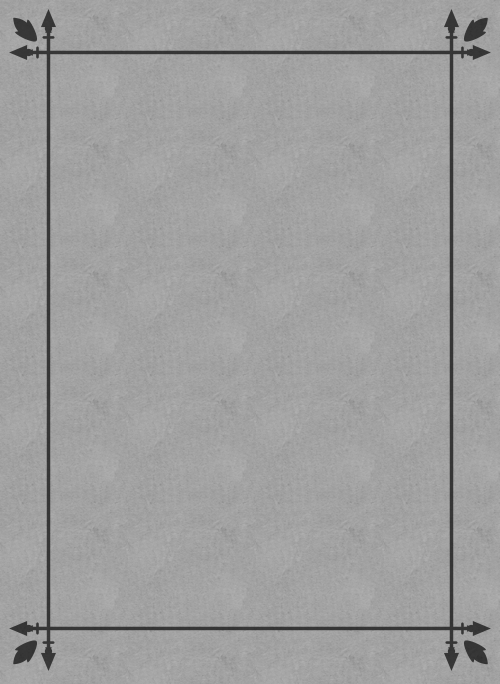女子たちが、タイミングを見計らったみたいに一斉に柾のほうへ顔を向けた。
「ねえねえ、成瀬くんってさ、週末なにして過ごしてるの?」
声の主は、やっぱりというか、俺の真正面に座っている女子——木村さんだ。
さっきから隙あらば柾に話しかけようとしてたし、満を持しての質問って感じ。
トーンは軽いくせに、目だけがやたらきらきらしてる。
あー……始まったな……モテ男タイム……
テーブルの上で、空気がさらっと切り替わるのがわかる。
「みんなでわちゃわちゃ」から、「柾を中心としたトークショー」モードへ。
柾はグラスを指でくるっと回しながら、少しだけ考えるように視線を泳がせた。
グラスの縁に触れる指がやけに綺麗なのは、今は忘れておきたい。
「うーん、特にこれと言って……」
その、控えめな答え方すら、なんかありそうに聞こえるからずるい。
「えー、絶対なんかしてるでしょ」
木村さんが、食い気味にかぶせてくる。
自分で質問しておいて、答えが「特に」だと納得いかないらしい。
ていうか「あなたの週末ライフ、私の想像通りであってほしい」オーラがすごい。
「当てっこしない?」
木村さんがぱっと身を乗り出す。
テーブルの上のグラスが、かすかに揺れた。
「私、成瀬くんはカフェ巡りとかしてそう!」
出た、カフェ男子……
思わず心の中でツッコむ。
口には出さない。出したら終わる。
「あーわかる!」
柾の斜め向かいに座ってる女子——篠田さんが、すぐさま乗っかってくる。
この二人、息が合いすぎててちょっと怖い。
「なんか、おしゃれカフェで本とか読んでそうじゃない?ていうか、映えスイーツの隣に座ってても違和感ないタイプ」
例えがもう顔面偏差値70前提なんだよな……。
俺が映えスイーツ好きって言ったら「映えスイーツがしょぼく見えるからやめて」って言われるやつだろ、知ってる。
「私はねー……ジムとか行ってるのかなって思った!」
篠田さんが、グラスを口元に運びながら首をかしげる。
氷がカランと鳴って、妙にそれっぽい演出になっているのが悔しい。
「わかる!ストイックそう!」
柾の真正面の席にいる結城さんが、ぱっと柾の腕のあたりを見て——。
「だって、いい体してるもんね!っきゃ!」
自分で言って、自分で勝手に照れている。
手で自分の頬を仰いで「やだ〜」とか言ってるけど、全然やだと思ってないやつだ、絶対。
柾は「え?」って顔で軽く笑ってるけど、女子三人は「きゃー」「やば」「それな」みたいな空気で勝手に盛り上がっていく。
「腕のラインきれいだよね」
「シャツ似合うタイプだよね〜」
「夏、半袖になったらどうしよう……」
どうしようって何……?
知らんけど、勝手にどうにかしてくれ……
盛り上がってるな……そして当然のように、俺の存在は華麗にスルー……!
こっちは同じテーブルの、しかも柾のすぐ隣の席なんだけどな。
物理的な距離はゼロ距離に近いのに、空気的な距離はもはやパーテーションどころか壁二枚分くらいある。
「え、でもカフェ似合う〜」
「ジムでタンクトップとか着てたら絶対やばいよね」
「てか、日曜の朝にランニングしてそう」
女子たちの妄想は、柾の知らないところで勝手に膨らんでいく。
現実の柾からどんどん離れていって、「理想の男・成瀬ver」が形成されているのがわかる。
カフェ×ジム×ランニング……勝手に理想の彼氏像、組み上がってるじゃん。
次あたり「NISAしてそう」とか言い出すだろ?
柾は「いやいや」と苦笑しながら、特に強く否定もしないで受け流している。
実際どうなのかはぼかしつつ、相手のテンションを壊さない範囲でやんわりかわす——。
この辺のさばき方も、ちゃんとモテ慣れてる人っぽい。
はー……遠い世界の会話だな……
グラスの水をちびちびやりながら、俺は適度にうなずく係に徹していた。
たまに「へー」とか「そうなんだ」とか、テキトーな相槌を挟む。
どうせ俺がしゃべっても、この柾トークショーの邪魔になるだけだ。
——そのときだ。
「相沢くんは、週末何して過ごすの?」
不意に、すぐ隣から俺の名前が呼ばれた。
「えっ」
びくっと変な声が出る。
喉が準備してなかった方向に声を出したせいで、予想以上に高い。
女子たちが一斉にこちらを見る。
「え、しゃべるんだこの人」みたいな、微妙なニュアンスが混じった視線が突き刺さる。
え、ちょっと待って、なんで俺に振る?
え!俺に話振るの!?
え、なに、今の流れ的に、カフェ巡りとかジムとかランニングとか、そういうリア充ワードを求められてる流れなんだけど!?
この成瀬柾トークショーに、急に一般人ゲスト参加みたいな感じ?
「先週は?」
柾が、ほんの少しだけ身を寄せてくる。
距離が近い。近すぎる。
肩と肩の間の空間が、軽く詰められた気がした。
香水の匂いがふわっと鼻先をかすめて、頭の中の処理能力が一瞬でオーバーヒートする。
近っ……ちょ、今、この距離でイケメンに見つめられるメンタル、俺持ってない……!
「あー……」
口が空回りしながら、なんとか言葉をひねり出す。
「先週は、ライブに行ったよ……」
「ライブ?」
篠田さんが、すかさず反応する。
ちょっと興味の色を浮かべた、けど——そこには軽くジャッジの気配も混じっていた。
「え?バンドとか?それともK-POPとか?」
質問というより、どっちかであってほしい期待を含んだ確認だ。
ここで「バンド!」って言えれば、「あ、音楽好きなんだ〜」で済むんだろうし、「K-POP!」って言えれば、「どのグループ?」みたいな女子受け良さそうなトークに移行できそう。
ここで「K-POPです」とか言えたら、もう少し陽キャ寄り判定が出るんだろうな、と頭の片隅で思う。
でも、嘘はつけない。
「あ、いや、その……」
一拍、間を置いてから、観念して口を開いた。
「い、いや、お笑いの……」
一瞬で、テーブルの温度が変わった気がした。
「……あー」
女子たちの視線が、目に見えて微妙な色に変わる。
さっきまでほんのり前のめりだった上半身が、わかりやすく椅子の背もたれに戻っていく。
出たよ、この「陰キャはこれだから〜」みたいな目!!
わかってたけど!知ってたけど!こうも露骨に温度差出されると、心のHP削れるんだよな……
別にいいだろ、お笑いライブ。
人間が生身で喋って笑わせてくれる、最高のエンタメじゃんか。
ネタで世界観つくって、オチで綺麗に回収して、爆発みたいに笑い起きるあの感じとか、めちゃくちゃ尊いだろ。
でも、彼女たちの中でキラキラ大学生の週末といえば、多分もっとこう——
合コン、ショッピング、インスタ映えイベント、季節ごとのフェス、みたいなやつなんだろう。
「お笑いなんだ〜……」
「へえ……」
テンションだけ半音下がった「へえ」が、地味に刺さる。
くそ……俺の週末、キラキラポイント低すぎる……
いや、俺的には満点なんだけどな……
言わなきゃよかったかな、と軽く後悔しかけたところで——。
「え、相沢くん、お笑い好きなの?」
隣から、ぱっと明るい声が飛んできた。
さっきまでより、ほんの少しだけトーンが高い。
柾が、心底驚いたみたいに目を輝かせて俺を見ていた。
「俺も!」
「えっ」
想定外すぎて、間抜けな返事しか出てこない。
思わず、グラスを持つ手がカタッと揺れた。
「どこのライブ会場行ったの?」
「あ、え、その……新宿の……」
篠田さんが、慌てて話に乗ろうとする。
「新宿かー。私も、前にルミネ行ったよ?」
たぶん、さっきの「陰キャっぽ」リアクションが若干悪目立ちした自覚があるんだろう。
柾がこの話に興味を示していることで、ここで挽回しとこう、みたいな気配がにじんでいる。
「ルミネって、あれだよね?ルミネtheよしもと……?」
「そうそう!」
木村さんが、自分の知識がヒットしたのが嬉しそうに胸を張る。
「よくテレビ出てる人とか出てるとこでしょ?」
「うん、そうそう」
そこまでは合ってる。合ってるんだけど——。
「あ、ルミネはあんまり行かないかも……」
正直に答えた瞬間、また少し空気がずれる。
「え、そうなんだ……?」
やめて、その「せっかく合わせたのに無駄にしやがって感」を滲ませるの……!
こっちは別にルミネを否定してるわけじゃないのに、なんか「空気読めてない人」みたいになるじゃん……!
どうフォローしようかと口ごもっていると——。
「もしかして、西新宿?」
柾が、すっと言葉を差し込んできた。
そのピンポイント感に、思わず心臓が跳ねる。
「……うん」
思わず姿勢を正してしまう。
まさか当ててくるとは思わなかった。
「ナルゲキ」
自分でもちょっと声が小さくなったのがわかる。
通じないだろうな、って半分諦めながら口にしたその名前を——。
「やっぱり」
柾の口元が、楽しそうにふわっと緩んだ。
「俺もよく行くよ!面白いよね、ナルゲキのK-PROライブ」
その瞬間、女子たちの表情がそろって固まった。
「……ナル、げき?」
「え、なにそれ」
「新宿の劇場?」
小声の検索ワードみたいなささやきが、テーブルの上を飛び交う。
「ナルゲキ 新宿で出るかな……」
「えっと……ナルゲキ お笑い……っと」
ちらっと視線を落とすと、スマホを太ももの上でそっと開いているのが見えた。
画面の光が膝のところでちらちら揺れている。
あ、絶対今「ナルゲキ」って打ってる……
俺と柾だけが、すっと通じ合ってる感じがして、ちょっと変な感覚になる。
劇場の椅子の固さとか、ネタ前の独特のざわつきとか、あの空気の湿度とか——そういう細かいところまで共有できる相手に、まさかここで出会うとは思ってなかった。
……俺とは程遠い世界の人だと思ってたけど、同じ趣味なんて、意外だ。
「そういえばさ」
そこで、結城さんが、思い出したように声を上げた。
「成瀬くんたちの大学って、お笑いサークルあったよね?」
「え、そうなの?」
篠田さんが身を乗り出す。
さっき検索してたスマホを、テーブルの下でぱたんと閉じる。
「あ、私の友達、こないだそこのお笑いサークルのライブ見てきたって言ってた。結構面白かったーって」
「へえ」
柾が少しだけ目を丸くしてから、すぐに笑う。
「あ、そうなんだ。俺は一年だから、まだ出たことないけど」
「え」
思わず、俺のほうが大きな声を出してしまった。
「じゃあ……入ってるんだ?お笑いサークル」
「うん。一応ね」
柾は、なんてことないみたいに言うけど、俺の頭の中では情報量が多すぎて、処理速度が追いつかない。
顔面国宝みたいなイケメンで、爽やかなのに、お笑いサークル所属???
設定盛りすぎじゃない?
「コンビ組んでるの?漫才?コント?あ、それともピン?」
気づいたら、矢継ぎ早に質問していた。
こういうときだけ、コミュ障フィルターが外れるのが我ながらずるい。
好きなジャンルの話になると、オタク特有の早口が出そうになるのを必死で押さえる。
柾は、少しだけ視線を泳がせてから、苦笑いを浮かべた。
「本当はコンビ組みたかったんだけどさ」
「うん」
「少し組むと、方向性が違うって言われて振られて……」
その言い方が妙におかしくて、俺は思わず吹き出した。
「ぶっ」
「え、そんなおかしい?」
「だって」
笑いをこらえきれなくて、テーブルに肘をついて肩を震わせる。
「成瀬くん、絶対モテるのに!相方には振られるんだね!」
「笑い事じゃないんだけど」
柾が、ちょっと不貞腐れたみたいに唇を尖らせる。
その表情が、完璧モードからちょっと崩れてて、妙に人間味があって——正直、かわいい。
「ここ一ヶ月、振られまくっててつらいんだけど。コンビも、トリオも、お試しユニットも、全部『ちょっと違うかな』って……」
「ここ一ヶ月で何人にアタックしたのそれ……」
「数えたくない」
「それさ、恋愛話だったら完全にメンヘラ案件だよね?」
「やめて」
柾が、グラスの水を一口飲んでから、ふぅと息を吐く。
「ネタ合わせして、ちょっと楽しくなってきたなって思った頃に、ごめん、やっぱりさ……って言われるの、地味にダメージくるんだよ」
「もしかしてさ」
木村さんが、そこでまた会話に乱入してくる。
「成瀬くん、イケメンすぎてサークルの中で浮いてるんじゃない?」
「それだ!」
結城さんが、手を打って同意する。
「そうだよ、嫉妬よ嫉妬。成瀬くんの隣に立つと自分がかすむから、組みたくないんだよ」
「いや、そういうんじゃないと思うけど……」
少し戸惑っているのか、柾が視線を落とす。
耳の先が、ほんのり赤い。
いや、でも実際その説あるだろ……同じステージに並んだら、観客の目線ぜんぶ持ってかれそうだし。
「ていうか、それ、相方のメンタル試されない?」
「顔面格差コンビって言われたくないもんね〜」
女子たちは女子たちで、また別方向に話を膨らませ始める。
お笑いの話なのか、ビジュアルの話なのか、もはやよくわからない。
俺は、グラスを指でくるくる回しながら、ぽつりと呟いた。
「俺、成瀬くんのネタ見たいな」
言った瞬間、空気が少し変わった。
女子たちの「イケメンいじり」路線から、すっと話題が本筋——お笑いのほうに戻ってくる。
柾が、こっちを見た。
さっきよりも、真っ直ぐな目。
「……見る?」
唐突にそう言うと、おもむろにスマホをポケットから取り出す。
「え、今?」
「どうせなら、生で見せたかったんだけど。まだライブ出てないし」
ロックを外して、何度か画面をタップする。
再生履歴なのか、フォルダなのか、慣れた指の動きだ。
ホーム画面のアイコン配置がちらっと目に入って、「あ、意外とシンプルなんだ」とかどうでもいい情報が頭に残る。
「同期の前で練習したときのやつ、撮ってもらっててさ。出来はまだまだだけど」
そう言って、柾はスマホをくるっと回して、俺のほうに画面を向けた。
俺の喉が、ごくりと鳴った。
柾のネタ動画……どんなのだろう?
「ねえねえ、成瀬くんってさ、週末なにして過ごしてるの?」
声の主は、やっぱりというか、俺の真正面に座っている女子——木村さんだ。
さっきから隙あらば柾に話しかけようとしてたし、満を持しての質問って感じ。
トーンは軽いくせに、目だけがやたらきらきらしてる。
あー……始まったな……モテ男タイム……
テーブルの上で、空気がさらっと切り替わるのがわかる。
「みんなでわちゃわちゃ」から、「柾を中心としたトークショー」モードへ。
柾はグラスを指でくるっと回しながら、少しだけ考えるように視線を泳がせた。
グラスの縁に触れる指がやけに綺麗なのは、今は忘れておきたい。
「うーん、特にこれと言って……」
その、控えめな答え方すら、なんかありそうに聞こえるからずるい。
「えー、絶対なんかしてるでしょ」
木村さんが、食い気味にかぶせてくる。
自分で質問しておいて、答えが「特に」だと納得いかないらしい。
ていうか「あなたの週末ライフ、私の想像通りであってほしい」オーラがすごい。
「当てっこしない?」
木村さんがぱっと身を乗り出す。
テーブルの上のグラスが、かすかに揺れた。
「私、成瀬くんはカフェ巡りとかしてそう!」
出た、カフェ男子……
思わず心の中でツッコむ。
口には出さない。出したら終わる。
「あーわかる!」
柾の斜め向かいに座ってる女子——篠田さんが、すぐさま乗っかってくる。
この二人、息が合いすぎててちょっと怖い。
「なんか、おしゃれカフェで本とか読んでそうじゃない?ていうか、映えスイーツの隣に座ってても違和感ないタイプ」
例えがもう顔面偏差値70前提なんだよな……。
俺が映えスイーツ好きって言ったら「映えスイーツがしょぼく見えるからやめて」って言われるやつだろ、知ってる。
「私はねー……ジムとか行ってるのかなって思った!」
篠田さんが、グラスを口元に運びながら首をかしげる。
氷がカランと鳴って、妙にそれっぽい演出になっているのが悔しい。
「わかる!ストイックそう!」
柾の真正面の席にいる結城さんが、ぱっと柾の腕のあたりを見て——。
「だって、いい体してるもんね!っきゃ!」
自分で言って、自分で勝手に照れている。
手で自分の頬を仰いで「やだ〜」とか言ってるけど、全然やだと思ってないやつだ、絶対。
柾は「え?」って顔で軽く笑ってるけど、女子三人は「きゃー」「やば」「それな」みたいな空気で勝手に盛り上がっていく。
「腕のラインきれいだよね」
「シャツ似合うタイプだよね〜」
「夏、半袖になったらどうしよう……」
どうしようって何……?
知らんけど、勝手にどうにかしてくれ……
盛り上がってるな……そして当然のように、俺の存在は華麗にスルー……!
こっちは同じテーブルの、しかも柾のすぐ隣の席なんだけどな。
物理的な距離はゼロ距離に近いのに、空気的な距離はもはやパーテーションどころか壁二枚分くらいある。
「え、でもカフェ似合う〜」
「ジムでタンクトップとか着てたら絶対やばいよね」
「てか、日曜の朝にランニングしてそう」
女子たちの妄想は、柾の知らないところで勝手に膨らんでいく。
現実の柾からどんどん離れていって、「理想の男・成瀬ver」が形成されているのがわかる。
カフェ×ジム×ランニング……勝手に理想の彼氏像、組み上がってるじゃん。
次あたり「NISAしてそう」とか言い出すだろ?
柾は「いやいや」と苦笑しながら、特に強く否定もしないで受け流している。
実際どうなのかはぼかしつつ、相手のテンションを壊さない範囲でやんわりかわす——。
この辺のさばき方も、ちゃんとモテ慣れてる人っぽい。
はー……遠い世界の会話だな……
グラスの水をちびちびやりながら、俺は適度にうなずく係に徹していた。
たまに「へー」とか「そうなんだ」とか、テキトーな相槌を挟む。
どうせ俺がしゃべっても、この柾トークショーの邪魔になるだけだ。
——そのときだ。
「相沢くんは、週末何して過ごすの?」
不意に、すぐ隣から俺の名前が呼ばれた。
「えっ」
びくっと変な声が出る。
喉が準備してなかった方向に声を出したせいで、予想以上に高い。
女子たちが一斉にこちらを見る。
「え、しゃべるんだこの人」みたいな、微妙なニュアンスが混じった視線が突き刺さる。
え、ちょっと待って、なんで俺に振る?
え!俺に話振るの!?
え、なに、今の流れ的に、カフェ巡りとかジムとかランニングとか、そういうリア充ワードを求められてる流れなんだけど!?
この成瀬柾トークショーに、急に一般人ゲスト参加みたいな感じ?
「先週は?」
柾が、ほんの少しだけ身を寄せてくる。
距離が近い。近すぎる。
肩と肩の間の空間が、軽く詰められた気がした。
香水の匂いがふわっと鼻先をかすめて、頭の中の処理能力が一瞬でオーバーヒートする。
近っ……ちょ、今、この距離でイケメンに見つめられるメンタル、俺持ってない……!
「あー……」
口が空回りしながら、なんとか言葉をひねり出す。
「先週は、ライブに行ったよ……」
「ライブ?」
篠田さんが、すかさず反応する。
ちょっと興味の色を浮かべた、けど——そこには軽くジャッジの気配も混じっていた。
「え?バンドとか?それともK-POPとか?」
質問というより、どっちかであってほしい期待を含んだ確認だ。
ここで「バンド!」って言えれば、「あ、音楽好きなんだ〜」で済むんだろうし、「K-POP!」って言えれば、「どのグループ?」みたいな女子受け良さそうなトークに移行できそう。
ここで「K-POPです」とか言えたら、もう少し陽キャ寄り判定が出るんだろうな、と頭の片隅で思う。
でも、嘘はつけない。
「あ、いや、その……」
一拍、間を置いてから、観念して口を開いた。
「い、いや、お笑いの……」
一瞬で、テーブルの温度が変わった気がした。
「……あー」
女子たちの視線が、目に見えて微妙な色に変わる。
さっきまでほんのり前のめりだった上半身が、わかりやすく椅子の背もたれに戻っていく。
出たよ、この「陰キャはこれだから〜」みたいな目!!
わかってたけど!知ってたけど!こうも露骨に温度差出されると、心のHP削れるんだよな……
別にいいだろ、お笑いライブ。
人間が生身で喋って笑わせてくれる、最高のエンタメじゃんか。
ネタで世界観つくって、オチで綺麗に回収して、爆発みたいに笑い起きるあの感じとか、めちゃくちゃ尊いだろ。
でも、彼女たちの中でキラキラ大学生の週末といえば、多分もっとこう——
合コン、ショッピング、インスタ映えイベント、季節ごとのフェス、みたいなやつなんだろう。
「お笑いなんだ〜……」
「へえ……」
テンションだけ半音下がった「へえ」が、地味に刺さる。
くそ……俺の週末、キラキラポイント低すぎる……
いや、俺的には満点なんだけどな……
言わなきゃよかったかな、と軽く後悔しかけたところで——。
「え、相沢くん、お笑い好きなの?」
隣から、ぱっと明るい声が飛んできた。
さっきまでより、ほんの少しだけトーンが高い。
柾が、心底驚いたみたいに目を輝かせて俺を見ていた。
「俺も!」
「えっ」
想定外すぎて、間抜けな返事しか出てこない。
思わず、グラスを持つ手がカタッと揺れた。
「どこのライブ会場行ったの?」
「あ、え、その……新宿の……」
篠田さんが、慌てて話に乗ろうとする。
「新宿かー。私も、前にルミネ行ったよ?」
たぶん、さっきの「陰キャっぽ」リアクションが若干悪目立ちした自覚があるんだろう。
柾がこの話に興味を示していることで、ここで挽回しとこう、みたいな気配がにじんでいる。
「ルミネって、あれだよね?ルミネtheよしもと……?」
「そうそう!」
木村さんが、自分の知識がヒットしたのが嬉しそうに胸を張る。
「よくテレビ出てる人とか出てるとこでしょ?」
「うん、そうそう」
そこまでは合ってる。合ってるんだけど——。
「あ、ルミネはあんまり行かないかも……」
正直に答えた瞬間、また少し空気がずれる。
「え、そうなんだ……?」
やめて、その「せっかく合わせたのに無駄にしやがって感」を滲ませるの……!
こっちは別にルミネを否定してるわけじゃないのに、なんか「空気読めてない人」みたいになるじゃん……!
どうフォローしようかと口ごもっていると——。
「もしかして、西新宿?」
柾が、すっと言葉を差し込んできた。
そのピンポイント感に、思わず心臓が跳ねる。
「……うん」
思わず姿勢を正してしまう。
まさか当ててくるとは思わなかった。
「ナルゲキ」
自分でもちょっと声が小さくなったのがわかる。
通じないだろうな、って半分諦めながら口にしたその名前を——。
「やっぱり」
柾の口元が、楽しそうにふわっと緩んだ。
「俺もよく行くよ!面白いよね、ナルゲキのK-PROライブ」
その瞬間、女子たちの表情がそろって固まった。
「……ナル、げき?」
「え、なにそれ」
「新宿の劇場?」
小声の検索ワードみたいなささやきが、テーブルの上を飛び交う。
「ナルゲキ 新宿で出るかな……」
「えっと……ナルゲキ お笑い……っと」
ちらっと視線を落とすと、スマホを太ももの上でそっと開いているのが見えた。
画面の光が膝のところでちらちら揺れている。
あ、絶対今「ナルゲキ」って打ってる……
俺と柾だけが、すっと通じ合ってる感じがして、ちょっと変な感覚になる。
劇場の椅子の固さとか、ネタ前の独特のざわつきとか、あの空気の湿度とか——そういう細かいところまで共有できる相手に、まさかここで出会うとは思ってなかった。
……俺とは程遠い世界の人だと思ってたけど、同じ趣味なんて、意外だ。
「そういえばさ」
そこで、結城さんが、思い出したように声を上げた。
「成瀬くんたちの大学って、お笑いサークルあったよね?」
「え、そうなの?」
篠田さんが身を乗り出す。
さっき検索してたスマホを、テーブルの下でぱたんと閉じる。
「あ、私の友達、こないだそこのお笑いサークルのライブ見てきたって言ってた。結構面白かったーって」
「へえ」
柾が少しだけ目を丸くしてから、すぐに笑う。
「あ、そうなんだ。俺は一年だから、まだ出たことないけど」
「え」
思わず、俺のほうが大きな声を出してしまった。
「じゃあ……入ってるんだ?お笑いサークル」
「うん。一応ね」
柾は、なんてことないみたいに言うけど、俺の頭の中では情報量が多すぎて、処理速度が追いつかない。
顔面国宝みたいなイケメンで、爽やかなのに、お笑いサークル所属???
設定盛りすぎじゃない?
「コンビ組んでるの?漫才?コント?あ、それともピン?」
気づいたら、矢継ぎ早に質問していた。
こういうときだけ、コミュ障フィルターが外れるのが我ながらずるい。
好きなジャンルの話になると、オタク特有の早口が出そうになるのを必死で押さえる。
柾は、少しだけ視線を泳がせてから、苦笑いを浮かべた。
「本当はコンビ組みたかったんだけどさ」
「うん」
「少し組むと、方向性が違うって言われて振られて……」
その言い方が妙におかしくて、俺は思わず吹き出した。
「ぶっ」
「え、そんなおかしい?」
「だって」
笑いをこらえきれなくて、テーブルに肘をついて肩を震わせる。
「成瀬くん、絶対モテるのに!相方には振られるんだね!」
「笑い事じゃないんだけど」
柾が、ちょっと不貞腐れたみたいに唇を尖らせる。
その表情が、完璧モードからちょっと崩れてて、妙に人間味があって——正直、かわいい。
「ここ一ヶ月、振られまくっててつらいんだけど。コンビも、トリオも、お試しユニットも、全部『ちょっと違うかな』って……」
「ここ一ヶ月で何人にアタックしたのそれ……」
「数えたくない」
「それさ、恋愛話だったら完全にメンヘラ案件だよね?」
「やめて」
柾が、グラスの水を一口飲んでから、ふぅと息を吐く。
「ネタ合わせして、ちょっと楽しくなってきたなって思った頃に、ごめん、やっぱりさ……って言われるの、地味にダメージくるんだよ」
「もしかしてさ」
木村さんが、そこでまた会話に乱入してくる。
「成瀬くん、イケメンすぎてサークルの中で浮いてるんじゃない?」
「それだ!」
結城さんが、手を打って同意する。
「そうだよ、嫉妬よ嫉妬。成瀬くんの隣に立つと自分がかすむから、組みたくないんだよ」
「いや、そういうんじゃないと思うけど……」
少し戸惑っているのか、柾が視線を落とす。
耳の先が、ほんのり赤い。
いや、でも実際その説あるだろ……同じステージに並んだら、観客の目線ぜんぶ持ってかれそうだし。
「ていうか、それ、相方のメンタル試されない?」
「顔面格差コンビって言われたくないもんね〜」
女子たちは女子たちで、また別方向に話を膨らませ始める。
お笑いの話なのか、ビジュアルの話なのか、もはやよくわからない。
俺は、グラスを指でくるくる回しながら、ぽつりと呟いた。
「俺、成瀬くんのネタ見たいな」
言った瞬間、空気が少し変わった。
女子たちの「イケメンいじり」路線から、すっと話題が本筋——お笑いのほうに戻ってくる。
柾が、こっちを見た。
さっきよりも、真っ直ぐな目。
「……見る?」
唐突にそう言うと、おもむろにスマホをポケットから取り出す。
「え、今?」
「どうせなら、生で見せたかったんだけど。まだライブ出てないし」
ロックを外して、何度か画面をタップする。
再生履歴なのか、フォルダなのか、慣れた指の動きだ。
ホーム画面のアイコン配置がちらっと目に入って、「あ、意外とシンプルなんだ」とかどうでもいい情報が頭に残る。
「同期の前で練習したときのやつ、撮ってもらっててさ。出来はまだまだだけど」
そう言って、柾はスマホをくるっと回して、俺のほうに画面を向けた。
俺の喉が、ごくりと鳴った。
柾のネタ動画……どんなのだろう?