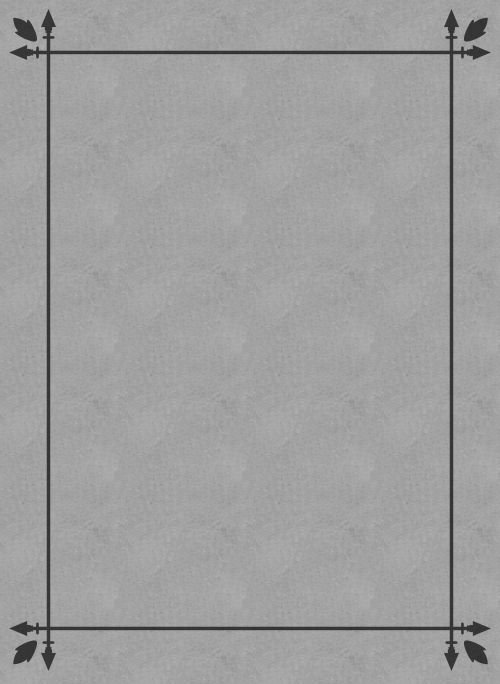ひどい悪夢から飛び起きると、窓から差し込む月明かりが部屋を淡く照らしていた。
跳ねるように鳴る心臓の鼓動が耳の奥に響き、息を上手く吸うことができなくて苦しい。
さっきまで見ていた悪夢が瞼の裏に焼きついたように鮮明に残っていて、何度も頭の中で映像を反芻している。
私の彼氏───アキトが私の前からいなくなってしまう夢だった。
『またね、コハル』
夢の中のアキトがそう短く私に告げると、背を向けて歩き出していった。どんなに叫んでも名前を呼んでも私の方を振り返ることは無く、ただ遠くに向かって歩いていくだけ。
追いかけようと足を踏み出しても、まるで泥の中を走ってるみたいに足が上手く動かなくて、距離がどんどん開いていくのをただ見ていることしかできなかった。
アキトがいない。それだけで世界が崩れ落ちるような絶望感が広がって息苦しかった。その感覚が、今でもまだ胸の奥に重い塊となってのしかかっている。
震える手で枕元に置いたスマホに手を伸ばし画面を点けると、午前二時を少し過ぎたところだった。まだ何時間もある夜の長さに、ため息が漏れる。
もう一度寝ようと目を閉じても、頭の中で悪夢が再生されて眠れなかった。布団をかぶって身体を丸めても、悪夢の残像が頭をちらついて消えてくれない。
結局、もう一度寝るのは諦めて部屋の天井をぼんやりと眺めることにした。
悪夢のせいで余計に夜の部屋が怖くて仕方ない。静まり返っていて薄暗くて、この世界には私以外誰もいなくなったような感覚に襲われて心細くなる。
もしアキトが隣にいてくれたら。そっと私のことを抱きしめて、いつものように頭を撫でてくれたら。それだけで私の心は救われるのに。
そんなことを考えていたら寂しさでだんだんと涙が滲んできた。
あまりに心細くてアキトにLINEを送ろうか迷った。だけどさっきの悪夢のことが頭をよぎって本当にいなくなってたらどうしようという不安に襲われて、『起きてる?』と打ちかけた手が止まる。それにもうアキトは寝ている時間だろうし、起こしてしまったら迷惑だ。
しばらく迷っているとアキトとの過去のやり取りが目に入ったので、心細さが紛れるかと思って遡ってみた。数週間前のデートの写真だったり夜に飯テロ画像を送り合ってたりと、懐かしい思い出が色々と蘇ってきて、つい口角が上がってしまう。アキトとのやり取りを振り返っている内に、少しだけ気持ちが楽になるのが分かった。
───ピコン。
その時、画面の上に軽快な音と共にLINEのメッセージ通知が出てきて、見てみるとアキトからの『コハル、起きてる?』という内容だった。
アキトから真夜中にLINEが来ることはこれまでも何度かあったけど、あまりのタイミングの良さにびっくりした。でも、それ以上にアキトがいることへの嬉しさについ笑みが溢れてしまう。
私はすかさず『起きてるよ。 どうしたの?』と送信する。
すると、一分も経たないうちに『コハルと話したいなと思ってさ、少し通話しない?』と返事が来たので『もちろん!』と送る。 すると、既読がつくと同時にアキトからの着信がきた。
電話に出るとすぐに通話が繋がる音がして、「こんな夜遅くにごめんね」という声が聞こえてきた。いつも聞き慣れた、落ち着きのあるアキトの声だ。
本当にアキトがいることに安心して、さっきまであんなにうるさかった心臓の鼓動がいくらか穏やかになっていくのが自分でも分かった。
「全然大丈夫! 私もちょうど起きてたし!」
気分が上がって思わず声が弾む。
すると、アキトが「......少し涙声じゃない? なんかあった?」と優しく私に尋ねた。
「......ううん、なんでもないよ」
アキトに心配をかけさせまいと言った言葉だったが、自分でもびっくりするくらい声が震えている。 確かに声が掠れていて鼻も詰まってるし、涙声を隠し通せるわけがなかった。
でもそれ以上にアキトがすぐに私の異変に気づいてくれたのが嬉しくて、ずっと我慢してきた涙がどんどん溢れ出してきた。
「良かったら、どうして泣いてるか教えてくれる? 何か怖い夢でも見たの?」
「......そう。アキトがいなくなっちゃう夢でね、すごく怖かった」
私は布団に顔を押し付けながら、掠れた声で答えた。
言葉を続けるたびに涙が止まらなくなって、どんどん声がぐずぐずになっていく。 そんな状態の私の話を、アキトは最後まで静かに聞いてくれた。
「ごめんね、せっかくの電話なのにこんな話しちゃって」
「全然大丈夫だよ。 むしろ通話かけて良かった」
アキトの声がいつもよりもずっと優しくて、じんわりと胸の奥に温かいものが広がっていく。
「それに、俺がコハルを置いてどこかになんて行かないよ。 ずっと隣にいるつもりだし」
「......本当に、ずっと私の隣にいてくれる?」
さらっとキザなセリフを口にするアキトに対して、つい確かめるように尋ねてしまう。アキトの言葉を疑うわけではないけど、悪夢によって生まれた不安は簡単には消えてくれなかった。
するとアキトはいつもの優しい口調で「もちろん。 俺がコハルのことをどれくらい好きか、コハルが一番よく知ってるでしょ?」と言って穏やかに笑った。
アキトのその言葉を聞いた瞬間、胸の奥に残っていた重い塊がすうっと溶けていくような感覚が走った。 スマホ越しに聞くアキトの声が、まるで本当に隣で抱きしめてくれてるみたいに温かい。
「......うん。 ありがとうね、アキト」
「どういたしまして」
それからアキトと朝になるまで色々な話をした。 次のデートで行きたいカフェの話、昨日あった面白い話。そして将来の私たちについて、声を弾ませながら様々な妄想を語り合った。
だんだんと窓の外が薄紫に染まっていき、外から聞こえる鳥の声が朝の訪れを知らせる頃。 なんとなく会話に一区切りがついてお開きの雰囲気になっていると、アキトの優しい声が私の名前を呼んだ。
『コハル』
『ん?』
『おやすみ。 また話そうね』
『......うん。 おやすみ、アキト』
そうして私たちはお互い眠気で蕩けた声でおやすみを言い合って通話を切った。
電話が切れた後も耳に残るアキトの声が、優しく私を抱きしめてくれているようで、つい笑みが溢れてしまう。 数時間前まで悪夢を見ていたとは思えないくらい、私の心はアキトで満たされていた。
きっとまた私が悪夢を見た時はアキトが助けてくれるだろう。そんな安心感に包まれながら、私は目を瞑り夢の世界へと身体を委ねる。
悪夢の傷跡は、もうどこにも残っていなかった。
跳ねるように鳴る心臓の鼓動が耳の奥に響き、息を上手く吸うことができなくて苦しい。
さっきまで見ていた悪夢が瞼の裏に焼きついたように鮮明に残っていて、何度も頭の中で映像を反芻している。
私の彼氏───アキトが私の前からいなくなってしまう夢だった。
『またね、コハル』
夢の中のアキトがそう短く私に告げると、背を向けて歩き出していった。どんなに叫んでも名前を呼んでも私の方を振り返ることは無く、ただ遠くに向かって歩いていくだけ。
追いかけようと足を踏み出しても、まるで泥の中を走ってるみたいに足が上手く動かなくて、距離がどんどん開いていくのをただ見ていることしかできなかった。
アキトがいない。それだけで世界が崩れ落ちるような絶望感が広がって息苦しかった。その感覚が、今でもまだ胸の奥に重い塊となってのしかかっている。
震える手で枕元に置いたスマホに手を伸ばし画面を点けると、午前二時を少し過ぎたところだった。まだ何時間もある夜の長さに、ため息が漏れる。
もう一度寝ようと目を閉じても、頭の中で悪夢が再生されて眠れなかった。布団をかぶって身体を丸めても、悪夢の残像が頭をちらついて消えてくれない。
結局、もう一度寝るのは諦めて部屋の天井をぼんやりと眺めることにした。
悪夢のせいで余計に夜の部屋が怖くて仕方ない。静まり返っていて薄暗くて、この世界には私以外誰もいなくなったような感覚に襲われて心細くなる。
もしアキトが隣にいてくれたら。そっと私のことを抱きしめて、いつものように頭を撫でてくれたら。それだけで私の心は救われるのに。
そんなことを考えていたら寂しさでだんだんと涙が滲んできた。
あまりに心細くてアキトにLINEを送ろうか迷った。だけどさっきの悪夢のことが頭をよぎって本当にいなくなってたらどうしようという不安に襲われて、『起きてる?』と打ちかけた手が止まる。それにもうアキトは寝ている時間だろうし、起こしてしまったら迷惑だ。
しばらく迷っているとアキトとの過去のやり取りが目に入ったので、心細さが紛れるかと思って遡ってみた。数週間前のデートの写真だったり夜に飯テロ画像を送り合ってたりと、懐かしい思い出が色々と蘇ってきて、つい口角が上がってしまう。アキトとのやり取りを振り返っている内に、少しだけ気持ちが楽になるのが分かった。
───ピコン。
その時、画面の上に軽快な音と共にLINEのメッセージ通知が出てきて、見てみるとアキトからの『コハル、起きてる?』という内容だった。
アキトから真夜中にLINEが来ることはこれまでも何度かあったけど、あまりのタイミングの良さにびっくりした。でも、それ以上にアキトがいることへの嬉しさについ笑みが溢れてしまう。
私はすかさず『起きてるよ。 どうしたの?』と送信する。
すると、一分も経たないうちに『コハルと話したいなと思ってさ、少し通話しない?』と返事が来たので『もちろん!』と送る。 すると、既読がつくと同時にアキトからの着信がきた。
電話に出るとすぐに通話が繋がる音がして、「こんな夜遅くにごめんね」という声が聞こえてきた。いつも聞き慣れた、落ち着きのあるアキトの声だ。
本当にアキトがいることに安心して、さっきまであんなにうるさかった心臓の鼓動がいくらか穏やかになっていくのが自分でも分かった。
「全然大丈夫! 私もちょうど起きてたし!」
気分が上がって思わず声が弾む。
すると、アキトが「......少し涙声じゃない? なんかあった?」と優しく私に尋ねた。
「......ううん、なんでもないよ」
アキトに心配をかけさせまいと言った言葉だったが、自分でもびっくりするくらい声が震えている。 確かに声が掠れていて鼻も詰まってるし、涙声を隠し通せるわけがなかった。
でもそれ以上にアキトがすぐに私の異変に気づいてくれたのが嬉しくて、ずっと我慢してきた涙がどんどん溢れ出してきた。
「良かったら、どうして泣いてるか教えてくれる? 何か怖い夢でも見たの?」
「......そう。アキトがいなくなっちゃう夢でね、すごく怖かった」
私は布団に顔を押し付けながら、掠れた声で答えた。
言葉を続けるたびに涙が止まらなくなって、どんどん声がぐずぐずになっていく。 そんな状態の私の話を、アキトは最後まで静かに聞いてくれた。
「ごめんね、せっかくの電話なのにこんな話しちゃって」
「全然大丈夫だよ。 むしろ通話かけて良かった」
アキトの声がいつもよりもずっと優しくて、じんわりと胸の奥に温かいものが広がっていく。
「それに、俺がコハルを置いてどこかになんて行かないよ。 ずっと隣にいるつもりだし」
「......本当に、ずっと私の隣にいてくれる?」
さらっとキザなセリフを口にするアキトに対して、つい確かめるように尋ねてしまう。アキトの言葉を疑うわけではないけど、悪夢によって生まれた不安は簡単には消えてくれなかった。
するとアキトはいつもの優しい口調で「もちろん。 俺がコハルのことをどれくらい好きか、コハルが一番よく知ってるでしょ?」と言って穏やかに笑った。
アキトのその言葉を聞いた瞬間、胸の奥に残っていた重い塊がすうっと溶けていくような感覚が走った。 スマホ越しに聞くアキトの声が、まるで本当に隣で抱きしめてくれてるみたいに温かい。
「......うん。 ありがとうね、アキト」
「どういたしまして」
それからアキトと朝になるまで色々な話をした。 次のデートで行きたいカフェの話、昨日あった面白い話。そして将来の私たちについて、声を弾ませながら様々な妄想を語り合った。
だんだんと窓の外が薄紫に染まっていき、外から聞こえる鳥の声が朝の訪れを知らせる頃。 なんとなく会話に一区切りがついてお開きの雰囲気になっていると、アキトの優しい声が私の名前を呼んだ。
『コハル』
『ん?』
『おやすみ。 また話そうね』
『......うん。 おやすみ、アキト』
そうして私たちはお互い眠気で蕩けた声でおやすみを言い合って通話を切った。
電話が切れた後も耳に残るアキトの声が、優しく私を抱きしめてくれているようで、つい笑みが溢れてしまう。 数時間前まで悪夢を見ていたとは思えないくらい、私の心はアキトで満たされていた。
きっとまた私が悪夢を見た時はアキトが助けてくれるだろう。そんな安心感に包まれながら、私は目を瞑り夢の世界へと身体を委ねる。
悪夢の傷跡は、もうどこにも残っていなかった。