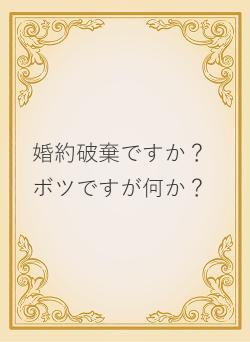翌朝、猫カフェにはやわらかな光が差していた。
昨晩の余韻がまだ店内に残っているようで、ミケはカウンターの上に置かれた帽子掛けをぼんやりと見つめていた。
マスターが帰っていった夜。
何かが終わったようで、それでいて何かが始まったような気がしていた。
ミケは朝の準備をする手を止め、胸に手を当てる。
「……本当に、覚えていたにゃ」
昨日の言葉がまだ心の奥に響いている。
“ありがとうな。──僕の可愛いミケ”
名前を呼ばれた時に胸の奥にぽっと灯った光は、一夜経った今もまだ消えていなかった。
あの頃と同じ優しい声で。
あの頃と同じ言い方で。
こんなに嬉しいことはない。
ミケは温め直したお湯をポットに満たし、カウンターに“二つ”のカップを置いた。
「今日は……二杯、淹れたい気分にゃ」
そう呟くと、外の風がやさしく扉を揺らす。
チリン……。
ドアベルの音が小さく鳴り響く。
だけど扉は開かなかった。風の仕業だ。
それでも、ミケのしっぽは一度だけふるりと揺れた。
「────ああ……そっか。今日は来ないにゃ」
昨夜、マスターは旅立ったのだから。
けれど、不思議と寂しくなかった。
行ってらっしゃい。
また、いつか。
そんな気持ちが胸に残ったままだったから。
ミケはカウンターの椅子に座り、ため息にも笑みが混じった声で呟く。
「いろんなお客さんの、最後のひとときを預かってきたけれど……昨日はミケの番だったにゃ」
チリン──音が鳴り、今度は先ほどとは違って、ゆっくりと扉が開く。
ミケは驚いて振り返る。
けれど店に入ってきたのは、思った人物ではなく、見知らぬ若い女性だった。
「あの……やってますか?」
「ぁ…………もちろん、にゃ。いらっしゃいませにゃ」
ミケは慌ててカウンターに戻り、メニューを差し出す。
女性は店内を見渡しながら、ふと笑みを浮かべた。
「友達に聞いてね。“あったかい思い出をくれるお店があるよ”って」
ミケの胸が、ふっと温かくなる。
「そうにゃ。ここは、そういう場所にゃ」
女性はコートを脱いで席に着くと、窓の外の光を見ながら続けた。
「でも……来る途中で、何か不思議な感覚がしたんです。ここ、初めてなのに……どこか懐かしいような」
女性の言葉に、ミケは静かに笑った。
「それはきっと、このお店に“誰かの想い”が残ってるからかもしれないにゃ。あったかいものは、なかなか消えないんですにゃ」
自分ではない誰かかもしれないし、かつて自分であった誰かかもしれない。
だけど皆、一度はたどり着いたかもしれない場所。
女性はうなずき、ふわりと笑った。
「ふふ。……じゃぁ、一杯、お願いしてもいいですか? 何か、忘れていた大事なものを思い出せるような味を」
ミケはにっこりと笑ってもふもふの分厚い手で自信の胸をトン、と叩いた。
「任せるにゃ。そのための、この猫カフェですにゃ」
豆を挽く音が、やさしく店に広がる。
この音が、ミケは好きだ。
誰かの記憶を呼び、誰かの心を温め、また新しい物語を連れてくる。
ふと、昨日のマスターの姿が頭に浮かぶ。
行ってらっしゃい。
また会えるにゃ。
その時は、もっといいブレンド淹れるにゃ。
ほかほかの白い湯気が立って、部屋中にコーヒーの香りが充満し始め、ミケが女性の前にそっとカップを置いた。
「どうぞにゃ。特製ブレンド、“夕暮れ仕立て”にゃ」
さっぱりとした飲み口で甘みもある、飲みやすいブレンド。
女性は嬉しそうにカップを両手で包み、ゆっくりとひと口飲んで──そして、ほっ、と息をついた。
「……ああ。ほんとだ。なんだか……帰ってきたみたいな味がしますね」
目尻を垂れて言った女性に、ミケはゆっくり頷く。
「おかえりなさいだにゃ。この店に来る人はみ~んにゃ……頑張ったその後に、ちゃぁんとここに帰ってきてるんですにゃ」
女性は不思議そうに目をぱちぱちとさせたけれど、すぐにどこか納得したような笑みを浮かべた。
ミケはふと棚の上、昨日の夜に置いた“もうひとつのカップ”に目をやる。
誰も座っていない席。
でも、そこには昨日のあの言葉のぬくもりが残っていた。
『──ありがとうな、僕の可愛いミケ』
胸の奥でそっと響く。
その残響に、ミケは小さく呟いた。
「……うん。そう。だからおかえりも、行ってらっしゃいも、また、いつでも言えるにゃ」
まるで自分に言い聞かせるように。
まるで、自分を慰めるかのように。
店の外では、風がやわらかく街灯を揺らしていた。
あたたかな光が、猫カフェの窓を笑わせるように照らしている。
そしてミケは、今日もまた、誰かの心をあたためる一杯を淹れはじめた。
END