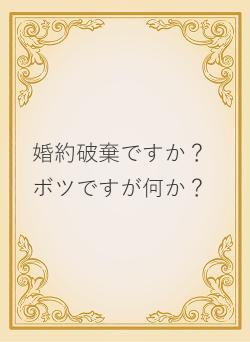だが、ミケは首を振って気持ちを整え、カップをそっと差し出した。
「どうぞですにゃ。人生ブレンドにゃ。長い年月を重ねた深みと、その中で感じた甘み、少しの苦み。そして“ありがとう”が詰まってるにゃ」
男はひと口飲んで、小さく息をつく。
「……ああ。深くて、落ち着く。ずっと探していた味に近い気がするよ」
「にゃはは……褒めても何も出ないにゃ。……でも、嬉しいにゃ。──マスターさんは珈琲、詳しいのにゃ?」
「詳しいかどうかはわからないけれど…………とても好きだったよ、ずっと、ね」
そう目を細める男に、ミケはしっぽを小さく揺らしながら、珍しく会話を繋げていく。
豆の産地の違い。
焙煎の癖。
ネルの扱い方。
お湯の温度。
マグカップの形──。
それらの会話は自然に、なめらかに、まるで何十年も前から続いていた話の続きをしているように弾んだ。
男は楽しそうに笑い、ミケも嬉しさで胸があったかくなる。
けれど、ふと、会話が途切れた。
男は空になりかけたカップを見つめたまま、ぽつりとつぶやいた。
「……ここは、不思議な場所だね。初めて来たはずなのに……来たことがあるような気がする」
「……そう、にゃか」
ミケはカップを拭く手を止めた。
あぁ、やめてくれ。
それ以上考えなくてもいい。
考えて、応えに行きついてしまったら、自分は店主ではいられなくなる。
しばらく静かな間が流れ、ミケはゆっくり言葉を紡いだ。
「にゃ……気のせいじゃないですにゃ。ここは、旅立つ前に心を休めに来る場所。みんにゃ……最後に、あったかい何かを思い出していくのです。お客さんの思い出がそうさせるのか、遠い昔のお客さんがここに来たことがあるからなのか、そうなる方は珍しくないんだにゃ」
落ち着いて。
あくまで、この猫カフェの店主として。
ミケの言葉に男は軽く眉を上げたが、不思議と驚きよりも納得の色が濃かった。
「ふむ……そうか。じゃあ私は……もう行くところがあるんだな」
その声はどこか寂しく、どこか穏やかだった。
ミケは胸の奥がちくりと痛んだ。
言いたいことは山ほどあった。
“あなたの猫だにゃ”
“ずっと大好きだにゃ”
“覚えてるにゃ?”
でも────。
「……にゃ」
それしか、声がうまく出なかった。
喉がぎゅっと縮まって、言葉にならない。
なにしろ、ミケは今、猫の姿でヒトの言葉を話す不思議な存在。
生前一緒にいたころの自分とは違う。
覚えていないだろう。
振り返ってもらえることなんて、ないのかもしれない。
人間にとっては、長い人生の短い一部でしかないのだから。
そんな思いが胸の中で渦巻いた。
男はゆっくり席を立ち、帽子を軽く被り直す。
「……いい店だったよ。また来たいくらいだ」
「ありがとにゃ。……また、来てほしいにゃ」
その時はもう来ないけれど。
だけど、願うならば、またあなたと話をしたい。
ミケはそんな思いを心に閉じ込めて、目を細めて笑った。
扉の前まで歩くと、男は店の明かりを浴びながら外へ出ようとした。
チリン──とドアベルがやわらかく揺れた、その時だった。
男が、一度だけ振り返った。
その目は優しくて、深くて、まるで長い長い時間の向こうを見通すような、ビー玉のようなキラキラとした目。
そして彼は、静かに言った。
「ありがとうな。────僕の可愛いミケ」
「……っ…………!!」
ミケのしっぽが大きく震えた。
名前を、呼ばれた。
忘れられていたと思っていた名を。
生前、何度も呼ばれたそのままの声で。
ミケの中に、胸を締めつけるほどの温かい思いが溢れた。
こぼれそうだった言葉が、ようやくひとつだけ形になった。
「……にゃあ、マスター。行ってらっしゃい、にゃ」
男は微笑み、静かに扉を閉めた。
チリン──、またベルの音が、しずかに夜に溶けていく。
店内には、珈琲の香りと、胸を満たす、ぬくもりだけが残った。
「…………ありがとう、にゃ」
窓の外の街灯が静かに揺れ、猫カフェを、優しい夜が包み込んだ。
その日ミケは、しばらくカップを片付けず、じっとそれを眺めて微笑んでいた。