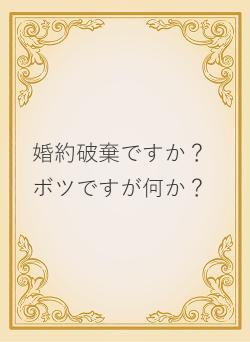その日、ミケの猫カフェは朝から大盛況だった。
たった一人で切り盛りするミケはてんやわんやで、もう朝のことはほぼ覚えていない。
こんなことはそうそうあるもんじゃない。
今日はなんだか妙な日になりそうにゃ、とミケは心の中で独り言ち田。
窓の向こうの街灯が淡い光を灯し始めている。
ミケはカウンターに並ぶカップを丁寧に並べながら、「何だかわからないけれど、そわそわするにゃ」と、尻尾をピンと立てた。
毎日のように訪れるお客さんたちの柔らかな記憶が、店内のあちこちにまだ残っている。
濡れたレインコートの匂い、古い毛糸のぬくもり、夕焼けの琥珀色。
どれも、ささやかで、愛しい。
そしてそのどれもが、ただただ、優しいのだ。
ミケは照明を一段落とし、落ち着いた音楽を流した。
この店の夜は、だいたいこうして始まる。
その時だった。
チリン──店の鈴が揺れ小さく可愛らしい音を立てた。
音の響き方が、いつもと違う。
まるで遠くから来た風が、鈴だけを優しく撫でたような、そんな響き。
「失礼」
入ってきたのは、古びた帽子を深くかぶった初老の男だった。
背筋は少し丸く、少しだけよれた深緑色のコートが肩を包んでいた。
いつもならすぐに「いらっしゃいませにゃ」と案内するのに、ミケはできなかった。
ただ茫然と、その男をまん丸の満月のような瞳で見つめるだけ。
男はそんなミケをよそに、店内を一度ゆっくり見渡し、カウンター席の真ん中に腰を下ろす。
「……ブレンドを一つ。深めで頼むよ」
注文を聞いて、ミケの胸がきゅうっと締まった。
「……はいにゃ。お好みのやつで淹れますにゃ」
声が少し震えそうになるのを、喉の奥で必死にこらえる。
男は気づいていないようだったが、その仕草の所々に、ミケの記憶の中で眠っていた“ある人”の面影がちらついた。
ミケは深煎りの豆を手に取り、ゆっくりと挽きはじめた。
豆が砕ける音が、どこか遠くの記憶を叩いているようだ。
湯を注ぐ。
ネルに落ちるしずくが、ぽとり、ぽとり、と静かに音を立てる。
深煎りのコーヒーはさっと入れるのがコツだ。
後半になればなるほど、えぐみが増してしまう。
さっと淹れて、抽出時間を短くすることで、深みの中にも甘みの引き立つコーヒーになってくれるのだ。
やがて香りが立ち昇ると、男は目を細めて呟いた。
「……あぁ……、いい香りだ。君のブレンドはどこか懐かしい香りがする」
その言葉に、ミケの心臓が跳ねた。
当然だ。
懐かしいに決まっている。
だってあなたが、ずっと大好きだった、慣れ親しんだ香りなのだから。
それを飲むのを、ずっと、見てきたのだから。