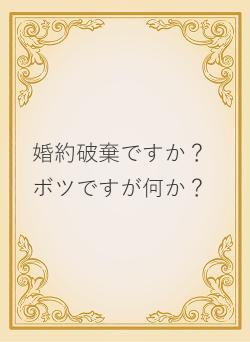やがて老犬はゆっくり席を立つ。
「ありがとう。あの夕焼けを、もう一度思い出させてくれて」
老犬の穏やかな笑みに、ミケも応えるように微笑んだ。
「思い出したくなったら、いつでもここに戻って来るにゃ。夕焼けの味は、ここに置いてあるにゃ」
気のすむまで、思い出せばいい。
思い出して、思い出して、思い出して、そして──すっきりとした心で旅立てばいいのだから。
老犬はそれに応えるように小さく尻尾を振り、扉へ向かう。
チリン──と扉が開いた先には、綺麗な夕焼け空。
夕暮れの光をまといながら、老犬は振り返って言った。
「優しい店だね。もう、大丈夫そうだ」
チリン──とまた音がして扉が閉まり、外の空はすでに夜へと溶けはじめていた。
ミケは静かに棚を見上げ、残った琥珀色の砂糖菓子にそっと触れた。
「思い出って不思議にゃ。少し思い出してあげるだけで、心がもう一度、あの日の夕焼けになるのにゃから」
そう呟き、ミケはキャンドルの火をじっと見つめた。
その光は、あの老犬の過ごしたであろう日々のように、ほっこりと暖かかった。
「ありがとう。あの夕焼けを、もう一度思い出させてくれて」
老犬の穏やかな笑みに、ミケも応えるように微笑んだ。
「思い出したくなったら、いつでもここに戻って来るにゃ。夕焼けの味は、ここに置いてあるにゃ」
気のすむまで、思い出せばいい。
思い出して、思い出して、思い出して、そして──すっきりとした心で旅立てばいいのだから。
老犬はそれに応えるように小さく尻尾を振り、扉へ向かう。
チリン──と扉が開いた先には、綺麗な夕焼け空。
夕暮れの光をまといながら、老犬は振り返って言った。
「優しい店だね。もう、大丈夫そうだ」
チリン──とまた音がして扉が閉まり、外の空はすでに夜へと溶けはじめていた。
ミケは静かに棚を見上げ、残った琥珀色の砂糖菓子にそっと触れた。
「思い出って不思議にゃ。少し思い出してあげるだけで、心がもう一度、あの日の夕焼けになるのにゃから」
そう呟き、ミケはキャンドルの火をじっと見つめた。
その光は、あの老犬の過ごしたであろう日々のように、ほっこりと暖かかった。