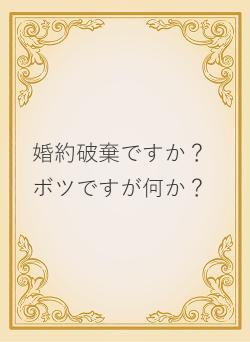その日の夕暮れは、まるで絵本のようだった。
空は淡い桃色から橙色にゆるやかに溶け合い、雲の端だけを金色に縁どって、街全体を優しい色に染めていた。
ミケは誰もいないカウンターの上で、夕暮れ色のキャンドルに火を灯していた。
この時間帯のどこか懐かしい静けさが、どこか心地いい。
「今日の夕焼け、綺麗だにゃあ……」
ミケがうっとりとしてそうつぶやいた瞬間、扉が開いて、チリン、と静かな音が響いた。
「いらっしゃいませだにゃ」
入ってきたのは、一匹の老犬。
毛並みは白と茶が混じり、ところどころ年齢の証である白い毛が増えている。
丸い背中に、ゆっくりした足取り。
目元には優しい皺が寄っていた。
「こんばんは。ここは暖かそうだね」
「にゃにゃ。どうぞ好きなところへ座るにゃ」
老犬はカウンター席に腰を落ち着かせると、深く息をつき、肩の力を抜いた。
「ふう……ずぅっと歩いてきたら、懐かしい匂いがしてね。つい寄り道をしたくなったんだ」
その言葉に、ミケは耳をぴんと立てた。
「懐かしい匂い……もしかしたら焙煎した豆の香りかにゃ?」
ミケが言うと、老犬は目を細め、深く頷いた。
焙煎豆の香りは良い。
深く、どこまでも香り漂って鼻腔をくすぐるのだ。
「……あぁ、そうだね。昔、飼い主さんと散歩した帰りに寄っていた店の匂いに、よく似ている」
ミケは胸の奥で、何かが温かくほどけるのを感じた。
老犬の沈んでいた瞳に、少しだけ光が戻っていたからだ。
それだけ優しい記憶が、この老犬の中にあるのだろう。
「飲み物はどうするにゃ? あったかいミルクでも……」
「いや、今日は匂いだけでいいんだ。昔みたいに、主人と一緒に飲んでいた気分になれる」
老犬が言うと、ミケは頷き、静かに深煎りの豆を挽いた。
香りがふわりと広がると、老犬は鼻先をくん、と動かし、懐かしそうに目を細める。
「……ああ、この匂いだ。丘の上の散歩道。夕焼けの色。あの人が笑っていた顔まで、全部思い出すよ」
老犬の目は、少し遠くを見ていた。
ミケはその視線の先を追うように、棚から琥珀色の砂糖菓子を取り出す。
「これ、夕焼けの味にゃ」
老犬は驚いたように目を丸くした。
「夕焼けの……?」
「にゃ。甘さも、香りも、あの空の色に似せた、特製のお菓子にゃ。良かったら食べるにゃ。柔らかく溶けるから食べやすいにゃ」
ミケが絵偏と口端を上げてそれを差し出すと、老犬はそれをそっと手に取り、おそるおそる口に入れ、舌の上で溶かした。
「…………!! ……ああ。本当に、似ている。懐かしい。丘の上から見た夕焼けの味がする。主人と、並んで座って……空が赤くなっていくのをずっと見ていた」
少しだけ、老犬の声が震えた。
ミケはそっと寄り添うように言った。
「素敵な時間だったんですにゃぁ」
しみじみとミケが言うと、老犬はゆっくり頷いた。
「そうさ。とても大切な時間だった。あの人はもういないけれど……でも、こうして思い出せるだけで、もう十分だと思える」
沈黙は、悲しさではなく、温かさの沈黙だった。
思い出が優しければ優しい程、離れ難いものだ。
だけどいつかは、離れなければならない時が来る。
ここはそのための場所でもあるのだ。