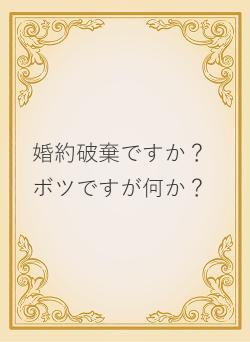「…………見てもいいかにゃ?」
「えぇ、どうぞ」
雌猫が差し出した薄紫色のマフラーは、暖かくて柔らかい。
編みかけの端はゆるんでいたが、それにはたしかに愛情がこもっているように感じた。
ミケはカウンターから針を取り出し、器用に爪と肉球で糸をすくいながら言った。
「ふむふむ……。たぶん、直せるにゃ。ほつれを直して、解けないようにできるにゃ」
ミケの言葉に、雌猫は驚いたように目をまん丸くした。
「そんなこと、できるの?」
「できるにゃ。あったかい気持ちが残ってる糸は、いくらでも形を取り戻すんですにゃ」
そう言うとミケは、雌猫の前にそっと生姜湯を淹れて差し出した。
「寒い日の思い出ブレンドにゃ。少量の生姜でにゃんこも安心ほっこりなのにゃ。待っている間、身体の芯からあったまると良いにゃ」
***
──暖炉の火がぱちぱちと跳ね、ミケの指先を明るく照らす。
雌猫は生姜湯を口に含むと、その優しい光を眺めながら、ぽつりぽつりと話し始めた。
「ご主人はね、とても優しい人だったのよ。外から帰ると毎日撫でてくれたし、マフラーだって……不器用なのに、一生懸命編んでくれたの。こんな、老いた猫のためにね」
ミケの手は止まらない。
「……『もっと綺麗に編んでくれたら綺麗なのに、不器用な人ね』なんていじわるなことを思ったけれどね。だけど、本当はそんなのどうでも良かったの。ただ、一緒にあたたかくなれたら、それでよかった」
雌猫は思い出を振り返る用に、じっ、と目を閉じる。
泣いてはいないのに、とてもしっとりとした静けさが漂う。
だけどそれが、妙に心地いい。
やがて──。
「できたにゃ!!」
そう声を上げてミケが差し出したのは、ふわりと伸びてほどけた部分のなくなった、薄紫色の綺麗なマフラー。
ほどけた部分を編み直し、少しだけ長さを足したのだ。
最初の方のところどころあるほつれはもう仕方がない。
これもまた、ご主人との思い出なのだから、まぁ良いだろう。
雌猫は震える手でそれを受け取り、そっと首に巻いた。
「……あったかい。とってもあったかいわ」
そう言って泣きそうな顔で笑う雌猫に、ミケの胸がじんわりと温かくなった。
「良かったにゃ。これで、もう少し安心して歩けるにゃ」
雌猫は静かに立ち上がった。
「ありがとう、素敵な店主さん。これで、あの人に怒られずに済むわ。ふふ、これであの人に怒られなくて済むわね。“この寒いのに、どうして巻いていなかったんだ”って。またあの優しい手で撫でてくれる」
ミケはその言葉に、少しだけ目を伏せた。
「きっと、喜んでくれるにゃ。だって、ずっと大事にしてたんですにゃ」
チリン、と音が鳴る。
雌猫は扉を開けると、外の夜風を一度吸い込んで、そして振り返って、優しい声で言った。
「ありがとう、素敵な店主さん。あなたの手は、暖炉みたいにあったかいわ。ほっかほかの生姜湯も、ありがとうね」
チリン、とまた小さな音がして、静かに扉が閉まる。
ミケの背中に残ったのは、暖炉の火と、毛糸のぬくもりだけだった。
ミケは小さく息をつき、小さく呟く。
「幸せな思い出って、ほどけても……また結べんるだにゃ」
暖炉の中で薪のはぜる音が、優しくそれを肯定してくれた気が下。