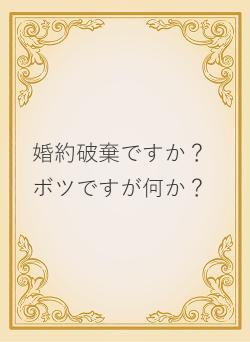その日は風が少し冷たくて、夜の空気が綺麗に澄んだ日だった。
ミケは大きくてふさふさとした白と茶色のぶち模様の身体を揺らしカフェの窓を拭きながら、外を行き交う人々を眺めていた。
「今日もたくさん通るにゃぁ」
毎日どこかでたくさんの人が命を終わらせる。
これはほんの一部だ。
それぞれがそれぞれに合った道を通り、最後の時を過ごし、そして長い旅に出る。
そんなこの場所も、冬が近づくと生きた世界と同じで、客の息が白くなる。
そんな季節は、どこか寂しい思いを抱えた者が、特に多く訪れる。
「……そろそろ暖炉、つけるかにゃ」
窓を拭いていたタオルを置いて、朝掃除したばかりの暖炉に薪をくべようとしたその時──。
扉の向こうで、コツ、コツ、と弱々しい爪の音がした。
チリン、と高い音が響いて、ゆっくりと扉が開く。
「こんばんは。少し、暖まってもいいかしら?」
入ってきたのは、真っ白な雌猫。
その足取りは少し頼りなく、首に巻かれたマフラーは短くてほどけかけていた。
「もちろんにゃ。寒かったでしょうにゃ」
雌猫はミケと目が合うと、ほっとしたように小さくうなずいた。
カウンターの端にそっと座り、ほどけた毛糸を指先でいじる。
「にゃにゃ? ……そのマフラー、大事なやつですね?」
ミケが尋ねると、雌猫はうつむき、かすかに笑った。
「……ええ。ご主人がね、冬になる前に編んでくれたものなの。ふふ、私、猫なのにね。……本当はね、もっと長くなる予定だったのに、途中で止まっちゃって。忙しくなって、最後まで編めなかったみたい」
静かに答えた雌猫に、ミケは椅子に座り、そっと視線を合わせた。
「大好きだったんですにゃね」
ミケにも覚えのある感情。
【好き】にもいろいろ種類がある。
だけどきっと、この雌猫の【好き】は、自分の中にあった【好き】と同じだ。
ミケの言葉に、雌猫は目を細めた。
「ええ、とっても。でもね、ご主人の所に帰る帰り道がわからなくなって……。寒い夜が増えるたびに、この中途半端なマフラーが、ちょっと心細くなるのよね」
ミケは胸の奥がきゅっとした。
毛糸のほつれは、思い出のほつれにも似ている。
触れ方を間違えれば、全部ほどけてしまうかもしれない。
この雌猫は、気づいていないのだ。
自分が今、どこにいるのか。
どうなったのか。
どこに行くのか。
それでもまだ、ご主人のもとに帰ろうとしている。