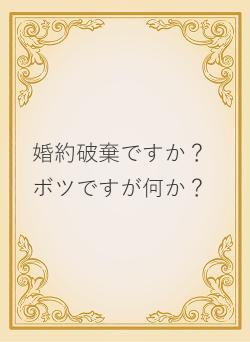夕暮れ時、猫カフェの看板を照らす街灯に、ぽつ、ぽつ、と雨粒が落ち始めた。
雲は薄い灰色で、きっと本降りにはならないけれど、これから先の長い道を行くには少し心細い。
だけどそんな天候も、この猫カフェの店主である“ミケ”にとっては好きなものだった。
だって、店内のオレンジ色の明かりが外へ滲み、小さな灯台みたいに道行く誰かを迎え入れることができるのだから。
ミケはカウンターでマグカップを磨きながら、短く分厚いしっぽで静かにリズムを刻んでいた。
雨の日は客が少なくなるけれど、その分、ふらっと訪れる人との小さな物語が生まれやすい。
そんな“ふい”が、ミケは大好きだ。
扉の外で、小さく水音が跳ねる。
ぱた、ぱたぱた。
木の扉が慌ただしく開いて、チリン、とドアベルが鳴った。
「す、すみませんっ!! あの、雨宿り、いいですか?」
レインコートのフードをかぶった母親と、その腕にしがみついている小さな男の子。
二人とも、雨粒をたくさん連れてきたみたいに濡れていた。
「もちろんにゃ。あったかい飲み物、どうですかにゃ?」
ミケが笑うと、男の子は母親の影からこわごわ顔を出した。
その顔が思いがけず真剣で、ミケは小さく首をかしげる。
「さぁさどうぞどうぞ。座って座って」
ミケに促されるがままに二人が席につくと、ミケはココアとミルクティーを用意してそっとテーブルへ置いた。
「ココアと、ミルクティーにゃ」
「あ、ありがとうございます。……ほら、あったかいよ。手が冷えてるでしょ?」
母親が息子の手を包むようにしてカップを持たせる。
湯気がほわりと上がったそれをそっと口に含んだ瞬間、男の子の凝り固まった小さな身体が、ふっと緩んだのが分かった。
「……おいしい。あまくて、あったかいね」
その言葉に、ミケの金色の目が三日月型になって、しっぽが嬉しそうに揺れる。
「雨の日の特別ブレンドにゃ。甘さしっかり、あったかさはぽかぽか多めですにゃ」
ミケが言うと、男の子はカップを両手で抱きながら、ぽつりと呟いた。
「……きょうね、ぼく、忘れちゃったの。大事なやつ」
ミケは耳をピンと立てて話に耳を傾け、母親も「あぁ……」と思い出したように視線を伏せた。
「何を忘れたのかにゃ?」
「えっとね……お父さんと一緒に描いた“ちっちゃい傘”の絵。学校に持っていくって言ったのに……机の上に置いたまま来ちゃったんだ」
声がだんだん細くなる。
男の子の目が潤んでいるのを見て、ミケはそっと隣に座った。
「その絵、大切なやつだったのにゃ?」
ミケの言葉に、男の子はこくりと頷く。
「お父さん、ずっとお仕事忙しかったんだけど、その日はお休みで……。学校の宿題で、『おうちの人と絵を描こう』っていうのがあってね、お父さんに『一緒に描いて』って言ったら、にこってして……。なのに、ぼく……忘れちゃった」
きっとそれを書いた翌日、家を出た後、母親と一緒に旅立ってしまったのだろう。
机の上に大事な絵を置き忘れたまま──。
言葉にならない想いに、母親がそっと背中を撫でる。
そんな様子に、ミケは三日月目を更に細めて、棚から小さな画用紙と色鉛筆セットを取り出した。
「じゃあにゃ、ここで“もう一枚”描くのはどうかにゃ? 丁度紙も色鉛筆もあるのにゃ」
男の子は涙を拭って、少しだけ顔を上げた。
「……描いていいの?」
「もちろんにゃ。好きなだけ、描いていいにゃ」
ミケが色鉛筆を差し出すと、男の子は嬉しそうな笑顔を浮かべ受け取り、すぐに夢中になった。
赤い傘と青い傘、それが歪んで、ちょっと曲がって……何度も描き直して。
小さな手を動かし続ける彼は、真剣そのもの。
母親は向かいの席で、微笑ましそうにその姿を見つめていた。
雨の音と色鉛筆のこすれる音だけが、やさしく店に満ちる。