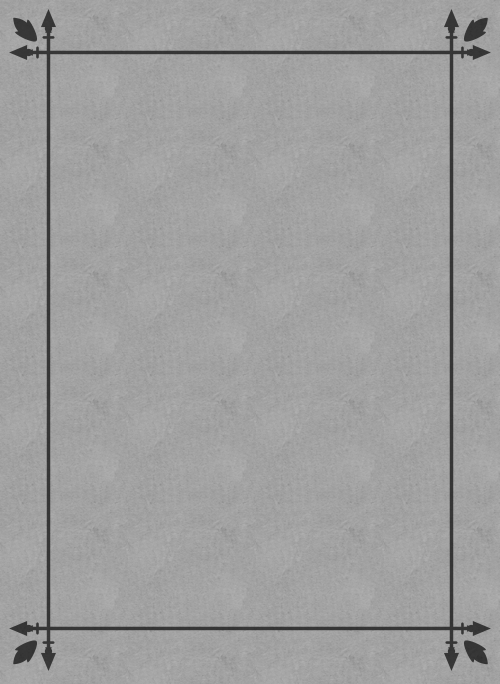事故現場から戻る道のりは、ほんの少しだけ、空が広く見えた。
雲の切れ間から淡い光がこぼれ、沈みゆく夕日の気配が、梓の頬に薄く触れる。
吸い込んだ空気は冷たかったが、その冷たさすら今は心地よい。
ミラは梓の胸の中で、大人しく丸まっていた。
小さな心臓が規則正しく刻むリズムが、梓の乱れた呼吸をそっと整えていく。
その体温は、長い間閉じこもっていた心の奥まで、静かに、ゆっくりと染み込んでいった。
「……ミラ。帰ろう」
声は驚くほど穏やかで、涙の余韻をまといながらも、確かに前を向こうとしていた。
あの場所に導かれ、あの声を聞いた──
そのすべてが、必要な時間だったように思えた。
家に着き、鍵を回す音がやけに大きく響く。
玄関に灯りがともった瞬間──
スマホが震えた。
たった一度だけ。
呼びかけるようでもなく、焦らすでもなく、
まるで「これで最後だよ」と優しく告げるような震えだった。
「……遼?」
梓は胸の奥が静かに跳ねるのを感じながら、震える指で画面をタップした。
表示されたのは、生きていた頃と同じ──あの、柔らかく笑う遼の写真。
そして、ほとんど間を置かずに音声メッセージが再生された。
雑音まじりの空気。
誰かが息を整える気配。
それから──聞き慣れた、低くて優しい声が流れ込んだ。
『ミラを守ってくれて、ありがとう。僕を想ってくれて……ありがとう。これからは、君が前を向いていく番だよ。』
たったそれだけ。
けれど、そこには過去の彼そのままの温度が宿っていた。
あの日々と同じ愛しさと、あのとき言えなかった想いをそっと包むような響きがあった。
胸がぎゅっと縮まり、
視界が一気に滲む。
「……遼……っ……」
呼びかけた声は、息に溶けてかすれた。
遼の声はそこで静かに途切れたが、その余韻は部屋中に淡い光のように広がっていた。
画面の光は、ゆっくり、ゆっくりと明度を落とし、最後の瞬間には、本当に手を振っているかのように柔らかく揺れて──
そして完全に暗転した。
二度と、ディスプレイは光を戻さなかった。
機能が停止したのか、不具合なのか、理由はわからない。
ただひとつ確かなのは、ミラと出会ってから起こった数々は奇跡だったということだ。
梓はソファに座り込んだまま、長い間、動けなかった。
遼が去った現実と、もう通知されないメッセージ。
彼の優しさが今なお自分を支えている現実が、胸の奥で静かにせめぎ合っていた。
そのとき──
膝の横に座ったミラが、そっと尻尾で梓の手に触れた。
あまりに小さく、あまりにささやかな仕草だったが、その一瞬で、梓の呼吸はやわらぎ、漂っていた悲しみがゆっくりと形を変えていった。
「……あなたも、行ってしまうのね。ミラ」
ミラは小さく喉を鳴らし、そっと足元に身を寄せた。
その温もりが、今日という日をそっと締めくくっていく。
顔を上げ、涙を拭い、梓は深く息を吸った。
気づくと、ミラは部屋から出ていっていた。
遼がくれた言葉も、ミラが導いてくれた奇跡も、すべては前へ進むために差し出されたものだったのだと、ようやく理解できた。
梓はそっと笑う。
静かで、優しくて、これからの未来へ続く光を含んだ微笑みだった。
「さよなら。──そして、ありがとう。」
その言葉は、風のように柔らかく部屋を通り抜け、壁や天井に反響することなく、
ただ静かに梓の胸へ還っていった。
新しい日々への扉が、たしかにそこで、静かに開いた。
雲の切れ間から淡い光がこぼれ、沈みゆく夕日の気配が、梓の頬に薄く触れる。
吸い込んだ空気は冷たかったが、その冷たさすら今は心地よい。
ミラは梓の胸の中で、大人しく丸まっていた。
小さな心臓が規則正しく刻むリズムが、梓の乱れた呼吸をそっと整えていく。
その体温は、長い間閉じこもっていた心の奥まで、静かに、ゆっくりと染み込んでいった。
「……ミラ。帰ろう」
声は驚くほど穏やかで、涙の余韻をまといながらも、確かに前を向こうとしていた。
あの場所に導かれ、あの声を聞いた──
そのすべてが、必要な時間だったように思えた。
家に着き、鍵を回す音がやけに大きく響く。
玄関に灯りがともった瞬間──
スマホが震えた。
たった一度だけ。
呼びかけるようでもなく、焦らすでもなく、
まるで「これで最後だよ」と優しく告げるような震えだった。
「……遼?」
梓は胸の奥が静かに跳ねるのを感じながら、震える指で画面をタップした。
表示されたのは、生きていた頃と同じ──あの、柔らかく笑う遼の写真。
そして、ほとんど間を置かずに音声メッセージが再生された。
雑音まじりの空気。
誰かが息を整える気配。
それから──聞き慣れた、低くて優しい声が流れ込んだ。
『ミラを守ってくれて、ありがとう。僕を想ってくれて……ありがとう。これからは、君が前を向いていく番だよ。』
たったそれだけ。
けれど、そこには過去の彼そのままの温度が宿っていた。
あの日々と同じ愛しさと、あのとき言えなかった想いをそっと包むような響きがあった。
胸がぎゅっと縮まり、
視界が一気に滲む。
「……遼……っ……」
呼びかけた声は、息に溶けてかすれた。
遼の声はそこで静かに途切れたが、その余韻は部屋中に淡い光のように広がっていた。
画面の光は、ゆっくり、ゆっくりと明度を落とし、最後の瞬間には、本当に手を振っているかのように柔らかく揺れて──
そして完全に暗転した。
二度と、ディスプレイは光を戻さなかった。
機能が停止したのか、不具合なのか、理由はわからない。
ただひとつ確かなのは、ミラと出会ってから起こった数々は奇跡だったということだ。
梓はソファに座り込んだまま、長い間、動けなかった。
遼が去った現実と、もう通知されないメッセージ。
彼の優しさが今なお自分を支えている現実が、胸の奥で静かにせめぎ合っていた。
そのとき──
膝の横に座ったミラが、そっと尻尾で梓の手に触れた。
あまりに小さく、あまりにささやかな仕草だったが、その一瞬で、梓の呼吸はやわらぎ、漂っていた悲しみがゆっくりと形を変えていった。
「……あなたも、行ってしまうのね。ミラ」
ミラは小さく喉を鳴らし、そっと足元に身を寄せた。
その温もりが、今日という日をそっと締めくくっていく。
顔を上げ、涙を拭い、梓は深く息を吸った。
気づくと、ミラは部屋から出ていっていた。
遼がくれた言葉も、ミラが導いてくれた奇跡も、すべては前へ進むために差し出されたものだったのだと、ようやく理解できた。
梓はそっと笑う。
静かで、優しくて、これからの未来へ続く光を含んだ微笑みだった。
「さよなら。──そして、ありがとう。」
その言葉は、風のように柔らかく部屋を通り抜け、壁や天井に反響することなく、
ただ静かに梓の胸へ還っていった。
新しい日々への扉が、たしかにそこで、静かに開いた。