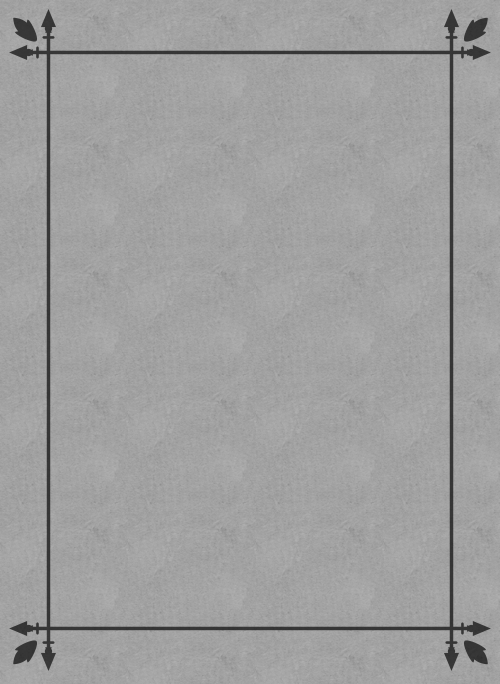ミラが膝の上で丸くなるたび、梓の胸の奥で、説明のつかない何かがゆっくりと膨らんでいく。
それは安堵のようでいて、同時に不意打ちの恐怖にも似ていた。
あの音声メッセージは何だったのか。
偶然?エラー?それとも……。
ありえないはずなのに、遼の声は確かに生きていた頃の温度を帯びていた。
耳ではなく、心臓のほうが先にそれを思い出したように震えた。
「……調べてみよう」
気づけば、梓はスマホを握りしめていた。
指先は少し汗ばみ、画面に触れるたび細かい震えが伝わる。
ゆっくりと検索欄に文字を打ち込む。
「#miracle_follow」
エンターを押した瞬間、画面いっぱいに流れ込む光の粒が、梓の視界を塗りつぶした。
無数の投稿が溢れ出す。
【亡くなった母の声を聞いた】
【飼い犬が夢に出てきて、尻尾を振っていた】
【もう一度だけ、父と話せた気がする】
スクロールすればするほど、常識では説明できない体験談が止めどなく現れる。
作り話──と切り捨てるにはあまりに具体的。
かと言って、現実として受け止めるには、どこか浮世離れしている。
ふと、胸の奥がひゅっと縮む。
投稿のほとんどに、ひとつの共通点があった。
「……#miracle_followと一緒に、猫の写真を投稿している……?」
白い猫。
ミラと、同じ。
梓の呼吸が止まった。
背筋をひんやりと冷たい指がなぞる。
さらに、もうひとつの共通点──
どの投稿も「大切な誰かへの想い」で満ちている。
【会いたい】
【もう一度だけ話したい】
【伝えられなかった言葉がある】
《タグを使うと、大切な人と一度だけつながれる。》
そんな都市伝説を、誰かが囁いていた。
「……信じられるわけ、ないよね」
そう口にしてみても、胸のざわつきは全く静まらなかった。
理性で否定しても、感情が追いつかない。
遼の声は、あまりに 遼そのものだったから。
横を見ると、ミラが静かに尻尾を揺らしていた。
その揺れは否応なく梓の心と呼応し、淡い光を帯びた瞳は「続けて」と語りかけるようだった。
「……もう一回だけ、試してみようか」
梓はミラをそっと抱き上げる。
ミラは小さく喉を鳴らし、彼女の胸に頬を寄せた。
その温もりに背中を押されるように、梓はカメラを向ける。
シャッター音が、静かな部屋にやわらかく響く。
今日の一枚は、優しい灯りに包まれていて、どこか希望の匂いがした。
その写真を#miracle_followと一緒に投稿した──その瞬間。
プツン、と通知音。
心臓が跳ねる。
喉がきゅっと締まる。
〈遼からDMが届きました〉
「え……また……?」
震える指で開く。
新しいメッセージがひとつ。
文章は短く、でもあまりに彼らしい。
『君の作る味噌汁、恋しいな』
胸の奥が一気に熱を帯びる。
これは、冬の朝──遼がよく言っていた言葉だ。
雪が降る前の日、「今日の、特に美味かった」と笑った顔がありありと思い出せる。
視界が潤み、文字が滲む。
スクロールすると、さらに続いていた。
『笑って。君の笑顔が好きだった』
遼が生きていた頃、何度も聞いた言葉。
その声色まで蘇り、胸の奥で弾ける。
「遼……」
掠れた声が漏れる。
悔しいほど弱くて、会いたさを隠しきれない。
ミラが膝の上で小さく鳴く。
その額がそっと梓の指先に触れ、まるで慰めるように寄り添った。
《タグを使うと、大切な人と一度だけつながれる。》
噂のはずだった。
ただの猫のはずだった。
なのに──
物語は静かに、必然のように動き始めていた。
それは安堵のようでいて、同時に不意打ちの恐怖にも似ていた。
あの音声メッセージは何だったのか。
偶然?エラー?それとも……。
ありえないはずなのに、遼の声は確かに生きていた頃の温度を帯びていた。
耳ではなく、心臓のほうが先にそれを思い出したように震えた。
「……調べてみよう」
気づけば、梓はスマホを握りしめていた。
指先は少し汗ばみ、画面に触れるたび細かい震えが伝わる。
ゆっくりと検索欄に文字を打ち込む。
「#miracle_follow」
エンターを押した瞬間、画面いっぱいに流れ込む光の粒が、梓の視界を塗りつぶした。
無数の投稿が溢れ出す。
【亡くなった母の声を聞いた】
【飼い犬が夢に出てきて、尻尾を振っていた】
【もう一度だけ、父と話せた気がする】
スクロールすればするほど、常識では説明できない体験談が止めどなく現れる。
作り話──と切り捨てるにはあまりに具体的。
かと言って、現実として受け止めるには、どこか浮世離れしている。
ふと、胸の奥がひゅっと縮む。
投稿のほとんどに、ひとつの共通点があった。
「……#miracle_followと一緒に、猫の写真を投稿している……?」
白い猫。
ミラと、同じ。
梓の呼吸が止まった。
背筋をひんやりと冷たい指がなぞる。
さらに、もうひとつの共通点──
どの投稿も「大切な誰かへの想い」で満ちている。
【会いたい】
【もう一度だけ話したい】
【伝えられなかった言葉がある】
《タグを使うと、大切な人と一度だけつながれる。》
そんな都市伝説を、誰かが囁いていた。
「……信じられるわけ、ないよね」
そう口にしてみても、胸のざわつきは全く静まらなかった。
理性で否定しても、感情が追いつかない。
遼の声は、あまりに 遼そのものだったから。
横を見ると、ミラが静かに尻尾を揺らしていた。
その揺れは否応なく梓の心と呼応し、淡い光を帯びた瞳は「続けて」と語りかけるようだった。
「……もう一回だけ、試してみようか」
梓はミラをそっと抱き上げる。
ミラは小さく喉を鳴らし、彼女の胸に頬を寄せた。
その温もりに背中を押されるように、梓はカメラを向ける。
シャッター音が、静かな部屋にやわらかく響く。
今日の一枚は、優しい灯りに包まれていて、どこか希望の匂いがした。
その写真を#miracle_followと一緒に投稿した──その瞬間。
プツン、と通知音。
心臓が跳ねる。
喉がきゅっと締まる。
〈遼からDMが届きました〉
「え……また……?」
震える指で開く。
新しいメッセージがひとつ。
文章は短く、でもあまりに彼らしい。
『君の作る味噌汁、恋しいな』
胸の奥が一気に熱を帯びる。
これは、冬の朝──遼がよく言っていた言葉だ。
雪が降る前の日、「今日の、特に美味かった」と笑った顔がありありと思い出せる。
視界が潤み、文字が滲む。
スクロールすると、さらに続いていた。
『笑って。君の笑顔が好きだった』
遼が生きていた頃、何度も聞いた言葉。
その声色まで蘇り、胸の奥で弾ける。
「遼……」
掠れた声が漏れる。
悔しいほど弱くて、会いたさを隠しきれない。
ミラが膝の上で小さく鳴く。
その額がそっと梓の指先に触れ、まるで慰めるように寄り添った。
《タグを使うと、大切な人と一度だけつながれる。》
噂のはずだった。
ただの猫のはずだった。
なのに──
物語は静かに、必然のように動き始めていた。