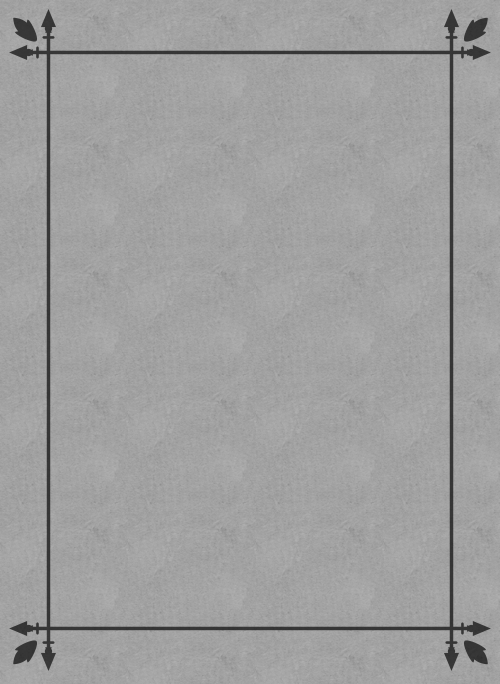通知音が止まない。
まるで自分の心臓がスマホの中に入り込み、そこから暴れているかのように。
一定ではなく、不規則で、落ち着く気配を見せない。
梓は喉の奥がかすかに鳴るのを感じながら、
震える指で「遼」の名前が表示されたDMを、もう一度タップした。
「……なんで……?」
自分でも説明できない期待と恐怖がないまぜになって、胸の奥で渦を巻く。
画面が開くと、そこには小さな「再生ボタン」のアイコン。
遼がよくふざけて送ってきた、「眠い」「迎えに行く」「早く帰ってきて」──
そんな何気ない音声メッセージと同じ形式。
今はもう、存在するはずのないもの。
梓は唇を小さく噛み、ほんの一瞬、指を浮かせたまま固まった。
「……嘘でしょ……?」
怖い。
けれど、それ以上に──聞きたい。
聞いてしまったら、崩れ落ちるとわかっていても。
躊躇いの末、指をそっと押し込んだ。
再生マークが動いた瞬間、部屋の空気がひとつ震えた気がした。
ふっと、優しい息遣い。
少し眠そうな、聞き慣れた低い声。
『寒くない?ちゃんと食べてる?』
その二言だけ。
短い。
けれど、そこに宿っていた温度は──
生きていた頃と、何ひとつ違わなかった。
太陽に触れたときのような柔らかなぬくもりが、耳の奥から胸の中心へ落ちていく。
梓は瞬間的に肩を震わせ、口を手で覆った。
「や……だって……遼のアカウント、もう……」
消えているはずなのに。
SNSからも、データからも、世界からも。
遼がいなくなった証拠のように、あの日の死を境に跡形もなく。
それでも、声は確かにそこにある。
震える指でプロフィールを開こうとすると、画面には冷たい文字が突き刺さった。
「このユーザーは存在しません」
「……どういう……こと……?」
喉が乾く。
頭の奥で警報のようにざわつく。
しかし理解は一ミリも追いつかない。
涙で視界がにじみ、画面の光が揺れた。
そんな梓の膝に、ふわりと白い影が前足をかける。
ミラだ。
スマホの画面を、まるで一緒に読むかのように覗き込み、
首をかしげたあと──喉を鳴らし、やさしい声で「ニャァ」。
慰めるような、促すような、落ち着いて、とでも言うような響き。
「ミラ……?」
名前を呼ぶと、ミラは細い尻尾を梓の腕に巻きつけ、そこに体温を預けてきた。
その瞬間、閉じ込めたはずの記憶が、脳裏で突然フラッシュする。
遼が死んだ夜は雨だった。
遼を駅まで迎えに行く途中の道はびしょ濡れになっていた。
そして、駅前の小さな公園を通り過ぎる途中、救急車の赤いライトがぐるぐる周囲を染めていた。
そこには人が集まり、ざわめいていた。
そして──
ストレッチャーに乗せられた遼を見た時、梓の叫び声が宙に溶けた。
(あれ?あの時、遼の足元に、小さく震えながらうずくまっていた白猫がいたような……)
「……そうだ。現場を見た人が言っていた……遼は助けようとしていたの……猫を……」
偶然?
そんなはずがない。
いや、偶然で処理してはいけない。
そう直感が告げる。
梓はミラの瞳を見つめた。
薄いブルーグレー。
夜雨の下で遼がよく着ていたフードの色。
彼が冬になると必ず選んでいたスウェットの色。
梓の好きだった、遼の似合う色。
「……似てる……すごく……」
喉から漏れた声は、涙で濡れて震えていた。
心臓が、一拍だけ強く跳ねた。
呼吸が乱れ、声がつまる。
ミラはさらにそっと身を寄せ、
梓の指先へ自分の額を押し当てる。
その温もりが、遼の指先の優しさと重なって──
梓の胸が痛みと安堵で同時に詰まった。
「遼……なの……?」
思わずこぼれた声。
言葉にした途端、胸の奥で何かがほどけていく気配がした。
もちろん返事はない。
けれどミラの瞳の奥で揺れる色は、どこまでも彼に酷似していた。
梓は震える手でスマホを持ち直し、DM画面に視線を戻す。
再生済みの音声メッセージが一つ。
無機質なアイコンのはずなのに、そこから遼の気配が滲んでくる。
そして──
画面右上で、新しい通知が小さく点滅した。
静かに、しかし確実に。
まるで、まだ続きがある、そう告げるように。
まるで自分の心臓がスマホの中に入り込み、そこから暴れているかのように。
一定ではなく、不規則で、落ち着く気配を見せない。
梓は喉の奥がかすかに鳴るのを感じながら、
震える指で「遼」の名前が表示されたDMを、もう一度タップした。
「……なんで……?」
自分でも説明できない期待と恐怖がないまぜになって、胸の奥で渦を巻く。
画面が開くと、そこには小さな「再生ボタン」のアイコン。
遼がよくふざけて送ってきた、「眠い」「迎えに行く」「早く帰ってきて」──
そんな何気ない音声メッセージと同じ形式。
今はもう、存在するはずのないもの。
梓は唇を小さく噛み、ほんの一瞬、指を浮かせたまま固まった。
「……嘘でしょ……?」
怖い。
けれど、それ以上に──聞きたい。
聞いてしまったら、崩れ落ちるとわかっていても。
躊躇いの末、指をそっと押し込んだ。
再生マークが動いた瞬間、部屋の空気がひとつ震えた気がした。
ふっと、優しい息遣い。
少し眠そうな、聞き慣れた低い声。
『寒くない?ちゃんと食べてる?』
その二言だけ。
短い。
けれど、そこに宿っていた温度は──
生きていた頃と、何ひとつ違わなかった。
太陽に触れたときのような柔らかなぬくもりが、耳の奥から胸の中心へ落ちていく。
梓は瞬間的に肩を震わせ、口を手で覆った。
「や……だって……遼のアカウント、もう……」
消えているはずなのに。
SNSからも、データからも、世界からも。
遼がいなくなった証拠のように、あの日の死を境に跡形もなく。
それでも、声は確かにそこにある。
震える指でプロフィールを開こうとすると、画面には冷たい文字が突き刺さった。
「このユーザーは存在しません」
「……どういう……こと……?」
喉が乾く。
頭の奥で警報のようにざわつく。
しかし理解は一ミリも追いつかない。
涙で視界がにじみ、画面の光が揺れた。
そんな梓の膝に、ふわりと白い影が前足をかける。
ミラだ。
スマホの画面を、まるで一緒に読むかのように覗き込み、
首をかしげたあと──喉を鳴らし、やさしい声で「ニャァ」。
慰めるような、促すような、落ち着いて、とでも言うような響き。
「ミラ……?」
名前を呼ぶと、ミラは細い尻尾を梓の腕に巻きつけ、そこに体温を預けてきた。
その瞬間、閉じ込めたはずの記憶が、脳裏で突然フラッシュする。
遼が死んだ夜は雨だった。
遼を駅まで迎えに行く途中の道はびしょ濡れになっていた。
そして、駅前の小さな公園を通り過ぎる途中、救急車の赤いライトがぐるぐる周囲を染めていた。
そこには人が集まり、ざわめいていた。
そして──
ストレッチャーに乗せられた遼を見た時、梓の叫び声が宙に溶けた。
(あれ?あの時、遼の足元に、小さく震えながらうずくまっていた白猫がいたような……)
「……そうだ。現場を見た人が言っていた……遼は助けようとしていたの……猫を……」
偶然?
そんなはずがない。
いや、偶然で処理してはいけない。
そう直感が告げる。
梓はミラの瞳を見つめた。
薄いブルーグレー。
夜雨の下で遼がよく着ていたフードの色。
彼が冬になると必ず選んでいたスウェットの色。
梓の好きだった、遼の似合う色。
「……似てる……すごく……」
喉から漏れた声は、涙で濡れて震えていた。
心臓が、一拍だけ強く跳ねた。
呼吸が乱れ、声がつまる。
ミラはさらにそっと身を寄せ、
梓の指先へ自分の額を押し当てる。
その温もりが、遼の指先の優しさと重なって──
梓の胸が痛みと安堵で同時に詰まった。
「遼……なの……?」
思わずこぼれた声。
言葉にした途端、胸の奥で何かがほどけていく気配がした。
もちろん返事はない。
けれどミラの瞳の奥で揺れる色は、どこまでも彼に酷似していた。
梓は震える手でスマホを持ち直し、DM画面に視線を戻す。
再生済みの音声メッセージが一つ。
無機質なアイコンのはずなのに、そこから遼の気配が滲んでくる。
そして──
画面右上で、新しい通知が小さく点滅した。
静かに、しかし確実に。
まるで、まだ続きがある、そう告げるように。