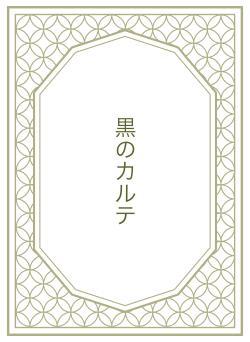「俺、莉太にすんげぇ興味ある」
クラスの――いや、全校生徒の人気者、橘碧生は、僕の顔をまじまじと見つめてそう言った。
思えば、物心ついた頃から僕は"かわいい"と自覚していたと思う。
母親譲りの二重の大きな目と色白で線の細い体。女の子が欲しかったらしい母は僕を男女の境なく育ててくれた。小さい頃は特に女の子に間違えられてばかりだったけれど、悪い気はしなかった。かわいいものが大好きだったし、プリンセスにも憧れてピンク色の色付きリップをこっそりと買ってつけてみたりして……。そんな生活を送る中で、中学卒業を控えた僕に父親は言った。
『高校生になるのだから、いいかげん男らしくしなさい!』
母親も当然のようにそれに従って、僕の日常は一変する。
――男らしさってなんだ?
僕は僕だ。でも、このままではいけないらしい。
鏡を見れば、男らしさからかけ離れた顔。誰かに『かわいい』と言われるのが嫌で、マスクが手放せなくなった。
目立たないようにひっそりと卒業までの三年間を過ごせたらよかった――のだけれど。
*•.
校門の両側に植えられた桜の花が風に吹かれてはらはらと舞い踊っている。
東京都立S高校。私立と引けを取らない進学率と、制服のかわいさで人気の高校だ。
僕がこの高校に入学したのは希望していた私立高校がすべて不合格だったから。あれから一年、今日から高二の新学期が始まる。
昇降口に張り出されたクラス表を見て小さなため息を吐いた。
「あ! 碧生くんと類くんいるじゃん!」
「このクラスあたりじゃない?」
スカートの短い女子たちが嬉しそうにはしゃいでいる。バスケ部のエース橘碧生と恋リア出演中の大門類のいるクラス。 “あたり”そういえるのは彼女が陽キャだからだろう。
僕には彼らが何者なのかなんて興味ない。ただ、静かに一年間をやり過ごせたらいい。
二階の教室に上がると、黒板に張られた座席表を見て席に着く。
前の席はあの橘碧生。百六十センチの僕にとって百八十センチを超える橘くんは聳え立つ壁だ。
(あ。黒板見えないや……)
すぐに先生が入って来てホームルームが始まる。担任は体育教師の安西先生。先生は軽く自己紹介をする。
「安西誠、二十七歳独身。趣味はスポーツ観戦。ラグビー部顧問をしてます。みんな、よろしくな!」
安西先生はゴリゴリの体育会系で生徒には人気があるようだけど、話し方とか勢いとか、正直僕は苦手なタイプ。なんか憂鬱だ。
始業式を済ませ、教室に戻ってくると安西先生は言った。
「二年は高校生活の要だ。このクラスで修学旅行へも行くしな。まずは自己紹介するか! じゃ、阿久津から~」
(やっぱりするのか自己紹介……)
教室の右端の席の人から立ち上がり、名前と自由に一言を添えていく。みんな当たり前のようにやっているけれど、僕はやりたくない。みんなに注目される時間が苦痛でたまらないから。
「大門類です」
長身で派手な見た目のイケメン。人気アイドルグループのセンターで歌っていそうな雰囲気。恋愛リアリティーショーに出演中の大門くんは他校の女子生徒が出待ちをするほどの人気者。番組内でついたあだ名が王子と言うのも頷ける。
「きゃーっ! 王子~」
ひとりの女子がそう叫ぶと投げキッスで応える。するとほかの女子が「王子わたしにもして~」とリクエストする。
「おまえら、静かにしろ! 大門もチャラいことすんな!」
あきれた様子の安西先生は「はい次~」と後ろの席の女子生徒を指名した。そこからはごく普通の自己紹介が続いていく。
やがてガタン、と前の椅子が引かれた。スッと立ち上がる均整の取れた体を思わず見上げる。
「橘碧生、バスケ部です。よろしくお願いします」
大門くんと同じように女子たちがざわついて、「彼女いるんですか?」と質問が飛ぶ。さすがはバスケ部の人気者。「秘密です」と答えると更に教室が沸いた。僕はその隙に立ち上がり「藤枝莉太です」と言ってすぐ席についた。
翌日から早速授業が始まる。僕は真新しい教科書を立てて教壇から見えなくすると塾の課題を広げた。二年生になってから量が増えてなかなか終わらせることができない。志望校は父親と同じ国立大学の法学部を志望校にしているけど、模試はずっとC判定のまま。両親はいい大学に入れと言うけれど、レベルを下げなければ難しいかもしれない。
必死で課題を進めていると、あっという間に昼休みがくる。教室から出ると中庭のベンチでお弁当を広げた。購買や食堂は混んでいるし、教室も騒がしい。この場所は校内の穴場だ。一年生の時に渡り廊下から偶然見つけて以来、毎日ここにくる。校舎から外に出てぐるりと回り込まなければならないからか、一度も誰かと鉢合わせしたことはなかった。
マスクを外し、水筒のお茶で喉の渇きを潤す。ランチバッグから二段のお弁当を開けると、春らしい彩のちらし寿司と好物の唐揚げ。母は毎日手作りのお弁当を作ってくれる。夕ご飯の残りを詰めるなんてことは一度もない。それがどれほど大変な事なのか、実はあまり分かっていない。
お弁当を食べ終えると教室に戻る。次の授業は移動教室だから、早めに準備を整えたかった。
ふと見れば僕の席に橘くんが座っていて、大門くんとなにやら楽しそうに話をしている。声を掛けるのを躊躇っていたら、大門くんが「おまえの席そっち」と前の机を指差した。
「どういうこと?」
困惑する僕に橘くんが言う。
「俺の後ろだと黒板見えねーかなと思って変えたんだ。安西っちには許可もらってる。で、あとこれなんだけどさ……」
橘くんは立ち上がり、僕に近づく。切れ長の意志の強そうな目で真っ直ぐにこちらを見る。
「机動かした時に落ちたみたいでさ」
彼が拳を広げると、ペンケースに入れていたはずの色付きのリップクリームが握られていた。
「これ……」
急に目の前が真っ白になった。誰にも話していない自分だけの秘密。それを橘くんに見つかってしまったなんて。
「ぼっ、僕のじゃないっ!」
「いや、でもこれペンケースから落ちたんだけど?」
「だから僕のじゃないってば!」
橘の手を振り払うと、色付きリップは床に落ちて転がっていく。勇気を振り絞って買った初めてのメイク道具。きれいなピンク色がお気に入りだったのに。
僕は急いで教科書を机から出すと、教室を出た。五、六時限目が選択授業で本当に良かったと思う。
橘くんたちとは放課後まで顔を合わさないで済む。
大好きなはずの日本史の授業は、その日ほとんど頭に入らなかった。
帰りのホームルームが終わり、足早に教室を出る。すると後ろから橘くんが追いかけてくる。
「ちょっとまてよ!」
バスケ部の橘くんにかけっこで勝てるはずもなく、あっという間に追いつかれ捕まってしまう。
「なんで逃げんだよ、莉太」
(いま、莉太って呼んだ?)
不意に下の名前で呼ばれて驚く。
「……なんで名前知ってるの?」
僕の名前なんて認識していないと思っていた。だって、自己紹介だって適当に済ませてしまったし。
「なんでって、当たり前だろ。クラスメイトなんだから。莉太は俺の名前分かる?」
「……橘くん」
「碧生な」
そう訂正され、呼び直す。
「ごめん、たち……あ、碧生くん」
遠慮がちに呼ぶと、橘くんはにかっと笑う。弾けるような笑顔というのはこういうものを言うのだろう。キラキラと光が弾け飛んだように見えた。
「えっと、あの、それでなんの用? 僕、塾に行かなくちゃいけなくて……」
「そっか、じゃあ手短に」
そう言って碧生くんは腰から直角に頭を下げる。
「莉太ごめん。席勝手に移動して、嫌だったよな」
「碧生くん。謝らないで……席の事は嫌じゃなかったよ」
むしろ気にしてくれて嬉しかった。先生に交渉して実行に移す行動力にも感心した。
でも、そんな思いを掻き消すくらい、僕の秘密を見られたことの方が嫌だった。
「もういい?」
碧生くんといるからか、さっきから女子の視線が痛い。出来るだけ早く離れたかったのに、碧生くんは僕の腕を掴んで人目に付かない場所まで引っ張って行く。
壁際に追い込まれて、僕の視界には碧生くんしか入らない。
「これさ、ちゃんと返したくて」
碧生くんは僕の手に色付きリップを握らせた。あの時転がっていったリップをわざわざ拾ってくれたのだろう。突っぱねることも出来たけど、素直に受け取る気になったのは彼の目が真っ直ぐ僕を見ていたからなのかもしれない。
それなのに、「莉太には似合わないよ」って耳元で囁いてくる。そんなこというために追いかけてきたのだろうか。もしそうなら相当タチが悪い。
「莉太はブルーベースだろ? このリップのシリーズで言ったらオーキッドかストロベリー、やっぱダークチェリーのほうが似合いそうだな」
碧生くんの口からでたことばとはにわかに信じられない。僕はポカンと口を開けて彼を見上げる。
「なに言ってるの?」
「なにって、莉太に似合うリップカラーの話しだけど?」
さも当然と言った様子で答える彼に、僕はこう続けた。
「それは分かってるけど、碧生くんは僕のこと変だって思わないの?」
碧生くんは「なんで?」と首を傾げる。
「なんでって、男なのにこんな物もってるなんて普通じゃないでしょ? うちのお父さんは男がメイクするなんてありえないって……だから」
父は少し昔気質なところがある。けど、いつも正しい。弁護士として社会で認められて、仕事をバリバリこなして僕たち家族を守ってる。だから父に従うのは当然だと母もそう言っている。
「それは親父さんの意見だろ。莉太の意見は? 莉太はどう思ってる?」
「えっ、僕⁈ 」
自分がどうしたいかなんて考えた事なかった。父や母が全てを決める。それで困ることなんて今まで無かった……おそらく。
「そう、莉太。おまえも親父さんと同意見?」
……同意見、のはずなはい。小さく首を振った。
「ぼ、僕は……男性とか女性とか関係なくメイクはしたい人がしていいと思う」
そうあって欲しいと言う願いを込めて言った。すると碧生くんは大きく頷いてくれる。
「だよな! で、莉太さ、今週の日曜日空いてる?」
唐突に聞かれてつい「日曜日? 空いてはいるけど……」と言ってしまった。なんの要件か聞けば良かったと後悔する。けど、時既に遅し……。
「俺に時間くれない?」
「なんで、僕?」
人気者の碧生くんが僕なんかに時間を費やす意味があるとは思えない。
「なんでって。俺、莉太にすんげえ興味ある」
まるで宝物を見つけたみたいに、碧生くんは目はキラキラと輝がやかせる。
「き、興味?」
驚いて、声が裏返る。
碧生くんの表情を見る限り、悪い意味ではなさそうだ。じゃあ、ど言う意味だなんだろう?頭の中でぐるぐる考えていると、「アカウント、教えて」とスマホを出してくる。「ほら、早く」と急かされて僕は閲覧専用で作ったあったアカウントのを見せる。
「これでいい?」
碧生くんは画面を操作してプロフィールを表示させると自分のスマホで読み込んだ。
「オケ。じゃあ、明後日の日曜日朝八時にハチ公前集合で! じゃあ、またな」
「え? あ、うん」
去っていく碧生くんの背中を茫然と見つめていた。
日曜日の七時過ぎ。母親には図書委員の仕事があるからと言って家を出た。
電車に乗り、待ち合わせ場所へと向かう。ひとりで渋谷行くのはこれが初めてだ。いや、厳密に言うと、街の中心部に来ること自体初めてで僕は緊張しながら電車に揺られる。
朝の渋谷駅前は思ったより空いていた。すごく込んでいると思っていたのでホッとする。指定されたハチ公を探す。すぐに見つかったのは、隣に碧生くんがいたから。
私服姿の碧生くんは、学校で見るよりとても目立っていた。ロンTに黒のワイドパンツというシンプルなコーディネートなのに、僕の視界に入る他の誰よりもスタイルが良くて、まるでファッション雑誌からそのまま抜け出した来たみたいだ。
「莉太!」
碧生くんは僕に気付くと大きく手を振った。僕は慌てて駆け寄る。
「碧生くん、ごめん遅れて!」
「ぜんぜん、遅れてねぇよ。十五分前だぞ、むしろ早すぎ!」
と言いつつ、碧生くんの方が早くないか?と僕は思う。もしかしたら僕ために早く来てくれたのかもしれない。そうだったら嬉しい。
「てか、日曜日なのになんで制服?」
碧生くんは不思議そうに首を傾げた。
「親には学校に行くって言って出てきたから」
それに、どんな服を着たらいいのか分からなかったから。
「まあ、いいや。行こうか!」
碧生くんは横断歩道を渡り、細い路地は入る。そこから大きな通りに出るとしばらく歩いて雑居ビルのエレベーターに乗った。四階でドアが開く。
「ここで降りるぞ」
降りるとすぐガラスのドアがあった。碧生くんは壁についている小さな箱を開けてボタンを押すような操作するとポケットから出した鍵でドアを開ける。ずいぶん手馴れている。
「入れよ」
碧生くんいに続いて中に入る。カフェみたいな内装に、鏡と椅子が置いてある。それから化粧品の香り。
「もしかして、ここ美容室? 勝手に入っていいの? 怒られない?」
僕が不安になって聞くと「許可はもらってる。じゃなければ鍵だって持ってないだろう?」と笑った。
「そっか、たしかに……」
「もしかして莉太って天然?」
「えっ、僕って天然なの?」
聞き返すと「いや、俺が聞いてるんだけど?」といいながらお腹を抱えてしゃがみ込む碧生くん。
「大丈夫?」
驚いて駆け寄る。苦しんでいる――わけではなかった。肩を震わせて笑いをこらえていた。
「あ、碧生くん。笑ってるの?」
「わりぃ、莉太。お前可愛すぎ」
「なんだよもう、心配して損した!」
「ごめんて」
碧生くんは涙を拭いながら立ち上がると、店内の照明をつけ、音楽をかける。
「ここにはよく来るの?」
「まあな。ここさ、母親の彼氏の店なんだ」
「お母さんの彼氏?」
それってどういうことだろう?不倫? 聞きなれないワードに混乱していると碧生くんは「うち母子家庭だからさ」と説明してくれた。碧生くんのお母さんも美容師でこの店の店長。オーナーの彼氏さんは碧生くんのことを息子のようにかわいがってくれているそうだ。
「ふたりの影響って訳じゃないけど、 ヘアメイキャップアーティスト目指してんの。高校卒業したらこの店でアシスタントしながら美容学校の通信科にいく」
「え、そうなの? 学年トップなのに?」
てっきり大学進学を目指していると思っていた。碧生くんならきっと、僕が目指す大学以上の学校へ入れるはず。
「先生たちは大学に進学しろって言うけどさ、そこでやりたいことがないなら行く意味ねぇだろ」
決して投げやりではない言い方だった。両親に言われたからと、とりあえず大学進学する事だけを目標にしている僕に真っ直ぐに刺さってくる。
じゃあ、僕はどうして大学を目指してるのだろう。そう考えさせられる。
「と言うわけだから、莉太。俺のモデルになってよ」
「モデル⁉ 僕が?」
「だって莉太、メイク好きなんだろ? だからほら、早く座る!」
碧生くんは椅子をくるりと向けると僕の両肩を押して椅子に座らせる。そして、鏡越しに僕を見つめると「マスクはずしていいか?」と聞く。
入学以来外さなかったマスクを外す――僕は躊躇った。でも、碧生くんなら僕を否定しないでくれそうな気がして……。ゴムに指をかけるとそっと外した。顔を上げると鏡越しに碧生くんと目が合う。
「やっぱりブルべだ」
「すごいね、見ただけでわかるなんて」
「必死で勉強したんだ、最初は肌の色に違いがあることすら知らなかったんだぜ。じゃあ、やろっか」
碧生くんは僕の首にタオルを巻くと、ヘアバンドで髪をまとめた。そしてワゴンを引き寄せて何やら準備を始める。
「アレルギーとがかぶれやすいとかはある?」
「ないけど」
「おけ。まずは保湿から」
そういって僕の顔にスプレーを吹きかける。それからマッサージをしながら美容液と化粧水、乳液と塗り重ねていく。動画ではいつも見ているこの工程を自分の顔に施してもらうのは初めてだ。
「これだけで十分すぎるくらい整ったんだけど、どう?」
僕は鏡を見た。透明感と艶があってまるでむきたてのゆで卵のよう。
「すごいね! ツヤツヤだ〜」
「だろ! 莉太の肌、ポテンシャルが高すぎてワクワクしてきた!」
碧生くんは目をキラキラさせて僕を見る。そして慣れた手つきで下地とファンデーションをスポンジで塗り広げていく。
「アイシャドーはラメ入りのグレーをのせて。リップはマットなダークチェリーでモードに――できた!」
碧生くんはヘアバンドを外した。鏡を見るといままで見たことのない僕がいる。凛として芯の強そうな顔。
「すごい、かっこいい」
その感想が正解かは分からない。でも、正直な気持ちだ。
「だろう! 莉太の魅力ってかわいいだけじゃないんだぜ」
「かわいいだけじゃない……」
ドキリとした。いちばん触れて欲しくない部分。だけど不思議と「ああそうか」って納得出来たのはこうしてメイクで証明してくれたからなのかもしれない。
「メイクはモデルの魅力を惹き出す魔法みたいなもんだ!」
「――偉そうに何言ってんの」
背後から聞こえた声に僕と碧生くんは振り返る。すると小柄な金髪の女性がすぐ傍に立っていた。ふたりで集中していたから気が付かなかったのだろう。
「げ!」
碧生くんは思い切り嫌そうな顔をする。
「こんにちは! あなたが莉太くん? はじめまして、理沙です。碧生からいろいろ聞いてるよ」
笑顔と目元が碧生くんに似ている。でもお母さんにしてはずいぶん若い。
「こんにちは。……碧生くんのお姉さん?」
そう思ったのだけれど、碧生くんからすぐに訂正が入る。
「母さんだから! 三十五になるのにすぐに調子に乗んだぜ」
ということは、十八歳で碧生くんを産んだのだ。
「でも、お姉さんにみえるよ。お洒落でカッコいいね碧生くんのお母さん」
お世辞なんかじゃなく、本当にそう思う。金髪のボブヘアに個性的なピアス。シンプルなTシャツにショートパンツ。靴は編み上げのブーツ。すべてが似合っていて素敵だ。僕の母親は今年五十歳で、あまり派手な方ではない。
「やだ、うれし~! お近づきのしるしに髪切ってあげようか?」
言いながら碧生くんを押しのけて僕の後ろに立つ。
「理沙やめろって。莉太に構わないでくれよ」
「なに、ヤキモチ?」
「そんなんじゃねーし。余計なお世話だって言ってんの。莉太もイヤなら断っていいんだぞ!」
「……切って欲しいです」
「え、マジ? いいのか?」
碧生くんは目を丸くする。
「うん。碧生くんのメイクを活かせる髪型にしたくて。でもどんな髪型が似合うんだろう……」
「そうだな。俺がもし、切るならマッシュにするかな。莉太の顔立ちがより引き立つと思う」
僕にマッシュが似合うのか疑問だが、碧生くんのいうとおりにすれば間違いはないだろう。それに碧生くんのお母さん、理沙さんも「いいと思う!」と賛成してくれている。
「マッシュでお願いします」
「まかせて!」
理沙さんは僕にカットクロスを巻いてスプレーで髪を濡らした。そして手際よく髪を切っていく。
碧生くんはすぐそばで見守っていてくれた、と言うより理沙さんの手元を真剣にみている。確かに惚れ惚れするほど手際がいい。
カット後に理沙さんはシャンプーをしてからドライヤーのかけ方のコツまで教えてくれる。
「仕上げはオイルとヘアミルクを混ぜて内側からつけて!」
「はい、分かりました!」
「少し束感が出るようつまんで、これで完成ね」
「うわ、すごい……」
その仕上がりに目を見張った。後で知ったことだけれど、理沙は予約の取れない人気スタイリストなのだとか。
「いいじゃん、莉太。すごく似合うよ! このヘアスタイルならメイクも替えたいな。いい?」
「もちろん」
碧生くんは口紅を落とすと赤みのあるリップグロスを僕の唇にたっぷりと塗った。そしてピンク色のチークを足す。赤みが加わるとより透明感が際立つから不思議だ。
でも、これは流石に……。
「女の子みたいじゃない?」
「うーん。かもしれないけど、莉太に似合ってたらよくない? こういうのは嫌い?」
そう聞かれたら答えはひとつだ。
「好きだよ。……僕に似合うよね?」
「あたりまえだろ!」
碧生くんの言葉に、泣きそうになる。
「莉太? どうかした?」
「ごめん、なんでもない。碧生くんのメイクが上手すぎて感動しちゃった」
すると理沙さんが鏡を覗き込んでくる。
「どれどれ〜あら、いいじゃない、似合いう! 莉太くん、ポテンシャル高すぎ! いろいろ試したくなるの分かる‼」
碧生くんと同じようなことをいいながら、「やるじゃん、碧生! 天才」と褒める。すると碧生くんは「うるせぇ」とまんざらでもない顔で悪態をつく。そこに、出勤してきていた店のスタッフが加わって碧生くんをいじる。
僕は羨望の眼差しを向けた。碧生くんは好きなことを貫いて、みんなに認められている。
「すごいな、碧生くんは」
「なに言ってんだよ、莉太だから俺のメイクが映えるんだぜ。また練習に付き合ってくれる?」
「僕でいいの?」
「俺は莉太がいいの!」
碧生くんは真剣な顔で僕を見つめる。僕も、メイクをしてもらうなら碧生くんがいい。
「そうだ、莉太。写真撮ろうぜ」
「うん」
それぞれのスマホのインカメで撮影する。
ヘアメイクのおかげか、恋人同士に見えなくも……ないか。
高校に入って初めて友達が出来た。楽しかった余韻に浸りながら玄関のドアを開ける。すると母親が驚いた様子で僕迎え入れた。
「莉太⁉ どうしたのその髪」
「友達のお母さんが切ってくれたんだ。似合うでしょ?」
僕が聞くと母は表情を曇らせる。さすがにメイクは落として帰ったのだけれど、もしそのままで帰ってきたらどんな反応をしたのだろう。今の僕には確かめる勇気すらないけれど……。
「せっかく切るならもっと短い方がお父さんも喜ぶと思うな……」
確かに父の好みなではないだろう。
「あのさ、お父さんがどう思うかじゃなくて、お母さんはどう思うの?」
碧生くんの受け売りだけど、母の本音が知りたかったからそう聞いた。すると母は一瞬考え込むようにして、僕を真っ直ぐに見る。
「……莉太にとても似合ってるわ」
そのひと言で僕は救われた気がした。
月曜日。教室に入ると碧生くんと大門くんがなにやら揉めている。
「だから、この子がお前のなんなのか教えろよ!」
「友達だって言ってんだろ」
「嘘つくなよ!」
大門くんが手に持ってるのは碧生くんのスマホだ。
「おはよう」
僕はふたりに声を掛ける。
「おはよう、莉太! お、セット上手いじゃん!」
碧生くんはそう言って親指を立てる。
「ありがとう。朝早起きして頑張ってみたんだ」
理沙さんのセットを再現できているか不安だったけど、碧生くんの言葉にホッと胸を撫で下ろす。
大門くんは僕らのやり取りを不思議そうに見ていたかと思うと、「あっ!」といきなり大声を張り上げて、「碧生のスマホの待ち受けの子って、もしかして藤枝⁉︎」と僕を指差す。
「待ち受け?」
「ほら、これ」
これは昨日碧生くんと撮った写真だ。待ち受けにしてくれたなんて、びっくりだ。でも嬉しい。
「その反応、やっぱり藤枝なんだな!」
大門くんは僕のマスクに手を伸ばす。すると碧生くんは僕を背後から抱きしめるように引き寄せた。
「おい、類〜なに勝手に触ろうとしてんの? ノンデリかよ」
嗜められ、大門くんはバツが悪そうに手を引っ込めた。
「……わりぃ、藤枝」
そんなキラキラした目で見つめられたら誰だって許してしまうと思う。さすがは恋リアで大注目されているだけのことはある。
「大丈夫だよ」
「よかったぁー、じゃあさ、俺とも友達になってくれる?」
(……どうしよう)
チラリと目だけで碧生くんをみる。すると、「どうしたい?」と返されてしまう。
大門くんは正直苦手だ。距離感近くて緊張するし、なんとなくペースを乱される感じがする。でも碧生くんの友達なら悪い人ではないのだろう。
「僕でよければ。よろしくお願いします」
こうして僕は、新学期早々に人気者の友達がふたりも出来てしまった。