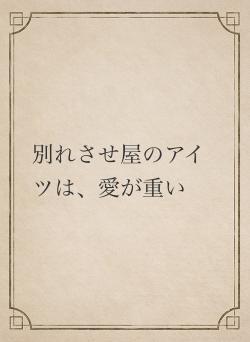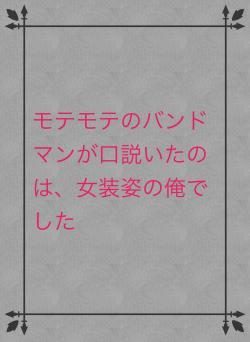第3校舎の屋上ドア前にある踊り場。そこが俺の秘密のサボり場所。仲の良い奴らにも教えていない、1人で過ごすための場所だったのに…。
3時間目の始まりを知らせるチャイムが鳴ると同時に踊り場に着いた俺は足を止めた。
「…。」
1人の男子生徒が足を投げ出した状態で座り、壁に背をくっつけ寝ていた。
ー誰だ、こいつ…。3年にこんな奴いねーし、2年か1年か?
寝ている顔をじっと見ていると、ぱちっと目が開いた。その男は目が合うと驚くこともなく、俺に話しかけた。
「…あ、先輩。お久しぶりです」
久しぶり?え、俺こいつと知り合いだっけ?
「…どっかで会ったっけ?」
「えー忘れたんですかぁ?もぉーひどいなぁ。僕ですよ、僕。友利です」
「ともり…え、あっ!お前、あのチビだった友利!?」
中3の時、内申を上げるための最後の悪あがきとして委員会に入った。俺の日頃の行いによって無意味な行為になったのは言うまでもない。その時に同じ委員会に1年生でいたのが友利だ。
その頃の友利は背が低く、顔も幼かったから小学生に間違われることもあった。
ーまさかこんなに成長するとは…。
「先輩が卒業してからの2年間で一気に伸びたんですよぉ」
変わってないのは、こいつの亀みたいなのんびりした喋り方だけだ。
「つーか、お前ここで何してんの?もう授業始まってっけど」
そう言いながら少しだけ距離を空け、友利の隣に座った。
「先輩がどこかでサボってないかなーって探してて、気付いたらここで寝てました」
…何で俺のこと探してんだよ。
「教室戻れよ。入学して2週間でサボるような不良でもねーだろ、お前」
「先輩は戻らないんですかぁ?」
「…お前に関係ねぇから。もしサボりてーなら他の場所にしろ。ここは俺だけの場所だから」
そう冷たく言い放つと、友利はぐっと俺に近づいてきて、真横に座った。そのまま俺の目をじっと見ながら口を開く。
「一緒にサボらせてくださいよ。せっかく2人っきりになれたんですから…」
さっきまでのゆるい雰囲気が嘘みたいに、甘ったるい言い方をする友利は、俺の知らない男の顔をしている。
自分の心臓がドクンッとなった気がした。…いや、何かの間違いだ。そもそも何で俺が友利なんかにドキドキしなきゃなんねんだよ。
俺は勢いよく立ち上がり、友利の視線から逃げるようにその場から離れた。
仕方なくグループの溜まり場である使われていない資料室に向かう俺はふと、あることを思い出した。
中学の卒業式の日、友利は何故か俺に第二ボタンを要求してきた。当時、俺には付き合っている子がいたし、男である友利にあげる選択肢は1ミリもなかった。
「まじで何なのあいつ…」
放課後、西原、田中、的場の3人とコンビニへ向かう。西原は3年間同じクラス、田中と的場は隣のクラスだ。バイトや用事のない放課後は、この4人で過ごすことが日常。
コンビニに入ると西原は、すぐさまお菓子コーナーへ行く。
「あっ、新しい味出てんじゃん!」
嬉しそうにお気に入りのお菓子を手にする。
田中はスイーツコーナーをチェックしていた。これは自分のためではない。
「このチョコプリン、サキちゃん好きそう。あ、こっちのシュークリームは、めぐちゃん食べたいって言ってたな」
根っからの女好きである田中の行動は、全て女子に繋がっている。
「いっつもブラックコーヒーで飽きねーの?」
店内の1番奥のドリンク棚の前でブラックコーヒーを手に取った的場に話しかける。
「飽きない」
仲の良い俺らにも必要最低限の言葉しか発さないクールな男だ。
次の日の教室では、ゴールデンウィーク明けに開催される球技大会の種目決めが行われていた。
「千賀、何出るー?」
後ろの席から西原が聞いてくる。
「んー、外ならサッカー、中ならバレーかな」
「じゃあ、サッカー出ようぜ!」
「りょーかい」
「2人とも球技大会は、サボんないでよっ!?」
隣の席の女子が口を挟んできた。授業をよくサボっている俺たちを信用していないのかもしれない。
「大丈夫だって!だって俺ら、体育サボったことねーもん!」
自慢げに西原は言ったが、そもそもサボらないことが当たり前だ。
週明けの火曜日。校門が閉まるギリギリに登校した俺は、教室に向かわず第3校舎の踊り場に行く。
踊り場に着くと、ほぼ何も入っていない鞄を枕にし寝転んだ。
しばらくして、目を閉じている俺の耳に微かに足音が聞こえた。廊下に響く足音は徐々に近づいて来たが、このまま通り過ぎるだろうと思っていた。
「あ、やっぱりいたぁ」
聞き覚えのある声に思わず目を開けた。
「おはようございまぁす」
友利は挨拶をして、当たり前のように寝転ぶ俺の側に座った。
「いや、何しに来たの?」
「朝のホームルームが終わったので、一緒にサボりに来たんですよ。あ、僕のことは気にせずそのまま寝ててください」
「お前がいたら気が散るんだけど。つーか、ここは俺の場所だから他でサボれって言ったよな?」
仕方なく起き上がり、友利の横であぐらをかいた。
「先輩、学校はみんなの場所ですよぉ。だからここでサボる権利は僕にもあります」
うわぁ、すげぇムカつく。
「ここでサボんのは自由だけど、俺がいる時はやめろって言ってんだよ」
「1人でサボるなんて寂しいじゃないですかぁ」
「寂しいなら大人しくみんなと授業受けとけよ。つーかお前、友達いねぇの?俺に構う暇あるなら、友達や彼女作れよ」
「友達はいるんで、大丈夫です。彼女は…いらないですね」
「え、なに、恋愛とか興味ないタイプか」
「違いますよぉ。興味ありありです」
「じゃあ、何で彼女いらねぇんだよ」
「そんなの決まってるじゃないですか。先輩のこと好きだからですよ」
「…は?…好き?」
「はい」
一瞬思考が停止した。表情1つ変えないまま返事をする友利にもう一度聞く。
「好きって、先輩としての話だよな?」
「いいえ、恋愛としてですよぉ」
「…そういう冗談いらねーって」
「冗談じゃないです。…本気ですよ」
少し俺の顔を覗き込み、友利は甘い声で言う。
あ、またこの顔と声…。
「僕が先輩の卒業式で第二ボタン欲しいって言ったの覚えてないでしょ?」
「えっ?あー…いや…」
「中1の時からずっとずっと先輩が好きなんです」
え、待て待て。こいつあの時、俺のこと好きだったの?2年間何の音沙汰もなかったけど、今も好きって本気で言ってんのか?
「…今度こそ絶対にこのボタンもらいます」
そう言って俺の第二ボタンに人差し指を当ててきた。
勝手に鼓動が激しくなる。俺は鞄を持ち、逃げるようにその場から走り去った。
「はぁ…はぁ…」
息切れをしながら、溜まり場である資料室のドアを開けた。
運良く誰もいない室内で、椅子にゆっくりと腰掛けた俺の鼓動はまだ激しい。これは走ったから…あいつのせいじゃない、そう自分に言い聞かせる。
それから数日経つとゴールデンウィークに突入し、バイトや西原たちとの予定で埋め尽くされているおかげで、友利のことを考えずに済んだ。
ゴールデンウィーク明けの登校日。朝、電車に乗り込むと友利の後ろ姿があった。
ーうわ、せっかく忘れてたのに…。
向こうに気付かれないうちに、急いで隣の車両に移動し、ドア近くに立った。
電車が進み出し、スマホをぼんやり見ていると耳元で囁き声がする。
「せーんぱい、おはようございます」
…友利だ。
俺は振り返ることなく、軽く「おはよ…」と言い、目線をスマホに落としたまま、背中に密着する友利の身体を意識しないことに必死だ。
そこまで満員でもねぇのに、何でこんな近いんだよ…。
「明日、何に出るんですか?」
「…サッカー」
「応援行けたら行きますねぇ」
「…。」
球技大会当日。グラウンドで開会式が行われ、俺たちはそれぞれ列の後ろの方で、ダルそうに校長の話や体育委員のルール説明を聞いている。田中は、いつもより髪型に気合いの入った女子たちをチェックしていた。
開会式後、各競技ごとにぞろぞろと生徒たちが移動を始め、俺は西原とサッカーコートに向かう。
「初戦の相手どのクラスだっけ?」
「千賀、トーナメント表見てねーのかよ。最初は2年3組と、んで次が4組で…」
赤点の常連とは思えない記憶力だな。
初戦を勝利で終え、コート外に出る俺と西原。
「田中と的場、バレーつってたよな?次の試合まで暇だし見に行くか!」
体育館に入ると試合中で、声援が飛び交っている。
「あ!ちょうど田中たち試合出てんじゃん」
「しゃーねー、応援してやるか」
田中たちが試合をしているコート横に行き、対戦相手のクラスを見た。
「…。」
そこには友利がいた。そういや、あいつ中学の時バレー部だった気がする。あれ…あの頃は背が低いからリベロしてた気がするけど…。
セッター役の生徒が上げたトスを高いジャンプで見事に打った友利。ボールは田中と的場の間に真っ直ぐ落ちていった。
「田中ー的場ー、レシーブしろよー!」
西原がヤジを入れる。
今あいつ、素人の俺から見ても分かるぐらい力加減してた。多分、本気で打ったらすげー威力なんだろうな…。
そんなことを考えながら、無意識に友利を見ていたら目が合った。友利はふっと微笑み、サーブを打つためコートの後方へ出た。
不覚にも友利の微笑みにドキッとしてしまった。
試合は友利のクラスが勝った。
「みんな、わざわざあんがとねー!可愛い声援に夢中になり過ぎて負けちゃった」
応援してくれていた女子たちに絡みに行く田中は、負けたことなんてどうでもよさそうだ。
「お疲れ、的場」
「うん」
「1年にやられるなんて、まだまだだな!」
西原の言葉は華麗にスルーされる。
「先輩」
友利が声をかけてきた。
「次の試合が終わったら応援に行きますねぇ」
そう言い残し去っていく。
「知り合い?」
西原の問いかけに「うん、一応」とだけ答え、体育館の出口へ向かった。
サッカーコート付近に戻るとチームの奴が叫んでくる。
「どこ行ってたんだよーっ!もう試合始まるぞー!」
「悪りぃ悪りぃ」
コート内に入り、1分も経たないうちに試合開始のホイッスルが響いた。
遅刻未遂を挽回するように西原は見事なドリブルを繰り返し、仲間にパスをする。
「西原やるじゃーん!」
応援に来ているクラスの女子が盛り上がり、その声に西原も満足そうだ。
試合は1点リードのまま、残り3分。
「せっかくならもう1点取りてぇな!」
「そだな」
「俺か千賀、どっちかでゴール決めっか」
「あいよ」
仲間からのパスを受け取り、ドリブルでゴールへ向かう西原。俺は逆サイドを走っている。
敵数人に囲まれた西原は、俺に何とかパスを出した。俺はボールを勢いよく蹴り、ゴールへ走る。
ー…ラッキー!ゴール前手薄じゃん。
シュートを放とうとした俺の足元にボールを奪いに来た敵の脚がぶつかり、バランスを崩した。
あ、やべ…
俺の体は宙に少し浮き、地面に右肩から落ちていく。
「いってぇ…」
「千賀っ!大丈夫か!?」
身体を起こし、立ちあがろうとする俺の元へ駆け寄ってくる西原より先に側に来たのは…
「先輩…」
「え…」
…友利だった。
「痛かったですよねぇ」
そう言いながら俺の背中あたりに手を添えると、いきなり身体を持ち上げ、お姫様抱っこをしてきた。
「は!?えっ!?」
ポカーンとする西原を視界の隅に残したまま、俺は抵抗する暇もなく連れて行かれる。
着いたのは保健室。いつも暇そうにしているおばちゃん先生の姿がない。
友利は俺をソファに降ろすと救急箱を開けた。
「肩、消毒しましょう」
隣に座った友利は、慣れた手つきで消毒を始めた。
「少し滲みますけど我慢してくださいねぇ」
すぅー…、滲みるのを歯を食いしばり我慢する。
「よく我慢できました」
子供扱いされ腹が立ったが、ここは素直に礼を言わねーと。
「ありがっ…」
え…
言葉を遮るように友利の唇が俺の唇に重なった。
…これって…キスだよな?
唇が離れ、静かに目が合う。
「あらー怪我人?」
おばちゃん先生がなんとも言えないタイミングで戻って来た。
「僕、決勝戦があるので先に行きますねぇ」
何事もなかったかのように保健室を出て行く友利。
え、さっきのって夢?あいつ俺に…いやいやいや、冗談キツいって。
親指で下唇にそっと触れた。
3時間目の始まりを知らせるチャイムが鳴ると同時に踊り場に着いた俺は足を止めた。
「…。」
1人の男子生徒が足を投げ出した状態で座り、壁に背をくっつけ寝ていた。
ー誰だ、こいつ…。3年にこんな奴いねーし、2年か1年か?
寝ている顔をじっと見ていると、ぱちっと目が開いた。その男は目が合うと驚くこともなく、俺に話しかけた。
「…あ、先輩。お久しぶりです」
久しぶり?え、俺こいつと知り合いだっけ?
「…どっかで会ったっけ?」
「えー忘れたんですかぁ?もぉーひどいなぁ。僕ですよ、僕。友利です」
「ともり…え、あっ!お前、あのチビだった友利!?」
中3の時、内申を上げるための最後の悪あがきとして委員会に入った。俺の日頃の行いによって無意味な行為になったのは言うまでもない。その時に同じ委員会に1年生でいたのが友利だ。
その頃の友利は背が低く、顔も幼かったから小学生に間違われることもあった。
ーまさかこんなに成長するとは…。
「先輩が卒業してからの2年間で一気に伸びたんですよぉ」
変わってないのは、こいつの亀みたいなのんびりした喋り方だけだ。
「つーか、お前ここで何してんの?もう授業始まってっけど」
そう言いながら少しだけ距離を空け、友利の隣に座った。
「先輩がどこかでサボってないかなーって探してて、気付いたらここで寝てました」
…何で俺のこと探してんだよ。
「教室戻れよ。入学して2週間でサボるような不良でもねーだろ、お前」
「先輩は戻らないんですかぁ?」
「…お前に関係ねぇから。もしサボりてーなら他の場所にしろ。ここは俺だけの場所だから」
そう冷たく言い放つと、友利はぐっと俺に近づいてきて、真横に座った。そのまま俺の目をじっと見ながら口を開く。
「一緒にサボらせてくださいよ。せっかく2人っきりになれたんですから…」
さっきまでのゆるい雰囲気が嘘みたいに、甘ったるい言い方をする友利は、俺の知らない男の顔をしている。
自分の心臓がドクンッとなった気がした。…いや、何かの間違いだ。そもそも何で俺が友利なんかにドキドキしなきゃなんねんだよ。
俺は勢いよく立ち上がり、友利の視線から逃げるようにその場から離れた。
仕方なくグループの溜まり場である使われていない資料室に向かう俺はふと、あることを思い出した。
中学の卒業式の日、友利は何故か俺に第二ボタンを要求してきた。当時、俺には付き合っている子がいたし、男である友利にあげる選択肢は1ミリもなかった。
「まじで何なのあいつ…」
放課後、西原、田中、的場の3人とコンビニへ向かう。西原は3年間同じクラス、田中と的場は隣のクラスだ。バイトや用事のない放課後は、この4人で過ごすことが日常。
コンビニに入ると西原は、すぐさまお菓子コーナーへ行く。
「あっ、新しい味出てんじゃん!」
嬉しそうにお気に入りのお菓子を手にする。
田中はスイーツコーナーをチェックしていた。これは自分のためではない。
「このチョコプリン、サキちゃん好きそう。あ、こっちのシュークリームは、めぐちゃん食べたいって言ってたな」
根っからの女好きである田中の行動は、全て女子に繋がっている。
「いっつもブラックコーヒーで飽きねーの?」
店内の1番奥のドリンク棚の前でブラックコーヒーを手に取った的場に話しかける。
「飽きない」
仲の良い俺らにも必要最低限の言葉しか発さないクールな男だ。
次の日の教室では、ゴールデンウィーク明けに開催される球技大会の種目決めが行われていた。
「千賀、何出るー?」
後ろの席から西原が聞いてくる。
「んー、外ならサッカー、中ならバレーかな」
「じゃあ、サッカー出ようぜ!」
「りょーかい」
「2人とも球技大会は、サボんないでよっ!?」
隣の席の女子が口を挟んできた。授業をよくサボっている俺たちを信用していないのかもしれない。
「大丈夫だって!だって俺ら、体育サボったことねーもん!」
自慢げに西原は言ったが、そもそもサボらないことが当たり前だ。
週明けの火曜日。校門が閉まるギリギリに登校した俺は、教室に向かわず第3校舎の踊り場に行く。
踊り場に着くと、ほぼ何も入っていない鞄を枕にし寝転んだ。
しばらくして、目を閉じている俺の耳に微かに足音が聞こえた。廊下に響く足音は徐々に近づいて来たが、このまま通り過ぎるだろうと思っていた。
「あ、やっぱりいたぁ」
聞き覚えのある声に思わず目を開けた。
「おはようございまぁす」
友利は挨拶をして、当たり前のように寝転ぶ俺の側に座った。
「いや、何しに来たの?」
「朝のホームルームが終わったので、一緒にサボりに来たんですよ。あ、僕のことは気にせずそのまま寝ててください」
「お前がいたら気が散るんだけど。つーか、ここは俺の場所だから他でサボれって言ったよな?」
仕方なく起き上がり、友利の横であぐらをかいた。
「先輩、学校はみんなの場所ですよぉ。だからここでサボる権利は僕にもあります」
うわぁ、すげぇムカつく。
「ここでサボんのは自由だけど、俺がいる時はやめろって言ってんだよ」
「1人でサボるなんて寂しいじゃないですかぁ」
「寂しいなら大人しくみんなと授業受けとけよ。つーかお前、友達いねぇの?俺に構う暇あるなら、友達や彼女作れよ」
「友達はいるんで、大丈夫です。彼女は…いらないですね」
「え、なに、恋愛とか興味ないタイプか」
「違いますよぉ。興味ありありです」
「じゃあ、何で彼女いらねぇんだよ」
「そんなの決まってるじゃないですか。先輩のこと好きだからですよ」
「…は?…好き?」
「はい」
一瞬思考が停止した。表情1つ変えないまま返事をする友利にもう一度聞く。
「好きって、先輩としての話だよな?」
「いいえ、恋愛としてですよぉ」
「…そういう冗談いらねーって」
「冗談じゃないです。…本気ですよ」
少し俺の顔を覗き込み、友利は甘い声で言う。
あ、またこの顔と声…。
「僕が先輩の卒業式で第二ボタン欲しいって言ったの覚えてないでしょ?」
「えっ?あー…いや…」
「中1の時からずっとずっと先輩が好きなんです」
え、待て待て。こいつあの時、俺のこと好きだったの?2年間何の音沙汰もなかったけど、今も好きって本気で言ってんのか?
「…今度こそ絶対にこのボタンもらいます」
そう言って俺の第二ボタンに人差し指を当ててきた。
勝手に鼓動が激しくなる。俺は鞄を持ち、逃げるようにその場から走り去った。
「はぁ…はぁ…」
息切れをしながら、溜まり場である資料室のドアを開けた。
運良く誰もいない室内で、椅子にゆっくりと腰掛けた俺の鼓動はまだ激しい。これは走ったから…あいつのせいじゃない、そう自分に言い聞かせる。
それから数日経つとゴールデンウィークに突入し、バイトや西原たちとの予定で埋め尽くされているおかげで、友利のことを考えずに済んだ。
ゴールデンウィーク明けの登校日。朝、電車に乗り込むと友利の後ろ姿があった。
ーうわ、せっかく忘れてたのに…。
向こうに気付かれないうちに、急いで隣の車両に移動し、ドア近くに立った。
電車が進み出し、スマホをぼんやり見ていると耳元で囁き声がする。
「せーんぱい、おはようございます」
…友利だ。
俺は振り返ることなく、軽く「おはよ…」と言い、目線をスマホに落としたまま、背中に密着する友利の身体を意識しないことに必死だ。
そこまで満員でもねぇのに、何でこんな近いんだよ…。
「明日、何に出るんですか?」
「…サッカー」
「応援行けたら行きますねぇ」
「…。」
球技大会当日。グラウンドで開会式が行われ、俺たちはそれぞれ列の後ろの方で、ダルそうに校長の話や体育委員のルール説明を聞いている。田中は、いつもより髪型に気合いの入った女子たちをチェックしていた。
開会式後、各競技ごとにぞろぞろと生徒たちが移動を始め、俺は西原とサッカーコートに向かう。
「初戦の相手どのクラスだっけ?」
「千賀、トーナメント表見てねーのかよ。最初は2年3組と、んで次が4組で…」
赤点の常連とは思えない記憶力だな。
初戦を勝利で終え、コート外に出る俺と西原。
「田中と的場、バレーつってたよな?次の試合まで暇だし見に行くか!」
体育館に入ると試合中で、声援が飛び交っている。
「あ!ちょうど田中たち試合出てんじゃん」
「しゃーねー、応援してやるか」
田中たちが試合をしているコート横に行き、対戦相手のクラスを見た。
「…。」
そこには友利がいた。そういや、あいつ中学の時バレー部だった気がする。あれ…あの頃は背が低いからリベロしてた気がするけど…。
セッター役の生徒が上げたトスを高いジャンプで見事に打った友利。ボールは田中と的場の間に真っ直ぐ落ちていった。
「田中ー的場ー、レシーブしろよー!」
西原がヤジを入れる。
今あいつ、素人の俺から見ても分かるぐらい力加減してた。多分、本気で打ったらすげー威力なんだろうな…。
そんなことを考えながら、無意識に友利を見ていたら目が合った。友利はふっと微笑み、サーブを打つためコートの後方へ出た。
不覚にも友利の微笑みにドキッとしてしまった。
試合は友利のクラスが勝った。
「みんな、わざわざあんがとねー!可愛い声援に夢中になり過ぎて負けちゃった」
応援してくれていた女子たちに絡みに行く田中は、負けたことなんてどうでもよさそうだ。
「お疲れ、的場」
「うん」
「1年にやられるなんて、まだまだだな!」
西原の言葉は華麗にスルーされる。
「先輩」
友利が声をかけてきた。
「次の試合が終わったら応援に行きますねぇ」
そう言い残し去っていく。
「知り合い?」
西原の問いかけに「うん、一応」とだけ答え、体育館の出口へ向かった。
サッカーコート付近に戻るとチームの奴が叫んでくる。
「どこ行ってたんだよーっ!もう試合始まるぞー!」
「悪りぃ悪りぃ」
コート内に入り、1分も経たないうちに試合開始のホイッスルが響いた。
遅刻未遂を挽回するように西原は見事なドリブルを繰り返し、仲間にパスをする。
「西原やるじゃーん!」
応援に来ているクラスの女子が盛り上がり、その声に西原も満足そうだ。
試合は1点リードのまま、残り3分。
「せっかくならもう1点取りてぇな!」
「そだな」
「俺か千賀、どっちかでゴール決めっか」
「あいよ」
仲間からのパスを受け取り、ドリブルでゴールへ向かう西原。俺は逆サイドを走っている。
敵数人に囲まれた西原は、俺に何とかパスを出した。俺はボールを勢いよく蹴り、ゴールへ走る。
ー…ラッキー!ゴール前手薄じゃん。
シュートを放とうとした俺の足元にボールを奪いに来た敵の脚がぶつかり、バランスを崩した。
あ、やべ…
俺の体は宙に少し浮き、地面に右肩から落ちていく。
「いってぇ…」
「千賀っ!大丈夫か!?」
身体を起こし、立ちあがろうとする俺の元へ駆け寄ってくる西原より先に側に来たのは…
「先輩…」
「え…」
…友利だった。
「痛かったですよねぇ」
そう言いながら俺の背中あたりに手を添えると、いきなり身体を持ち上げ、お姫様抱っこをしてきた。
「は!?えっ!?」
ポカーンとする西原を視界の隅に残したまま、俺は抵抗する暇もなく連れて行かれる。
着いたのは保健室。いつも暇そうにしているおばちゃん先生の姿がない。
友利は俺をソファに降ろすと救急箱を開けた。
「肩、消毒しましょう」
隣に座った友利は、慣れた手つきで消毒を始めた。
「少し滲みますけど我慢してくださいねぇ」
すぅー…、滲みるのを歯を食いしばり我慢する。
「よく我慢できました」
子供扱いされ腹が立ったが、ここは素直に礼を言わねーと。
「ありがっ…」
え…
言葉を遮るように友利の唇が俺の唇に重なった。
…これって…キスだよな?
唇が離れ、静かに目が合う。
「あらー怪我人?」
おばちゃん先生がなんとも言えないタイミングで戻って来た。
「僕、決勝戦があるので先に行きますねぇ」
何事もなかったかのように保健室を出て行く友利。
え、さっきのって夢?あいつ俺に…いやいやいや、冗談キツいって。
親指で下唇にそっと触れた。