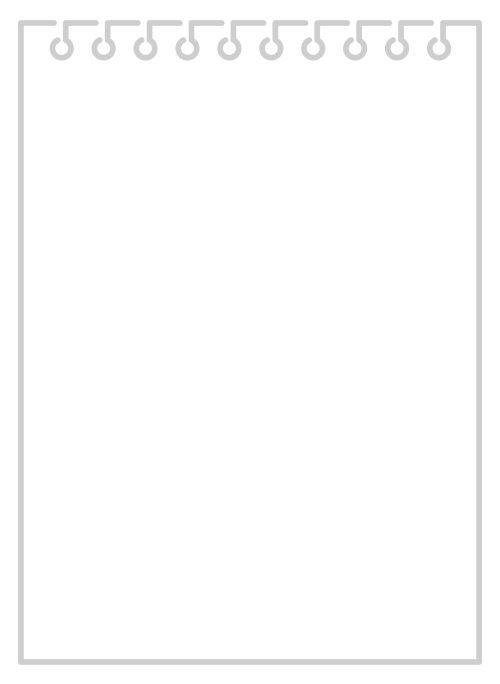私と彼は、住んでいる世界が違うのだと思う。
1つの机を前にして私の正面に座ってはいるものの、その間にはマリアナ海溝よりも深い溝がある。
まあ、そのマリアナ海溝という名の茶色机の上で私は日誌を広げているのだけれど。やばい手がめっちゃ震える。
「高梨って、字きれいだね」
マリアナ海溝の上で頬杖をついた彼。一度顔を上げたが好きな人の顔が目の前にあるということがどうにも信じ難くてすぐに視線を下におろす。
「別にきれいじゃないよ…」
あなたの存在自体がきれいなんですけどね!!
なんて、そんな続きの言葉が口から出かかって「ふんぬっ」とわけのわからない声がもれた。
「なに怒ってんの」と彼がクスクス笑う。はあ!笑った!好き!
「日誌、書くの遅くてごめんね、一ノ瀬くん先に帰っていいよ」
「いやいや、休みのやつの代わりの日直だとしても、さすがにそれはさ、それに書いてもらってるし、いつまででも待つよ」
『いつまででも待つよ』という声が何度も何度も頭の中でリピートされる。しばらくこの思い出だけで生きていけそう。白米5杯いける。
わざと日誌を書くスピードを遅くしている、ということが彼にどうにかバレないような塩梅を保つ。天才か、私。いつまででも待つ、というのはただの気遣いだろうけど、大いに甘えようと思う。
こんなこと、これから先もうないだろうから。
学校、小さなクラスという檻の中ではヒエラルキーという目に見えない階級が存在する。
誰しもが上手く生きていくためにそれ相応の階級に属し、その範囲内で幸せを探していくのだと思う。
クラスでは目立たず、煌びやかな世界にただ憧れることしかできない、そんな私が恋をしてしまったのは、首が痛くなるほど見上げた先にいる、彼、一ノ瀬くんであった。
高校2年生になった最初の席替えで隣の席になり、優しく話しかけてくれた一ノ瀬くん。ころっと落ちた。
おそらく、ダメだと自制をすればするほど人間弱くなる生き物なのかもしれない。
好きになったらダメ、好きになったらダメ、ヒエラルキーを崩したものは処刑される。
「…ありがとう、一ノ瀬くん」
「いいえ、高梨はこういうの雑にしないから先生の信頼あついよな、内申点とか超良さそう」
ほほほほほめられた!一ノ瀬くんに!と、飛び上がりそうな気持ちをこらえて「そんなことないよ」と喉から声を絞り出す。
なんだか少年漫画の悪役の死にかけのような声が出てしまった。一ノ瀬くんがまたクスクスと笑う。
「ねえ、高梨」
「はい」
「ゲーム、しない?」
「ゲーム…?」
『どんな1日でしたか』と書かれた日誌の最後。
行の最後の最後までつかい、丸まで丁寧に書いたあと、持ちかけられたそれに私はシャーペンを置いて顔を上げる。
一ノ瀬くんは頬杖をついたまま、目を細める。
「そう、ゲーム、名付けて『例えばゲーム』」
聞いたことがない。ヒエラルキートップ層たちで流行っているゲームだろうか。
「例えば〇〇だったら?ってきいて、相手の質問に考えて答える。はい、始めます」
「一ノ瀬くん、待って待って、あの、よく分からない」
一ノ瀬くんが2回、手のひらを叩いた。え、リズムゲームなのこれ。大喜利か何かだろうか、無理だ、絶対無理。絶対色んな意味でボロが出る。
「例えば、俺が毒リンゴを差し出したら?」
2回、音が鳴る。
「食べる」
「即答かよ」と笑った一ノ瀬くん。一ノ瀬くんから差し出されたリンゴなら食べるだろう、毒だろうがなんだろうが本望だ。
また音が鳴り、「次、高梨が言って」とにこやかに促される。焦りながらも頭の中をフル回転させた。
「た、例えば、明日世界が滅ぶとしたら?」
「ええ、あー、あっ、でっかいステーキ食べる」
かわいい。いつもは少し大人びた様子の一ノ瀬くんが、少年のように放ったそれ。心臓がきゅっと痛くなる。もっと好きにさせないでください、お願いだから!
「例えば、このまま教室に閉じ込められたら?」
「さいこ、…最悪です」
「ふっ、」
「たっ、例えば、永遠に日直を任せられたら?」
「最悪…うーん、高梨となら別にいいかな」
続きの音が鳴らなかった。「え」と声をもらした私。思考回路が回らないうちに一ノ瀬くんがゆっくりと手を机におろして、再び頬杖をつく。
少し傾いた顔が、窓から差し込む夕日の色にほのかに染まった。
その唇が、小さく動いた。「例えば」と
「例えば、俺が君のことを好きだって言ったら?」
どうやったって、この溝は飛び越えられないと思っていたので、正解はキャパオーバーで爆発しそうになる、だ。夢かと思って自分の頬をつねったがしっかり痛かった。痛さで泣けているのか、夢みたいな現実に泣けているのか、訳も分からない。
答えを焦らせるような音は何もなく、ただ教室の時計の音と、外で聞こえる野球部の声が入り混じって、やけに響いていた。
心臓が、爆発する。
「…からかってる?」
「そう思うなら続けてよ、高梨」
「えっと、」
ゆっくりと息を吸う。
「例えば、私が一ノ瀬くんを好きって言ったら?」
一ノ瀬くんは、片手を机についた。
見えない溝を払いのけるかのように、身をこちらに近づけた。
触れる直前、彼の唇がゆっくりと動く。
「俺もだよって、キスをする」
君と例えばの話をしよう
end