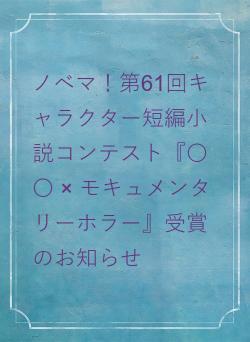雪の日にひろったから名前はユキ。手のひらに、ふうわりと軽い白い子猫。母親とはぐれ、雪の降りつむ公園でにーにーと鳴いていた。私は赤い傘を置き、子猫を抱き上げた。子猫は私の指をくわえ力強くちうちうと吸った。
それからユキと私の二人暮らしが始まった。
目も開かぬころに拾ったせいか、ユキは毛繕いが下手な猫に育った。いつも適当に舌で毛をなでつけるだけで常にフケが浮いていた。
本当なら親猫が見本を見せて覚えさせるのだろうけれど、残念ながら私は毛皮を持ち合わせない。仕方なく猫用ブラシで毛をすいてやると、ユキは怒って私の手を噛んだ。
噛んだと言っても育ての親への遠慮からか甘噛みだったけれど。
ユキの喉元を撫でてご機嫌をとりながら、なんとかかんとか毛をすきおわる。すき終わってもユキはまだまだ撫でろと飽かず喉をごろごろ言わせつづけた。
猫のごろごろには、癒し効果があるらしい。私はユキと暮らしているあいだ、一度も風邪をひかなかった。大した病気もしなかった。もしかしたら、私が寝ている胸元に夜な夜なユキが鎮座ましまし、私を暖めていてくれたからかもしれない。
海苔がユキの好物だった。
コンビニおにぎりを食べていると、どこからかにゅうと現れて「海苔をくれなきゃ化けてでるぞ」と言わんばかりに、びゃーびゃーと鳴いた。
しかたなく海苔をちぎって鼻先にぶらさげてやると親の仇かと思う勢いで食らいつく。いつもは甘噛みなのに海苔がからむと獰猛な野生に目覚めたかのごとく牙を立てる。
私の指には未だに、ぷっすりと開いた牙の跡が仲良く二個、並んでいる。
そう言えばユキはふすまを自分で開けて、押入れの布団の間に挟まるのが大好きだった。
『ふすまを閉める猫は化ける』と聞いたことがある。開けるだけで閉めなかったユキは、残念ながら化けそこなったようで19歳で見えなくなった。猫としては長寿の類に入ると思う。
腎臓が弱りエサも水もほとんど取らないようになり、体は叙々に細っていった。最後の三ヶ月、ユキは悟りを開いた僧侶のように日がな物思いして、たまに、にーと鳴いた。
布団に入った私の胸の上、ユキはふうわりと軽くなった。
だが、どれだけ痩せても、歩くのが億劫なほど足腰が弱っても、最後の夜までユキは私の胸の上でごろごろと喉を鳴らした。まるで私のための子守唄のように。
翌朝ユキは一声しっかりとびゃーと鳴くと、玄関の引き戸を勝手に開けて出ていった。外は眩しいくらいに雪がつもり、ユキの小さな足跡がてんてんと雪の上に残ったが、すぐに昼の陽の中に溶けていった。
猫は死ぬときに、遺体を人目に晒さないというが、ユキは足跡さえも消して行った。それきりユキには会っていない。
詫び住まいに咳の音を響かせる夜には、ユキのことを思い出す。あの、ごろごろの音と共に。私の胸はユキの指定席として、今でも開けたままにしてある。
それからユキと私の二人暮らしが始まった。
目も開かぬころに拾ったせいか、ユキは毛繕いが下手な猫に育った。いつも適当に舌で毛をなでつけるだけで常にフケが浮いていた。
本当なら親猫が見本を見せて覚えさせるのだろうけれど、残念ながら私は毛皮を持ち合わせない。仕方なく猫用ブラシで毛をすいてやると、ユキは怒って私の手を噛んだ。
噛んだと言っても育ての親への遠慮からか甘噛みだったけれど。
ユキの喉元を撫でてご機嫌をとりながら、なんとかかんとか毛をすきおわる。すき終わってもユキはまだまだ撫でろと飽かず喉をごろごろ言わせつづけた。
猫のごろごろには、癒し効果があるらしい。私はユキと暮らしているあいだ、一度も風邪をひかなかった。大した病気もしなかった。もしかしたら、私が寝ている胸元に夜な夜なユキが鎮座ましまし、私を暖めていてくれたからかもしれない。
海苔がユキの好物だった。
コンビニおにぎりを食べていると、どこからかにゅうと現れて「海苔をくれなきゃ化けてでるぞ」と言わんばかりに、びゃーびゃーと鳴いた。
しかたなく海苔をちぎって鼻先にぶらさげてやると親の仇かと思う勢いで食らいつく。いつもは甘噛みなのに海苔がからむと獰猛な野生に目覚めたかのごとく牙を立てる。
私の指には未だに、ぷっすりと開いた牙の跡が仲良く二個、並んでいる。
そう言えばユキはふすまを自分で開けて、押入れの布団の間に挟まるのが大好きだった。
『ふすまを閉める猫は化ける』と聞いたことがある。開けるだけで閉めなかったユキは、残念ながら化けそこなったようで19歳で見えなくなった。猫としては長寿の類に入ると思う。
腎臓が弱りエサも水もほとんど取らないようになり、体は叙々に細っていった。最後の三ヶ月、ユキは悟りを開いた僧侶のように日がな物思いして、たまに、にーと鳴いた。
布団に入った私の胸の上、ユキはふうわりと軽くなった。
だが、どれだけ痩せても、歩くのが億劫なほど足腰が弱っても、最後の夜までユキは私の胸の上でごろごろと喉を鳴らした。まるで私のための子守唄のように。
翌朝ユキは一声しっかりとびゃーと鳴くと、玄関の引き戸を勝手に開けて出ていった。外は眩しいくらいに雪がつもり、ユキの小さな足跡がてんてんと雪の上に残ったが、すぐに昼の陽の中に溶けていった。
猫は死ぬときに、遺体を人目に晒さないというが、ユキは足跡さえも消して行った。それきりユキには会っていない。
詫び住まいに咳の音を響かせる夜には、ユキのことを思い出す。あの、ごろごろの音と共に。私の胸はユキの指定席として、今でも開けたままにしてある。