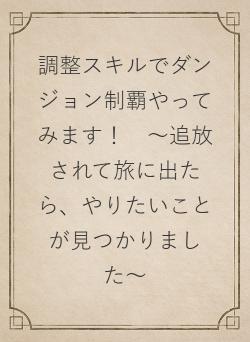ぐわりとドラゴンの大きな口が開く。
『おのれ人間! ガルブをどこへやった!!!!』
その中で青い炎がちらついたかと思うと、とんでもない勢いで空島に向かって放たれた。
とはいえそれは想定済。どうせ過保護なドラゴンなんて目の前見えてなくて、息子の名前聞くだけで暴走するだろうってね。
「防御結界、起動」
もともと空島は、これをくれた神様の保護魔法がかかっていて、そこにくわえてぼくが考案した防御結界の魔道具がかけられている。
まあ、神様の保護魔法のほうが全然強いだろうから、もしかしたらぼくの防御結界なんていらないかもしれないけど、念には念を入れよ、という感じだ。
ドラゴンの青い炎が空島を包み込むが、空島は無傷のまま。
顔をしかめた……ように見えるドラゴンに向かって、ぼくは親指でアトリエを指しながら言い放った。
「あんたの息子、ぼくんとこに家出してきて、今あそこのアトリエを占領してんだよね」
『……アトリエ?』
「そうか。アトリエっていう単語はドラゴンにはないのか。ぼくの家ってこと。あそこに見えるでしょ、黄色のおうち」
というかよくよく考えると、ガルブのような子ドラゴンだけじゃなくて、目の前の大人ドラゴンにもちゃんと翻訳魔道具は効いてるのか。
これでほぼほぼ実証成功ではあるけれど、もう少し詰めたいんだよね……
『ガルブは無事なのか!』
しかし再び我を忘れたかのようにドラゴンは大声をあげ、空気がビシビシと震える。
まあ、心配してるだけなんだろうけど、普通に大声自体は保護魔法を貫通して窓が割れそうだから勘弁してほしい。
「無事だけど……寝不足だったみたいだから、もう少し寝かせてあげてよ」
『なぬぅ! ガルブ!』
「うるさい」
魔法特務機関の所属を示すローブの内ポケットから、簡易射出魔道具を取り出してドラゴンの額めがけて打つ。
ぼくが魔法特務機関に来て最初のほうに作った、拳銃式の魔道具だけど、非殺傷武器かつ威力もそこまでないから、相手に意識を向けるのに持ってこいだ。
ドラゴンに効くのかどうかはわからなかったけど、意外と効いたようだ。
『むぅ……すまない』
「ま、心配してるのは伝わってくるから別にいいよ。ところでこのあたりにこの大雪が凌げそうなひらけた場所ってある?」
『ひらけた場所? 何をするつもりだ?』
「何って……ガルブが起きるまでの間、あんたとおしゃべりしたいんだけど」
腰に手を当てて、コンコンとそばにあった翻訳魔道具の機械を叩く。
別にこのまま会話すること自体は可能だけど、ドラゴンはまだ飛んでるし、吹雪はまだまだ強いしで、あまり環境的によろしくない。主にぼくの。
それにガルブみたいな子ドラゴンは睡眠時間が長く、ひとたび寝るとなかなか起きないと聞いたことがある。
ぼくがガルブを持てたら良かったけど、あいにくそんな魔道具はまだ作っていない。
さすがにこのドラゴンにアトリエの中からガルブを連れていってもらうのは体長的に無理だし、ガルブが起きるのを待つしかないってことだ。
ドラゴンはじっとぼくを見つめていたが、ふいと顔を逸らす。
『こちらへ来い……変わった――――』
そして勢いよく羽ばたいたかと思うと一瞬にしてその場から去ってしまった。
最後のほうは翻訳魔道具の範囲から外に出てしまったからか、ただの咆哮にしか聞こえなかった。
「あ、ちょっと待って! この空島、さすがにそんなに早くは移動できないんだけど!」
すでに吹雪の向こうに姿を消してしまったドラゴンを眺めて、ぼくはそう叫んだが、残念なことに、咆哮しか聞こえなかった。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
ドラゴンの去った方向へ進むこと十分ほど。
少しずつ吹雪が弱まっていく中、空島が着地できそうなひらけた場所でドラゴンが待っていた。
『遅い』
「あんたが早いんだよ……」
憮然とした様子のドラゴンの言葉にため息をつきながらも、ぼくは空島を操ってひらけた場所に着地させる。
ボフッ、とまるで雪に飛び込んだような可愛い音が聞こえた。
意外とこの空島大きいんだけど、それでもひらけた場所があるっていうのはすごいな。ドーニッヒ山脈自体かなり大きな場所だけど、あまり山にはこういった平地は少ないからな。
「あ、そうだ。一応、あんたの息子が無事かどうか、そこの窓から見ておきなよ」
よくよく考えたら、このドラゴン、ぼくが噓ついてるかどうかも気にせずにぼくをここまで案内していたということになる。
別に噓ついているわけじゃないけど、信用しすぎるのもいかがなものかと思う。人間って意外と狡猾な生き物だから。
『問題ない。ガルブの魔力を探知した』
「あ、そうなんだ。魔力って動物の個体によって違うものなんだ?」
『はっ。人間はそんなこともわからないのか?』
「少なくとも、これまでそんな論文は読んだことなかったな。それにぼく、魔力持ってないから探知できないんだ」
『そんな馬鹿なことがあるわけ……』
先ほどよりも少し抑えた声で笑い声をあげるドラゴンだったが、すぐにその笑い声は止まった。そして、ぐいと勢いよくぼくに顔を近づけてきた。
吹雪の中を移動してきたからか、ドラゴンの鱗からひんやりと冷気が伝わってくる。
『……本当だな』
「でしょ? だからこういう道具作ってんの。この魔道具も空気中の魔力を吸収してるから使えてるだけ」
『本当に変わった人間だな、お前は』
「よく言われる」
ふん、と鼻息を吐いて応えるドラゴンを横目に、ぼくは翻訳魔道具に近づいた。
『何をするつもりだ』
「そんな警戒しないでよ。ガルブが起きるまでの間、時間潰しに付き合ってもらおうと思って」
翻訳魔道具にある無数のボタンのうち、ある一つを押す。すると、分厚いノートのような機械が現れる。
それを持ってドラゴンのそばに座ると、あぐらをかいて座った。
「んじゃ、ちょっとお話ししよっか」
『おのれ人間! ガルブをどこへやった!!!!』
その中で青い炎がちらついたかと思うと、とんでもない勢いで空島に向かって放たれた。
とはいえそれは想定済。どうせ過保護なドラゴンなんて目の前見えてなくて、息子の名前聞くだけで暴走するだろうってね。
「防御結界、起動」
もともと空島は、これをくれた神様の保護魔法がかかっていて、そこにくわえてぼくが考案した防御結界の魔道具がかけられている。
まあ、神様の保護魔法のほうが全然強いだろうから、もしかしたらぼくの防御結界なんていらないかもしれないけど、念には念を入れよ、という感じだ。
ドラゴンの青い炎が空島を包み込むが、空島は無傷のまま。
顔をしかめた……ように見えるドラゴンに向かって、ぼくは親指でアトリエを指しながら言い放った。
「あんたの息子、ぼくんとこに家出してきて、今あそこのアトリエを占領してんだよね」
『……アトリエ?』
「そうか。アトリエっていう単語はドラゴンにはないのか。ぼくの家ってこと。あそこに見えるでしょ、黄色のおうち」
というかよくよく考えると、ガルブのような子ドラゴンだけじゃなくて、目の前の大人ドラゴンにもちゃんと翻訳魔道具は効いてるのか。
これでほぼほぼ実証成功ではあるけれど、もう少し詰めたいんだよね……
『ガルブは無事なのか!』
しかし再び我を忘れたかのようにドラゴンは大声をあげ、空気がビシビシと震える。
まあ、心配してるだけなんだろうけど、普通に大声自体は保護魔法を貫通して窓が割れそうだから勘弁してほしい。
「無事だけど……寝不足だったみたいだから、もう少し寝かせてあげてよ」
『なぬぅ! ガルブ!』
「うるさい」
魔法特務機関の所属を示すローブの内ポケットから、簡易射出魔道具を取り出してドラゴンの額めがけて打つ。
ぼくが魔法特務機関に来て最初のほうに作った、拳銃式の魔道具だけど、非殺傷武器かつ威力もそこまでないから、相手に意識を向けるのに持ってこいだ。
ドラゴンに効くのかどうかはわからなかったけど、意外と効いたようだ。
『むぅ……すまない』
「ま、心配してるのは伝わってくるから別にいいよ。ところでこのあたりにこの大雪が凌げそうなひらけた場所ってある?」
『ひらけた場所? 何をするつもりだ?』
「何って……ガルブが起きるまでの間、あんたとおしゃべりしたいんだけど」
腰に手を当てて、コンコンとそばにあった翻訳魔道具の機械を叩く。
別にこのまま会話すること自体は可能だけど、ドラゴンはまだ飛んでるし、吹雪はまだまだ強いしで、あまり環境的によろしくない。主にぼくの。
それにガルブみたいな子ドラゴンは睡眠時間が長く、ひとたび寝るとなかなか起きないと聞いたことがある。
ぼくがガルブを持てたら良かったけど、あいにくそんな魔道具はまだ作っていない。
さすがにこのドラゴンにアトリエの中からガルブを連れていってもらうのは体長的に無理だし、ガルブが起きるのを待つしかないってことだ。
ドラゴンはじっとぼくを見つめていたが、ふいと顔を逸らす。
『こちらへ来い……変わった――――』
そして勢いよく羽ばたいたかと思うと一瞬にしてその場から去ってしまった。
最後のほうは翻訳魔道具の範囲から外に出てしまったからか、ただの咆哮にしか聞こえなかった。
「あ、ちょっと待って! この空島、さすがにそんなに早くは移動できないんだけど!」
すでに吹雪の向こうに姿を消してしまったドラゴンを眺めて、ぼくはそう叫んだが、残念なことに、咆哮しか聞こえなかった。
◆ ◇ ◆ ◇ ◆
ドラゴンの去った方向へ進むこと十分ほど。
少しずつ吹雪が弱まっていく中、空島が着地できそうなひらけた場所でドラゴンが待っていた。
『遅い』
「あんたが早いんだよ……」
憮然とした様子のドラゴンの言葉にため息をつきながらも、ぼくは空島を操ってひらけた場所に着地させる。
ボフッ、とまるで雪に飛び込んだような可愛い音が聞こえた。
意外とこの空島大きいんだけど、それでもひらけた場所があるっていうのはすごいな。ドーニッヒ山脈自体かなり大きな場所だけど、あまり山にはこういった平地は少ないからな。
「あ、そうだ。一応、あんたの息子が無事かどうか、そこの窓から見ておきなよ」
よくよく考えたら、このドラゴン、ぼくが噓ついてるかどうかも気にせずにぼくをここまで案内していたということになる。
別に噓ついているわけじゃないけど、信用しすぎるのもいかがなものかと思う。人間って意外と狡猾な生き物だから。
『問題ない。ガルブの魔力を探知した』
「あ、そうなんだ。魔力って動物の個体によって違うものなんだ?」
『はっ。人間はそんなこともわからないのか?』
「少なくとも、これまでそんな論文は読んだことなかったな。それにぼく、魔力持ってないから探知できないんだ」
『そんな馬鹿なことがあるわけ……』
先ほどよりも少し抑えた声で笑い声をあげるドラゴンだったが、すぐにその笑い声は止まった。そして、ぐいと勢いよくぼくに顔を近づけてきた。
吹雪の中を移動してきたからか、ドラゴンの鱗からひんやりと冷気が伝わってくる。
『……本当だな』
「でしょ? だからこういう道具作ってんの。この魔道具も空気中の魔力を吸収してるから使えてるだけ」
『本当に変わった人間だな、お前は』
「よく言われる」
ふん、と鼻息を吐いて応えるドラゴンを横目に、ぼくは翻訳魔道具に近づいた。
『何をするつもりだ』
「そんな警戒しないでよ。ガルブが起きるまでの間、時間潰しに付き合ってもらおうと思って」
翻訳魔道具にある無数のボタンのうち、ある一つを押す。すると、分厚いノートのような機械が現れる。
それを持ってドラゴンのそばに座ると、あぐらをかいて座った。
「んじゃ、ちょっとお話ししよっか」