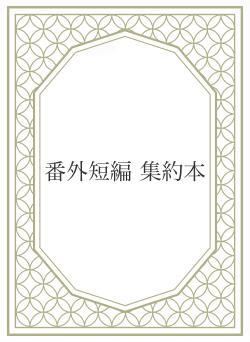***
「優陽から僕に会いたいって言ってくるなんて初めてだよね?」
「宮永さんは忙しいのにごめんなさい。それにお店も選ばせちゃって」
「いや、嬉しいんだって。大人に頼るところは頼りなさい」
金曜日の夜、僕は宮永さんとセブファクの事務所近くの戸建ての和食料理屋さんに連れてきてもらっていた。
看板も出ていないし、一見すると普通の民家。
掘りごたつの完全個室へと案内されて、宮永さんと二人きりの空間になった。
僕から宮永さんを誘ったわけだけど、何を食べたいか聞いてくれて。
いつもは完全に宮永さんに任せきりにしているけれど、今回は和食がいいと伝えることにした。
長いことアメリカに行っていたから、宮永さんは日本食が恋しいかなとも思ったし、僕は和食が1番好きだから……。
こうして少しずつ相手のことも考えながら僕の意思表示や選択もしていこう。
「ちょうどアメリカ土産も渡したかったし」
そう言った宮永さんの隣には紙袋ぎっしりにお土産が入っていた。
「毎回こんなに申し訳ないよ」
「お土産選んでると、あれもこれも優陽に食べさせたくなっちゃうんだよな。優陽のことを考えながらチョイスしてる時間が楽しいから遠慮なくもらってくれると助かる」
「ありがとう」
宮永さんの微笑には包容力がある。
たっちゃんが言っていたように宮永さんは僕を昔から特別に可愛がってくれていた。
宮永さんは優しいから、生まれた途端に身内が一人も居なくなった僕に気遣ってくれているのかと思っていたけど……。
『優陽くんの父親って宮永さんじゃないかしら……』
美織さんたちでさえ勘ぐっている僕の父親なのかの答えが出るのかもしれない。
でも、いざ質問するとなると躊躇してしまう……。
そわそわしたまま、一通り美味しいご飯を食べ終わった頃、先に宮永さんから質問があった。
「優陽は一条琉唯くんと何か関係があるの?」
「え!?」
まさか宮永さんから琉唯の話題を出されると思わなくて、緊張していた僕は大げさなほどに反応してしまった。
「一条くんと映画のPRで一緒だった日、一条くんは誰かと強張った表情で電話していて、”優陽”って名前がよく聞こえてきていた。それから血相を変えた慌てた様子で楽屋から飛び出していったんだけど」
それってまさか、僕がノアさんに軟禁されていたのを助けてくれた日のこと……?
やっぱり琉唯は僕を助けるために仕事を抜けてくれていたんだろう。
「その少し前には侑くんから一条くんのスマホに電話がかかってきているのを偶然画面で見てもいる」
たっちゃんが宮永さんから琉唯のことを聞かれたのはだからだったのか……。
「”ゆうひ”って珍しい名前でもないと思うけど。侑くんと二人揃えば、偶然でもないのかと思って」
宮永さんに何て答えるのが正解なんだろう?
でも、宮永さんには何となく小手先だけでごまかしたくなくて……。
「琉唯は僕が初めて好きになった人……」
僕の言葉に意表を突かれたのか、宮永さんは表情が固まった。
「でも、振られちゃった……」
笑うつもりだったのに、目元が不自然に熱くなってくる。
「僕も自分が男を好きになるとは思わなかったんだけどね……」
「関係ないよ。それは」
柔らかい宮永さんの笑みが僕をまるごと肯定して受け止めてくれているようで、気持ちが凪いだ。
「僕もずっと好きな人が居る……」
「……」
「たぶん僕は生涯その人しか愛せないのかもしれない」
哀愁の漂う声色で言葉を放ち、宮永さんはテーブルの木目へと視線を落とした。
「……宮永さんの、その相手は咲良菜緒?」
「え?」
僕はバッグの中から1冊のノートを取り出して、中をパラパラとめくり目的のページを開いた。
「これ華澄高の映像研究部の記録ノートの1冊なんですけど、ここを宮永さんに見てもらいたくて」
宮永さんは僕から開かれたノートを受け取る。
琉唯が気づいた映像研究部の記録ノートの片隅に認められていた一文。
――いずみ先輩、大好き。直子
すぐに問題の文字を見つけたみたいで、宮永さんは眉根を寄せた。
「驚いた……こんなものが残っていたとは……」
「これを書いたのは咲良菜緒……僕のお母さんじゃないのかなと思っていて」
「確かに菜緒の筆跡に間違いないね」
「このいずみ先輩っていうのは宮永さんですよね?」
「……」
「僕のお父さんは宮永さんなんですか?」
一気に喋り終わって、僕は息を吐き出していた。
自分でも知らないうちに緊張の糸が張り詰めていたらしい。
宮永さんはノートの文言に縫い留められたように視線を動かさなかった。
個室には重々しい無言が続く。
それを打ち破ったのは宮永さんだった。
「――僕だけが優陽の父親を知っている」
その台詞に痛いくらいに胸の音が鳴った。
「もちろん頼さんも真実は知らない。この秘密は墓場まで持っていくつもりだった」
「……それはどうして……?」
「ごめん、優陽。例え優陽だとしても言えない。それが菜緒との約束だから」
やっぱり宮永さんが僕の父親で咲良菜緒に何らかの理由で口止めをされているということなのだろう。
宮永さんの表情は苦渋を語るもので、これ以上聞いてはいけないんだと頭では理解できる。
でも、僕は……。
「教えてください。咲良菜緒はもう亡くなってしまったけれど、僕は今を生きているから……」
僕の真っ直ぐな視線を宮永さんは受け止めてくれている。
少し考え込むように黙ってから宮永さんは重い口を開いた。
「――菜緒は清純派なイメージで売られていたけど、実は私生活は奔放というか飾り気がなかった」
「……」
「プロフィールでは好きな食べ物をチーズケーキとグラタンにしてたけど、実際はエイヒレとたこわさだし。お酒を呑むのもカクテル類じゃ呑んだ気がしないって、イモ焼酎が一番好きだったし。現場でも気を抜くと木登り始めようとするし」
「……木登り……咲良菜緒のイメージにないね」
「うん。そういうとこも菜緒は猫みたいだった。ちょうどいい木を見つけると登りたくなるらしい。女優なんだから怪我をされると困るから止めろって頼さんも僕も何度も注意してた。いつまでも菜緒は小学生の悪ガキって感じ」
宮永さんは僕を慈悲深い目で見つめながらも、有し日の咲良奈緒を脳裏に思い浮かべているのだろう。
「何か意外。たっちゃんみたい」
「ああ。確かに落ち着きの無さとやんちゃさで言ったら優陽より侑くんのほうが近い」
二人で微笑み合う。
さっきまでの重たい空気はいつの間にか軽くなっていた。
「――少し整理する時間がほしい」
「え……?」
「優陽が言った通りだ。菜緒は亡くなっていて、優陽は今を生きている。優陽に話す心の準備をしたい」
「……」
「――優陽が本当に自分の父親の話を聞くタイミングだと思えた時、誰をその場に同席させてもいいから僕に連絡して」
「それって……」
「たぶん優陽自身でそのタイミングは判断出来るはずだ。それが例え明日だとしても、必ず真実を話すよ」
今日はこれ以上の答えは聞けなかった。
はっきりしたのは宮永さんは僕の父親の正体を唯一知っている存在だということ……。
「優陽から僕に会いたいって言ってくるなんて初めてだよね?」
「宮永さんは忙しいのにごめんなさい。それにお店も選ばせちゃって」
「いや、嬉しいんだって。大人に頼るところは頼りなさい」
金曜日の夜、僕は宮永さんとセブファクの事務所近くの戸建ての和食料理屋さんに連れてきてもらっていた。
看板も出ていないし、一見すると普通の民家。
掘りごたつの完全個室へと案内されて、宮永さんと二人きりの空間になった。
僕から宮永さんを誘ったわけだけど、何を食べたいか聞いてくれて。
いつもは完全に宮永さんに任せきりにしているけれど、今回は和食がいいと伝えることにした。
長いことアメリカに行っていたから、宮永さんは日本食が恋しいかなとも思ったし、僕は和食が1番好きだから……。
こうして少しずつ相手のことも考えながら僕の意思表示や選択もしていこう。
「ちょうどアメリカ土産も渡したかったし」
そう言った宮永さんの隣には紙袋ぎっしりにお土産が入っていた。
「毎回こんなに申し訳ないよ」
「お土産選んでると、あれもこれも優陽に食べさせたくなっちゃうんだよな。優陽のことを考えながらチョイスしてる時間が楽しいから遠慮なくもらってくれると助かる」
「ありがとう」
宮永さんの微笑には包容力がある。
たっちゃんが言っていたように宮永さんは僕を昔から特別に可愛がってくれていた。
宮永さんは優しいから、生まれた途端に身内が一人も居なくなった僕に気遣ってくれているのかと思っていたけど……。
『優陽くんの父親って宮永さんじゃないかしら……』
美織さんたちでさえ勘ぐっている僕の父親なのかの答えが出るのかもしれない。
でも、いざ質問するとなると躊躇してしまう……。
そわそわしたまま、一通り美味しいご飯を食べ終わった頃、先に宮永さんから質問があった。
「優陽は一条琉唯くんと何か関係があるの?」
「え!?」
まさか宮永さんから琉唯の話題を出されると思わなくて、緊張していた僕は大げさなほどに反応してしまった。
「一条くんと映画のPRで一緒だった日、一条くんは誰かと強張った表情で電話していて、”優陽”って名前がよく聞こえてきていた。それから血相を変えた慌てた様子で楽屋から飛び出していったんだけど」
それってまさか、僕がノアさんに軟禁されていたのを助けてくれた日のこと……?
やっぱり琉唯は僕を助けるために仕事を抜けてくれていたんだろう。
「その少し前には侑くんから一条くんのスマホに電話がかかってきているのを偶然画面で見てもいる」
たっちゃんが宮永さんから琉唯のことを聞かれたのはだからだったのか……。
「”ゆうひ”って珍しい名前でもないと思うけど。侑くんと二人揃えば、偶然でもないのかと思って」
宮永さんに何て答えるのが正解なんだろう?
でも、宮永さんには何となく小手先だけでごまかしたくなくて……。
「琉唯は僕が初めて好きになった人……」
僕の言葉に意表を突かれたのか、宮永さんは表情が固まった。
「でも、振られちゃった……」
笑うつもりだったのに、目元が不自然に熱くなってくる。
「僕も自分が男を好きになるとは思わなかったんだけどね……」
「関係ないよ。それは」
柔らかい宮永さんの笑みが僕をまるごと肯定して受け止めてくれているようで、気持ちが凪いだ。
「僕もずっと好きな人が居る……」
「……」
「たぶん僕は生涯その人しか愛せないのかもしれない」
哀愁の漂う声色で言葉を放ち、宮永さんはテーブルの木目へと視線を落とした。
「……宮永さんの、その相手は咲良菜緒?」
「え?」
僕はバッグの中から1冊のノートを取り出して、中をパラパラとめくり目的のページを開いた。
「これ華澄高の映像研究部の記録ノートの1冊なんですけど、ここを宮永さんに見てもらいたくて」
宮永さんは僕から開かれたノートを受け取る。
琉唯が気づいた映像研究部の記録ノートの片隅に認められていた一文。
――いずみ先輩、大好き。直子
すぐに問題の文字を見つけたみたいで、宮永さんは眉根を寄せた。
「驚いた……こんなものが残っていたとは……」
「これを書いたのは咲良菜緒……僕のお母さんじゃないのかなと思っていて」
「確かに菜緒の筆跡に間違いないね」
「このいずみ先輩っていうのは宮永さんですよね?」
「……」
「僕のお父さんは宮永さんなんですか?」
一気に喋り終わって、僕は息を吐き出していた。
自分でも知らないうちに緊張の糸が張り詰めていたらしい。
宮永さんはノートの文言に縫い留められたように視線を動かさなかった。
個室には重々しい無言が続く。
それを打ち破ったのは宮永さんだった。
「――僕だけが優陽の父親を知っている」
その台詞に痛いくらいに胸の音が鳴った。
「もちろん頼さんも真実は知らない。この秘密は墓場まで持っていくつもりだった」
「……それはどうして……?」
「ごめん、優陽。例え優陽だとしても言えない。それが菜緒との約束だから」
やっぱり宮永さんが僕の父親で咲良菜緒に何らかの理由で口止めをされているということなのだろう。
宮永さんの表情は苦渋を語るもので、これ以上聞いてはいけないんだと頭では理解できる。
でも、僕は……。
「教えてください。咲良菜緒はもう亡くなってしまったけれど、僕は今を生きているから……」
僕の真っ直ぐな視線を宮永さんは受け止めてくれている。
少し考え込むように黙ってから宮永さんは重い口を開いた。
「――菜緒は清純派なイメージで売られていたけど、実は私生活は奔放というか飾り気がなかった」
「……」
「プロフィールでは好きな食べ物をチーズケーキとグラタンにしてたけど、実際はエイヒレとたこわさだし。お酒を呑むのもカクテル類じゃ呑んだ気がしないって、イモ焼酎が一番好きだったし。現場でも気を抜くと木登り始めようとするし」
「……木登り……咲良菜緒のイメージにないね」
「うん。そういうとこも菜緒は猫みたいだった。ちょうどいい木を見つけると登りたくなるらしい。女優なんだから怪我をされると困るから止めろって頼さんも僕も何度も注意してた。いつまでも菜緒は小学生の悪ガキって感じ」
宮永さんは僕を慈悲深い目で見つめながらも、有し日の咲良奈緒を脳裏に思い浮かべているのだろう。
「何か意外。たっちゃんみたい」
「ああ。確かに落ち着きの無さとやんちゃさで言ったら優陽より侑くんのほうが近い」
二人で微笑み合う。
さっきまでの重たい空気はいつの間にか軽くなっていた。
「――少し整理する時間がほしい」
「え……?」
「優陽が言った通りだ。菜緒は亡くなっていて、優陽は今を生きている。優陽に話す心の準備をしたい」
「……」
「――優陽が本当に自分の父親の話を聞くタイミングだと思えた時、誰をその場に同席させてもいいから僕に連絡して」
「それって……」
「たぶん優陽自身でそのタイミングは判断出来るはずだ。それが例え明日だとしても、必ず真実を話すよ」
今日はこれ以上の答えは聞けなかった。
はっきりしたのは宮永さんは僕の父親の正体を唯一知っている存在だということ……。