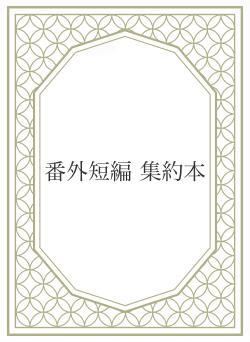***
琉唯に振られて塞ぎ込んだ気持ちのまま、酷暑が続いた夏休みは蝉の鳴き声が連れ去って、今日から華澄高では2学期がスタートする。
「――結局、優陽と夏休みを満喫出来なかったな」
今日は始業式で陸上部の朝練のないたっちゃんと一緒に自転車で登校して、駐輪場から昇降口に向かっている。
9月になったからといって、暑さが和らぐなんてことは一切なく、今日も太陽は地上をギラギラと熱している。
夏休み明けで久しぶりに会った友だちとはしゃいでいる生徒と長い休み明けの憂鬱さを隠していない生徒と半々くらいに見受けられた。
「たっちゃん、夏休みの後半は陸上部の合宿に行ってたもんね」
「そう。高地トレーニング死ぬほどきつかった。優陽は?」
「僕は何の予定もなく部室と家の往復で終わっちゃったよ」
「”あいつ”とは?」
ビクッと胸が震える。
たっちゃんが指しているのは琉唯のことだろう。
あの時はそれどころじゃなくて流していたけど、僕がノアさんに軟禁された日、琉唯はたっちゃんに連絡を取って、僕を迎えに来る手配をとっていた。
いつの間に琉唯とたっちゃんの二人は連絡先を交換していたんだろうって疑問は残っている。
「僕は振られたんだよね」
「そっか。優陽は振られたか……って、はぁ?!」
たっちゃんが大きな声を出したから、周囲の生徒たちも何事かと振り返って注目を浴びた。
「たっちゃん、声大きいって……」
「優陽。ちょっとこっち来い!」
みんなに見られているのがわかったのか、たっちゃんは昇降口へと続く階段からは少し逸れて、庭のようになっている木陰へと僕を誘い込む。
確かにここなら人通りは少ないけれど、たっちゃんは小声で話し始めた。
「何で優陽があいつに振られるんだよ。っていうか、優陽あいつのこと好きなのか?」
「……うん。告白して普通に振られたけど」
「――ありえねぇ……」
たっちゃんは頭を抱え出した。
ありえないというのは何を指しているのだろう。
「僕もまさか自分の初恋の相手が男で芸能人だなんて思ってもみなかったけど」
「いや、それはいいんだよ。誰が誰を好きになろうと好きになっちまったら、仕方ないだろ」
「じゃあ何がありえないの?」
「それは……俺から言うことじゃないか……」
たっちゃんは後頭部をかきながら、僕から目線を外した。
「僕、琉唯には咲良菜緒の隠し子だって打ち明けたんだ……」
「え? 言ったのか?」
「うん。自分でもわかってはいたけど、琉唯にはっきり僕は咲良菜緒の代わりだったって言われた」
「……」
「咲良菜緒じゃなくて、やっぱり僕が居なければ……」
「はい、それNG」
たっちゃんは僕の頬肉をそれぞれ両手でむにっと摘む。
「優陽は自分の出生のことで周りに引け目を感じてるみたいだけど、そんなの優陽がどうにか出来た問題じゃないだろ」
「……」
「優陽はこんなに周りに愛されてんのにさ。それに自分の命を賭してまで産んでくれたって、これ以上ない愛情を優陽は咲良菜緒からもらってるくせに」
「……」
「――俺は優陽が好きだよ」
僕の頬を柔らかく摘みながら、たっちゃんの眼差しが優しくなって……。
「――好きって言っても、なんていうか、優陽を守りたいとは思っても、優陽にキスしたいとかそういうのは思ったことないし、優陽が一条を好きな気持ちとは違うんだろうけど、優陽の一番近くに居るのは俺であってほしかった」
「……」
「父さんも母さんも優陽のこと好きだし、宮永さんなんか優陽だけ実の息子みたいにネコ可愛がりだし、俺、昔は優陽に嫉妬してた」
「たっちゃんが僕に嫉妬……?」
「何で俺の周りの大人はみんな優陽ばっかり可愛がって、俺には厳しいんだろうって。ま、実際に優陽はかわいいから仕方ないんだけど」
驚いた……。
僕は何の壁も遠慮もなく頼政さんや美織さんに甘えられるたっちゃんがうらやましかったのに。
たっちゃんは僕の一番近くに居て、どんな時も僕の味方で居てくれて、僕のことをよく知っている理解者で。
世界でたった一人の、たっちゃんって存在がずっとずっと心強かった。
「一条と優陽の問題に俺が口を挟むつもりはないけど、本当に一条は優陽を咲良菜緒の代わりにしてたと思うのか?」
「……」
「一条になら咲良菜緒の子どもだって打ち明けてもいいと思えるほど、警戒心の高い優陽が一条は信用できたんだろ?」
たっちゃんは僕の両頬をそれぞれ手で包み込んで、言い聞かせるような優しい声色と眼差しで問いかけてくる。
涙腺が緩み始めて奥歯を噛み締めるけど、手遅れで……。
いつだって琉唯は僕を見てくれてたし、僕に気遣ってくれていた。
でも僕は自信がなくて、勝手に捻くれて、どうせ琉唯は咲良菜緒が好きなんだからってお母さんに嫉妬して、理由を作って自分を守ろうとして……。
「……でも、僕は琉唯に振られたから……」
泣き崩れそうになる僕をたっちゃんは抱き締めてくれていた。
予鈴に身体が反応する僕を、
「――無理すんな。今、教室なんて行けねぇだろ」
と、そのまま更に密着するように腕の力が強くなった。
「だめ。たっちゃんに遅刻1回が記録されちゃう」
僕はドンッとたっちゃんの胸を押して、ポケットからハンカチを取り出し目元を濡らす涙を急いで拭った。
たっちゃんはクッと笑みを刻むと、「優陽らしいわ」と僕の手首を掴んで昇降口まで歩き始めた。
「――そういえばさ、結構前……8月の上旬くらいなんだけど、俺がセブファクの事務所に寄った時に宮永さんに会って、
『侑くんって一条琉唯くんと友だちなの?』
って聞かれたんだよな」
「何で?」
「……さあ」
たっちゃんは不思議そうな表情をしている。
宮永さんは琉唯と共演した映画が公開されたすぐ後に海外ロケでアメリカに行ってしまった。
最近、やっと帰国していて、今週の金曜の夜に僕は宮長さんと会う約束をしている。
その時に僕は宮永さんに確かめようとしていることがあった。
琉唯に振られて塞ぎ込んだ気持ちのまま、酷暑が続いた夏休みは蝉の鳴き声が連れ去って、今日から華澄高では2学期がスタートする。
「――結局、優陽と夏休みを満喫出来なかったな」
今日は始業式で陸上部の朝練のないたっちゃんと一緒に自転車で登校して、駐輪場から昇降口に向かっている。
9月になったからといって、暑さが和らぐなんてことは一切なく、今日も太陽は地上をギラギラと熱している。
夏休み明けで久しぶりに会った友だちとはしゃいでいる生徒と長い休み明けの憂鬱さを隠していない生徒と半々くらいに見受けられた。
「たっちゃん、夏休みの後半は陸上部の合宿に行ってたもんね」
「そう。高地トレーニング死ぬほどきつかった。優陽は?」
「僕は何の予定もなく部室と家の往復で終わっちゃったよ」
「”あいつ”とは?」
ビクッと胸が震える。
たっちゃんが指しているのは琉唯のことだろう。
あの時はそれどころじゃなくて流していたけど、僕がノアさんに軟禁された日、琉唯はたっちゃんに連絡を取って、僕を迎えに来る手配をとっていた。
いつの間に琉唯とたっちゃんの二人は連絡先を交換していたんだろうって疑問は残っている。
「僕は振られたんだよね」
「そっか。優陽は振られたか……って、はぁ?!」
たっちゃんが大きな声を出したから、周囲の生徒たちも何事かと振り返って注目を浴びた。
「たっちゃん、声大きいって……」
「優陽。ちょっとこっち来い!」
みんなに見られているのがわかったのか、たっちゃんは昇降口へと続く階段からは少し逸れて、庭のようになっている木陰へと僕を誘い込む。
確かにここなら人通りは少ないけれど、たっちゃんは小声で話し始めた。
「何で優陽があいつに振られるんだよ。っていうか、優陽あいつのこと好きなのか?」
「……うん。告白して普通に振られたけど」
「――ありえねぇ……」
たっちゃんは頭を抱え出した。
ありえないというのは何を指しているのだろう。
「僕もまさか自分の初恋の相手が男で芸能人だなんて思ってもみなかったけど」
「いや、それはいいんだよ。誰が誰を好きになろうと好きになっちまったら、仕方ないだろ」
「じゃあ何がありえないの?」
「それは……俺から言うことじゃないか……」
たっちゃんは後頭部をかきながら、僕から目線を外した。
「僕、琉唯には咲良菜緒の隠し子だって打ち明けたんだ……」
「え? 言ったのか?」
「うん。自分でもわかってはいたけど、琉唯にはっきり僕は咲良菜緒の代わりだったって言われた」
「……」
「咲良菜緒じゃなくて、やっぱり僕が居なければ……」
「はい、それNG」
たっちゃんは僕の頬肉をそれぞれ両手でむにっと摘む。
「優陽は自分の出生のことで周りに引け目を感じてるみたいだけど、そんなの優陽がどうにか出来た問題じゃないだろ」
「……」
「優陽はこんなに周りに愛されてんのにさ。それに自分の命を賭してまで産んでくれたって、これ以上ない愛情を優陽は咲良菜緒からもらってるくせに」
「……」
「――俺は優陽が好きだよ」
僕の頬を柔らかく摘みながら、たっちゃんの眼差しが優しくなって……。
「――好きって言っても、なんていうか、優陽を守りたいとは思っても、優陽にキスしたいとかそういうのは思ったことないし、優陽が一条を好きな気持ちとは違うんだろうけど、優陽の一番近くに居るのは俺であってほしかった」
「……」
「父さんも母さんも優陽のこと好きだし、宮永さんなんか優陽だけ実の息子みたいにネコ可愛がりだし、俺、昔は優陽に嫉妬してた」
「たっちゃんが僕に嫉妬……?」
「何で俺の周りの大人はみんな優陽ばっかり可愛がって、俺には厳しいんだろうって。ま、実際に優陽はかわいいから仕方ないんだけど」
驚いた……。
僕は何の壁も遠慮もなく頼政さんや美織さんに甘えられるたっちゃんがうらやましかったのに。
たっちゃんは僕の一番近くに居て、どんな時も僕の味方で居てくれて、僕のことをよく知っている理解者で。
世界でたった一人の、たっちゃんって存在がずっとずっと心強かった。
「一条と優陽の問題に俺が口を挟むつもりはないけど、本当に一条は優陽を咲良菜緒の代わりにしてたと思うのか?」
「……」
「一条になら咲良菜緒の子どもだって打ち明けてもいいと思えるほど、警戒心の高い優陽が一条は信用できたんだろ?」
たっちゃんは僕の両頬をそれぞれ手で包み込んで、言い聞かせるような優しい声色と眼差しで問いかけてくる。
涙腺が緩み始めて奥歯を噛み締めるけど、手遅れで……。
いつだって琉唯は僕を見てくれてたし、僕に気遣ってくれていた。
でも僕は自信がなくて、勝手に捻くれて、どうせ琉唯は咲良菜緒が好きなんだからってお母さんに嫉妬して、理由を作って自分を守ろうとして……。
「……でも、僕は琉唯に振られたから……」
泣き崩れそうになる僕をたっちゃんは抱き締めてくれていた。
予鈴に身体が反応する僕を、
「――無理すんな。今、教室なんて行けねぇだろ」
と、そのまま更に密着するように腕の力が強くなった。
「だめ。たっちゃんに遅刻1回が記録されちゃう」
僕はドンッとたっちゃんの胸を押して、ポケットからハンカチを取り出し目元を濡らす涙を急いで拭った。
たっちゃんはクッと笑みを刻むと、「優陽らしいわ」と僕の手首を掴んで昇降口まで歩き始めた。
「――そういえばさ、結構前……8月の上旬くらいなんだけど、俺がセブファクの事務所に寄った時に宮永さんに会って、
『侑くんって一条琉唯くんと友だちなの?』
って聞かれたんだよな」
「何で?」
「……さあ」
たっちゃんは不思議そうな表情をしている。
宮永さんは琉唯と共演した映画が公開されたすぐ後に海外ロケでアメリカに行ってしまった。
最近、やっと帰国していて、今週の金曜の夜に僕は宮長さんと会う約束をしている。
その時に僕は宮永さんに確かめようとしていることがあった。