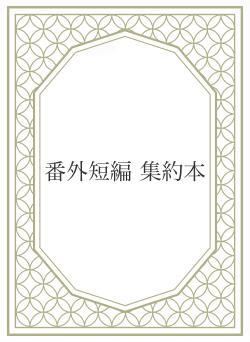高校は華澄学園高等学校に入学した。
芸術総合コースがあって、芸能界に所属している人間への支援が手厚く、俳優としての道筋しか描けていなかったから、ほぼ一択で進学を決めた。
芸術総合コースは一般の生徒とは校舎も違って教室前には常に警備員が立ち、セキュリティもしっかりしている。
そこで出会ったのが一学年上の滝川ノアだった。
ノアは俺が所属しているシムプロの社長の娘。
わかりやすいくらいにノアが女王様気質なのは、滝川社長の妻であり、ノアの母親であるアンナさんから引き継がれているのだろう。
ノアの祖父はシムプロの創業者であり現在は会長。
アンナさんは会長の実の娘。
明瞭なほど、生活の全てがブランド志向。
滝川社長とも、かなり強引な手段を使って結婚したとシムプロのスタッフたちが噂話していたのが聞こえてきたことがある。
ノアが芸術総合コースの生徒の中で俺に目をつけたのは必然といえば必然だった。
芸能人としてのランクは俺が現時点では一番上にあたるのだろう。
所属事務所もシムプロ。
ノアにとって、都合よく自尊心を満たせる相手が俺だった。
ノアは俺に恋人になれとは言わない。
けれど、仕事以外では自分が俺に最優先されないと気が済まない。
ノアはシムプロ創業者一族で、機嫌を損ねれば俺の仕事に支障が出る可能性がある。
そうなればどうなるか、ノアは俺の事情をよく知っていた。
「琉唯って初めてだったんだ。意外だけどノアが琉唯の初体験の相手なんて嬉しい」
俺はノアで初めて女の身体を知った。
だからといって、心が動くかと言えば全くそれもなく。
セックスは嫌いだった。
最中は脳が快楽を感じてはいるのだろう。
それよりも精を吐き出した後の気怠さや虚しさに襲われる感覚が不快でしかなくて。
したくなくてもノアから命じられればするしかない。
義務としての行為でしかなかった。
――咲良菜緒は私生活で恋愛感情を知っていたんだろう。
俺がロールモデルにしている女優。
咲良菜緒は演技が演技じゃないと思えるほど自然で圧巻。
出演作によって別人に感じられるのに、どこか演じる役全てに“咲良菜緒“にしか出せないらしさもある。
咲良菜緒の演技から学ぶために、何作も何度も息遣いから瞬きまで細部まで研究していた俺にとって、咲良菜緒がプライベートで恋をしていたという憶測は確信に近いほど自信があった。
咲良菜緒に恋愛がらみの報道は一切でていなかったらしいけれど、あの咲良菜緒が恋に落ちるほどの相手はどんな人間だったんだろう。
CMの記者発表、各映画賞の授賞式の参加、映画の舞台挨拶くらいしか公の場には出てこなかったらしく、役としての咲良菜緒は出演作を通して確かに見ているのに、”咲良菜緒”本人がどんな人物だったのか知っている者は少ないと聞く。
俺が産まれた頃に亡くなっているせいか、現実味がないほど透明感のある美貌だからか、演技力がありすぎるからか、咲良菜緒はどこか実在していたことに現実味を帯びない幻想的な憧れの存在。
――だから、夜桜のもとで初めて優陽と出会った時、幻なのかと疑った。
全てが新しい経験だった。
たった数秒、優陽が視界にはいっただけで脳の髄まで記憶に刻まれ、大きく心が動かされて。
雷に打たれたように……そんな表現が大げさでないほど、鮮烈に胸が熱くなった。
『――嘘だろ。咲良菜緒が居る……』
俺はそう呟きながら、花あかりのもとで涙を流す美しい子にどうしようもないほど心を奪われてしまった。
確かに顔は咲良菜緒によく似ていたけれど、咲良菜緒とは違う。
性別も年齢も名前もわからない。
ただ華澄高のジャージを着てたってことくらいしか情報がない。
それが優陽だったと俺が知るのは、ほんの……俺には長く思えた先の話。
俺を見て慌てたように優陽は走り去ってしまったけれど、また会いたくてどうしようもなくなって。
俺はなりふり構わず優陽を探した。
同じ高校だから、すぐに再会出来るかと思えば、全く優陽は見つからなかった。
幻と言えるほど、涙を流す優陽は美しく、儚く、淡く、今にも泡沫のように消えてしまいそうで。
――ただ強く抱きしめたい。
俺はまともじゃなくなったのかと自分でも驚くくらい、優陽に想い乱されていた。
だから、アネックス館の廊下で偶然にも優陽とぶつかった時、探し続けた子が目の前に現れて爆発したように感情が溢れ出て、
『――やっと、見つけた。咲良菜緒』
気づいた時には優陽を腕の中に閉じ込め、抱き締めていた。
探し続けた分だけ絶対に優陽を手放したくないし、逃がしたくない。
多少、強引でも優陽が入部している映像研究部の部室までついていった。
実際に間近で見て、会話を交わして、体温のある優陽に俺はまた魅了されていた。
同じ人間に一目ぼれを二度もするなんてあるのだろうか?
映像研究部の部室で優陽と時間を共有できることになって、この上なく喜びを感じていた。
芸術総合コースがあって、芸能界に所属している人間への支援が手厚く、俳優としての道筋しか描けていなかったから、ほぼ一択で進学を決めた。
芸術総合コースは一般の生徒とは校舎も違って教室前には常に警備員が立ち、セキュリティもしっかりしている。
そこで出会ったのが一学年上の滝川ノアだった。
ノアは俺が所属しているシムプロの社長の娘。
わかりやすいくらいにノアが女王様気質なのは、滝川社長の妻であり、ノアの母親であるアンナさんから引き継がれているのだろう。
ノアの祖父はシムプロの創業者であり現在は会長。
アンナさんは会長の実の娘。
明瞭なほど、生活の全てがブランド志向。
滝川社長とも、かなり強引な手段を使って結婚したとシムプロのスタッフたちが噂話していたのが聞こえてきたことがある。
ノアが芸術総合コースの生徒の中で俺に目をつけたのは必然といえば必然だった。
芸能人としてのランクは俺が現時点では一番上にあたるのだろう。
所属事務所もシムプロ。
ノアにとって、都合よく自尊心を満たせる相手が俺だった。
ノアは俺に恋人になれとは言わない。
けれど、仕事以外では自分が俺に最優先されないと気が済まない。
ノアはシムプロ創業者一族で、機嫌を損ねれば俺の仕事に支障が出る可能性がある。
そうなればどうなるか、ノアは俺の事情をよく知っていた。
「琉唯って初めてだったんだ。意外だけどノアが琉唯の初体験の相手なんて嬉しい」
俺はノアで初めて女の身体を知った。
だからといって、心が動くかと言えば全くそれもなく。
セックスは嫌いだった。
最中は脳が快楽を感じてはいるのだろう。
それよりも精を吐き出した後の気怠さや虚しさに襲われる感覚が不快でしかなくて。
したくなくてもノアから命じられればするしかない。
義務としての行為でしかなかった。
――咲良菜緒は私生活で恋愛感情を知っていたんだろう。
俺がロールモデルにしている女優。
咲良菜緒は演技が演技じゃないと思えるほど自然で圧巻。
出演作によって別人に感じられるのに、どこか演じる役全てに“咲良菜緒“にしか出せないらしさもある。
咲良菜緒の演技から学ぶために、何作も何度も息遣いから瞬きまで細部まで研究していた俺にとって、咲良菜緒がプライベートで恋をしていたという憶測は確信に近いほど自信があった。
咲良菜緒に恋愛がらみの報道は一切でていなかったらしいけれど、あの咲良菜緒が恋に落ちるほどの相手はどんな人間だったんだろう。
CMの記者発表、各映画賞の授賞式の参加、映画の舞台挨拶くらいしか公の場には出てこなかったらしく、役としての咲良菜緒は出演作を通して確かに見ているのに、”咲良菜緒”本人がどんな人物だったのか知っている者は少ないと聞く。
俺が産まれた頃に亡くなっているせいか、現実味がないほど透明感のある美貌だからか、演技力がありすぎるからか、咲良菜緒はどこか実在していたことに現実味を帯びない幻想的な憧れの存在。
――だから、夜桜のもとで初めて優陽と出会った時、幻なのかと疑った。
全てが新しい経験だった。
たった数秒、優陽が視界にはいっただけで脳の髄まで記憶に刻まれ、大きく心が動かされて。
雷に打たれたように……そんな表現が大げさでないほど、鮮烈に胸が熱くなった。
『――嘘だろ。咲良菜緒が居る……』
俺はそう呟きながら、花あかりのもとで涙を流す美しい子にどうしようもないほど心を奪われてしまった。
確かに顔は咲良菜緒によく似ていたけれど、咲良菜緒とは違う。
性別も年齢も名前もわからない。
ただ華澄高のジャージを着てたってことくらいしか情報がない。
それが優陽だったと俺が知るのは、ほんの……俺には長く思えた先の話。
俺を見て慌てたように優陽は走り去ってしまったけれど、また会いたくてどうしようもなくなって。
俺はなりふり構わず優陽を探した。
同じ高校だから、すぐに再会出来るかと思えば、全く優陽は見つからなかった。
幻と言えるほど、涙を流す優陽は美しく、儚く、淡く、今にも泡沫のように消えてしまいそうで。
――ただ強く抱きしめたい。
俺はまともじゃなくなったのかと自分でも驚くくらい、優陽に想い乱されていた。
だから、アネックス館の廊下で偶然にも優陽とぶつかった時、探し続けた子が目の前に現れて爆発したように感情が溢れ出て、
『――やっと、見つけた。咲良菜緒』
気づいた時には優陽を腕の中に閉じ込め、抱き締めていた。
探し続けた分だけ絶対に優陽を手放したくないし、逃がしたくない。
多少、強引でも優陽が入部している映像研究部の部室までついていった。
実際に間近で見て、会話を交わして、体温のある優陽に俺はまた魅了されていた。
同じ人間に一目ぼれを二度もするなんてあるのだろうか?
映像研究部の部室で優陽と時間を共有できることになって、この上なく喜びを感じていた。