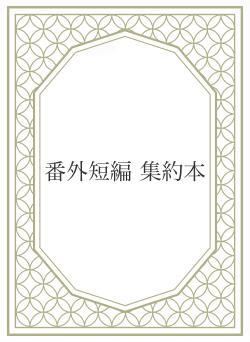***
――幻想的な夜桜の下で泣いていた君が今まで視界が映してきた何よりも美しくて、胸をかきむしりたくなるくらい狂おしくて……
あの瞬間から優陽だけが頭から離れてくれない。
俺を産んだ母親は出産と同時に、父さんのことが嫌いで目障りで仕方なくなったと言っていた。
『こんなジメジメした団地暮らしなんて最悪』
『生物のオスは強くないと生きていけないんだって。あなたは人間で良かったわね』
『あの家は新車買ってるのに、うちは10年落ちの軽自動車の中古しか買えないなんて』
『夫婦は相互扶助? 一方的にもたれかかってきて何が相互よ。役立たずが』
俺に記憶が残ってる時期から、いつも母親は父さんを罵倒していた。
父さんは大量に薬を飲んで、脂汗をかきながらも俺を保育園へ登園させてから勤務先の工場へ行く。
帰りは俺を保育園まで迎えに来て、一緒に帰り道にあるスーパーで買い物して、帰宅後は家事をこなす。
小学校は一人で登下校して放課後は学童になったけど。
そんなルーティンで俺は何となく自分の体調不良は父さんが力を尽くして守ろうとしてる生活のリズムを壊すようで言えなくなった。
『――琉唯。流行りのゲームを買ってやれなくて、外食すら余り連れて行けなくてごめんな』
父さんはいつも俺に謝っていた。
確かに周りの同級生たちが人気ゲームに夢中になってはいるけれど、自分もほしいとは思ったことがなくて。
穏やかで感情的にならず、どんな時でも俺を包み込むように受け止めてくれる父さんが居てくれるだけで良かった。
そんな父さんがどんどん痩せていくことが幼心にも怖かったけど、言葉に出来なかった。
古い団地住まいでも家はあるし、軽の中古車でも自家用車を持っていて、高級品で身の回りを固められなくても衣食住には困らない。
それだけの暮らしでは母親は満たされなかった。
母親もパート勤務に出てはいたものの、ストレスを酒やスロットで発散させて家には不在がち。
パート収入は全て自分の懐に入れていたらしい。
今の環境は父さんのせいで、自分はかわいそうな被害者だと父さんを責め続けていた。
父さんは何ひとつ言い返さず、困ったように笑うだけ。
結局、俺が小4になった頃、父さんの身体が限界を迎えて完全に働けなくなった一番最悪のタイミングで母親は出て行った。
――そして俺は芸能界に飛び込んだ。
未だに撮影現場でも私生活でも女の甲高いヒステリックな声が耳に飛び込むと背筋に悪寒が走る。
――女って、みんな、こうなんだろうか?
主張が強いばかりで、依存心が強くて、計算高く、リスクを被りそうになれば、家族でさえ割り切って切り捨てる。
女はみんな多かれ少なかれ俺たちを切り捨てた母親のようなのかと、恋心が生まれたことはない。
俺が恋愛感情を知らないまま、育ったのはそれも原因の一つかとも思う。
「一条くんってさ、恋したことないでしょ?」
仕事が増えてきてから、演技指導の男性講師に見透かされたように指摘されたことがあった。
「一条くんはさぞかしモテてきたと思うんだけど。たった一人を想って、他はどうでもよくなって、常に頭から離れなくて、想い乱れた経験なんてないんじゃない?」
「ないですね。これからも俺にあると思えないです」
「一条くんが恋を覚えたら更に役者として一皮むけると思うんだけどな」
「演技力でどうにかします」
「演技を越えた先の話だよ」
演技を越えた先の話とは何だろう。
様々な役を演じさせてもらえるようになったけど、まだ本格的なラブストーリーへの出演経験はない。
――たった一人を想う。
恋の仕方がわからないし、わからなくてもいい。
父と母を見てきたからか結婚への憧れもなかった。
むしろ色恋沙汰はスキャンダルの火種になって仕事が減ることを考えたらリスクでしかない。
父さんの医療費や手術代、介護施設の利用料……。
俺に仕事のオファーが来てコンスタントに仕事が入るまで、滝川社長の恩情で今の事務所にはだいぶ立て替えてもらってきた。
ここまで面倒みてくれる事務所はなかなかないから、きちんと仕事で恩返しをしていきたい。
先行きを考えると、まだ盤石に俺の収入と蓄えがあるとは全く言えない状態。
父さんの病状が回復したら、また一緒に暮らしたい。
苦労してきた分だけ、楽をさせてやりたかった。
今からだっていろいろな経験をさせてあげたい。
芸能界が甘くないのは百も承知。
売れれば後は安泰ってわけでもなく。
だから俺は俳優として、何一つ失敗するわけにはいかなかった。
期待通り程度では飽きられる。
期待を常に越えていく必要があった。
あいにく俺は天才型じゃなかった。
感覚で芝居が出来るほどの才能はない。
台本を記憶するのも必死。
監督の助言を体現するのにも一苦労。
だから努力で補うしかない。
――俺は、いつまで走り続けなければいけないのだろう……。
――父さんは本当に良くなるのだろうか。
今では誰かの介助がないとどこにも行けず、開頭手術も受けていて左半身に麻痺が残ってしまった。
ふと間ができると底のない不安に襲われる。
目の前のスケジュールを懸命にこなして、先のことを考えないようにしていた。
――幻想的な夜桜の下で泣いていた君が今まで視界が映してきた何よりも美しくて、胸をかきむしりたくなるくらい狂おしくて……
あの瞬間から優陽だけが頭から離れてくれない。
俺を産んだ母親は出産と同時に、父さんのことが嫌いで目障りで仕方なくなったと言っていた。
『こんなジメジメした団地暮らしなんて最悪』
『生物のオスは強くないと生きていけないんだって。あなたは人間で良かったわね』
『あの家は新車買ってるのに、うちは10年落ちの軽自動車の中古しか買えないなんて』
『夫婦は相互扶助? 一方的にもたれかかってきて何が相互よ。役立たずが』
俺に記憶が残ってる時期から、いつも母親は父さんを罵倒していた。
父さんは大量に薬を飲んで、脂汗をかきながらも俺を保育園へ登園させてから勤務先の工場へ行く。
帰りは俺を保育園まで迎えに来て、一緒に帰り道にあるスーパーで買い物して、帰宅後は家事をこなす。
小学校は一人で登下校して放課後は学童になったけど。
そんなルーティンで俺は何となく自分の体調不良は父さんが力を尽くして守ろうとしてる生活のリズムを壊すようで言えなくなった。
『――琉唯。流行りのゲームを買ってやれなくて、外食すら余り連れて行けなくてごめんな』
父さんはいつも俺に謝っていた。
確かに周りの同級生たちが人気ゲームに夢中になってはいるけれど、自分もほしいとは思ったことがなくて。
穏やかで感情的にならず、どんな時でも俺を包み込むように受け止めてくれる父さんが居てくれるだけで良かった。
そんな父さんがどんどん痩せていくことが幼心にも怖かったけど、言葉に出来なかった。
古い団地住まいでも家はあるし、軽の中古車でも自家用車を持っていて、高級品で身の回りを固められなくても衣食住には困らない。
それだけの暮らしでは母親は満たされなかった。
母親もパート勤務に出てはいたものの、ストレスを酒やスロットで発散させて家には不在がち。
パート収入は全て自分の懐に入れていたらしい。
今の環境は父さんのせいで、自分はかわいそうな被害者だと父さんを責め続けていた。
父さんは何ひとつ言い返さず、困ったように笑うだけ。
結局、俺が小4になった頃、父さんの身体が限界を迎えて完全に働けなくなった一番最悪のタイミングで母親は出て行った。
――そして俺は芸能界に飛び込んだ。
未だに撮影現場でも私生活でも女の甲高いヒステリックな声が耳に飛び込むと背筋に悪寒が走る。
――女って、みんな、こうなんだろうか?
主張が強いばかりで、依存心が強くて、計算高く、リスクを被りそうになれば、家族でさえ割り切って切り捨てる。
女はみんな多かれ少なかれ俺たちを切り捨てた母親のようなのかと、恋心が生まれたことはない。
俺が恋愛感情を知らないまま、育ったのはそれも原因の一つかとも思う。
「一条くんってさ、恋したことないでしょ?」
仕事が増えてきてから、演技指導の男性講師に見透かされたように指摘されたことがあった。
「一条くんはさぞかしモテてきたと思うんだけど。たった一人を想って、他はどうでもよくなって、常に頭から離れなくて、想い乱れた経験なんてないんじゃない?」
「ないですね。これからも俺にあると思えないです」
「一条くんが恋を覚えたら更に役者として一皮むけると思うんだけどな」
「演技力でどうにかします」
「演技を越えた先の話だよ」
演技を越えた先の話とは何だろう。
様々な役を演じさせてもらえるようになったけど、まだ本格的なラブストーリーへの出演経験はない。
――たった一人を想う。
恋の仕方がわからないし、わからなくてもいい。
父と母を見てきたからか結婚への憧れもなかった。
むしろ色恋沙汰はスキャンダルの火種になって仕事が減ることを考えたらリスクでしかない。
父さんの医療費や手術代、介護施設の利用料……。
俺に仕事のオファーが来てコンスタントに仕事が入るまで、滝川社長の恩情で今の事務所にはだいぶ立て替えてもらってきた。
ここまで面倒みてくれる事務所はなかなかないから、きちんと仕事で恩返しをしていきたい。
先行きを考えると、まだ盤石に俺の収入と蓄えがあるとは全く言えない状態。
父さんの病状が回復したら、また一緒に暮らしたい。
苦労してきた分だけ、楽をさせてやりたかった。
今からだっていろいろな経験をさせてあげたい。
芸能界が甘くないのは百も承知。
売れれば後は安泰ってわけでもなく。
だから俺は俳優として、何一つ失敗するわけにはいかなかった。
期待通り程度では飽きられる。
期待を常に越えていく必要があった。
あいにく俺は天才型じゃなかった。
感覚で芝居が出来るほどの才能はない。
台本を記憶するのも必死。
監督の助言を体現するのにも一苦労。
だから努力で補うしかない。
――俺は、いつまで走り続けなければいけないのだろう……。
――父さんは本当に良くなるのだろうか。
今では誰かの介助がないとどこにも行けず、開頭手術も受けていて左半身に麻痺が残ってしまった。
ふと間ができると底のない不安に襲われる。
目の前のスケジュールを懸命にこなして、先のことを考えないようにしていた。