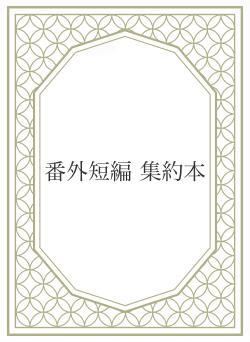手術室近くの待合室の椅子へと琉唯と並んで腰を落とす。
消灯が訪れているからか館内は薄暗く、耳に痛いほど静かで不安感を煽ってくる。
須山さんという女性は特に琉唯の親類というわけでもないようで、琉唯と幾つか情報のやり取りをして「夜勤の職員に引継ぎしてあるから」と姿を消してしまった。
「――優陽は何も聞かないでいてくれるんだ」
二人だけの空間になって、琉唯が僕へと口を開いた。
さっきまで蝶野さんか須山さんが居たから。
「琉唯に質問する空気じゃなかったかと思って……」
電話の段階からただならぬ様子は察していた。
わざわざ休日に僕に会いたいと言って迎えに来るほどの何かがあって、僕の手を握る手の力の加減が不安定になるほどで……。
なのに、僕の知りたい欲求を優先して、琉唯に僕の疑問を解消してもらおうなんて思えなかった。
「――何で優陽はそんなに優しいの?」
「別に優しいわけじゃないよ。琉唯は話せる時が来たら話すでしょ?」
「俺を信用してくれてるんだ。嬉しい」
「琉唯とは……その、付き合いも長くなってきてるし」
「――良かった。今この瞬間に優陽が隣にいて」
ずっと僕の手を握ったまま、琉唯はもう片手でキャップを取り去った。
僕の眼鏡越しに交差したいつもは鋭い琉唯の眼差しが儚く感じられて。
琉唯と視線の先が結び合ったまま、握り返す手に力を込めた。
「――今オペ室に居るのが俺の父親。病気が進行していて今はもう自力で歩くことさえ出来ない。だから、この病院と併設されている介護施設で面倒を見てもらっている。今、父さんには俺しか身内がいないから」
足元に視線を落として、言葉を紡ぎ始めた琉唯。
――お母さんは?
そう僕が感じた疑問に答えるように、
「母親は俺が小4の頃に俺たちを置いて出て行って、離婚も成立済み。今では別の場所で家庭を築いて楽しく暮らしているって聞いている。一応、俺も有名人になったのに会いたいとも思われないくらい良い思い出がないらしい」
と、琉唯は自嘲混じりに告げる。
僕は黙って、琉唯の話に耳を傾け続けていた。
「元々、父さんは身体が強いほうじゃなかったんだよな。それなりには普通に社会生活を送れていたんだけど、昔から父さんはよく母さんに罵声を浴びせられていた。”情けない”だの”役立たず”だの。父さんも何も言い返さないんだよな。俺が母さんに意見すると”ガキは黙ってろ”って言われるだけだった。俺が小4の頃には父さんが本格的に外で働くのが難しくなって、そのタイミングで母親が愛想をつかせて家を出た……」
琉唯の心情を思うと、気道が塞がれたように胸の辺りが息苦しくなる。
「俺の実家って、この病院から近い築何十年と経っている古い団地にあるんだけど、家にお金が余りないってことも、父さんの治療にも、これから生活していくのにも、たくさん金が必要だってことは小学生ながらに理解できてはいた。父親は病気で働けなくなって、母親にも捨てられて、どうすればいいのかわからなくなって……。今だったら公的な援助に頼るとか考えつくんだけど、その時の俺は自分がどうにかしないとって気持ちしかなかった」
「……」
「どうしたら小学生の俺でも金を稼げるか考えついた先がこの世界だった」
さっきまで儚く見えた琉唯の眼差しに力が戻る。
それは内心の決意を滲ませるような危うい力強さがあった。
それからも琉唯は続けて話してくれた。
電気代の節約のためとテレビを余りつけない家で育った琉唯には芸能界の知識があまり無かった。
原宿でスカウトされることが多いと聞き、一人で原宿に向かって、最初にスカウトされたのが今の事務所のシムプロだった。
「本当に今の事務所に声をかけられたのはラッキーだったと思う。もし、悪徳芸能事務所から先に声をかけられてたら、絶対に騙されてた」
――それくらい無知だった。
そう苦く笑った琉唯。
確かに芸能プロダクションもピンキリで、性風俗への足がかりにされたり、レッスン料と称して法外なお金を巻き上げる悪質な事務所も少なくはないと聞く。
シムプロは日本三大芸能事務所といわれるほどの大手だし、原宿に行ってすぐに縁があったのだから琉唯は運があったのだろう。
咲良菜緒もセブファクの社長である頼政さんに拾われなかったら、女優としての輝かしいキャリアは積めなかったはずだ。
「スカウトされるとこまでは順調だった。けど、前に優陽に話したよな? なかなか俺は俳優として芽が出なかったって」
消灯が訪れているからか館内は薄暗く、耳に痛いほど静かで不安感を煽ってくる。
須山さんという女性は特に琉唯の親類というわけでもないようで、琉唯と幾つか情報のやり取りをして「夜勤の職員に引継ぎしてあるから」と姿を消してしまった。
「――優陽は何も聞かないでいてくれるんだ」
二人だけの空間になって、琉唯が僕へと口を開いた。
さっきまで蝶野さんか須山さんが居たから。
「琉唯に質問する空気じゃなかったかと思って……」
電話の段階からただならぬ様子は察していた。
わざわざ休日に僕に会いたいと言って迎えに来るほどの何かがあって、僕の手を握る手の力の加減が不安定になるほどで……。
なのに、僕の知りたい欲求を優先して、琉唯に僕の疑問を解消してもらおうなんて思えなかった。
「――何で優陽はそんなに優しいの?」
「別に優しいわけじゃないよ。琉唯は話せる時が来たら話すでしょ?」
「俺を信用してくれてるんだ。嬉しい」
「琉唯とは……その、付き合いも長くなってきてるし」
「――良かった。今この瞬間に優陽が隣にいて」
ずっと僕の手を握ったまま、琉唯はもう片手でキャップを取り去った。
僕の眼鏡越しに交差したいつもは鋭い琉唯の眼差しが儚く感じられて。
琉唯と視線の先が結び合ったまま、握り返す手に力を込めた。
「――今オペ室に居るのが俺の父親。病気が進行していて今はもう自力で歩くことさえ出来ない。だから、この病院と併設されている介護施設で面倒を見てもらっている。今、父さんには俺しか身内がいないから」
足元に視線を落として、言葉を紡ぎ始めた琉唯。
――お母さんは?
そう僕が感じた疑問に答えるように、
「母親は俺が小4の頃に俺たちを置いて出て行って、離婚も成立済み。今では別の場所で家庭を築いて楽しく暮らしているって聞いている。一応、俺も有名人になったのに会いたいとも思われないくらい良い思い出がないらしい」
と、琉唯は自嘲混じりに告げる。
僕は黙って、琉唯の話に耳を傾け続けていた。
「元々、父さんは身体が強いほうじゃなかったんだよな。それなりには普通に社会生活を送れていたんだけど、昔から父さんはよく母さんに罵声を浴びせられていた。”情けない”だの”役立たず”だの。父さんも何も言い返さないんだよな。俺が母さんに意見すると”ガキは黙ってろ”って言われるだけだった。俺が小4の頃には父さんが本格的に外で働くのが難しくなって、そのタイミングで母親が愛想をつかせて家を出た……」
琉唯の心情を思うと、気道が塞がれたように胸の辺りが息苦しくなる。
「俺の実家って、この病院から近い築何十年と経っている古い団地にあるんだけど、家にお金が余りないってことも、父さんの治療にも、これから生活していくのにも、たくさん金が必要だってことは小学生ながらに理解できてはいた。父親は病気で働けなくなって、母親にも捨てられて、どうすればいいのかわからなくなって……。今だったら公的な援助に頼るとか考えつくんだけど、その時の俺は自分がどうにかしないとって気持ちしかなかった」
「……」
「どうしたら小学生の俺でも金を稼げるか考えついた先がこの世界だった」
さっきまで儚く見えた琉唯の眼差しに力が戻る。
それは内心の決意を滲ませるような危うい力強さがあった。
それからも琉唯は続けて話してくれた。
電気代の節約のためとテレビを余りつけない家で育った琉唯には芸能界の知識があまり無かった。
原宿でスカウトされることが多いと聞き、一人で原宿に向かって、最初にスカウトされたのが今の事務所のシムプロだった。
「本当に今の事務所に声をかけられたのはラッキーだったと思う。もし、悪徳芸能事務所から先に声をかけられてたら、絶対に騙されてた」
――それくらい無知だった。
そう苦く笑った琉唯。
確かに芸能プロダクションもピンキリで、性風俗への足がかりにされたり、レッスン料と称して法外なお金を巻き上げる悪質な事務所も少なくはないと聞く。
シムプロは日本三大芸能事務所といわれるほどの大手だし、原宿に行ってすぐに縁があったのだから琉唯は運があったのだろう。
咲良菜緒もセブファクの社長である頼政さんに拾われなかったら、女優としての輝かしいキャリアは積めなかったはずだ。
「スカウトされるとこまでは順調だった。けど、前に優陽に話したよな? なかなか俺は俳優として芽が出なかったって」