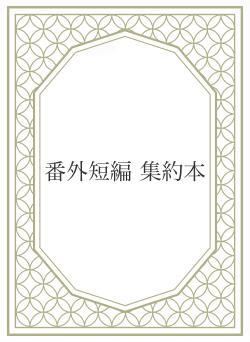***
今日は海の日……と言えども、友だちゼロで海水浴などのアクティビティと無縁の僕はクーラーの利いた自室で勉強をしていた。
窓から見える外は今日も晴れ上がっていて、ギラギラと燃えている太陽の光が陽炎を作っているのがガラス越しにもわかる。
絶対に今日もうだるような暑さだ。
麦茶をお代わりしようと、空になったグラスのコップを持って、階段を下りた時だった。
「もうー侑は何でこうも忘れ物が多いのかしら」
美織さんのひとり言がリビングから漏れ聞こえてきた。
「どうしたの?」
「あら、優陽。侑が部活の替えのTシャツを入れた巾着袋一式忘れていったのよ」
美織さんの手にあるのは、スポーツブランドのロゴが入ったブラックの巾着。
たっちゃんは祝日の今日も陸上部の活動で朝から学校に行っている。
「僕、学校まで届けてくるよ」
「え、いいの?」
「これだけ暑いのにたっちゃん替えの服がないと困るだろうし。それにずっと家に閉じこもっているのも良くないから、僕も気分を変えて午後は学校の部室で勉強してこようかな」
「優陽が迷惑じゃないならお願いしてもいい?」
「うん、もちろん」
「優陽、助かるわ。その前に昼食、作ってあるから食べていきなさい」
「ありがとう。美織さん」
美織さんが用意してくれた昼食を食べ終え、制服に着替えた僕は華澄高へと向かった。
さすがに一番気温が上がる時間帯で日陰を選んだとしても外を歩くのは危険だったから、バスで向かうことにする。
バスに揺られながら、こんな暑い中、外で働いてくれている人たちって、ありがたいな……なんて工事現場で汗水垂らして労働してくれている方々を見つめながら思う。
あの人たちも琉唯を知っているのかな。
自分が知らない人たちに自分を知られているって、どんな感覚なのだろう。
咲良菜緒や宮永さんにとっても、芸能界で活躍している人たちには普通の感覚なんだろうか。
生まれた時から当たり前のように芸能界に関わっている人が身近に居るけれど、僕にはわからない。
――琉唯がわからない……。
「え? 優陽、学校まで届けにきてくれたんだ」
華澄高校のグラウンドに到着すると、たっちゃんは陸上部の部員たちと屋根付きの休憩スペースに居た。
大型の扇風機が2台、ウォータージャグも3つ置かれている。
こまめに休憩に入っているようで、熱中症対策はされているみたいだ。
「サンキュ。マジで助かった。Tシャツ汗でびしょびしょでさ」
たっちゃんは僕から受け取った巾着を受け取るやいなや、その場で来ていたTシャツを脱ぎ始めた。
近くに居た女子部員から「きゃっ」と桃色の悲鳴がとんでくる。
しっかりたっちゃんの筋肉質な上半身に視線がロックオンされていた。
たっちゃんは新しいTシャツに腕を通しながら、
「優陽もう帰んの?」
と、僕に質問してきた。
「せっかく学校に来たから僕も部活してから帰るよ」
「そっか。また何か優陽にお礼させて」
「そんなのいいよ。三連休ずっと家に引きこもっちゃうところだったし」
「優陽はぜんぜん焼けずに色白のままだもんな」
たっちゃんが僕の頬を両手で包むように触れて顔を接近させてきた。
「おーい、七嶋。男といちゃついてるところなんか見せつけてくるんじゃねぇよ」
休憩している部員たちから囃し立てるような声が飛んでくる。
「そんなんじゃないって」
ぶっきらぼうに返したたっちゃんは休憩が終わり、灼熱のグラウンドへと戻っていく。
たっちゃんと別れた僕は映像研究部の部室で映画を観ていた。
暗幕を引いて暗がりの中で映画を観ている僕と違い、たっちゃんは太陽の下が良く似合う。
自然と視線を奪って、みんなの輪の中心にいて。
いつだって、たっちゃんは真っ直ぐで眩しくて僕を照らしてくれる太陽みたいな存在だ。
さっき、たっちゃんに頬を触られたけど、僕は何も反応しなかった……。
琉唯に僕の顔を触られた時は、あれほど身体が勝手に反応してしまうのに。
琉唯、もう僕に触れたりしないつもりなのかな……。
僕はソファーの上に三角座りになって足を抱え込み自分の身体をギュッと抱き締めた。
水曜から琉唯には会っていないし、特に連絡が来るわけでもない。
琉唯に会いたい……なんて、どうしてこんなに強く思っているのだろう。
僕はそのままうつらうつらと夢と現実の狭間をさまよっていたようだ。
――ブブッ……
「うわっ……!」
机の上に置いておいたスマホの振動音が大きく響いて、僕は座ったままソファーの上で跳ねた。
いつの間にか映画は終わっていて、暗幕の隙間から入り込むのはオレンジ色の明かり。
スマホに表示された名前が僕の脳内を急激に覚醒させた。
今日は海の日……と言えども、友だちゼロで海水浴などのアクティビティと無縁の僕はクーラーの利いた自室で勉強をしていた。
窓から見える外は今日も晴れ上がっていて、ギラギラと燃えている太陽の光が陽炎を作っているのがガラス越しにもわかる。
絶対に今日もうだるような暑さだ。
麦茶をお代わりしようと、空になったグラスのコップを持って、階段を下りた時だった。
「もうー侑は何でこうも忘れ物が多いのかしら」
美織さんのひとり言がリビングから漏れ聞こえてきた。
「どうしたの?」
「あら、優陽。侑が部活の替えのTシャツを入れた巾着袋一式忘れていったのよ」
美織さんの手にあるのは、スポーツブランドのロゴが入ったブラックの巾着。
たっちゃんは祝日の今日も陸上部の活動で朝から学校に行っている。
「僕、学校まで届けてくるよ」
「え、いいの?」
「これだけ暑いのにたっちゃん替えの服がないと困るだろうし。それにずっと家に閉じこもっているのも良くないから、僕も気分を変えて午後は学校の部室で勉強してこようかな」
「優陽が迷惑じゃないならお願いしてもいい?」
「うん、もちろん」
「優陽、助かるわ。その前に昼食、作ってあるから食べていきなさい」
「ありがとう。美織さん」
美織さんが用意してくれた昼食を食べ終え、制服に着替えた僕は華澄高へと向かった。
さすがに一番気温が上がる時間帯で日陰を選んだとしても外を歩くのは危険だったから、バスで向かうことにする。
バスに揺られながら、こんな暑い中、外で働いてくれている人たちって、ありがたいな……なんて工事現場で汗水垂らして労働してくれている方々を見つめながら思う。
あの人たちも琉唯を知っているのかな。
自分が知らない人たちに自分を知られているって、どんな感覚なのだろう。
咲良菜緒や宮永さんにとっても、芸能界で活躍している人たちには普通の感覚なんだろうか。
生まれた時から当たり前のように芸能界に関わっている人が身近に居るけれど、僕にはわからない。
――琉唯がわからない……。
「え? 優陽、学校まで届けにきてくれたんだ」
華澄高校のグラウンドに到着すると、たっちゃんは陸上部の部員たちと屋根付きの休憩スペースに居た。
大型の扇風機が2台、ウォータージャグも3つ置かれている。
こまめに休憩に入っているようで、熱中症対策はされているみたいだ。
「サンキュ。マジで助かった。Tシャツ汗でびしょびしょでさ」
たっちゃんは僕から受け取った巾着を受け取るやいなや、その場で来ていたTシャツを脱ぎ始めた。
近くに居た女子部員から「きゃっ」と桃色の悲鳴がとんでくる。
しっかりたっちゃんの筋肉質な上半身に視線がロックオンされていた。
たっちゃんは新しいTシャツに腕を通しながら、
「優陽もう帰んの?」
と、僕に質問してきた。
「せっかく学校に来たから僕も部活してから帰るよ」
「そっか。また何か優陽にお礼させて」
「そんなのいいよ。三連休ずっと家に引きこもっちゃうところだったし」
「優陽はぜんぜん焼けずに色白のままだもんな」
たっちゃんが僕の頬を両手で包むように触れて顔を接近させてきた。
「おーい、七嶋。男といちゃついてるところなんか見せつけてくるんじゃねぇよ」
休憩している部員たちから囃し立てるような声が飛んでくる。
「そんなんじゃないって」
ぶっきらぼうに返したたっちゃんは休憩が終わり、灼熱のグラウンドへと戻っていく。
たっちゃんと別れた僕は映像研究部の部室で映画を観ていた。
暗幕を引いて暗がりの中で映画を観ている僕と違い、たっちゃんは太陽の下が良く似合う。
自然と視線を奪って、みんなの輪の中心にいて。
いつだって、たっちゃんは真っ直ぐで眩しくて僕を照らしてくれる太陽みたいな存在だ。
さっき、たっちゃんに頬を触られたけど、僕は何も反応しなかった……。
琉唯に僕の顔を触られた時は、あれほど身体が勝手に反応してしまうのに。
琉唯、もう僕に触れたりしないつもりなのかな……。
僕はソファーの上に三角座りになって足を抱え込み自分の身体をギュッと抱き締めた。
水曜から琉唯には会っていないし、特に連絡が来るわけでもない。
琉唯に会いたい……なんて、どうしてこんなに強く思っているのだろう。
僕はそのままうつらうつらと夢と現実の狭間をさまよっていたようだ。
――ブブッ……
「うわっ……!」
机の上に置いておいたスマホの振動音が大きく響いて、僕は座ったままソファーの上で跳ねた。
いつの間にか映画は終わっていて、暗幕の隙間から入り込むのはオレンジ色の明かり。
スマホに表示された名前が僕の脳内を急激に覚醒させた。