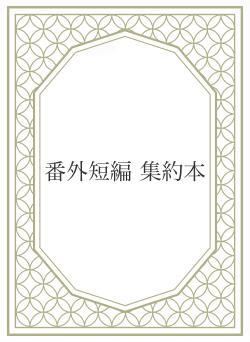思いのほか真剣な琉唯の眼差しが僕を貫いて、言葉が詰まる。
僕の意見って、本当にどっちでもいいんだ。
だって、そうやって他人の選んだもので生きてきたから、いざ自分で選択するとなると思いのほか戸惑ってしまった。
「……豚まんがいい」
たったそれだけ答えるのに妙に緊張してしまった。
ただお土産をチョイスするだけなのに、自分の意志を伝えることに慣れていなさ過ぎて。
「――ん。よく言えました」
子どもを褒めるかのように琉唯に微笑まれる。
琉唯が僕の頭へと手を伸ばしかける動作を途中で止めたことにも気がついてしまった。
僕に触れてくれて構わないのに……。
「あ、あの!」
「――何?」
「琉唯だったら、どっちを選ぶ?」
僕は琉唯をもっと知りたい。
表舞台に立っている琉唯のことは少し調べれば、すぐに答えが出るだろう。
好きな色も、好きな食べ物も今、ハマっていることも……。
でも、僕は大衆に向けて答えたものじゃなくて琉唯から直接知りたい。
琉唯は僕から質問を受けたことに驚いたのか目を瞠った。
それから唇にゆったりとカーブを描くと、
「――チーズケーキ」
と、答えてくれた。
実は甘いものが好きな琉唯だから、そうじゃないかと思っていた。
正解だったことに僕は微笑んでしまう。
自己管理も仕事のうちとかで、体型や肌に影響が出ないよう好きなものを好きなようには食べられないと琉唯が言っていたのを思い出す。
琉唯は笑顔の僕を見て、口を隠すように手を当てて数秒間、視線を外した。
「やっぱり両方、買ってくる」
「え?」
「優陽と一緒に食べたい」
「……う、うん」
何で琉唯がちょっと照れているんだろうか。
僕まで気恥ずかしい気持ちに襲われた。
「――あのさ、優陽」
「何?」
「”たっちゃん”のことなんだけど」
あの日以来、その話には触れてこなかった琉唯。
何を琉唯に言われるのか、僕の心臓がギュッと強く掴まれたように動揺を主張した。
「2年1組、七嶋侑。陸上部所属」
琉唯はたっちゃんを調べたのか?
それくらいだったら簡単にわかるとは思うけど。
「”たっちゃん”の父親ってセブンスターファクトリーの社長なんだな」
思わず息を呑む。
僕の表情から何かを読み取ろうとしているのか琉唯のミステリアスな視線が僕に据えられている。
「――かつて、咲良菜緒が所属していた芸能事務所の……」
僕は不自然も反応しないように気をつけながら、どう琉唯に答えるのが正解なのか必死に頭の中で考えていた。
僕が咲良菜緒の隠し子だということは秘密でも、僕の保護者代わりがたっちゃんの両親である頼政さんと美織さんであることは特別に隠しているわけじゃない。
対外的には僕はたっちゃんの遠縁だということにもなっている。
そこまで琉唯が知っているのかどうかわからないけど、少し調べればわかることだった。
「うん。そうだね」
琉唯がどこまで知っているのかわからない以上、口を開くのは最低限にしよう。
これで咲良菜緒と僕との関わりが全くのゼロではないってことが琉唯に露呈してしまったのは事実であって……。
「――俺、セブファク所属の俳優って尊敬する人多いんだよな。演技力が高くて円熟していて、現場で一緒になると学ぶことが多い」
琉唯は僕のことについて言及することはなかった。
「この間、共演した宮永泉さんは現場の雰囲気も良くしてくれるし、俺にも気さくに声かけてくれるし、役への適応力と深みが段違いだし、また現場一緒になりたい」
琉唯はいつもと変わらない様子で映像研究部のノートの1冊を読みながら話を続けた。
でも、やっぱり僕と物理的に少し距離をとられていて、胸の奥がギュッと締め付けられているような感覚に襲われる。
――もう少し近くに座ってもいいよ。
――僕に触れてもいいんだよ。
そんなの、琉唯に言えるわけないじゃないか……。
僕が、琉唯の好きな咲良菜緒だったらいいのに……。
琉唯との距離感を測れないまま、僕は琉唯と時間と空間を共有していた。
僕の意見って、本当にどっちでもいいんだ。
だって、そうやって他人の選んだもので生きてきたから、いざ自分で選択するとなると思いのほか戸惑ってしまった。
「……豚まんがいい」
たったそれだけ答えるのに妙に緊張してしまった。
ただお土産をチョイスするだけなのに、自分の意志を伝えることに慣れていなさ過ぎて。
「――ん。よく言えました」
子どもを褒めるかのように琉唯に微笑まれる。
琉唯が僕の頭へと手を伸ばしかける動作を途中で止めたことにも気がついてしまった。
僕に触れてくれて構わないのに……。
「あ、あの!」
「――何?」
「琉唯だったら、どっちを選ぶ?」
僕は琉唯をもっと知りたい。
表舞台に立っている琉唯のことは少し調べれば、すぐに答えが出るだろう。
好きな色も、好きな食べ物も今、ハマっていることも……。
でも、僕は大衆に向けて答えたものじゃなくて琉唯から直接知りたい。
琉唯は僕から質問を受けたことに驚いたのか目を瞠った。
それから唇にゆったりとカーブを描くと、
「――チーズケーキ」
と、答えてくれた。
実は甘いものが好きな琉唯だから、そうじゃないかと思っていた。
正解だったことに僕は微笑んでしまう。
自己管理も仕事のうちとかで、体型や肌に影響が出ないよう好きなものを好きなようには食べられないと琉唯が言っていたのを思い出す。
琉唯は笑顔の僕を見て、口を隠すように手を当てて数秒間、視線を外した。
「やっぱり両方、買ってくる」
「え?」
「優陽と一緒に食べたい」
「……う、うん」
何で琉唯がちょっと照れているんだろうか。
僕まで気恥ずかしい気持ちに襲われた。
「――あのさ、優陽」
「何?」
「”たっちゃん”のことなんだけど」
あの日以来、その話には触れてこなかった琉唯。
何を琉唯に言われるのか、僕の心臓がギュッと強く掴まれたように動揺を主張した。
「2年1組、七嶋侑。陸上部所属」
琉唯はたっちゃんを調べたのか?
それくらいだったら簡単にわかるとは思うけど。
「”たっちゃん”の父親ってセブンスターファクトリーの社長なんだな」
思わず息を呑む。
僕の表情から何かを読み取ろうとしているのか琉唯のミステリアスな視線が僕に据えられている。
「――かつて、咲良菜緒が所属していた芸能事務所の……」
僕は不自然も反応しないように気をつけながら、どう琉唯に答えるのが正解なのか必死に頭の中で考えていた。
僕が咲良菜緒の隠し子だということは秘密でも、僕の保護者代わりがたっちゃんの両親である頼政さんと美織さんであることは特別に隠しているわけじゃない。
対外的には僕はたっちゃんの遠縁だということにもなっている。
そこまで琉唯が知っているのかどうかわからないけど、少し調べればわかることだった。
「うん。そうだね」
琉唯がどこまで知っているのかわからない以上、口を開くのは最低限にしよう。
これで咲良菜緒と僕との関わりが全くのゼロではないってことが琉唯に露呈してしまったのは事実であって……。
「――俺、セブファク所属の俳優って尊敬する人多いんだよな。演技力が高くて円熟していて、現場で一緒になると学ぶことが多い」
琉唯は僕のことについて言及することはなかった。
「この間、共演した宮永泉さんは現場の雰囲気も良くしてくれるし、俺にも気さくに声かけてくれるし、役への適応力と深みが段違いだし、また現場一緒になりたい」
琉唯はいつもと変わらない様子で映像研究部のノートの1冊を読みながら話を続けた。
でも、やっぱり僕と物理的に少し距離をとられていて、胸の奥がギュッと締め付けられているような感覚に襲われる。
――もう少し近くに座ってもいいよ。
――僕に触れてもいいんだよ。
そんなの、琉唯に言えるわけないじゃないか……。
僕が、琉唯の好きな咲良菜緒だったらいいのに……。
琉唯との距離感を測れないまま、僕は琉唯と時間と空間を共有していた。