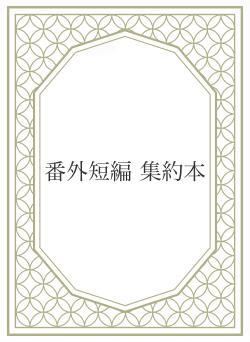***
日々、最高気温は35℃を越えて、人体に危険なほど夏の暑さは容赦なかった。
たっちゃんも陸上部は朝練こそ屋外で行われるものの、最近は17時以降でないと暑さ指数に引っかかり、学校からグラウンドの利用許可が下りず、その間は近くの区民体育館を借りて練習していると聞いた。
「――けどさ、やっぱり体育館だと走る感覚が全然違うんだよな。体育館の固い床とフィールドを蹴り上げるのって全く違うし。夏が暑すぎるのも考えものだよな」
そう、たっちゃんが零していた。
来週の金曜日は1学期の終業式で約1ヶ月の夏休みに突入する。
期末考査の返却も先週には終わって、僕はまた総合点で学年1位だった。
たっちゃんも今回は全体的に点数が高くて総合点も順位も上がったらしく、美織さんが喜んでいた。
『侑、教えてくれた優陽に感謝しなさいよ』
『してるし。それに優陽に教えてもらってない文系科目も点数上がってんだって』
『優陽みたいな模範的な優等生が侑の傍に居てくれて、本当にありがたいわ。勉強の大切さに気づくのが遅いけど』
『なんで全部、優陽の手柄みたいに言うんだよ』
たっちゃんの期末の結果を美織さんに感謝されたけど、こんな七嶋家の会話は日常的な光景で美織さんもちゃんとたっちゃんの努力を認めているだろう。
期末考査の最終日。
――琉唯に無理やりキスされてしまった日。
琉唯は時間の許す限り、
『ごめん、優陽』
と謝りながら、ずっと泣いている僕を落ち着かせるように頭を撫でてくれた。
マネージャーの蝶野さんからの電話で渋々出て行ったけれど。
蝶野さんって名前しか知らなかったけど、男性だったと僕が知ったのはこの時。
『琉唯くーん、仕事に穴あける気なの? 学校から全然出てこないし、連絡もつかないから僕の胃に穴が空きそうだったよー』
電話口から漏れてきた蝶野さんの声は泣きそうなほどに切羽つまった焦ったもので、仕事に支障が出ないギリギリまで僕の傍にいてくれたのだとわかった。
週が明けて、映像研究部の部室に昼休みに顔を出した琉唯は今まで通りであの日のことには少しも触れてこない。
あれは僕が見た夢なのかと錯覚するほどに。
熱い舌も指先も、キスのたびに漏れる濡れた音も、琉唯の体温も僕の身体が覚えているのに。
あの出来事について話題が及んでも僕は困るはずなのに、なかったことにされるのも心が痛んだ。
ただ、琉唯は物理的に僕と少し距離をとるようになった。
今まではプロジェクタで映画を観る時に肩が触れるくらい近かったくせに、二人の間にもう一人座れるくらいには距離をとられる。
僕の頬や髪に遠慮なしに触れてきたのに、それもなくなった。
そんな琉唯の様子に僕はどうしようもないくらい寂しく感じて。
無理やり琉唯にキスされたのに、どうして僕は琉唯を拒絶しないんだろう。
誰かに対してこんな気持ちを抱いたのは初めてで。
僕は咲良菜緒じゃないのに……。
琉唯の傍に居ると、琉唯が僕を見ているわけじゃないのがわかって、部室の酸素濃度が薄くなったのかと勘違いするくらい息苦しさを覚えた。
それでも琉唯から離れたくないなんて。
この気持ちをどう扱ったらいいのかわからない。
「優陽は豚まんとチーズケーキだったら、どっちがいい?」
週の真ん中の水曜日、昼休みに映像研究部の部室にやってきた琉唯に唐突に聞かれた。
「え? いきなり何?」
「明日から仕事の関係で大阪に行くから、優陽にお土産買ってくる」
「そんな琉唯は忙しいんだし、僕に気を遣わなくていいって」
「実際に買いに行くのは蝶野さんだと思うけど。金は俺が出す」
いや、誰が店頭に購入しにいくかでも資金源がどこかでもなくて……。
明日から琉唯が居ないのか……なんて打ち沈んでいる場合じゃない。
琉唯は僕が遠慮を貫くと悟ったのだろう。
「絶対に優陽に買ってくる。――で、どっち?」
若手トップの俳優、恋人にしたいイケメン殿堂入りの一条琉唯に微笑みの圧力をかけられてしまえば抗い方を失ってしまう。
「どっちでもいいよ」
「いいから優陽が好きなほう選べって」
「琉唯が選んだものでいいよ」
「それがわからないから聞いてるんだろ」
「本当に僕はどっちでも……」
「――優陽。俺は優陽の意見を聞きたい」
日々、最高気温は35℃を越えて、人体に危険なほど夏の暑さは容赦なかった。
たっちゃんも陸上部は朝練こそ屋外で行われるものの、最近は17時以降でないと暑さ指数に引っかかり、学校からグラウンドの利用許可が下りず、その間は近くの区民体育館を借りて練習していると聞いた。
「――けどさ、やっぱり体育館だと走る感覚が全然違うんだよな。体育館の固い床とフィールドを蹴り上げるのって全く違うし。夏が暑すぎるのも考えものだよな」
そう、たっちゃんが零していた。
来週の金曜日は1学期の終業式で約1ヶ月の夏休みに突入する。
期末考査の返却も先週には終わって、僕はまた総合点で学年1位だった。
たっちゃんも今回は全体的に点数が高くて総合点も順位も上がったらしく、美織さんが喜んでいた。
『侑、教えてくれた優陽に感謝しなさいよ』
『してるし。それに優陽に教えてもらってない文系科目も点数上がってんだって』
『優陽みたいな模範的な優等生が侑の傍に居てくれて、本当にありがたいわ。勉強の大切さに気づくのが遅いけど』
『なんで全部、優陽の手柄みたいに言うんだよ』
たっちゃんの期末の結果を美織さんに感謝されたけど、こんな七嶋家の会話は日常的な光景で美織さんもちゃんとたっちゃんの努力を認めているだろう。
期末考査の最終日。
――琉唯に無理やりキスされてしまった日。
琉唯は時間の許す限り、
『ごめん、優陽』
と謝りながら、ずっと泣いている僕を落ち着かせるように頭を撫でてくれた。
マネージャーの蝶野さんからの電話で渋々出て行ったけれど。
蝶野さんって名前しか知らなかったけど、男性だったと僕が知ったのはこの時。
『琉唯くーん、仕事に穴あける気なの? 学校から全然出てこないし、連絡もつかないから僕の胃に穴が空きそうだったよー』
電話口から漏れてきた蝶野さんの声は泣きそうなほどに切羽つまった焦ったもので、仕事に支障が出ないギリギリまで僕の傍にいてくれたのだとわかった。
週が明けて、映像研究部の部室に昼休みに顔を出した琉唯は今まで通りであの日のことには少しも触れてこない。
あれは僕が見た夢なのかと錯覚するほどに。
熱い舌も指先も、キスのたびに漏れる濡れた音も、琉唯の体温も僕の身体が覚えているのに。
あの出来事について話題が及んでも僕は困るはずなのに、なかったことにされるのも心が痛んだ。
ただ、琉唯は物理的に僕と少し距離をとるようになった。
今まではプロジェクタで映画を観る時に肩が触れるくらい近かったくせに、二人の間にもう一人座れるくらいには距離をとられる。
僕の頬や髪に遠慮なしに触れてきたのに、それもなくなった。
そんな琉唯の様子に僕はどうしようもないくらい寂しく感じて。
無理やり琉唯にキスされたのに、どうして僕は琉唯を拒絶しないんだろう。
誰かに対してこんな気持ちを抱いたのは初めてで。
僕は咲良菜緒じゃないのに……。
琉唯の傍に居ると、琉唯が僕を見ているわけじゃないのがわかって、部室の酸素濃度が薄くなったのかと勘違いするくらい息苦しさを覚えた。
それでも琉唯から離れたくないなんて。
この気持ちをどう扱ったらいいのかわからない。
「優陽は豚まんとチーズケーキだったら、どっちがいい?」
週の真ん中の水曜日、昼休みに映像研究部の部室にやってきた琉唯に唐突に聞かれた。
「え? いきなり何?」
「明日から仕事の関係で大阪に行くから、優陽にお土産買ってくる」
「そんな琉唯は忙しいんだし、僕に気を遣わなくていいって」
「実際に買いに行くのは蝶野さんだと思うけど。金は俺が出す」
いや、誰が店頭に購入しにいくかでも資金源がどこかでもなくて……。
明日から琉唯が居ないのか……なんて打ち沈んでいる場合じゃない。
琉唯は僕が遠慮を貫くと悟ったのだろう。
「絶対に優陽に買ってくる。――で、どっち?」
若手トップの俳優、恋人にしたいイケメン殿堂入りの一条琉唯に微笑みの圧力をかけられてしまえば抗い方を失ってしまう。
「どっちでもいいよ」
「いいから優陽が好きなほう選べって」
「琉唯が選んだものでいいよ」
「それがわからないから聞いてるんだろ」
「本当に僕はどっちでも……」
「――優陽。俺は優陽の意見を聞きたい」