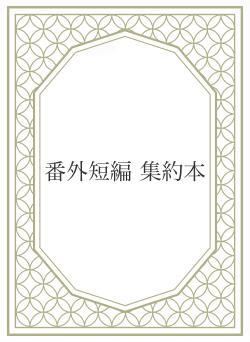***
期末考査の全日程が終了した。
多かれ少なかれ誰もが解き放たれたような面持ちをしている。
最終日もお昼前には下校になるから、明日から週末なことも相まって部活動の生徒以外ははしゃぎながら遊びに行く計画を立てたりと楽しそうだ。
今日は美織さんがたっちゃんと2人分お弁当を用意してくれたから、僕も帰りのSHR終了後に映像研究部の部室に向かった。
期末考査が終わると、脳内に余白が出来るからか思い出してしまう。
――いずみ先輩、大好き。直子
宮永さんと咲良菜緒は本当に恋人同士だったのか?
関係を隠してる理由があった?
結婚……はしていないはずだ。
宮永さんには結婚歴がないと聞く。
どうして、宮永さんは自分が父親だって僕に言ってくれないんだろう。
僕も僕でもんもんとしているくらいなら宮永さんに聞いてみればいいのに。
でも、僕に言ってこないってことは隠しておきたいことだとわかるから……。
芸術総合コースの面々はとっくに下校しているのかアネックス館に人影はまばらだった。
数日ぶりに映像研究部の部室の鍵を開けて、引き戸を開こうとした時、
「――優陽」
急に背後から伸びてきた手に手首を掴まれた。
飛び出すのではないかと思うくらいに心臓が跳ねる。
「え!?」
その存在に気づいた時には僕は琉唯に映像研究部の部室の中へと引き入れられていた。
ガチャンと鍵が閉められる音が響いたかと思えば、琉唯は僕を自分の身体と壁の間へ閉じ込めてくる。
一連の行為が不意をつかれすぎて、目の前で起こっていることと脳内の認識にズレが生じていた。
今日も仕事で来られないって琉唯は言っていたのに……。
「……琉唯、いきなり何?」
不安にかられながら目線を上昇させる。
壁に手をつき、冷たい虹彩で僕を見下ろしている琉唯。
無表情なのに顔立ちが余りにも美しすぎるのと琉唯の憤然が流れ込むように僕へと伝わってきてゾクッと背筋が凍りついた。
「――優陽。あいつ誰?」
「あいつって……?」
声が少し上ずってしまった。
いつもよりも琉唯の声が低音だったから。
「朝、一緒に登校してたやつ」
何で琉唯が知っているんだろうと思いつつも、
「たっちゃんのこと……?」
と、素直に答えてしまった。
琉唯の眉間が不機嫌にピクッと歪む。
「その”たっちゃん”は優陽の何?」
「何って言われても……」
なんて琉唯に答えるのが正解なんだろう?
――僕は咲良菜緒の隠し子で、たっちゃんは咲良菜緒が所属していたセブファクの社長の息子で、たっちゃんの両親に僕も産まれた時から育ててもらっていて……。
なんて正直に打ち明けられるはずもなく。
「たっちゃんは……、ずっと僕の一番近くにいる人だよ」
物心つく前から、たっちゃんのそばに居るんだ。
たっちゃんは6月生まれだから、僕より8ヶ月早く誕生している。
僕が3月の最終日に産まれて、咲良菜緒が亡くなって、月齢が違う乳児2人を育児した美織さんは本当に大変だっただろう。
それでも美織さんは僕が誕生してからの写真も動画もたくさん記録しておいてくれていた。
「1番近くって何だよ、それ。あの男と付き合ってんの?」
「付き合うって、たっちゃんは男だよ」
「関係ねぇよ」
琉唯は僕の腰を引き寄せてくる。
器用に僕の眼鏡を取り去って、近くの棚へと置く。
僕の頭を押さえながら琉唯の綺麗な顔が間近に迫ってきて、最初から乱暴に唇を重ねられた。
舌を割り入れられ、口内を探るように僕の舌を絡め取られる。
「んっ……ふっ……」
くちゅっ、と濡れた音が口内から漏れて全身が強張った。
反射的に逃げようとしたら、僕の腰に回された琉唯の力が強くなる。
これ、いつ呼吸したらいいんだろう。
「やっ……待っ……」
「――待たねぇ」
顔を背けるのを許さないというように、僕の後頭部に添えられた手に力がこもる。
僕の口内を琉唯の熱い舌で貪り尽くされるようだ。
溶かされるような、痺れるような感覚が脳から全身に伝わって、目に水分が蓄えられていく。
「はあっ……」
息継ぎの仕方がわからなくて酸素不足になった僕と琉唯の視線が間近で交差する。
「こういうの、あいつにもさせてんの?」
こんなに意地悪な質問してくるくせに、どこか琉唯は自分が傷ついたような目をしているから何も言葉が出てこなくなった。
「優陽は何にも知らなそうな無垢な顔しておきながら、」
琉唯の指先が僕の目の端に溜まった涙を拭う。
「こんなに相手を誘うような目で見つめて、ねだってんの?」
「違っ……」
否定しようと思ったのに、再び噛みつかれるようなキスをされて僕の声は吸い込まれる。
「琉唯……、んっ……」
琉唯の熱い舌に僕の思考が溶かされていくような気がした。
無理やりされているのに、強く僕を求められているようで生々しくて、どこか甘くて。
「ふぅ、はっ…ん……」
「優陽……」
喉の奥から自然に漏れる吐息と声が恥ずかしい。
唇が離れた合間に琉唯から呼ばれる自分の名前がなぜか嬉しい。
――こんな感覚、知らなかった。
初めての行為なのに、相手は琉唯なのに……。
力づくでされてしまっているのに……。
自分がおかしくなってしまいそうで怖い。
怖くて逃げたいと思うのに、もっと琉唯にしてほしくて……。
僕の思考回路は普通じゃなくなっていた。
期末考査の全日程が終了した。
多かれ少なかれ誰もが解き放たれたような面持ちをしている。
最終日もお昼前には下校になるから、明日から週末なことも相まって部活動の生徒以外ははしゃぎながら遊びに行く計画を立てたりと楽しそうだ。
今日は美織さんがたっちゃんと2人分お弁当を用意してくれたから、僕も帰りのSHR終了後に映像研究部の部室に向かった。
期末考査が終わると、脳内に余白が出来るからか思い出してしまう。
――いずみ先輩、大好き。直子
宮永さんと咲良菜緒は本当に恋人同士だったのか?
関係を隠してる理由があった?
結婚……はしていないはずだ。
宮永さんには結婚歴がないと聞く。
どうして、宮永さんは自分が父親だって僕に言ってくれないんだろう。
僕も僕でもんもんとしているくらいなら宮永さんに聞いてみればいいのに。
でも、僕に言ってこないってことは隠しておきたいことだとわかるから……。
芸術総合コースの面々はとっくに下校しているのかアネックス館に人影はまばらだった。
数日ぶりに映像研究部の部室の鍵を開けて、引き戸を開こうとした時、
「――優陽」
急に背後から伸びてきた手に手首を掴まれた。
飛び出すのではないかと思うくらいに心臓が跳ねる。
「え!?」
その存在に気づいた時には僕は琉唯に映像研究部の部室の中へと引き入れられていた。
ガチャンと鍵が閉められる音が響いたかと思えば、琉唯は僕を自分の身体と壁の間へ閉じ込めてくる。
一連の行為が不意をつかれすぎて、目の前で起こっていることと脳内の認識にズレが生じていた。
今日も仕事で来られないって琉唯は言っていたのに……。
「……琉唯、いきなり何?」
不安にかられながら目線を上昇させる。
壁に手をつき、冷たい虹彩で僕を見下ろしている琉唯。
無表情なのに顔立ちが余りにも美しすぎるのと琉唯の憤然が流れ込むように僕へと伝わってきてゾクッと背筋が凍りついた。
「――優陽。あいつ誰?」
「あいつって……?」
声が少し上ずってしまった。
いつもよりも琉唯の声が低音だったから。
「朝、一緒に登校してたやつ」
何で琉唯が知っているんだろうと思いつつも、
「たっちゃんのこと……?」
と、素直に答えてしまった。
琉唯の眉間が不機嫌にピクッと歪む。
「その”たっちゃん”は優陽の何?」
「何って言われても……」
なんて琉唯に答えるのが正解なんだろう?
――僕は咲良菜緒の隠し子で、たっちゃんは咲良菜緒が所属していたセブファクの社長の息子で、たっちゃんの両親に僕も産まれた時から育ててもらっていて……。
なんて正直に打ち明けられるはずもなく。
「たっちゃんは……、ずっと僕の一番近くにいる人だよ」
物心つく前から、たっちゃんのそばに居るんだ。
たっちゃんは6月生まれだから、僕より8ヶ月早く誕生している。
僕が3月の最終日に産まれて、咲良菜緒が亡くなって、月齢が違う乳児2人を育児した美織さんは本当に大変だっただろう。
それでも美織さんは僕が誕生してからの写真も動画もたくさん記録しておいてくれていた。
「1番近くって何だよ、それ。あの男と付き合ってんの?」
「付き合うって、たっちゃんは男だよ」
「関係ねぇよ」
琉唯は僕の腰を引き寄せてくる。
器用に僕の眼鏡を取り去って、近くの棚へと置く。
僕の頭を押さえながら琉唯の綺麗な顔が間近に迫ってきて、最初から乱暴に唇を重ねられた。
舌を割り入れられ、口内を探るように僕の舌を絡め取られる。
「んっ……ふっ……」
くちゅっ、と濡れた音が口内から漏れて全身が強張った。
反射的に逃げようとしたら、僕の腰に回された琉唯の力が強くなる。
これ、いつ呼吸したらいいんだろう。
「やっ……待っ……」
「――待たねぇ」
顔を背けるのを許さないというように、僕の後頭部に添えられた手に力がこもる。
僕の口内を琉唯の熱い舌で貪り尽くされるようだ。
溶かされるような、痺れるような感覚が脳から全身に伝わって、目に水分が蓄えられていく。
「はあっ……」
息継ぎの仕方がわからなくて酸素不足になった僕と琉唯の視線が間近で交差する。
「こういうの、あいつにもさせてんの?」
こんなに意地悪な質問してくるくせに、どこか琉唯は自分が傷ついたような目をしているから何も言葉が出てこなくなった。
「優陽は何にも知らなそうな無垢な顔しておきながら、」
琉唯の指先が僕の目の端に溜まった涙を拭う。
「こんなに相手を誘うような目で見つめて、ねだってんの?」
「違っ……」
否定しようと思ったのに、再び噛みつかれるようなキスをされて僕の声は吸い込まれる。
「琉唯……、んっ……」
琉唯の熱い舌に僕の思考が溶かされていくような気がした。
無理やりされているのに、強く僕を求められているようで生々しくて、どこか甘くて。
「ふぅ、はっ…ん……」
「優陽……」
喉の奥から自然に漏れる吐息と声が恥ずかしい。
唇が離れた合間に琉唯から呼ばれる自分の名前がなぜか嬉しい。
――こんな感覚、知らなかった。
初めての行為なのに、相手は琉唯なのに……。
力づくでされてしまっているのに……。
自分がおかしくなってしまいそうで怖い。
怖くて逃げたいと思うのに、もっと琉唯にしてほしくて……。
僕の思考回路は普通じゃなくなっていた。