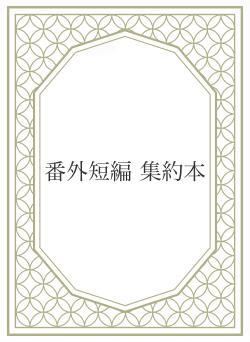***
7月の開始と同時に三日間の期末考査期間に入った。
テスト期間は3日目の全科目が終了するまで部活動が完全禁止。
映像研究部の部室に行けないから琉唯と顔を合わせていない。
けど、午後や夜に勉強のことで質問メッセージが来たりしていた。
休みになるわけではなく、仕事の合間を有効に活用しながら勉強しているみたいでハードそうだ。
考査期間は陸上部の朝練がないたっちゃんと自転車で登校していた。
「暑い……。溶ける」
肌へと突き刺すように陽の光が頭上から降り注がれている。
たっちゃんと横並びで学校の駐輪場から昇降口に向かう。
代謝が良いのかたっちゃんの精悍な顔立ちは幾筋も汗が流れていた。
それでも清潔感があって、どことなく色気さえ漂っているのはたっちゃんがイケメンだからだろうか。
たっちゃんってシトラスの香りが似合っている。
何の匂いなんだろう。
「やっと今日の午前中で期末考査が終わるな」
「うん。早くこの独特な緊張感から解放されたい」
「――だな」
屋外の部活動でいつの間にか日焼けしていたたっちゃんはワイルドな魅力が増したと僕と同じクラスの女子たちが最近はしゃぎながら話していた。
「七嶋ーおはよー」
「おはー七嶋」
「おう。おはよう」
「教室まで俺たちと一緒に行こうぜー」
たっちゃんに走り寄りながらノリ良く挨拶してきた二人組の男たちは、たっちゃんと同じクラスなんだろう。
「悪い。俺、今日は優陽と登校してるから。また後でな」
たっちゃんが笑顔できっぱり断ると、二人の視線はたっちゃんの隣に居る僕に向けられた。
「うっわ。陰キャ丸出し」
「だっせー」
いささか失礼すぎる嘲りを含んだ感想を僕にぶつけられた。
こんな扱いに慣れている僕は見下されても何とも思わないけど、たっちゃんの評価が下がらないかそわそわしてしまう。
「――平気でそういうこと人に言えちゃうやつって神経疑うわ」
たっちゃんが真顔で言う。
温度のない冷たい声色だった。
たっちゃんは顔が整っているだけに感情を消失させれば、表現し難い迫力がある。
たっちゃんのクラスメイトの男たちは、たっちゃんを怒らせた自覚はあるのか恐れを成したように凍りついていた。
「悪い、七嶋。俺たち調子に乗ったわ。先に行ってる」
「ごめん。後で教室でな」
二人は引きつった声で口々にたっちゃんに伝えると、速い足取りで昇降口の中へと消えて行った。
「謝る相手が違うよな。悪かった、優陽」
たっちゃんがばつが悪そうな顔で僕に謝ってくる。
「僕はこんな扱い慣れてるから気にしなくていいよ」
「慣れなくていいんだよ。自分に反撃してこなさそうな人を軽視する発言がいやだ」
「それより、同じクラスの友だちだよね? たっちゃんはいいの?」
「これで離れていくような友だちならいらねぇわ」
たっちゃんは何らうろたえることもなく言った。
たっちゃんの真っ直ぐなぶれない男気はかっこいい。
「僕はいい子たちだと思ったけど……」
「はあ?」
たっちゃんは目を白黒させながら、素っ頓狂な声を出した。
僕が何を言っているのかわからないって顔に書いてある。
「もちろん僕に言ってきたことは良くないと思うけど」
「当たり前だろ」
「二人ともすぐに”ごめん”って言葉が出てきていたし、言い訳せずに自分の非を認めていたし」
「……」
「誰にだって間違いはあるんだから、反射的に素直に謝れる人って僕はいいと思うんだ」
そう答えたら、たっちゃんが急に横から勢いよく僕を抱き締めてきた。
僕を包むシトラスの香り。
「ちょっと……」
「ほんっと優陽、好きだわ」
僕を抱え寄せながら、たっちゃんが頭上でつぶやく。
登校時間の昇降口前で人が多いのに……。
たっちゃんの腕の隙間から薄っすら見えたけど、たっちゃんを見つめる女子たちが色めいていた。
僕みたいな地味なガリ勉眼鏡が近くに居たら、たっちゃんのファンに恨まれてしまう。
「たっちゃん、暑い」
「悪い。優陽がかわいかったから」
僕から離れたたっちゃんはもう怒りの感情がしまわれていてホッとした。
「俺、優陽が教えてくれたおかげでテストの1日目2日目、結構手ごたえあるんだよな」
「それなら良かった」
「返却されないとわからないけど。今回は父さんと母さんに『優陽を見習え』攻撃されなくて済むかも」
たっちゃんと横並びで歩いて昇降口に入る。
今の場面を琉唯に見られていたなんて、この時の僕は知るよしもなかった。
7月の開始と同時に三日間の期末考査期間に入った。
テスト期間は3日目の全科目が終了するまで部活動が完全禁止。
映像研究部の部室に行けないから琉唯と顔を合わせていない。
けど、午後や夜に勉強のことで質問メッセージが来たりしていた。
休みになるわけではなく、仕事の合間を有効に活用しながら勉強しているみたいでハードそうだ。
考査期間は陸上部の朝練がないたっちゃんと自転車で登校していた。
「暑い……。溶ける」
肌へと突き刺すように陽の光が頭上から降り注がれている。
たっちゃんと横並びで学校の駐輪場から昇降口に向かう。
代謝が良いのかたっちゃんの精悍な顔立ちは幾筋も汗が流れていた。
それでも清潔感があって、どことなく色気さえ漂っているのはたっちゃんがイケメンだからだろうか。
たっちゃんってシトラスの香りが似合っている。
何の匂いなんだろう。
「やっと今日の午前中で期末考査が終わるな」
「うん。早くこの独特な緊張感から解放されたい」
「――だな」
屋外の部活動でいつの間にか日焼けしていたたっちゃんはワイルドな魅力が増したと僕と同じクラスの女子たちが最近はしゃぎながら話していた。
「七嶋ーおはよー」
「おはー七嶋」
「おう。おはよう」
「教室まで俺たちと一緒に行こうぜー」
たっちゃんに走り寄りながらノリ良く挨拶してきた二人組の男たちは、たっちゃんと同じクラスなんだろう。
「悪い。俺、今日は優陽と登校してるから。また後でな」
たっちゃんが笑顔できっぱり断ると、二人の視線はたっちゃんの隣に居る僕に向けられた。
「うっわ。陰キャ丸出し」
「だっせー」
いささか失礼すぎる嘲りを含んだ感想を僕にぶつけられた。
こんな扱いに慣れている僕は見下されても何とも思わないけど、たっちゃんの評価が下がらないかそわそわしてしまう。
「――平気でそういうこと人に言えちゃうやつって神経疑うわ」
たっちゃんが真顔で言う。
温度のない冷たい声色だった。
たっちゃんは顔が整っているだけに感情を消失させれば、表現し難い迫力がある。
たっちゃんのクラスメイトの男たちは、たっちゃんを怒らせた自覚はあるのか恐れを成したように凍りついていた。
「悪い、七嶋。俺たち調子に乗ったわ。先に行ってる」
「ごめん。後で教室でな」
二人は引きつった声で口々にたっちゃんに伝えると、速い足取りで昇降口の中へと消えて行った。
「謝る相手が違うよな。悪かった、優陽」
たっちゃんがばつが悪そうな顔で僕に謝ってくる。
「僕はこんな扱い慣れてるから気にしなくていいよ」
「慣れなくていいんだよ。自分に反撃してこなさそうな人を軽視する発言がいやだ」
「それより、同じクラスの友だちだよね? たっちゃんはいいの?」
「これで離れていくような友だちならいらねぇわ」
たっちゃんは何らうろたえることもなく言った。
たっちゃんの真っ直ぐなぶれない男気はかっこいい。
「僕はいい子たちだと思ったけど……」
「はあ?」
たっちゃんは目を白黒させながら、素っ頓狂な声を出した。
僕が何を言っているのかわからないって顔に書いてある。
「もちろん僕に言ってきたことは良くないと思うけど」
「当たり前だろ」
「二人ともすぐに”ごめん”って言葉が出てきていたし、言い訳せずに自分の非を認めていたし」
「……」
「誰にだって間違いはあるんだから、反射的に素直に謝れる人って僕はいいと思うんだ」
そう答えたら、たっちゃんが急に横から勢いよく僕を抱き締めてきた。
僕を包むシトラスの香り。
「ちょっと……」
「ほんっと優陽、好きだわ」
僕を抱え寄せながら、たっちゃんが頭上でつぶやく。
登校時間の昇降口前で人が多いのに……。
たっちゃんの腕の隙間から薄っすら見えたけど、たっちゃんを見つめる女子たちが色めいていた。
僕みたいな地味なガリ勉眼鏡が近くに居たら、たっちゃんのファンに恨まれてしまう。
「たっちゃん、暑い」
「悪い。優陽がかわいかったから」
僕から離れたたっちゃんはもう怒りの感情がしまわれていてホッとした。
「俺、優陽が教えてくれたおかげでテストの1日目2日目、結構手ごたえあるんだよな」
「それなら良かった」
「返却されないとわからないけど。今回は父さんと母さんに『優陽を見習え』攻撃されなくて済むかも」
たっちゃんと横並びで歩いて昇降口に入る。
今の場面を琉唯に見られていたなんて、この時の僕は知るよしもなかった。