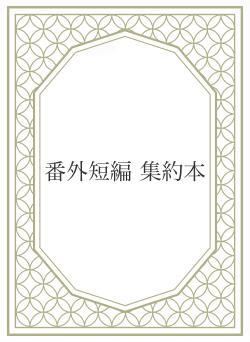琉唯は棚から1冊のノートを取り出して、持ってきた。
そのノートの表紙を見ると№11と書かれている。
映像研究部の11冊目の部内の記録ノート。
琉唯は僕の隣に腰を落とすと、そのノートを渡してきた。
「普通にこのノートも映画の感想が書かれていたり、映画の構想が練られていて、読んでいるだけで面白い。けど、最後から2番目のページ開いて」
「最後から2番目?」
言われたとおりにノートを後ろからめくる。
日記のように日付と名前と映画の感想が様々な筆跡で書かれていた。
その中で右ページの端の下側に明らかに違う文言。
他の文字はシャーペンで書かれているのに、これだけ黒のサインペンのようなものでノートの罫線を無視して書かれていた。
いうなれば落書きやいたずら書きの類のもの。
時系列に沿って書かれたのではなく、後から追記されたような感じだ。
――いずみ先輩、大好き。直子
僕はその丸みを帯びた文字を見た途端に凍りついてしまった。
「これだけ何か浮いてて、気になった」
琉唯の言葉が両耳を通り過ぎる。
琉唯は気がついていない。
それはそうだ。
咲良菜緒が映像研究部に所属していたことも咲良菜緒の本名も知らない。
咲良菜緒は華澄高に”芸名”で通っていた。
この文字を書いたのは間違いなく僕のお母さんだ。
この筆跡には見覚えがある。
咲良菜緒の世間に公表していない本名は――桜庭直子。
そして、いずみ先輩って……。
宮永さんの下の名前は泉。
やっぱり美織さんたちが言っていたように咲良菜緒が好きだったのは宮永さんだ。
事務所の先輩だから、”いずみ先輩”って呼んでいたのか。
「優陽、どうした? 顔色が悪い。まだ寒いか?」
「ううん、平気」
僕はノートを閉じて丸テーブルの上に置いた。
冷たい汗が背中を滑り落ちる。
あの文字を目に留めた途端、文字から流れ込むように僕へと伝わってきた。
女優の顔とは違う一人の女子高生としての咲良菜緒の無邪気な恋心。
「――なぁ、優陽」
「……」
僕の顎を長い指先で掴み、自分のほうへと向けさせてくる琉唯。
熱と憂いが混在した琉唯の瞳が僕を捕らえて、胸の奥で何かが疼き出した。
「俺と優陽が初めて咲き誇る夜桜の下で会った日を覚えてるか?」
「覚えてるけど……」
「あの時、何で優陽は泣いてた?」
静かに息を呑む。
まるで琉唯の真剣な視線に拘束されているかのようだ。
「優陽が余り自分のことを話すタイプじゃないのはわかってるし」
「……」
「自己評価が低すぎるのも何でなのか気になるし」
「……」
「優陽っていつもどこか儚げで、優陽の全てを知りたくてどうしようもなくなる」
そこで言葉が切れて、重量さえ感じる静寂が琉唯と僕を包む。
琉唯は僕から目を離さなくて、僕も身動きひとつとれなくて……。
琉唯は僕の母親が咲良菜緒だとは知らない。
泣いてた理由なんて言えるわけがない。
――僕の全てを知りたいなんて。好きだとは言われていないけど、まるで告白されているみたいだ……。
でも、琉唯が好きなのは僕じゃない。
咲良菜緒だ。
一条琉唯が高度な演技力を伴った名実ともに若手№1と呼ばれる俳優だからだろうか。
余計に僕に言われていると勘違いしそうになってしまう。
やけに遠くで予鈴のチャイムが響き渡った。
「授業に遅れちゃうから、もう戻ろう」
立ち上がって荷物をまとめる僕にはぐらかされたと琉唯は思っただろうか。
「――ん。そうだな」
傷ついたような表情を覗かせた琉唯に罪悪感が募る。
僕が琉唯に答えられることなんて何もない。
琉唯が興味あるのは僕じゃなくて咲良菜緒だ。
琉唯にこんなに求められる咲良菜緒がどうしようもなく羨ましい。
――僕は咲良菜緒に嫉妬しているのか。
自覚できた感情が苦しくてたまらなかった。
そのノートの表紙を見ると№11と書かれている。
映像研究部の11冊目の部内の記録ノート。
琉唯は僕の隣に腰を落とすと、そのノートを渡してきた。
「普通にこのノートも映画の感想が書かれていたり、映画の構想が練られていて、読んでいるだけで面白い。けど、最後から2番目のページ開いて」
「最後から2番目?」
言われたとおりにノートを後ろからめくる。
日記のように日付と名前と映画の感想が様々な筆跡で書かれていた。
その中で右ページの端の下側に明らかに違う文言。
他の文字はシャーペンで書かれているのに、これだけ黒のサインペンのようなものでノートの罫線を無視して書かれていた。
いうなれば落書きやいたずら書きの類のもの。
時系列に沿って書かれたのではなく、後から追記されたような感じだ。
――いずみ先輩、大好き。直子
僕はその丸みを帯びた文字を見た途端に凍りついてしまった。
「これだけ何か浮いてて、気になった」
琉唯の言葉が両耳を通り過ぎる。
琉唯は気がついていない。
それはそうだ。
咲良菜緒が映像研究部に所属していたことも咲良菜緒の本名も知らない。
咲良菜緒は華澄高に”芸名”で通っていた。
この文字を書いたのは間違いなく僕のお母さんだ。
この筆跡には見覚えがある。
咲良菜緒の世間に公表していない本名は――桜庭直子。
そして、いずみ先輩って……。
宮永さんの下の名前は泉。
やっぱり美織さんたちが言っていたように咲良菜緒が好きだったのは宮永さんだ。
事務所の先輩だから、”いずみ先輩”って呼んでいたのか。
「優陽、どうした? 顔色が悪い。まだ寒いか?」
「ううん、平気」
僕はノートを閉じて丸テーブルの上に置いた。
冷たい汗が背中を滑り落ちる。
あの文字を目に留めた途端、文字から流れ込むように僕へと伝わってきた。
女優の顔とは違う一人の女子高生としての咲良菜緒の無邪気な恋心。
「――なぁ、優陽」
「……」
僕の顎を長い指先で掴み、自分のほうへと向けさせてくる琉唯。
熱と憂いが混在した琉唯の瞳が僕を捕らえて、胸の奥で何かが疼き出した。
「俺と優陽が初めて咲き誇る夜桜の下で会った日を覚えてるか?」
「覚えてるけど……」
「あの時、何で優陽は泣いてた?」
静かに息を呑む。
まるで琉唯の真剣な視線に拘束されているかのようだ。
「優陽が余り自分のことを話すタイプじゃないのはわかってるし」
「……」
「自己評価が低すぎるのも何でなのか気になるし」
「……」
「優陽っていつもどこか儚げで、優陽の全てを知りたくてどうしようもなくなる」
そこで言葉が切れて、重量さえ感じる静寂が琉唯と僕を包む。
琉唯は僕から目を離さなくて、僕も身動きひとつとれなくて……。
琉唯は僕の母親が咲良菜緒だとは知らない。
泣いてた理由なんて言えるわけがない。
――僕の全てを知りたいなんて。好きだとは言われていないけど、まるで告白されているみたいだ……。
でも、琉唯が好きなのは僕じゃない。
咲良菜緒だ。
一条琉唯が高度な演技力を伴った名実ともに若手№1と呼ばれる俳優だからだろうか。
余計に僕に言われていると勘違いしそうになってしまう。
やけに遠くで予鈴のチャイムが響き渡った。
「授業に遅れちゃうから、もう戻ろう」
立ち上がって荷物をまとめる僕にはぐらかされたと琉唯は思っただろうか。
「――ん。そうだな」
傷ついたような表情を覗かせた琉唯に罪悪感が募る。
僕が琉唯に答えられることなんて何もない。
琉唯が興味あるのは僕じゃなくて咲良菜緒だ。
琉唯にこんなに求められる咲良菜緒がどうしようもなく羨ましい。
――僕は咲良菜緒に嫉妬しているのか。
自覚できた感情が苦しくてたまらなかった。