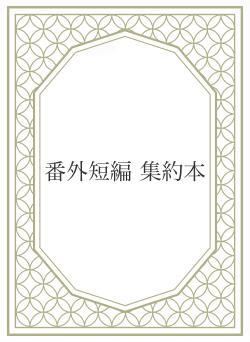***
週末はほとんど期末考査の勉強に費やした。
土日両方とも夜はたっちゃんとダイニングテーブルで頭をくっつけて勉強をした。
二人とも終わったらすぐに眠れるようにラウンジウェア姿なものの、お風呂で心身ともにリラックスしたからか、たっちゃんはすぐに舟をこぎ始める。
「もうちょっと頑張ろう」
「ん。部活ハードだったからもう眠い」
言葉だと起きないから、眠りの世界に旅立ちそうになるたびに、たっちゃんの高い鼻をつまんで起こした。
週明けは朝から気温が上昇し、徒歩で華澄高に到着する頃には身体が汗ばんでいた。
まだ8時なのに、夏の太陽の威力はすさまじい。
けれど、僕は顔に汗を余りかかなかった。
これは芸能界にとっては重宝される体質だ。
がんがん照明が照りつけて熱くなるセット内でも、汗だくにならず化粧落ちも少ない。
咲良菜緒も顔面に汗をかくタイプではなかったと聞いた。
遺伝で僕に咲良菜緒から受け継がれている。
僕は芸能界に関係ないから、活かせる場がないのだけれど。
「――優陽。寒い?」
「え?」
お昼休みは相変わらず琉唯と映像研究部の部室に来ていた。
お弁当を食べている僕と期末考査のために先に勉強を始めている琉唯。
いつの間にか隣から僕に視線を注がれていた。
「腕、鳥肌たってる」
「カーディガン、教室に忘れてきちゃって」
華澄高校はどこも空調が利いている。
ゆえに校内では少し肌寒く感じる時もあった。
特にアネックス館は本館と比べて施設が新しい分、性能も上手なのか空調の利きが良い。
どの生徒も左胸に校章刺繍入りの紺色のカーディガンを夏季でも常備していて冷房対策していた。
4時間目が体育だったから体操服から制服に着替えて、カーディガンを羽織らずに映像研究部の部室に来てしまった。
教室にカーディガンだけ取りに戻るのも少し遠いし億劫。
全館空調だから部室だけで温度を調節できないし、身体は冷える。
おかずを口に運びながら葛藤していた時に琉唯から指摘を受けた。
「優陽、おいで」
「……おいでって何?」
「いい。俺から行く」
琉唯は僕に近づくと、僕の身体を両足で挟むように座ってきた。
後ろから琉唯に包み込まれるように両腕で抱き締められる。
「ちょっと、琉唯」
「優陽。少しは温まった?」
「これじゃお弁当食べられないよ」
「優陽は俺を気にせず、食べていればいい」
気にするって!
ソファーに座ったまま、僕は背後から回された琉唯の腕の中におさまってしまう。
肩に乗せられた琉唯の顎。
近すぎるくらいそばに琉唯の顔があって……。
寒かったはずの僕は頭のてっぺんから足の指先まで一気に熱くなった。
「気にしないなんて無理」
「優陽。俺を意識してる?」
耳元で琉唯の魅力的な低音ボイスで話されてたら意識しないなんて誰が出来るのだろう。
布を隔てているとはいえ、琉唯の腕や胸板が鍛えられているとわかる。
琉唯からの問いかけには答えず、そのままの姿勢でお弁当を食べていたけど、味を感じている余裕はなくなってしまった。
美織さんのお弁当どれも美味しいのに……。
「もう大丈夫だから、離れてよ」
からになったお弁当箱を包んでから、僕は琉唯との距離をとろうと身をよじる。
「優陽は寒いんだろ。無理しなくていいって」
「もう寒くないよ」
男同士でこんなに密着して過ごすのは不自然じゃないんだろうか。
僕には男友達って居たことがないから、一般常識的な感覚がよくわからない。
そもそも琉唯は僕の友だち?
友だちって表現は何だかしっくりこない。
琉唯にとって、敬愛している咲良菜緒に似ているから僕に構っているってだけ……。
わかっていたはずなのに、どうしてこんなに胸が苦しいと主張してくるんだろう。
「俺が寒いから、このままでいろよ」
「琉唯はカーディガン着てる。それに僕は湯たんぽじゃない」
「――たまに、いつまで気を張っていればいいのかわからなくなる」
「……」
「少しでいいから、このままでいさせて」
琉唯は僕に回す腕の力を強めた代わりに、声は少し弱々しくなった。
芸能界の一線で目覚ましい活躍をしている琉唯だけれど、きっと光がたくさん当たっている分だけ大きな影も出来るのだろう。
不安に駆られることも、自信が揺らぐ時もあるだろうし、走り続けるには休息だって必要だ。
琉唯の知らないところで滝川社長も宮永さんも琉唯のことを褒めてたよ。
二人とも数えきることが出来ないほどの俳優や俳優志望の人間を見てきているはずで審美眼は確か。
それは聞いた情報を僕が漏らさないと宮永さんが滝川社長に伝えてくれていたから琉唯には言わずに、しばらくそのままにされていた。
「そういえば、映像研究部の記録ノート。1冊ずつ持ち帰って合間に読み進めていたんだけど」
琉唯は冷静さを取り戻したのか自ら話を切り替え、僕から離れて立ち上がった。
琉唯の体温が遠ざかった感覚。
僕から何かが欠けたように物足りなくなった。
週末はほとんど期末考査の勉強に費やした。
土日両方とも夜はたっちゃんとダイニングテーブルで頭をくっつけて勉強をした。
二人とも終わったらすぐに眠れるようにラウンジウェア姿なものの、お風呂で心身ともにリラックスしたからか、たっちゃんはすぐに舟をこぎ始める。
「もうちょっと頑張ろう」
「ん。部活ハードだったからもう眠い」
言葉だと起きないから、眠りの世界に旅立ちそうになるたびに、たっちゃんの高い鼻をつまんで起こした。
週明けは朝から気温が上昇し、徒歩で華澄高に到着する頃には身体が汗ばんでいた。
まだ8時なのに、夏の太陽の威力はすさまじい。
けれど、僕は顔に汗を余りかかなかった。
これは芸能界にとっては重宝される体質だ。
がんがん照明が照りつけて熱くなるセット内でも、汗だくにならず化粧落ちも少ない。
咲良菜緒も顔面に汗をかくタイプではなかったと聞いた。
遺伝で僕に咲良菜緒から受け継がれている。
僕は芸能界に関係ないから、活かせる場がないのだけれど。
「――優陽。寒い?」
「え?」
お昼休みは相変わらず琉唯と映像研究部の部室に来ていた。
お弁当を食べている僕と期末考査のために先に勉強を始めている琉唯。
いつの間にか隣から僕に視線を注がれていた。
「腕、鳥肌たってる」
「カーディガン、教室に忘れてきちゃって」
華澄高校はどこも空調が利いている。
ゆえに校内では少し肌寒く感じる時もあった。
特にアネックス館は本館と比べて施設が新しい分、性能も上手なのか空調の利きが良い。
どの生徒も左胸に校章刺繍入りの紺色のカーディガンを夏季でも常備していて冷房対策していた。
4時間目が体育だったから体操服から制服に着替えて、カーディガンを羽織らずに映像研究部の部室に来てしまった。
教室にカーディガンだけ取りに戻るのも少し遠いし億劫。
全館空調だから部室だけで温度を調節できないし、身体は冷える。
おかずを口に運びながら葛藤していた時に琉唯から指摘を受けた。
「優陽、おいで」
「……おいでって何?」
「いい。俺から行く」
琉唯は僕に近づくと、僕の身体を両足で挟むように座ってきた。
後ろから琉唯に包み込まれるように両腕で抱き締められる。
「ちょっと、琉唯」
「優陽。少しは温まった?」
「これじゃお弁当食べられないよ」
「優陽は俺を気にせず、食べていればいい」
気にするって!
ソファーに座ったまま、僕は背後から回された琉唯の腕の中におさまってしまう。
肩に乗せられた琉唯の顎。
近すぎるくらいそばに琉唯の顔があって……。
寒かったはずの僕は頭のてっぺんから足の指先まで一気に熱くなった。
「気にしないなんて無理」
「優陽。俺を意識してる?」
耳元で琉唯の魅力的な低音ボイスで話されてたら意識しないなんて誰が出来るのだろう。
布を隔てているとはいえ、琉唯の腕や胸板が鍛えられているとわかる。
琉唯からの問いかけには答えず、そのままの姿勢でお弁当を食べていたけど、味を感じている余裕はなくなってしまった。
美織さんのお弁当どれも美味しいのに……。
「もう大丈夫だから、離れてよ」
からになったお弁当箱を包んでから、僕は琉唯との距離をとろうと身をよじる。
「優陽は寒いんだろ。無理しなくていいって」
「もう寒くないよ」
男同士でこんなに密着して過ごすのは不自然じゃないんだろうか。
僕には男友達って居たことがないから、一般常識的な感覚がよくわからない。
そもそも琉唯は僕の友だち?
友だちって表現は何だかしっくりこない。
琉唯にとって、敬愛している咲良菜緒に似ているから僕に構っているってだけ……。
わかっていたはずなのに、どうしてこんなに胸が苦しいと主張してくるんだろう。
「俺が寒いから、このままでいろよ」
「琉唯はカーディガン着てる。それに僕は湯たんぽじゃない」
「――たまに、いつまで気を張っていればいいのかわからなくなる」
「……」
「少しでいいから、このままでいさせて」
琉唯は僕に回す腕の力を強めた代わりに、声は少し弱々しくなった。
芸能界の一線で目覚ましい活躍をしている琉唯だけれど、きっと光がたくさん当たっている分だけ大きな影も出来るのだろう。
不安に駆られることも、自信が揺らぐ時もあるだろうし、走り続けるには休息だって必要だ。
琉唯の知らないところで滝川社長も宮永さんも琉唯のことを褒めてたよ。
二人とも数えきることが出来ないほどの俳優や俳優志望の人間を見てきているはずで審美眼は確か。
それは聞いた情報を僕が漏らさないと宮永さんが滝川社長に伝えてくれていたから琉唯には言わずに、しばらくそのままにされていた。
「そういえば、映像研究部の記録ノート。1冊ずつ持ち帰って合間に読み進めていたんだけど」
琉唯は冷静さを取り戻したのか自ら話を切り替え、僕から離れて立ち上がった。
琉唯の体温が遠ざかった感覚。
僕から何かが欠けたように物足りなくなった。