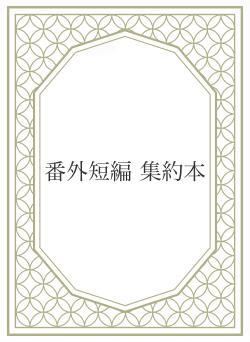***
――金曜日の夜。
僕は宮永さんにディナーに誘われていた。
宮永さんも名と顔が知られている芸能人とだけあって、いつも外食は隠れ家と呼ばれる個室がしっかりしたレストランが多い。
今回もセブファクの事務所から程近い雑居ビルの7階に入った和風モダンの創作料理屋さん。
電球色のペンダントライトが温かみのあるリラックスした空間を演出してくれている。
こうして宮永さんはご飯に連れ出してくれることが定期的にあった。
放課後は仕事で琉唯が映像研究部の部室に来られないこともわかっていたから、僕もすぐに七嶋家に帰って私服に着替えてから宮永さんに会っていた。
「どれも、すごく美味しい」
「良かった。優陽はこれが食べたいってリクエストしてこないから、笑顔を見られてホッとするよ」
対面に座る宮永さんの笑顔は今日も優しい。
「僕、好き嫌いないから……」
正確には好き嫌いを無くした。
本当の家族じゃない僕を育ててくれている美織さんに申し訳なくて、物心がついた時には出されたものは全部完食しなくちゃって思ってた。
ブロッコリーの歯応え、玉ねぎの酸味、ピーマンの苦味、魚のくさみ、いろいろ苦手なものはある。
食べているうちに、平気になっていっただけ。
『げー。にんじん食べたくないっ! 毎日ハンバーグにしてよ』
『侑は好き嫌いが多すぎ。優陽を見習いなさい』
素直に美織さんに気持ちを伝えられるたっちゃんがうらやましかった。
「もっと優陽は意思表示してもいいんだよ」
「うん。でも宮永さんが選んでくれたお店に連れてきてもらえるだけで嬉しいんだ」
「そうか」
自分が何を食べたいのか、特にこだわりもない。
食べたいものだけじゃなく、どんなことでも自分から何かを選ばなくても誰かに選んでもらったもので僕は良かった。
「優陽は来月夏休みか?」
「うん。予定は何もないけどね。その前に1学期の期末考査があるけれど。あ、宮永さんに誕生日にもらったシャーペンがすごく使いやすくて、勉強がはかどってる。ありがとう」
「それなら良かった」
宮永さんの笑顔には相手を安心させるパワーが宿っているのか、ほっと安心できる。
咲良菜緒も宮永さんに対してそんな風に思っていたのだろうか?
それとも……。
『優陽くんの父親って宮永さんじゃないかしら……』
そう美織さんたちに思われるくらい、もっと別の何かがあったのかな?
宮永さんは独身で過去に結婚歴もないと聞く。
もしかしたら宮永さんは僕の父親かもしれない。
いったん考えてしまうと、どんな風に僕は宮永さんに懐いていたのかわからなくなってしまう。
でも、宮永さんへの接し方が不自然にならないよう気を付けていた。
いろいろ話しながら食べているうちにお腹が膨らんでいく。
「優陽は華澄高では映像研究部に入部してるんだっけ?」
「うん、部員は僕ひとりだけだけど……」
そう答えながらも琉唯の顔が過ぎる。
琉唯は部員じゃないし、映像研究部の部室に来ていることは秘密だけれど。
「やっぱり親子だな」
「え?」
「菜緒も入部してただろ。映像研究部」
お猪口を片手に持つ宮永さんにそう言われて、僕は石化したように動きが止まってしまった。
宮永さんはそんな僕の様子を気に留める。
「優陽は知らなかった?」
「初めて聞いたよ」
「確か菜緒本人が僕に映像研究部って言ってたよ。でも、菜緒は忙しくてほとんど部活は出られていないんじゃないかな。学校の出席日数もギリギリで卒業していたし。それに菜緒は部活動で制作する映画には出演禁止って頼さんに言われてた」
昔の映像研究部は部員が多く、自分たちで映画を創ったりしていたはずだ。
その頃に咲良菜緒も部員だったのか。
宮永さんがお手洗いでいったん退室してからも偶然の一致に驚いていた。
あの部室に……、今では琉唯と時間を共有することが増えた映像研究部の部室に咲良菜緒も居たのだろうか?
一人で宮永さんを待っていたら、僕のLINEにメッセージが入る。
[優陽、眼鏡かけたままだよな? そのまま外さないで]
宮永さんからのメッセージを疑問に思っていると、戻ってきた宮永さんはもう一人別の誰かを連れていた。
「たまたま遭遇して僕らの仕事上、立ち話しているわけにもいかないんで、連れてきた。少しだけ話していてもいい?」
「……うん、もちろん」
宮永さんが自分の隣に座るように促したのは仕立ての良いスーツを着こなした40代前後の男の人。
顔にしわは刻まれているけれど、彫りの深い整った顔立ちをしている。
頼政さんとはまた別の威圧感をまとっていた。
「こちらはシムプロダクションの社長の滝川大地さん。滝川さん、この子は僕が産まれた時から息子同様にかわいがっていて、ここで聞いた情報を漏らすような子じゃないって僕が保証するから安心してくれていい」
――金曜日の夜。
僕は宮永さんにディナーに誘われていた。
宮永さんも名と顔が知られている芸能人とだけあって、いつも外食は隠れ家と呼ばれる個室がしっかりしたレストランが多い。
今回もセブファクの事務所から程近い雑居ビルの7階に入った和風モダンの創作料理屋さん。
電球色のペンダントライトが温かみのあるリラックスした空間を演出してくれている。
こうして宮永さんはご飯に連れ出してくれることが定期的にあった。
放課後は仕事で琉唯が映像研究部の部室に来られないこともわかっていたから、僕もすぐに七嶋家に帰って私服に着替えてから宮永さんに会っていた。
「どれも、すごく美味しい」
「良かった。優陽はこれが食べたいってリクエストしてこないから、笑顔を見られてホッとするよ」
対面に座る宮永さんの笑顔は今日も優しい。
「僕、好き嫌いないから……」
正確には好き嫌いを無くした。
本当の家族じゃない僕を育ててくれている美織さんに申し訳なくて、物心がついた時には出されたものは全部完食しなくちゃって思ってた。
ブロッコリーの歯応え、玉ねぎの酸味、ピーマンの苦味、魚のくさみ、いろいろ苦手なものはある。
食べているうちに、平気になっていっただけ。
『げー。にんじん食べたくないっ! 毎日ハンバーグにしてよ』
『侑は好き嫌いが多すぎ。優陽を見習いなさい』
素直に美織さんに気持ちを伝えられるたっちゃんがうらやましかった。
「もっと優陽は意思表示してもいいんだよ」
「うん。でも宮永さんが選んでくれたお店に連れてきてもらえるだけで嬉しいんだ」
「そうか」
自分が何を食べたいのか、特にこだわりもない。
食べたいものだけじゃなく、どんなことでも自分から何かを選ばなくても誰かに選んでもらったもので僕は良かった。
「優陽は来月夏休みか?」
「うん。予定は何もないけどね。その前に1学期の期末考査があるけれど。あ、宮永さんに誕生日にもらったシャーペンがすごく使いやすくて、勉強がはかどってる。ありがとう」
「それなら良かった」
宮永さんの笑顔には相手を安心させるパワーが宿っているのか、ほっと安心できる。
咲良菜緒も宮永さんに対してそんな風に思っていたのだろうか?
それとも……。
『優陽くんの父親って宮永さんじゃないかしら……』
そう美織さんたちに思われるくらい、もっと別の何かがあったのかな?
宮永さんは独身で過去に結婚歴もないと聞く。
もしかしたら宮永さんは僕の父親かもしれない。
いったん考えてしまうと、どんな風に僕は宮永さんに懐いていたのかわからなくなってしまう。
でも、宮永さんへの接し方が不自然にならないよう気を付けていた。
いろいろ話しながら食べているうちにお腹が膨らんでいく。
「優陽は華澄高では映像研究部に入部してるんだっけ?」
「うん、部員は僕ひとりだけだけど……」
そう答えながらも琉唯の顔が過ぎる。
琉唯は部員じゃないし、映像研究部の部室に来ていることは秘密だけれど。
「やっぱり親子だな」
「え?」
「菜緒も入部してただろ。映像研究部」
お猪口を片手に持つ宮永さんにそう言われて、僕は石化したように動きが止まってしまった。
宮永さんはそんな僕の様子を気に留める。
「優陽は知らなかった?」
「初めて聞いたよ」
「確か菜緒本人が僕に映像研究部って言ってたよ。でも、菜緒は忙しくてほとんど部活は出られていないんじゃないかな。学校の出席日数もギリギリで卒業していたし。それに菜緒は部活動で制作する映画には出演禁止って頼さんに言われてた」
昔の映像研究部は部員が多く、自分たちで映画を創ったりしていたはずだ。
その頃に咲良菜緒も部員だったのか。
宮永さんがお手洗いでいったん退室してからも偶然の一致に驚いていた。
あの部室に……、今では琉唯と時間を共有することが増えた映像研究部の部室に咲良菜緒も居たのだろうか?
一人で宮永さんを待っていたら、僕のLINEにメッセージが入る。
[優陽、眼鏡かけたままだよな? そのまま外さないで]
宮永さんからのメッセージを疑問に思っていると、戻ってきた宮永さんはもう一人別の誰かを連れていた。
「たまたま遭遇して僕らの仕事上、立ち話しているわけにもいかないんで、連れてきた。少しだけ話していてもいい?」
「……うん、もちろん」
宮永さんが自分の隣に座るように促したのは仕立ての良いスーツを着こなした40代前後の男の人。
顔にしわは刻まれているけれど、彫りの深い整った顔立ちをしている。
頼政さんとはまた別の威圧感をまとっていた。
「こちらはシムプロダクションの社長の滝川大地さん。滝川さん、この子は僕が産まれた時から息子同様にかわいがっていて、ここで聞いた情報を漏らすような子じゃないって僕が保証するから安心してくれていい」