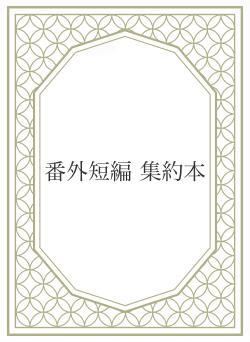***
僕の誕生日は母の命日だ。
――3/31。
同じ学年で最後から2番目に誕生日を迎えるのが遅い、この日。
春休み中の、この日。
年度末の、この日。
僕は16歳になった。
この日、僕は部活で高校に来ていた。
春休み中だったから学校指定のジャージを着ていた。
そして、部活動中に部室で眠りこけたのだ。
戸締りを確認するため、見回りに来ていた用務員のおじさんに起こされ、僕は寝ぼけ眼のまま、昇降口から校舎の外に出た。
春分の日を超え、日が延びたとはいえ空は真っ暗。
そこには残り数日で満月になるであろう月が浮かんでいた。
見る者を誘い込むように妖しく輝いている。
辺りを見回すまでもなく、運動部の生徒さえ一人も姿が見えない。
普段の賑やかな校内を知っているからこそ、暗さもあって心細さが僕を襲う。
――たっちゃんも、もう帰ったよね……?
花冷えする夜風に身震いしながら校門を目指す。
校舎から校門までの通りの両端には等間隔で桜の木が植えられている。
冬の厳しい寒さを越えた桜は満開だった。
外灯に照らされ、夜桜はしっとりと、しとやかに、咲き誇っている。
直に儚く散ると知りながら……。
僕は一本の桜の木の前で立ち止まった。
太い幹に両手を添える。
気のせいだとわかっていながら心臓のようにドクドクと命が鼓動する音が手のひらから伝わってくるような気がした。
そのまま目線を上昇させていく。
枝を淡く彩るように幾つも幾つも咲いている桜の花。
夜でも桃色の明かりを灯したように明るく見える。
――きれいだ……。
何でこんなに桜を見つめているだけで、胸が苦しくなるのか。
切なくなるのか。
無性に泣きたくなる……と思った時には、はらはらと涙が溢れていた。
分厚いレンズの大きな眼鏡を外し、桜の木を見上げたまま、ぬぐうこともせず涙が頬を伝い続ける。
――お母さん。僕、16歳になったよ。
――僕が生まれてきちゃって、ごめんなさい……。
――みんな僕よりもお母さんが生きていてくれたほうが良かったはずなのに……。
「っ……」
16年前の今日、僕は産まれ、お母さんは死んだ……。
逆だったら良かったのにといつも思ってた。
思いながら16歳になった。
「うぅっ……」
僕の誕生日なんかなくたっていいのに……。
どれほど夜桜の下で涙を流し続けたのか、ふっと何か視線を感じて、目線の先を移行する。
そこには数メートル離れた先、この高校の制服を着た長身の男が立っていた。
僕のほうを切れ長の目で見据えて……。
神様が慎重に精巧に丹念に造り上げたような美しい顔は衝撃を受けたように驚きを現していた。
――この人、同じ学年の芸術総合コースの人気俳優 一条 琉唯だ。
演じる役によって変化する髪型は今はハニーブロンドの癖のないサラサラヘアーで、それが無理なく似合ってしまうほど、端正な面立ちにスマートな体軀。
やがて、黙って僕を見ていた彼の薄い唇が言葉を発した。
「――嘘だろ。咲良菜緒が居る……」
僕の誕生日は母の命日だ。
――3/31。
同じ学年で最後から2番目に誕生日を迎えるのが遅い、この日。
春休み中の、この日。
年度末の、この日。
僕は16歳になった。
この日、僕は部活で高校に来ていた。
春休み中だったから学校指定のジャージを着ていた。
そして、部活動中に部室で眠りこけたのだ。
戸締りを確認するため、見回りに来ていた用務員のおじさんに起こされ、僕は寝ぼけ眼のまま、昇降口から校舎の外に出た。
春分の日を超え、日が延びたとはいえ空は真っ暗。
そこには残り数日で満月になるであろう月が浮かんでいた。
見る者を誘い込むように妖しく輝いている。
辺りを見回すまでもなく、運動部の生徒さえ一人も姿が見えない。
普段の賑やかな校内を知っているからこそ、暗さもあって心細さが僕を襲う。
――たっちゃんも、もう帰ったよね……?
花冷えする夜風に身震いしながら校門を目指す。
校舎から校門までの通りの両端には等間隔で桜の木が植えられている。
冬の厳しい寒さを越えた桜は満開だった。
外灯に照らされ、夜桜はしっとりと、しとやかに、咲き誇っている。
直に儚く散ると知りながら……。
僕は一本の桜の木の前で立ち止まった。
太い幹に両手を添える。
気のせいだとわかっていながら心臓のようにドクドクと命が鼓動する音が手のひらから伝わってくるような気がした。
そのまま目線を上昇させていく。
枝を淡く彩るように幾つも幾つも咲いている桜の花。
夜でも桃色の明かりを灯したように明るく見える。
――きれいだ……。
何でこんなに桜を見つめているだけで、胸が苦しくなるのか。
切なくなるのか。
無性に泣きたくなる……と思った時には、はらはらと涙が溢れていた。
分厚いレンズの大きな眼鏡を外し、桜の木を見上げたまま、ぬぐうこともせず涙が頬を伝い続ける。
――お母さん。僕、16歳になったよ。
――僕が生まれてきちゃって、ごめんなさい……。
――みんな僕よりもお母さんが生きていてくれたほうが良かったはずなのに……。
「っ……」
16年前の今日、僕は産まれ、お母さんは死んだ……。
逆だったら良かったのにといつも思ってた。
思いながら16歳になった。
「うぅっ……」
僕の誕生日なんかなくたっていいのに……。
どれほど夜桜の下で涙を流し続けたのか、ふっと何か視線を感じて、目線の先を移行する。
そこには数メートル離れた先、この高校の制服を着た長身の男が立っていた。
僕のほうを切れ長の目で見据えて……。
神様が慎重に精巧に丹念に造り上げたような美しい顔は衝撃を受けたように驚きを現していた。
――この人、同じ学年の芸術総合コースの人気俳優 一条 琉唯だ。
演じる役によって変化する髪型は今はハニーブロンドの癖のないサラサラヘアーで、それが無理なく似合ってしまうほど、端正な面立ちにスマートな体軀。
やがて、黙って僕を見ていた彼の薄い唇が言葉を発した。
「――嘘だろ。咲良菜緒が居る……」