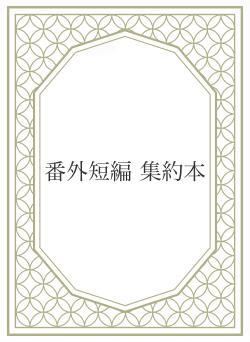***
暦の上では夏至が過ぎていた。
華澄高の制服は男女ともに夏は白か紺の半袖ポロシャツになる。
何となく男子は白を選ぶ人が多いけれど、女子は紺が多い印象だ。
平均気温が過去最高だと毎年ニュースで聞いているような気がしているけれど、今年も例外ではなく蒸し暑い日が多い。
僕と若手№1俳優、一条琉唯との誰にも知られない映像研究部室での密会は続いていた。
売れっ子の琉唯は高校生でありながら、とにかく忙しい。
琉唯本人は、
「アイドル活動してる奴のほうが忙しいって。あいつら本当にスケジュール異常」
と言っていたけど。
まだ情報解禁になっていない映画の撮影に入っていて、並行してCMや雑誌の撮影やインタビュー、アンバサダーを務めるブランドのファッションショーへの参加など学校を休む日も多いし、放課後なんて数えられるほどしか部室に来ていない。
部室に来ても疲れているのか、たまにソファーで寝てしまうことだってある。
学生の本分は勉強にあるなんて言われているけれど、琉唯の場合は完全に本分が仕事になっていた。
それでも同じ時間を過ごすたびに、ひとつずつ知っていった琉唯のこと。
5月下旬の中間考査前は琉唯と一緒に勉強をしていて、琉唯に質問された問題を教えたりしていた。
「優陽。教えるのうまい。わかりやすい。ありがとう」
琉唯は中間考査の結果が今までで一番良かったらしく機嫌が良かった。
僕は今回のテストも学年で1番を明け渡さなかった。
「何で優陽はこんなに勉強頑張れんの? 尊敬しかない」
琉唯にそう問われた時、僕は褒められた喜びよりも打ち沈んでしまった。
僕が勉強を頑張るのは、産まれた時から僕を育ててくれている七嶋家の足を引っ張らないためだ。
もちろん頼政さんも美織さんも、たっちゃんもそんなこと気にするような人たちじゃないけれど、出来る限り迷惑をかけない僕でいたいだけ。
いつだって価値があるのは咲良菜緒で、価値がないのは僕。
強い意志で学びたいものがあるわけでもなく、夢や目標を設定できているわけでもなく、将来は安定した堅い仕事に就いて、七嶋家に恩返ししたいだけ。
琉唯に尊敬してもらえるなんてもってのほかだ。
「――最近、雨が多いよな」
今日の昼休みは琉唯と7月上旬に行われる1学期の期末考査に向けて一緒に勉強をしていた。
窓の外には空から落下していく細かい雨と灰色の世界が広がっている。
この間、中間考査が終わったばかりだと思ったら、もう期末考査の準備だ。
こうやって目的もないまま目の前のことに追い立てられ続けて、僕の行きつく先には何があるというのだろう。
「関東の梅雨明け、まだ発表されてないからね」
「俺、雨が続くの嫌い」
琉唯が参考書に突っ伏しながら、唇を尖らせた。
琉唯は僕の前ではやけに子どもっぽくなる。
芸能人として大衆向けに見せている琉唯の姿とのギャップにも慣れつつあった。
「僕も雨の日は荷物が増えるし、そんなに好きじゃなかったけど、雨のおかげでお気に入りの傘の出番がくるから嫌いじゃないよ。それにこの時期だと雨粒に濡れた紫陽花が綺麗だし」
ノートに文字を走らせながら答えると、琉唯からは何も返答がない。
無視された?
僕が顔を上げた途端、琉唯に頭を撫でられた。
「傘なんて蝶野さんから差し出されたビニ傘に入るだけで気にしたことなかった」
蝶野さんというのは琉唯のマネージャーだ。
よく学校まで琉唯を車で迎えに来ている。
姿かたちまでは僕が見たことはないし、どうやら男らしいということしか僕は知らない。
「あ、でも、ビニール傘って透明だから差しながら光や雨粒が弾けるのが透けて見えて面白いと思う」
「面白いのは優陽」
「ばかにした?」
「ううん。次に傘を差した時に俺も見てみる」
片手で頬杖をつき、もう片手で僕の髪へと指を絡めてくる琉唯。
「優陽は何から何まで綺麗だよな」
「いや、僕は男だし。全く綺麗なんかじゃないよ」
「男だからとか女だからとか関係ないって。優陽は綺麗だよ。人として」
誰よりも綺麗な琉唯が僕に綺麗だと言う。
それは僕が咲良菜緒に似ているからでしかないのに、ぎこちなく鼓動が乱された。
「優陽も昔から芸能界にスカウトされてきてるよな」
「一回もないよ」
「何で?」
「何でって普通の人は、そんな簡単にスカウトなんてされるものじゃないから」
「どう見たって優陽は普通の枠に収まってないだろ」
暦の上では夏至が過ぎていた。
華澄高の制服は男女ともに夏は白か紺の半袖ポロシャツになる。
何となく男子は白を選ぶ人が多いけれど、女子は紺が多い印象だ。
平均気温が過去最高だと毎年ニュースで聞いているような気がしているけれど、今年も例外ではなく蒸し暑い日が多い。
僕と若手№1俳優、一条琉唯との誰にも知られない映像研究部室での密会は続いていた。
売れっ子の琉唯は高校生でありながら、とにかく忙しい。
琉唯本人は、
「アイドル活動してる奴のほうが忙しいって。あいつら本当にスケジュール異常」
と言っていたけど。
まだ情報解禁になっていない映画の撮影に入っていて、並行してCMや雑誌の撮影やインタビュー、アンバサダーを務めるブランドのファッションショーへの参加など学校を休む日も多いし、放課後なんて数えられるほどしか部室に来ていない。
部室に来ても疲れているのか、たまにソファーで寝てしまうことだってある。
学生の本分は勉強にあるなんて言われているけれど、琉唯の場合は完全に本分が仕事になっていた。
それでも同じ時間を過ごすたびに、ひとつずつ知っていった琉唯のこと。
5月下旬の中間考査前は琉唯と一緒に勉強をしていて、琉唯に質問された問題を教えたりしていた。
「優陽。教えるのうまい。わかりやすい。ありがとう」
琉唯は中間考査の結果が今までで一番良かったらしく機嫌が良かった。
僕は今回のテストも学年で1番を明け渡さなかった。
「何で優陽はこんなに勉強頑張れんの? 尊敬しかない」
琉唯にそう問われた時、僕は褒められた喜びよりも打ち沈んでしまった。
僕が勉強を頑張るのは、産まれた時から僕を育ててくれている七嶋家の足を引っ張らないためだ。
もちろん頼政さんも美織さんも、たっちゃんもそんなこと気にするような人たちじゃないけれど、出来る限り迷惑をかけない僕でいたいだけ。
いつだって価値があるのは咲良菜緒で、価値がないのは僕。
強い意志で学びたいものがあるわけでもなく、夢や目標を設定できているわけでもなく、将来は安定した堅い仕事に就いて、七嶋家に恩返ししたいだけ。
琉唯に尊敬してもらえるなんてもってのほかだ。
「――最近、雨が多いよな」
今日の昼休みは琉唯と7月上旬に行われる1学期の期末考査に向けて一緒に勉強をしていた。
窓の外には空から落下していく細かい雨と灰色の世界が広がっている。
この間、中間考査が終わったばかりだと思ったら、もう期末考査の準備だ。
こうやって目的もないまま目の前のことに追い立てられ続けて、僕の行きつく先には何があるというのだろう。
「関東の梅雨明け、まだ発表されてないからね」
「俺、雨が続くの嫌い」
琉唯が参考書に突っ伏しながら、唇を尖らせた。
琉唯は僕の前ではやけに子どもっぽくなる。
芸能人として大衆向けに見せている琉唯の姿とのギャップにも慣れつつあった。
「僕も雨の日は荷物が増えるし、そんなに好きじゃなかったけど、雨のおかげでお気に入りの傘の出番がくるから嫌いじゃないよ。それにこの時期だと雨粒に濡れた紫陽花が綺麗だし」
ノートに文字を走らせながら答えると、琉唯からは何も返答がない。
無視された?
僕が顔を上げた途端、琉唯に頭を撫でられた。
「傘なんて蝶野さんから差し出されたビニ傘に入るだけで気にしたことなかった」
蝶野さんというのは琉唯のマネージャーだ。
よく学校まで琉唯を車で迎えに来ている。
姿かたちまでは僕が見たことはないし、どうやら男らしいということしか僕は知らない。
「あ、でも、ビニール傘って透明だから差しながら光や雨粒が弾けるのが透けて見えて面白いと思う」
「面白いのは優陽」
「ばかにした?」
「ううん。次に傘を差した時に俺も見てみる」
片手で頬杖をつき、もう片手で僕の髪へと指を絡めてくる琉唯。
「優陽は何から何まで綺麗だよな」
「いや、僕は男だし。全く綺麗なんかじゃないよ」
「男だからとか女だからとか関係ないって。優陽は綺麗だよ。人として」
誰よりも綺麗な琉唯が僕に綺麗だと言う。
それは僕が咲良菜緒に似ているからでしかないのに、ぎこちなく鼓動が乱された。
「優陽も昔から芸能界にスカウトされてきてるよな」
「一回もないよ」
「何で?」
「何でって普通の人は、そんな簡単にスカウトなんてされるものじゃないから」
「どう見たって優陽は普通の枠に収まってないだろ」