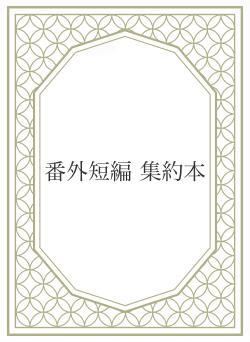「ありがとう、宮永さん」
今年50歳になる宮永泉さんは仕事が途切れない中堅俳優。
ずっとセブファクに所属しており、いかにも優しそうな風貌と口調だけれど、時にはヤクザの役だろうとこなしてしまう演技派だ。
今のセブファクでは一番の稼ぎ頭だと思う。
紙袋にはバターサンドや生チョコレートやポテトチップチョコレートなど北海道土産がぎっしり。
そして、誕生日プレゼントはスイスの高級筆記用具メーカーの1万円以上する高級シャープペンシルだった。
「こんな高いもの受け取れないよ」
「遠慮することないって。優陽は勉強頑張ってるって聞いてる。それに優陽は僕の子どもみたいなものだと思っているから」
宮永さんに穏やかに微笑まれ、言葉が詰まる。
僕も宮永さんには昔から父親のように懐いていた。
迫力があって緊張してしまう頼政さんより柔和な雰囲気の宮永さんのほうが親しみやすかった。
そして、それは咲良菜緒も一緒だったらしく、僕と同じように宮永さんに懐いていたらしい。
去年の僕の誕生日、同じようにこの会場でバースデイパーティをしてくれた日。
終了後に、僕は事務所を出たものの美織さんたちと片づけを一緒にしようと戻ってきた。
その時に、たまたま美織さんとベテラン事務スタッフさんが会話しているのを聞いてしまった。
『優陽くんの父親って宮永さんじゃないかしら……』
『やっぱりそう思う? 確かに菜緒と宮永さんって異常なほど距離が近かったわよね』
『宮永さんって優陽くんに対して特別かわいがっている気がするし』
そのまま僕は美織さんたちに声をかけることなく立ち去った。
僕は父親を知らない。
咲良菜緒は極秘で妊娠をしたけれど、世間的には体調不良の療養で活動休止しているということになっていて、セブファクの一部の人間を除いてガチガチに情報規制がかけられていたそうだ。
そして誰もお腹の子の父親が誰かは知らなかった。
ただ一人、咲良菜緒を除いて……。
そんな咲良菜緒は僕の出産時に常位胎盤早期剥離で大量出血をして、僕は助かったけれど母体である咲良菜緒は失血死した。
対外的には咲良菜緒は心不全が理由で亡くなったことになっている。
国民的女優といえるほど、その名を知られていた咲良菜緒急逝のニュースは日本国内をとびこえて海外でも大々的に報道されるほど当時衝撃を与えた。
「先代社長の頼さんの父親が亡くなっても、頼さんはセブファクを継ぐ気まったくなかったよな」
「そりゃそうだよ。これからコンサルでバリバリ稼いでやろうと思ったタイミングで親父が亡くなるわ、当時は売れない俳優だらけでセブファクは潰れかけだわ、芸能界なんて興味ないわで嫌々だったのが菜緒を見つけて変わったんだよ」
「当時、小5だった菜緒を頼さんが文字通り拾ってきた時は驚いたよ。しかも3年で演技力つけさせろって僕に一任してくるし」
「菜緒は野良猫みたいなものだった。それも、とびきり上等で毛並みの良いな。菜緒を初めて見た瞬間、こいつを絶対に日本のトップ女優にまで押し上げてやるって火がついたよ」
また頼政さんと宮永さんのこの話が始まった。
アルコールが進むと、毎回と言っていいほど、有し日の咲良菜緒の話をする。
咲良菜緒は両親が事故で亡くなり、邪魔者扱いで親せきをたらい回しにされた挙げ句、手を出されそうになり、逃げた先の公園で頼政さんと出会ったと聞いている。
「小5から中2まで、みっちり芝居の稽古をつけたうえで、菜緒をデビューさせたのも良かったよな。しかも映画中心にしてCM以外にはテレビには出さない売り出し方も特異性と神秘性を煽って大成功したし。セブファクをここまで再興した頼さんの手腕はすごいよ」
「いや、宮永が菜緒を女優として育成してくれたおかげだって。最初は余りにも演技が出来なさすぎて心配だったけど、よくデビュー時にあそこまで育て上げたよ」
宮永さんが褒め上手だからか頼政さんは饒舌になる。
この二人は旧知の仲で宮永さんは先代社長の時からセブファクに所属している酸いも甘いも嚙み分けた古株。
僕は二人が咲良菜緒の話をし始めると、身が縮こまる気持ちになる。
咲良菜緒じゃなく、お前が居なければよかったと遠回しに言われているような気がしてしまうのだ。
被害妄想だとわかってはいるけれど、いたたまれなくなる。
まだ飲んでいたい大人組より先に未成年で明日も学校の僕とたっちゃんは21時前には事務所を去った。
4月上旬の夜風は冷える。
僕が持っていた紙袋の一部をたっちゃんが持ってくれた。
二人で並んで七嶋家まで歩いて帰宅する。
「ねえ、たっちゃん」
「何?」
「華澄高でショートカットのかわいい子っていえば誰だと思う?」
「優陽」
余りにも当然のようにたっちゃんが答えるから、僕は思わず立ち止まってしまった。
「僕、女子じゃないけど」
「かわいい子だろ? じゃあ優陽じゃん」
「そういう冗談やめてよ」
「冗談じゃなく俺は本気でそう思うだけだけど?」
たっちゃんは真顔で言う。
僕は何でこんなことをたっちゃんに聞いてしまったんだろう。
一条琉唯を気にしているからだと認めたくなかった。
今年50歳になる宮永泉さんは仕事が途切れない中堅俳優。
ずっとセブファクに所属しており、いかにも優しそうな風貌と口調だけれど、時にはヤクザの役だろうとこなしてしまう演技派だ。
今のセブファクでは一番の稼ぎ頭だと思う。
紙袋にはバターサンドや生チョコレートやポテトチップチョコレートなど北海道土産がぎっしり。
そして、誕生日プレゼントはスイスの高級筆記用具メーカーの1万円以上する高級シャープペンシルだった。
「こんな高いもの受け取れないよ」
「遠慮することないって。優陽は勉強頑張ってるって聞いてる。それに優陽は僕の子どもみたいなものだと思っているから」
宮永さんに穏やかに微笑まれ、言葉が詰まる。
僕も宮永さんには昔から父親のように懐いていた。
迫力があって緊張してしまう頼政さんより柔和な雰囲気の宮永さんのほうが親しみやすかった。
そして、それは咲良菜緒も一緒だったらしく、僕と同じように宮永さんに懐いていたらしい。
去年の僕の誕生日、同じようにこの会場でバースデイパーティをしてくれた日。
終了後に、僕は事務所を出たものの美織さんたちと片づけを一緒にしようと戻ってきた。
その時に、たまたま美織さんとベテラン事務スタッフさんが会話しているのを聞いてしまった。
『優陽くんの父親って宮永さんじゃないかしら……』
『やっぱりそう思う? 確かに菜緒と宮永さんって異常なほど距離が近かったわよね』
『宮永さんって優陽くんに対して特別かわいがっている気がするし』
そのまま僕は美織さんたちに声をかけることなく立ち去った。
僕は父親を知らない。
咲良菜緒は極秘で妊娠をしたけれど、世間的には体調不良の療養で活動休止しているということになっていて、セブファクの一部の人間を除いてガチガチに情報規制がかけられていたそうだ。
そして誰もお腹の子の父親が誰かは知らなかった。
ただ一人、咲良菜緒を除いて……。
そんな咲良菜緒は僕の出産時に常位胎盤早期剥離で大量出血をして、僕は助かったけれど母体である咲良菜緒は失血死した。
対外的には咲良菜緒は心不全が理由で亡くなったことになっている。
国民的女優といえるほど、その名を知られていた咲良菜緒急逝のニュースは日本国内をとびこえて海外でも大々的に報道されるほど当時衝撃を与えた。
「先代社長の頼さんの父親が亡くなっても、頼さんはセブファクを継ぐ気まったくなかったよな」
「そりゃそうだよ。これからコンサルでバリバリ稼いでやろうと思ったタイミングで親父が亡くなるわ、当時は売れない俳優だらけでセブファクは潰れかけだわ、芸能界なんて興味ないわで嫌々だったのが菜緒を見つけて変わったんだよ」
「当時、小5だった菜緒を頼さんが文字通り拾ってきた時は驚いたよ。しかも3年で演技力つけさせろって僕に一任してくるし」
「菜緒は野良猫みたいなものだった。それも、とびきり上等で毛並みの良いな。菜緒を初めて見た瞬間、こいつを絶対に日本のトップ女優にまで押し上げてやるって火がついたよ」
また頼政さんと宮永さんのこの話が始まった。
アルコールが進むと、毎回と言っていいほど、有し日の咲良菜緒の話をする。
咲良菜緒は両親が事故で亡くなり、邪魔者扱いで親せきをたらい回しにされた挙げ句、手を出されそうになり、逃げた先の公園で頼政さんと出会ったと聞いている。
「小5から中2まで、みっちり芝居の稽古をつけたうえで、菜緒をデビューさせたのも良かったよな。しかも映画中心にしてCM以外にはテレビには出さない売り出し方も特異性と神秘性を煽って大成功したし。セブファクをここまで再興した頼さんの手腕はすごいよ」
「いや、宮永が菜緒を女優として育成してくれたおかげだって。最初は余りにも演技が出来なさすぎて心配だったけど、よくデビュー時にあそこまで育て上げたよ」
宮永さんが褒め上手だからか頼政さんは饒舌になる。
この二人は旧知の仲で宮永さんは先代社長の時からセブファクに所属している酸いも甘いも嚙み分けた古株。
僕は二人が咲良菜緒の話をし始めると、身が縮こまる気持ちになる。
咲良菜緒じゃなく、お前が居なければよかったと遠回しに言われているような気がしてしまうのだ。
被害妄想だとわかってはいるけれど、いたたまれなくなる。
まだ飲んでいたい大人組より先に未成年で明日も学校の僕とたっちゃんは21時前には事務所を去った。
4月上旬の夜風は冷える。
僕が持っていた紙袋の一部をたっちゃんが持ってくれた。
二人で並んで七嶋家まで歩いて帰宅する。
「ねえ、たっちゃん」
「何?」
「華澄高でショートカットのかわいい子っていえば誰だと思う?」
「優陽」
余りにも当然のようにたっちゃんが答えるから、僕は思わず立ち止まってしまった。
「僕、女子じゃないけど」
「かわいい子だろ? じゃあ優陽じゃん」
「そういう冗談やめてよ」
「冗談じゃなく俺は本気でそう思うだけだけど?」
たっちゃんは真顔で言う。
僕は何でこんなことをたっちゃんに聞いてしまったんだろう。
一条琉唯を気にしているからだと認めたくなかった。