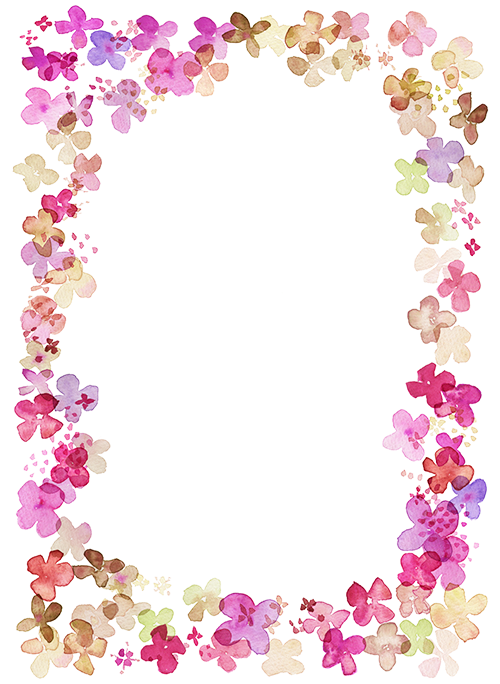誰のことかと不思議に思ってると、また誰かに名前を呼ばれた。
「入川君!」
「あ、進堂先輩も卒業おめでとうございます」
俺のファンクラブの自称会長。彼はやつれた顔で俺の手をとった。
「はぁ……これから毎日入川君の顔を見られなくなると思うと、胃に穴が空きそう。俺のボタンを渡すから、入川君も俺のこと忘れないでほしい」
「あー、ちょい待ち。入ちゃんには俺のボタンあげたから、二個もいらないって」
「は!? 赤城のボタンこそいらないだろ。入川君、それ返しちゃいな」
「ま、まぁまぁ……落ち着いて。お二人のボタン大事にしますから……」
二人分のボタンを握り締め、改めてお辞儀した。
「本当に寂しいな。入川君、良かったら俺が行く大学に来てね。文化祭も呼ぶから」
「はぁ、やだやだ。入ちゃん、俺の大学にしな。大学でまで変なファンクラブつくられたらたまんないでしょ」
この二人はどうしても口論になる相性らしい。
どっちの大学も遊びに行きます、と告げて何とか宥める。
「ありがとう、入川君。いなくなっても、俺達のこと忘れないでね」
「はい、もちろん」
俺の平坦な学園生活を賑やかにした人達だから、ぶっちゃけ一生忘れない。
でも、また会いたいな。
感謝の言葉と握手を交わし、彼らを見送った。
今日は三年生全員が主役だ。泣いてる子も多いし、先輩も目立たずに済むかもしれない。
毎日大変だったから卒業式ぐらいは平穏に過ごしてほしいけど……。
「……いた」
思ったとおり、見事に周りに溶け込んでる。
大好きな恋人の元へ、ひとを掻き分けながら歩いていった。
本当はすぐにでも後ろから抱き締めたい。けどぐっと堪え、笑顔で名前を呼んだ。
「朋空先輩! おつかれ」
「雅月。良かった、捜してたんだ」
「あはは、俺も。……卒業おめでとう、先輩」
「ん。ありがと」
卒業証書を持った先輩の前に行ったら、感慨深くてこっちが泣きそうになった。
立派になって……と言いかけ、俺は母親じゃなかったと思いとどまる。咳払いして、先輩の周りを見回した。
「あ。先輩、お母さんは?」
「もう帰ったよ。でも夜は……父さんと、三人で飯食いに行く予定」
「そっか……」
「うん。……でも、夜まで一緒にいてくれるよな?」
朋空先輩は腰に手を当て、不敵に笑った。
断られるなんて微塵も思ってない笑顔。そういうところが本当に羨ましい。
幼い頃からずっと憧れて、心奪われていたひと。
焦がれてやまなかったひと。
求め過ぎててちょっと恥ずかしいけど、ゆっくり頷いた。
「はぁ。来月から先輩がいないなんて……耐えられるかなぁ」
「問題ないだろ。同じマンションだし」