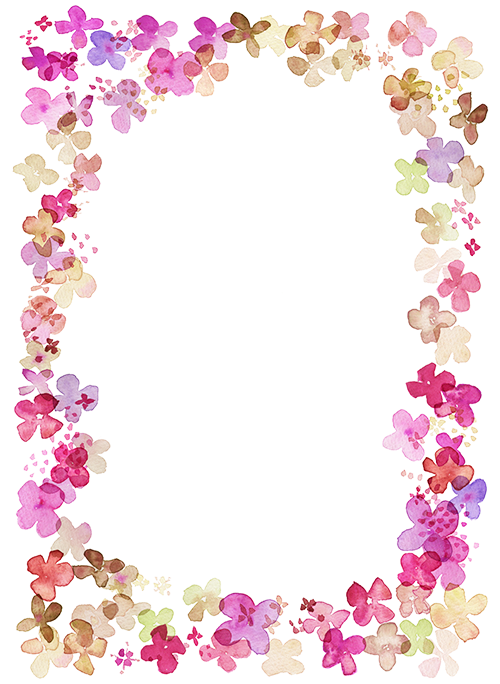危機感や警戒心というものがまるでなかった。皆無じゃなくて、マイナスのスタートだった。
『僕、道案内お願いできる? この辺のこと全然分からなくて』
自分も引っ越したばかりでまだ自信はなかったけど、少しでも役に立てたら、と思って男の人の方へ歩いた。
けど直後に腕を掴まれそうになって、それで……気付いたら、全速力で走っていた。
何が起きたのかもよく分からず、ただ無我夢中で。
俺の手を引いたのは朋空先輩だった。彼は近くのマンションに入り、息を切らしながら俺を壁の奥に押し込んだ。
『ど、とうしたの?』
『しっ! ……あいつ、手に何か持ってた』
何でいきなり逃げたのか訊こうとしたけど、口を手で塞がれてしまった。しゃがむように言われた為、屈んで植木鉢の陰に隠れる。見ると男の人も俺達を追ってきていた。
『光ってたから、刃物かもしんない』
朋空先輩は小声で囁いた。
俺はこんな状況でもまるで頭が処理できず、先輩に抱かれることしかできなかった。
男のひとがいなくなるまで、ひたすら息を殺して隠れた。まさか別のマンションの中までやってくるなんて。
すぐに近くの部屋に助けを求めたかったけど、留守かもしれないし、ドアが開くのを待つ前に捕まる可能性もある。
だから結局、マンションの住人がやってくるまでその場に留まり続けた。
『もう大丈夫。……帰ろうか』
気付けば外は真っ暗で、俺達のマンションの前にはパトカーが停まっていた。
朋空先輩が言った通り。……刃物を持った男を見た、という通報があったらしい。
帰りが遅くなったこともあり、俺達は親に色々聞かれた。
衝撃が大き過ぎて、無意識に記憶を封じてしまったのかもしれない。不安そうに俺を抱き締める母も、顔に影を落とす先輩のことも。
あの男のひとは、最初確実に朋空先輩を連れて行こうとしていた。でも先輩が距離をとるから、油断してる俺に近付いたんだ。
俺がもっとしっかりしていたら────。
その後悔は、何年も先まで続いた。
無理やり頭から消していた記憶を取り戻し、口元を押さえる。
朋空先輩は、あの事件をきっかけに俺から離れたんだ。
いくらなんでも、綺麗さっぱり忘れ過ぎだろう。全力で自分にツッコみたかったけど、現実はため息をつくことしかできなかった。
「あった。そんなこと……」
「なーに、急にどうしたの」
「急でもないんだけどね。ずっと、放置してただけのことだから……」
心配そうに見つめる母に笑い、テーブルに伏せる。
本当に、自分が許せない。というより、不甲斐なさに涙が出そうだった。
小学生だった自分にできることなんてなかったかもしれないけど、それでも先輩の傍に居続けることはできただろう。それなのに俺は、先輩から避けられてると思い、会いに行けずにいたんだ。
「あのときはアンタと朋空君も呆然としてたし、あまり深くは訊けなかったからね。不審者も捕まったから、傷口を抉るようなことをしちゃいけないと思って」
「う、うん。……おかげさまで、俺は綺麗に忘れてた」
でも朋空先輩は、今日までこの記憶を背負っていたんだろう。
「朋空さん……じゃないや。朋空先輩と、久しぶりに学校で話したんだ」
「本当! ……元気だった?」
「うん」
顔を上げ、背もたれに倒れる。
これは言っていいのか分からなかったけど……悩んだ末に、震える声で呟いた。
「俺……やっぱ、朋空先輩好きだ……って思った」
「そう。そうね、アンタ朋空君にほんと懐いてたもんね」
親ガモについてく子ガモのように……と、母は俺とだいぶ温度差のある調子で笑った。
でもここで重たいカミングアウトをするつもりもなかったし、軽く受け取ってもらえてホッとした。
「……さ、夜ご飯作るかー」
「……雅月。あのときは怖い思いさせてごめんね」
立ち上がって背伸びしてると、母は暗い面持ちで告げた。
「何言ってんの。母さんは関係ないじゃん」
「ううん。帰りが遅かったから、いつも夜まで独りにさせてたでしょ。それは親の責任よ」
「そんな……」
それも全部、俺を育てる為だ。責任を感じる必要なんて一ミリもない。
でも、こういうことなのかな。
俺は母も朋空先輩も被害者だと思ってる。悪いことなんて何もないと思うけど、彼らは自分が原因だと思い、責めている。
優しいからこそ抱いてしまう、罪悪感。それはいつまでもその人の心に根を張り、息ができないように締め上げる。
「……違うよ」
そんなのはおかしい。悪いひとは誰か分かりきってるし、自分を虐める必要なんてない。
もちろん俺も後悔はしてる。俺がもっとしっかりしてれば、不審者に気付いて大人を呼べたのに、と。
けど気付いててもそれが上手くいくとは限らないし、どこまでいってもifの話なんだ。
「誰も悪くない。だから大丈夫!」
「雅月……」
あれが悪い、これが悪いって考えたらキリがない。
確かに、もっと大変なことが起きていた可能性があるから、軽率なことは言えないけど。でも、自分を責めて苦しくなるぐらいなら一旦忘れてもいいと思う。
「ていいか、当事者の俺が覚えてなくてほんとごめん」
「あはっ。雅月らしいわ。もちろん良い意味でね」
母は立ち上がり、食事の支度を始めた。
「いつも本当にありがとね」
「いやー……こちらこそ」
改めて言われると恥ずかしくて、また適当に返してしまった。
でも、いつもの明日を迎える為に必要なことだ。おどけて、誰かを笑わせて。それでまた、日常を取り戻している。
◇
「ねえ、眠り姫って君?」
「いえ」
マンションから高校までの、徒歩十五分の道程。
たったこれだけの距離で、見知らぬ他校の生徒が声を掛けてくる。
いい加減慣れたものの、やはり疲れる。寝不足の朝は尚さら。
朋空は小さなため息をつき、鞄を肩に掛け直した。
( 昨日は失敗したな…… )
帰り際、雅月に言ってしまったことを一晩後悔していた。
ずっと触れないようにしていたのに、何故今さら取り出してしまったんだろう。
家庭の事情を打ち明けて、もっと色々共有したいと欲張ってしまったんだろうか。だとしたら軽率にも程がある。
あれは雅月にとってもトラウマになってるかもしれないのに。
自己嫌悪から乱暴に頭を掻く。
思い出していたのは、小学校のときに起きた事件のことだった。
不審者情報が流れていたとき、公園にいた自分と雅月に話しかけてきた男がいた。長いこと離れた位置から自分達を見ていることは気付いていたが、雅月が家に帰りたくなさそうだったからその場に留まったのだ。
でも今思えば、場所を移動するなりいくらでも方法があった。あまりにも愚かで、能天気な判断をした自分が許せない。
男は初めから自分をターゲットにしてると分かっていた。雅月を巻き込んだのは、他でもない自分なんだ。